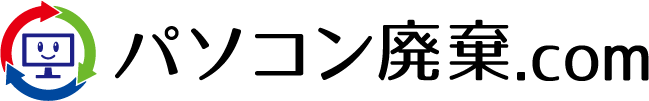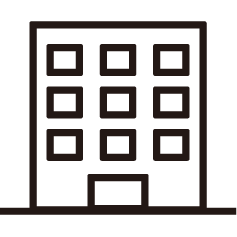404 Not Found
PS4からPS5に買い替えると、すぐにゲームを始めたいと思いますよね。しかしPS4から買い替えた場合には、PS5にデータ移行する必要があります。しかし、PS5のデータ移行方法が複雑で、どの方法を選べば良いのか迷ってしまう方も多いでしょう。
この記事では、PS4からPS5へのデータ移行方法を3通り詳しく解説します。それぞれの方法のメリットとデメリット、必要な準備、注意点などを分かりやすくまとめました。
データ移行できない場合の対処法や、使わなくなったPS4の処分前に行うべき初期化方法も紹介するので、参考にしてください。
【この記事でわかること】
- PS4からPS5にデータ移行する3通りの方法
- PS5へデータ移行する場合の事前準備
- データ移行する場合の注意点
- データ移行できない場合の対処法
PS4からPS5に移行できるデータ

PS4からPS5へ移行できるデータは以下の通りです。移行できるデータは、初期設定中、初期設定後のタイミングによって異なります。PS4で撮影したスクリーンショットやビデオクリップは、移行できないため注意しましょう。
| 移行できるデータ | データ内容 | 初期設定中 | 初期設定後 |
|---|---|---|---|
| セーブデータ | PS5でプレイ可能なゲームのセーブデータ | 〇 | 〇 |
| ユーザー情報やアカウント情報 | 転送元のPS4にサインインしたことがあるすべてのユーザーが対象プロフィール フレンドリスト トロフィー DLCなど | 〇 | - |
| 本体設定 | 言語設定 音声設定 ネットワーク設定 ログイン情報など | 〇 | - |
参考:PlayStationサポート PS4からPS5にゲームとセーブデータを移行する方法
ログインパスワードは、PS4のデータが引き継がれます。PS5にログインする場合も同じパスワードを入力しましょう。
同じゲーム・セーブデータが、すでに移行先のPS5に保存されている場合は、データが移行されません。
ユーザー情報が引き継がれるため、データ移行後にPS5にPS4のアカウントでログインすると、購入したダウンロードソフトや、DLCなどは購入履歴から再ダウンロードできます。
ファミリーメンバー(子ども)では、初期設定中にPS5にデータ移行できません。ファミリーメンバー(大人)アカウントで初期設定すれば、初期設定中にデータ移行できます。
または、ファミリーメンバー(子ども)アカウントで初期設定を完了し、初期設定後にデータ移行しましょう。
PS4からPS5にデータ移行する際に必要な準備

PS4からPS5にデータ移行する際に必要な準備は以下のとおりです。
- PS4とPS5を同じネットワークに接続する、同じアカウントでログインする
- PS4とPS5のシステムソフトウェアを最新バージョンにアップデートする
- PS5に十分な空き容量があることを確認する
- PS4で使用していたアカウントのパスワードを控えておく
- トロフィー情報を同期する
- 必要な物品をそろえる
それぞれ確認していきます。
PS4とPS5を同じネットワークに接続する、同じアカウントでログインする
PS4のデータをPS5に移行する前には、必ず同じネットワークに接続し、同じアカウントでログインしましょう。PS4とPS5にそれぞれ異なるアカウントでログインした場合は、データ移行できません。
PS4とPS5のシステムソフトウェアを最新バージョンにアップデートする
PS4とPS5のシステムソフトウェアを最新バージョンにアップデートすることで、安定してデータ移行ができます。
以下の手順で、PS4とPS5のシステムソフトウェアをアップデートしてください。
【PS4のシステムソフトウェアをアップデートする手順】
- PS4をインターネットに接続する
- ホーム画面から「設定」>「システム」>「システムソフトウェアアップデート」を選択する
- 画面の指示に従ってアップデートを実行する
参考:PlayStationサポート PS4のシステムソフトウェアをアップデートする方法
【PS5のシステムソフトウェアをアップデートする手順】
- PS5をインターネットに接続する
- ホーム画面から「設定」>「システム」を選択する
- 「システムソフトウェア」>「システムソフトウェアアップデートと設定」を選択する
- 「システムソフトウェアアップデート」を選択してアップデートを実行する
参考:PlayStationサポート PS5のシステムソフトウェアをアップデートする方法
アップデートが完了したら、PS4とPS5を再起動してください。
PS5に十分な空き容量があることを確認する
PS4から移行するデータ量によっては、PS5に十分な空き容量がない場合があります。以下の手順でPS5の空き容量を確認しましょう。新しいPS5にデータ移行する場合は、空き容量の確認は不要です。
- PS5のホーム画面から「設定」>「ストレージ」を選択する
- 画面に表示される「システムストレージ」の空き容量を確認する
空き容量が不足している場合は、不要なデータを削除する、拡張ストレージを使用するなどの対策が必要です。
PS4で使用していたアカウントのパスワードを控えておく
PS4からPS5へのデータ移行中に、PS4で使用していたアカウントのパスワードを入力する必要があります。事前にパスワードを控えておくことで、スムーズにデータ移行を進めることができます。
パスワードを忘れた場合は、PlayStationサポートに問い合わせてください。
トロフィー情報を同期する
PS4でこれまで獲得したトロフィーは、PS5へ移行できます。以下の手順で、トロフィーを同期させて置きましょう。
- ホーム画面でプロフィール写真を選択し「トロフィー」を選択
- オプションボタンを押し「PlayStation Networkと同期」を選択
参考:PlayStationサポート 手動でトロフィーを同期する
必要な物品をそろえる
PS4からPS5へのデータ移行には、以下の物品が必要です。
- LANケーブル(有線LAN接続を選択する場合)
- PS4とPS5を接続できるケーブル
- 拡張ストレージ(必要な場合)
スムーズにデータ移行するためにも、必要な物品を事前に準備しておきましょう。必要な準備が整ったら、データ移行へ進みます。
PS4からPS5へのデータ移行方法

PS4からPS5へのデータ移行方法は主に3つあります。
- ネットワークを利用したデータ移行方法
- オンラインストレージを利用したデータ移行方法
- 拡張ストレージを利用したデータ移行方法
いずれの方法でもPS4からPS5へデータ移行できます。状況に合わせて、データ移行方法を選びましょう。それぞれの手順を詳しく解説します。
ネットワークを利用したデータ移行方法
ネットワークを利用したデータ移行方法は、外部ストレージデバイスなどを用意する必要がなく、比較的手軽にデータ移行ができる点や一度に大量のデータを移行できる点がメリットです。
しかし、転送するデータ量によっては数時間から数十時間の時間がかかる場合があります。ネットワークに接続する際は、Wi-Fi接続ではなくLANケーブルで接続すると、データ移行の時間が短縮できるためおすすめです。
LANケーブルが1本しかない場合は、PS4とPS5を同じネットワークに接続し、PS4とPS5をLANケーブルで接続すると、有線接続と同程度の速度でデータを転送できます。
ネットワークを利用したデータ移行の手順は以下の通りです。
- 本体の電源が入っていることを確認する
- PS4にPS5で利用するアカウントにログインする
- PS4とPS5をWi-FiまたはLANケーブルで接続する
- PS5のホーム画面から「設定」>「システム」>「システムソフトウェア」を選択し「データ転送」>「続ける」の順に選択する
- PS5に「データ転送を準備」のお画面で「続ける」を選択する
- 「PS4が見つかりました」と表示されたらPS4の電源ボタンを音が出るまで長押しする
- 移行したいデータを選択し、「データ転送を開始する」を選択する
データ転送中にPS5本体が自動で再起動し、その後本体を使えるようになります。ゲームデータなど一部のデータは、本体再起動後も転送作業が行われています。
PS5でゲームをプレイできる状態になると、ホーム画面にゲームのサムネイルが表示されます。サムネイルを選択することで、他のデータの転送中でもゲームをプレイできます。
データ移行時間はネットワークの速度やデータ容量によって変わるため、時間に余裕を持って実行するのがおすすめです。
データ転送の進捗状況は、コントロールセンターから「ダウンロード/アップロード」を選択することで確認できます。
オンラインストレージ(PS5クラウド)を利用したデータ移行方法
オンラインストレージ(PS5クラウド)を利用すれば、簡単にデータ移行できます。
オンラインストレージは、有料サービスである「PS Plus」加入者限定のサービスです。加入している場合、PS4のセーブデータをクラウドストレージにアップロードすると、同じアカウントでログインしたPS5でダウンロードできます。
PS Plusへの加入が必要ですが、オンラインストレージを利用すれば、PS4とPS5を接続する必要がなく、インターネット環境があればどこでもデータ移行できる点がメリットです。
ただしオンラインストレージを利用して移行できるデータは、セーブデータのみです。ゲームをする際には、PlayStation Storeから再ダウンロードが必要です。
移行するデータ容量によっては、アップロード、ダウンロードに時間がかかるため、時間に余裕をもって実行しましょう。
詳しい手順は、以下の通りです。
- PS4にPS5と同じアカウントでログインする
- PS4のホーム画面から「設定」>「アプリケーションデータ管理」>「セーブデータ」>「オンラインストレージにアップロードする」を選択する
- 移行するゲームのセーブデータを選択して、アップロードする
- PS5でPS Plusに、同じアカウントでログインする
- PS5のホーム画面から「設定」>「セーブデータとゲーム/アプリ設定」>「セーブデータ(PS4)」を選択する
- 「本体ストレージからダウンロードまたは削除」を選択し、「クラウドストレージにダウンロードする」タブを選択
- ダウンロードしたいゲームのセーブデータを選択して、ダウンロードする
参考:PlayStationサポート PS5でPlayStation Plusクラウドストレージを管理する
拡張ストレージを利用したデータ移行方法
拡張ストレージとは、HDDやSDDなどのPlayStationの容量を増やすための周辺機器のことです。
PS4で利用していた場合には、拡張ストレージをPS5につなぎ変えるだけでPS4のゲームをプレイできるため、簡単です。また、PS4用のゲームを拡張ストレージから直接プレイできるため、PS5にはPS5用のゲームを保存する容量が確保できる点もメリットです。
ただし、PS5のゲームは拡張ストレージに保存したままではプレイできません。拡張ストレージからゲームデータをコピーして、PS5の内部ストレージに戻すとプレイできます。PS5用のゲームは、再ダウンロードするよりも、拡張ストレージからコピーする方が早いため、おすすめです。
セーブデータは、USBメモリを使い保存します。拡張ストレージを接続したまま、USBメモリを差し込み、設定画面の「アプリケーションセーブデータ管理」を選択します。
「本体ストレージのセーブデータ」から「USBストレージ機器にコピーする」を選択すると、セーブデータのコピーが完了します。
詳しい手順は、以下の通りです。
- PS4のUSBポートに対応した拡張ストレージを接続する
- 「本体ストレージ」を選択してOPTIONボタンを軽く押す
- 「拡張ストレージへ移動する」を選択する
- 移動したいデータにチェックマークを入れ「移動する」から「OK」を選択する
- 「クイックメニュー」から「サウンドと周辺機器」から「拡張ストレージの使用を停止する」から「OK」を選択する
- PS4から拡張ストレージを取り外してPS5に取り付けて起動する
- 拡張ストレージを認識して、PS4のゲームがプレイできれば移行完了
この方法は、インターネット環境に依存せずにデータ移行が可能である点がメリットです。
参考:PlayStationサポート PS4でアプリケーションを拡張ストレージに移動する方法
PS4からPS5へデータ移行する場合の注意点

PS4からPS5へのデータ移行は、PS5でゲームをプレイするために必要なことです。しかし、いくつかの注意点を守らなければ、データが消失したり、移行がうまくいかなかったりというトラブルが発生する可能性があります。
ここでは、PS4からPS5へデータ移行する際に注意すべきポイントを詳しく解説します。
移行するデータ容量によっては時間がかかる
PS4からPS5へデータ移行する際、移行するデータ容量によって時間が大きく変わります。ゲームソフトやセーブデータの容量によっては、数時間から丸一日かかる場合もあるため、時間に余裕を持ってデータ移行を開始しましょう。
データ移行中にキャンセルしない
データ移行中の画面にキャンセルの表記があり、クリックすればキャンセルできます。しかしデータ移行中にキャンセルすると、データが破損したり、移行がうまくいかなかったりする可能性があります。データ移行中は、他の操作をせずに完了まで待ちましょう。
万が一、データ移行が途中で止まってしまった場合は、慌てずにPS4とPS5の電源を切り、再度データ移行を試みましょう。
一部のPS4のゲームはPS5版にアップグレードできる
PS4のゲームの中には、PS5版にアップグレードできるものがあります。PS5版にアップグレードすると、グラフィックの向上やフレームレートの増加などのメリットがあります。さらに微細な振動を感じる「ハプティックフィードバック」に対応し、ゲームへの没入感をより楽しめたり、ロード時間が短くなることもあります。
PS5版へのアップグレードが可能な場合は、データ移行の際にPS5版をダウンロードしてインストールすることで、PS5の性能を活かしてゲームを楽しめます。ただし、ディスク版のPS4のソフトの場合は、ディスクドライブ搭載のPS5でなければアップグレードできない点に注意しましょう。
PS4のデータを移行してもデータはなくならない
PS4からPS5へデータを移行しても、PS4のデータは消えません。PS4とPS5で同じデータを共有できます。
PS4で引き続きゲームをプレイしたい場合は、PS4のデータを移行した後もPS4を保管しておきましょう。PS4のデータを削除したい場合は、データ移行後にPS4のデータを消去しても問題ありません。
省電力モードは解除しておく
PS4とPS5は省電力モードに設定すると、データ移行中に自動的に電源が切れてしまう可能性があります。データ移行中は、PS4とPS5の省電力モードを解除しておきましょう。PS4とPS5は設定画面から、省電力モードを解除できます。
データ移行中は電源を切らない、レストモードにしない
データ移行中は、PS4とPS5の電源を絶対に切ってはいけません。また、データ移行中には手動でレストモードにもしないようにしましょう。
電源を切ったり、レストモードにしたりすると、データが破損したり、移行がうまくいかなかったりする可能性があります。
PS4からPS5へのデータ移行ができない場合の対処法

PS4からPS5へのデータ移行ができない場合、以下の対処法を試してみましょう。
- ルーターの電源を入れ直す
- PS5に対応しているゲームか確認する
- PS4とPS5の両方で同じアカウント、ネットワークを使用しているか確認する
- 使用しているインターネット接続が安定しているかをチェックする
それぞれ、詳しく解説します。
ルーターの電源を入れ直す
データ移行がうまくいかない場合は、ルーターの電源を入れ直すことで改善される場合があります。
具体的な手順は以下の通りです。
- ルーターの電源を切る
- 30秒程度待ってから、再度ルーターの電源を入れる
- ルーターの電源が入ったら、PS4とPS5の両方を再起動する
これにより、一時的にインターネット接続が切断されたり、データ移行に失敗したりしていた場合が改善されることがあります。
PS5に対応しているゲームか確認する
ほとんどのPS4のゲームは、PS5でプレイできますが、ごく一部にPS5に対応していないゲームもあります。どうしてもゲームデータが移行できない場合は、ゲームタイトルがPS5に対応しているかを以下の方法で確認しましょう。
- プレイステーション公式サイトのゲーム情報ページを確認する
- ゲームディスクのパッケージ裏面を確認する
- PS Storeでゲームの詳細情報を表示する
PS4とPS5の両方に最新のシステムソフトウェアをインストールする
PS4とPS5のシステムソフトウェアが最新バージョンでない場合、正常にデータ移行できない可能性があります。PS4とPS5の両方で、事前に最新のシステムソフトウェアをインストールしておきましょう。
PS4とPS5の両方で同じアカウント、ネットワークを使用しているか確認する
PS4とPS5で異なるアカウントを使用している場合、データ移行はできません。PS4とPS5で同じアカウントを使用していることを確認しましょう。
また、ネットワークを利用してデータ移行する場合は同じネットワークに接続する必要があります。LANケーブルが同じルーターに接続しているか、同じネットワーク名のWi-Fiに接続していることを確認しましょう。
使用しているインターネット接続が安定しているかをチェックする
PS5のデータ移行には、安定したインターネット回線が必要です。使用しているインターネット回線が安定していることを確認しましょう。
インターネット接続が安定しているかは、以下の方法で確認できます。
- 他の機器でインターネット接続に問題がないか確認する
- PS4またはPS5のネットワーク設定を確認する
- インターネット回線の速度を測定する
上記の対処法を試してもデータ移行ができない場合は、PlayStationサポートで相談するのがおすすめです。
使わなくなったPS4は処分前に初期化をしておく

使わなくなったPS4を処分する際は、必ず初期化をしておきましょう。
ゲームのセーブデータやダウンロードコンテンツ、個人情報が含まれるアカウント設定など、様々なデータがPS4には保存されています。初期化しないまま処分すると、これらの情報が第三者の手に渡るリスクがあります。
PS4を初期化をしておくことで、プライバシー保護と第三者による不正利用を防ぐことができます。
また、他の人へ譲渡する場合にも初期化がおすすめ。初期化することで、PS4の動作が軽くなり、他の人が使用する際にも問題が起きにくくなります。
PS4を初期化するには、以下の2つの方法があります。
- [設定]>[初期化]>[設定を初期値に戻す]を選択する
- [設定]>[初期化]>[PS4を初期化する]を選択し、[クイック]もしくは[フル]どちらかを選択して初期化をする
初期化には数時間かかることもあるため、時間に余裕をもって実行しましょう。
参考:PlayStationサポート PlayStation®4を初期化する方法
パソコン廃棄.comならPlayStationも無料で処分できます。一緒に送るパソコンがある場合には、送料も無料。データ消去も不要で処分できるため簡単です。PlayStationの処分に困ったら、ぜひご利用ください。
PS5を売却・廃棄する前にやっておくべき初期化の方法に関しては、下記記事でも詳しく解説しています。
PS5を売却・廃棄する前にやっておくべき初期化の方法を紹介!>>
まとめ:PS5のデータ移行には時間がかかる!余裕を持って実行しよう

PS5を購入すると、すぐにゲームをプレイしたいと思いますが、事前にデータ移行が必要です。PS4からPS5へのデータ移行はデータ容量にもよりますが、数時間から丸一日かかることもあります。時間に余裕を持って実行しましょう。
データ移行中には電源を切らない、キャンセルしないなどの注意点もあります。大切なデータを失わないために、事前に確認しておきましょう。
データ移行することで新しいPS5でもPS4のゲームを引き続き楽しめるようになることや、これまでの成果や進行状況が引き継がれるため、よりスムーズに遊び続けられます。この記事を参考に、PS5にデータ移行して新しいゲームライフを楽しんでください。
PlayStationの処分に困ったら、いつでも無料で利用できるパソコン廃棄.comをぜひご利用ください。
パソコン廃棄.comでPlayStationの処分をする>>

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
PS5を購入したいけれど、寿命が気になる方も多いのではないでしょうか。また、本当にPS5を購入するべきか判断に迷う方もいるでしょう。
この記事では、PS5本体の寿命や、寿命を延ばす方法についてや、PS5を購入するかどうかの判断基準について解説します。
これからPS5を購入しようか悩んでいる方やPS4から買い替えるか悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
【この記事でわかること】
- PS5の寿命は5~9年、コントローラーは7か月~1年半程度
- PS5の寿命が近い症状は異音や電源が落ちるなど
- レストモードは寿命に関係しないが長時間の使用は避ける
- PS5の寿命を延ばすためには定期的なメンテナンスと適切な使い方を守る
- PS5を購入するかの判断基準は遊びたいゲームの有無や高性能でプレイしたいかなど
PS5の寿命は何年?本体とコントローラーの寿命を解説

PS5は2020年11月に発売された最新ゲーム機です。高性能なグラフィックとスムーズな動作で、多くのゲーマーを魅了しています。
PS5にはもちろん寿命があり、本体とコントローラーの寿命がそれぞれ異なります。PS5のコントローラーは、ワイヤレス接続のためバッテリーの寿命もあります。ここでは、PS5の本体とコントローラーの寿命について、それぞれ解説します。
PS5本体の寿命は5~9年
PS5本体の寿命は使用頻度や環境などによって大きく異なりますが、通常5~9年と考えられます。2020年発売のPS5の寿命はソニー公式サイトでは公開されていないため、PS4の寿命を参考にした数字です。
PS4は2013年に発売され、2023年現在でも多くの人が使用していますが、発売から10年近く経過したこともあり、故障や不具合が徐々に増えてきています。
PS5はPS4よりも高性能な部品を使用しており単純に比較することはできませんが、5~9年程度が寿命の目安となるでしょう。
PS5が寿命を迎えてしまう理由には、以下の要因があります。
- 電子部品の劣化
- ハードウェアの更新
- ソフトウェアの互換性
PS5は長時間の使用により電子部品が劣化し、故障しやすくなります。例えば、新しいハードウェアが登場すると、古いモデルがパフォーマンス不足となることもあります。
PS5に限らずパソコンや他のゲーム機でも、世代が変わると新しいソフトウェアが旧モデルとの互換性がなくなることがあります。
具体例として、PS3からPS4への移行時には、多くのゲームが新世代に対応していましたが、古いゲームはプレイできなくなりました。
そのため、仮にPS6が発売された場合に、PS5でプレイできないゲームが増えると寿命を迎えるとも考えられます。
PS5コントローラーの寿命は7か月~1年半程度
PS5のコントローラーの寿命は短く、約417時間といわれています。これは、1日2時間使用すると7か月で寿命になる計算となります。
PS4の実例を参考にすると、4年間に6回もコントローラーを買い替えたという事例もあります。コントローラーは常に手に触れて操作するため、摩擦や摩耗によって部品が劣化しやすいためです。
PS5のコントローラーは、長時間の連続使用だけでなく、強い力でボタンを押したり、スティックを乱暴に操作したりしても寿命が短くなります。落下や衝撃にも弱いため、丁寧に扱いましょう。
また、PS5のコントローラーはワイヤレス接続で充電式です。フル充電で約7時間使用できますが、繰り返し充電するほどバッテリーが劣化して徐々に稼働時間が短くなります。
PS5のコントローラーを毎日フル充電を続けると、1年半で寿命を迎えるといわれています。PS5のコントローラーはバッテリーだけの交換ができないため、バッテリーが寿命を迎えた場合にコントローラーも寿命を迎えます。
PS5のコントローラーはリチウムイオン電池です。常にフル充電するのではなく、20~80%に保つことで寿命を延ばすことができるでしょう。
PS5の寿命が近い症状とは?

PS5は2020年発売の新しいゲーム機のため、寿命が近い症状についてわからないことも多いです。しかし、2013年に発売されたPS4の症状を参考にするとPS5の寿命が近いと考えられる症状がわかります。ここでは、PS5の寿命が近いと判断できる症状について詳しく解説します。
PS5から異音がする
PS5本体から異常に大きなファンの音や、今まで聞こえなかったような異音が聞こえる場合は、故障の兆候である可能性があります。特に、以下の症状には注意が必要です。
- ファンの音が異常に大きい
- ゲーム中に異音が聞こえる
- ディスクドライブから異音が聞こえる
このような異音が発生した場合は、使用を中止して修理などの対応を検討しましょう。
電源がつかない・落ちる
電源ボタンを押しても電源が入らない場合は、コンセントや電源コードの異常、HDMIの接触不良などが原因のことがあります。またPS5に熱がこもりすぎた場合にも、電源が勝手に落ちることがあり、使用をやめて休ませることで改善することもあります。
しかし、頻繁に起こる場合やなかなか改善しない場合は、電源ユニットやマザーボードなどの故障が考えられ、寿命が近い可能性があります。
PS5の電源がつかない場合の対処法は、下記記事でも詳しく解説しています。
PS5の電源が入らない原因は?確認することや対処法を紹介!>>
フリーズやエラーが多発
ゲーム中に頻繁にフリーズしたり、エラーメッセージが表示されたりする場合は、ハードディスクやソフトウェアに問題がある可能性があります。
PS5のエラーは、電源ランプの色や点滅の仕方でも確認できます。電源ランプが白に点灯してもつかない場合や、白や青、赤色で点滅し続ける場合は不具合が起こっていることを現わしています。
ハードディスクの修理やソフトウェアの更新などで改善することもありますが、あまりにも頻繁に起こる場合は寿命が近いのかもしれません。
画質や音質の劣化
美しい映像が魅力のPS5ですが、画質や音質に劣化が見られる場合も、寿命が近いサインです。画面がカクカクしたり、音声が途切れたりする場合は、映像出力や音声出力に問題がある可能性が高いでしょう。
電源がついているものの、画面が映らない場合にも注意が必要です。モニターやHDMIの不具合の可能性もありますが、頻繁に起こる場合は本体の寿命も疑いましょう。
その他の症状
その他には、以下の症状が現れた場合も寿命が近いと考えられます。
- コントローラーが認識されない
- ディスクトラブルが起こる(読み込まれない・勝手に排出されるなど)
- インターネット接続が不安定
再起動などで改善することもありますが、頻繁に起こる場合は寿命が近い可能性もあります。早めに修理に出すなどを検討しましょう。
PS5をレストモードにすると寿命に影響する?

PS5には、省電力モードである「レストモード」が搭載されています。PS4の「スタンバイモード」と同様で、PS5の電源を完全に落とさず省電力で待機するパソコンのスリープモードのようなものです。
レストモードでは、電源オフにするとできないコントローラーの充電や、ゲームのダウンロードやアップデートを待機状態で実行できます。また、起動までの時間を通常の半分以下にできるため、スムーズにゲームをプレイできることもメリットです。
結論、PS5をレストモードにしても寿命に大きな影響を与えることはないと言われていますが、以下の点には注意する必要があります。
- 長期間レストモードのまま放置しない
- 停電時に不具合が起こる可能性がある
- 雷雨などの際は電源ケーブルを抜く
- 定期的に本体の掃除を行う
長期間レストモードのまま放置すると、本体内部に熱が溜まって故障につながる可能性があります。また、停電などのトラブルが起こった場合にはPS5本体や保存データに不具合が起こる可能性もあります。
レストモード中には、誤って電源コードを抜くなどしないように注意しましょう。雷雨などの際は落雷による故障を防ぐために、電源ケーブルを抜きレストモードにはしないことをおすすめします。
レストモードは、PS5を長持ちさせるために有効な機能です。 基本的にはレストモードを使用しつつ、長時間使わない時や雷雨の時には電源を切りましょう。
PS5の寿命を延ばす使い方

PS5には寿命があり、長く快適に使い続けるためには適切な使い方と定期的なメンテナンスが必要です。PS5の寿命を延ばすための使い方は以下の通りです。
- 電源を適切に管理する
- 高温・低温環境での使用を避ける
- 傷のあるディスクを使用しない
- 定期的にシステムをアップデートする
- PS5スタンドを必ず使用する
- 定期的にホコリを掃除する
- メーカーの保証期間内であれば修理を依頼する
ここでは、PS5の寿命を延ばす使い方やメンテナンス方法を詳しく解説していきます。
電源を適切に管理する
長時間連続使用すると本体内部に熱が溜まり、故障につながる可能性があります。ゲームに熱中すると長時間プレイしてしまいますが、1日数時間程度の使用に留めてこまめに休憩を取るようにしましょう。
また、レストモードで放置していても消費電力が発生します。長時間使用しない場合は、完全に電源をオフにしましょう。電源を切ることで、本体の寿命を延ばすだけでなく、電気代の節約にもなります。
高温・低温環境での使用を避ける
高温または低温環境での使用は、PS5の寿命に悪影響を与える可能性があります。高温環境では、本体の冷却機能が十分に働かず、電子部品の劣化が進行します。
PS5の周りは余計な物を置かず、通気性を良くしましょう。日当たりの良い場所や暖房器具の近くに設置すると、本体が高温になりすぎることがあります。夏場は特に、エアコンなどで室温を適切に保つことも重要です。
PS5を長時間使用し続けると、本体が熱くなりすぎることがあります。ノートPC用の冷却パットを使用するなどで、本体が熱くなりすぎないように注意しましょう。
反対に低温環境でも、液晶画面や電子部品にダメージを与えることがあります。最適な使用環境は、5℃~35℃です。PS5の寿命を延ばすためには、最適な温度を守って使用しましょう。
参考:PS5 セーフティガイド
傷のあるディスクを使用しない
傷のあるディスクをPS5で使用すると、読み取りエラーになり、使用し続けるとPS5が故障する可能性があります。
ディスクに汚れがある場合は、必ず柔らかい布で中心から外へ向かって軽くふき取りましょう。ディスクは非常に傷つきやすいため、丁寧に使用してください。
ディスクを傷つけないためには、以下の点に注意しましょう。
- 再生面を手で触らない
- 直射日光があたる場所や温度、湿度の高い場所で使用しない
- 長期間使わないときはケースで保管する
参考:PS5 セーフティガイド
定期的にシステムをアップデートする
PS5のシステムを定期的にアップデートすることは、パフォーマンスの向上やセキュリティを維持するために重要です。
システムアップデートすることで新機能の追加や、バグやセキュリティの脆弱性の修正などが実行されます。
新機能を追加するとPS5の使い勝手が向上します。例えば、省電力化機能が追加されると、消費電力が抑えられ、本体内部の熱が抑えられ故障のリスクを減らせます。またバグやセキュリティホールの修正によって、不正アクセスやデータ破損を防ぎPS5を安全に使用できます。
常にシステムを最新の状態に保つことで、PS5を快適に使用し続けることが可能です。以下の手順で、PS5のシステムを自動でアップデートできるため、設定しておくことをおすすめします。
- PS5本体の電源を入れる
- 画面左上の「設定」を選択
- 「システム」を選択
- 「システムソフトウェア」を選択
- 「システムソフトウェアアップデートと設定」を選択
- 「アップデートファイルを自動でダウンロード」と「アップデートファイルを自動でインストール」を有効にする
参考:PlayStationサポート PlayStationで自動ダウンロードと自動アップデートを設定する方法
PS5スタンドを必ず使用する
PS5は縦置き、横置きどちらでも排熱性能などに違いはありません。縦置き、横置きでもPS5スタンドを必ず使用することが、本体の安定性や冷却効果を向上させるために重要です。
PS5スタンドを使用すると、機器に適切な空間が確保されオーバーヒートを防ぐため、PS5の故障を防ぐことができます。
例えばPS5スタンドを使い、PS5を縦置きにすれば、省スペース化や見た目もスマートになります。縦置きにより、机や棚の上のスペースを有効活用し、本体が目立たないように配置できるメリットもあります。
横置きの場合でも、そのまま本体を横置きにすると安定しないため、横置きスタンドの活用がおすすめです。
PS5スタンドを使用することで、機器の安定性や冷却効果が向上します。PS5の寿命を延ばすためには、スタンドを使用しましょう。
定期的にホコリを掃除する
PS5は精密機械のため、ホコリや汚れが溜まると故障の原因になります。
ホコリが機器内部に蓄積するとPS5の冷却効果が低下してオーバーヒートを起こしたり、異音が聞こえるようになったりして故障の原因になります。
PS5には掃除がしやすいようにダストキャッチャーが設けられています。定期的にカバーを外して、ダストキャッチャーの清掃を行いましょう。
PS5の掃除方法は、以下の通りです。
- 本体の電源を切る(レストモードにしない)
- 本体に接続しているコード類や、スタンドをすべて取り外す
- 本体が熱い場合は熱が冷めるのを待つ
- PS5の本体カバーを外す
- ダストキャッチャーにたまったホコリを掃除機で取り除く
- 通気孔にたまったホコリがあれば掃除機で取り除く
- キャビネット(本体やコントローラーのプラスチック部分)は柔らかい布で拭く
- 端子類の汚れを乾いた布でふき取る
メーカーの保証期間内であれば修理を依頼する
PS5は、1年間のメーカー保証が付いています。保証期間内に故障した場合、無料で修理を受けられます。PS5は精密機械のため、自分で修理すると故障を悪化させてしまう可能性があります。
また、保証期間内に自分で修理すると、保証の対象外になることもあります。保証期間内に修理が必要な場合は、必ずソニーのサポートに連絡しましょう。
PS5を購入するかの判断基準

PS5は高性能で魅力的なゲーム機ですが、非常に高価です。PS5を購入するかどうかの判断基準には、以下のポイントがあります。
- 遊びたいゲームがあるか
- PS4を持っているか
まず、新しいゲームが魅力的かどうかを考慮しましょう。PS5独占タイトルや次世代ゲームへの興味があれば、購入を検討する価値があります。
また、性能の向上も重要なポイントです。PS5はPS4よりも高画質・高音質でゲームを楽しめます。さらに、価格や入手の容易さも判断基準となります。予算が許す範囲内で入手できるかどうかや、在庫状況を確認することも重要です。
PS4を持っているかどうかもポイントです。PS4を持っておらず、これからPlayStationを購入したい場合はPS5の購入がおすすめですが、PS4を持っている場合、その判断は状況によって異なります。ここからは、それぞれの判断基準について詳しく解説します。
遊びたいゲームがあるか
最初の判断基準は、PS5で遊びたいゲームがあるかどうかです。
PS5には独占タイトルや次世代のゲームが多数登場しており、今後も増えていくと予想されます。PS5でしかプレイできないゲームがある場合は、PS5の購入を検討しましょう。
PS4で発売されたゲームの中には、PS5でフレームレートや解像度が向上するアップグレード版が提供されているものもあります。プレイしているゲームがアップグレードされた場合にも検討の余地があるでしょう。
また、PS5はPS4との互換性にも優れており、過去の名作を遊ぶこともできます。PS4の4,000タイトル以上をプレイできるため、PS5があればより幅広いゲームをプレイできます。
プレイしたいゲームがある場合は、そのゲームを楽しむためにPS5を購入することを検討してみてください。
PS4を持っているか
すでにPS4を持っている場合は、PS5を購入するかどうかは状況によって判断基準が異なります。
PS5はPS4から大幅に性能が向上しています。公開されている数字で比較すると、CPUは2倍以上、GPUはおよそ5倍、メモリは2倍になっています。さらにストレージの読み込み速度は、55倍と超高速です。PS5は4Kや8Kに対応しており、高解像度の美しいグラフィックを楽しめます。そのため性能向上を実感したい、新機能を利用したいなどがある場合はPS5の購入を検討しましょう。
一方で、PS4で遊ぶゲームがまだ多くある場合や、PS4で十分満足している場合は、PS5の購入を見送ることも一つの選択肢です。特にPS4 ProはPS4よりも高性能なモデルのため、PS5との性能差は小さくなります。プレイするゲームによっては、体感できるほどの性能差を感じない場合もあります。
PS4を持っている場合は、プレイしたいゲームの有無や性能差で購入を判断すると良いでしょう。
まとめ:PS5の寿命は5~9年!メンテナンスで延ばそう

PS5本体の寿命は5~9年、コントローラーの寿命は7か月~1年半程度です。寿命が近くなると、異音がする、電源がつかない、フリーズの多発、画質や音質の劣化など様々な症状が現れます。
PS5の寿命を延ばすためには、定期的なメンテナンスと適切な使い方が大切です。電源や温度の管理、定期的なシステムアップデートなどを実行しましょう。
また、使用する際にはPS5スタンドを使用し、定期的にホコリを清掃することで、オーバーヒートによる故障を防げるため、結果的に寿命を延ばすことに繋がります。
PS5を購入するかどうかの判断は、遊びたいゲームの有無やPS4の所有状況によって変わります。PS5でプレイしたいゲームがある場合や、PS4を持っていない場合には、PS5の購入がおすすめです。
この記事を参考に、PS5のメンテナンスを実行して、楽しいゲームライフを過ごしましょう。もしもPS4からPS5に買い替えた場合は、古いPS4の処分が必要です。
パソコン廃棄.comならPlayStationも無料で処分可能です。一緒に送るパソコンがある場合には、送料も無料で処分できます。事前連絡やデータ消去も不要で処分できるため簡単です。PlayStationの処分に困ったら、ぜひご利用ください。
パソコン廃棄.comでPlayStationの処分をする>>

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
PS5を売却・廃棄する際には初期化が必要ですが、やり方がわからないと困っている方もいるでしょう。
この記事では、PS5の初期化方法や、売却・廃棄をする前にやっておくべき手順を解説します。
この記事を読めば、個人情報やセーブデータが第三者の手に渡らないように、正しい方法でPS5を売却・処分できます。
PS5の初期化方法やデータバックアップ、機器認証の解除など、全ての手順をわかりやすく解説しています。できない場合の対処法も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
【この記事でわかること】
- PS5の初期化が必要な理由
- PS5のバックアップ方法
- 初期化する方法
- 売却・廃棄前にするべきこと
- できない場合の対処法
PS5を初期化しないで売却・廃棄する危険性

PS5を初期化せずに売却・廃棄すると、個人情報やデータが第三者に漏れるリスクがあります。
例えば、自動ログインが設定されているPS5の場合、初期化しないで手放すとアカウントに残ったウォレットの使い込みや、クレジットカードを勝手に使用されるなどのオンラインサービスを悪用される可能性があります。
アカウント情報やフレンド情報などから個人情報の流出、セーブデータの不正利用なども考えられるため、PS5を手放す際には初期化が必要です。
また大手買取店では、データが残ったPS5本体の買取をしていないこともあります。PS5を初期化していなければ、最悪の場合、無料買取となり買取価格が1円もつかないことにもなりかねません。
このようなトラブルを防ぐためには、PS5を売却・廃棄前に必ず初期化することが重要です。
PS5の初期化前にやっておくべきバックアップ

PS5を初期化するとデータはすべて削除されます。そのため、初期化する前には、データのバックアップを取っておきましょう。PS5でバックアップできるデータは、以下の通りです。
- ゲームとアプリ
- セーブデータ
- スクリーンショットとビデオクリップ
- 設定
必要なデータだけをバックアップしたい場合は、個別でバックアップを取りましょう。なお、トロフィーはバックアップデータに含まれません。データをバックアップする前に、手動でステータスを更新しましょう。
PS5のデータは、USBなどの外部ストレージに保存する方法と、クラウドにアップロードして保存する方法があります。
それぞれ解説します。
USBなどの外部ストレージにバックアップする方法
PS5の本体ストレージに保存されているデータは、USBなどの外部ストレージにバックアップできます。以下の手順でデータをバックアップしましょう。
- PS5にUSBドライブを接続する
- ホーム画面から「設定」>「システム」を選択
- 「システムソフトウェア」>「バックアップと復元」>「PS5をバックアップ」を選択
- バックアップしたいデータの種類を選択し、「次へ」を選択
- 「バックアップ」を選択
- 「バックアップが完了しました。PS5を再起動します。」と表示されたら「OK」を選択する
参考:Playstationサポート PS5のデータをUSBドライブにバックアップする方法
バックアップからPS5を復元する際には、システムソフトウェアのバージョンが、バックアップしたときの本体のバージョンと同じかそれ以上であることが必要です。復元する際には、システムソフトウェアのバージョンに注意しましょう。
USBからデータを復元すると、PS5に保存されている全てのデータが消去されてしまいます。購入済みのゲームなどは再ダウンロードすればプレイできますが、あらかじめゲームやアプリのデータなども外付けハードディスクなどに移動させておくと安心です。
クラウドにアップロードしてバックアップする方法
PS Plusに加入していれば、クラウドストレージにデータをバックアップして保存できます。簡単にバックアップできる上に、次回以降データを呼び出すのも簡単なためおすすめです。
クラウドストレージとPS5のデータを自動で同期する設定にしている場合は、本体とクラウドストレージ両方に最新のデータに同期されています。初期化する前には、データが保存できていることを確認しましょう。クラウドにデータをバックアップする方法は、以下の通りです。
- ホーム画面から「設定」を選択する
- 「設定」>「セーブデータとゲーム/アプリ設定」の順に移動する
- 「セーブデータ(PS5)」の「本体ストレージ」を選択する
- 「本体ストレージからアップロードまたは削除」を選択し、「クラウドストレージにアップロードする」タブを選択する
- アップロードしたいセーブデータを選択し、「アップロード」を選択する
参考:Playstationサポート PS5のPlayStation Plusクラウドストレージ
なお、PS Plusの有効期限が過ぎた場合でも、半年間はクラウドストレージにデータが保存されません。解約してしまった場合でも半年以内に再加入すれば、保存していたデータを復元できます。
なお、新しいPS5に買い替える場合は、データ移行も可能です。PS5のデータ移行の方法は、下記記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。
PS4からPS5にデータ移行する方法は?3通りの方法を紹介>>
PS5を初期化する方法

ここまでの準備が整ったら、PS5を初期化しましょう。PS5を初期化する手順は、以下の通りです。
- PS5本体の電源を入れる
- ホーム画面から、ユーザーを選択する
- 画面上部の「設定」(歯車アイコン)を選択し、「システム」へ進む
- 「システムソフトウェア」を選択し、「初期化」へ進む
- 「PS5の初期化」を選択する
初期化が完了すると、PS5は工場出荷時の状態に戻り、個人情報およびデータが全て削除されます。なお、プリインストールされているゲーム「ASTRO’s PLAYROOM』」を復元するには、PlayStation®Storeからダウンロードしてください。
参考:Playstationサポート 本体を工場出荷時の状態に戻す
PS5の初期化で消えるデータと消えないデータ

PS5を初期化すると、セーブデータやアカウント情報などのデータはどうなるのでしょうか?
PS5を初期化すると本体は工場出荷状態に戻るため、ダウンロードしたゲームは遊べなくなるのかと不安になる方もいるでしょう。ここではPS5を初期化すると、消えるデータと消えないデータについて解説します。
PS5を初期化すると消えるデータ
PS5を初期化すると、工場出荷状態に戻ります。そのため本体に保存されているさまざまなデータが消去されます。
消えるデータには、ユーザーアカウント情報、ゲームのセーブデータ、ダウンロードしたゲームやアプリなどが含まれます。
具体的には以下のようなデータが対象です。
- ユーザー登録情報
- ゲームのセーブデータ
- ゲームやアプリのインストールデータ
- システム設定
これらのデータは初期化することで消えてしまい、一度削除されると復元できません。
初期化しても消えないデータ
一方で、初期化しても消えないデータもあります。PlayStation ネットワークアカウントやオンラインストレージに保存されたセーブデータ、購入したゲームやアプリ、トロフィー情報などのデータは初期化しても消えません。
これまでPS5にダウンロードしたゲームは、本体から削除されますが、遊べなくなるわけではありません。プレイステーションでダウンロードしたソフトは、ソニーアカウントと紐づいています。
そのため同じアカウントでプレイステーションストアにログインすれば、ライブラリから無料でソフトを再ダウンロードできます。
しかし、セーブデータは初期化によって消えてしまうため、初期化前に重要なデータが消えないよう、以下の手順を踏んでバックアップを取りましょう。オンラインゲームの場合は、セーブデータがサーバーへ保存されるため、バックアップを取る必要はありません。
- セーブデータをPS Plusのオンラインストレージにアップロードする
- 必要に応じてUSBなどの外部ストレージにデータをコピーする
これらの手順を踏むことで、データを安全に保管し、新しいPS5や他のPS5で利用可能になります。
PS5を売却・廃棄する前の注意点

PS5を売却や廃棄する前に、以下の点に注意して準備を進めましょう。
データのバックアップを取ることや、初期化することのほかにも以下のように注意することがあります。
- PS PLUSの解約(完全にPS5を手放す場合)
- 機器認証を解除する
- ディスクを取り出す
- アカウントの登録情報を削除する
- 本体をクリーニングする
それぞれ解説します。
PS PLUSの解約(完全にPS5を手放す場合)
PS5を完全に手放して、今後Playstationのゲームをしない場合はPS PLUSを解約しましょう。
PS5を初期化しても、PS PLUSは解約されないため、解約しないでいると料金が発生し続けます。そのため、Playstationでもう遊ばない方は、忘れずPS PLUSを解約しましょう。PS PLUSの解約手順は、以下の通りです。
- 「設定」から「ユーザーとアカウント」にアクセスする
- 「アカウント」から「お支払い方法と定額サービス」、「定額サービス」、「PlayStation PLUS」を選択する
- 「定額サービスをキャンセル」を選択する
誤って解約した場合、次回のお支払い日までに「定額サービスを再度有効にする」を選択すると、定額サービスが継続されます。
また解約後6か月間はデータが保存されているため、再びプレイしたい場合は、再度PS PLUSに加入することで遊べるようになります。
参考:Playstationサポート PlayStation®Plusの利用権を解約する方法
機器認証を解除する
PlayStation®Storeで購入したコンテンツは、利用できるPS5の台数が制限されています。そのため、機器認証を解除しなければ新しいPlaystationを購入した際に購入したコンテンツやデータを引き継げなくなる恐れがあります。
また、アカウントに紐づいた個人情報が漏洩してしまうリスクもあるため、PS5を売却や廃棄する前に、プレイステーション ネットワークアカウントとの機器認証を解除しましょう。これにより、アカウントと本体の関連付けが解かれ、新しい所有者が自分のアカウントで利用できるようになります。
機器認証の解除方法は以下の通りです。
- ホーム画面で「設定」を選択する
- 「ユーザーとアカウント」を選択する
- 「その他」から「コンテンツ共有とオフラインプレイ」を選択する
- 「無効にする」を選択する
これで機器認証が解除され、アカウントと本体の関連付けが切れます。売却や廃棄する前に、この手順を必ず行いましょう。PS5を手放したあとにリモートで登録解除することもできますが、登録解除できるのは6か月に一度だけです。
USB機器とディスクの取り外し
手元に残しておきたいものは、すべて本体から取り外しましょう。特に、本体からディスクを取り出すのを忘れないように注意してください。
ディスクを安全に取り外すには、PlayStationの電源を切り、コントローラーのボタン操作ではなく、本体のボタンを使用しましょう。
ディスクが詰まった場合は、以下の手順で取り外してください。
- 電源ボタンを3秒間長押ししてPS5の電源を切り、本体からすべてのケーブルや機器を取り外す
- 平らな場所に柔らかい布を敷いてその上に本体を置き、本体のベースを取り外す
- ディスクスロットが左側に来るように本体を置く
- PS5のディスクドライブからカバーを取り外す※
- カバーを外して見えるディスクドライブの中の黒くて丸い部品を確認する
- 部品についた黒くて丸いプラスチックフィルムを剥がすか押す
- フィルムに覆われたネジが現れる(新しい型の本体にはこのプラスチックのキャップがない場合があります)
- プラスドライバーを使用し、ネジを時計回りに回す
- ディスクのほぼ全体が見えるようになるまでネジを回す
- そっとディスクを取り外す(ディスクドライブから無理やりディスクを取り出さないように注意)
- 上端から少し離れた位置(2cm程度)から、下カバーをスライドさせて元の場所に取り付ける
- カバーが固定されると「カチッ」という音がする
- すべてのケーブルを再接続し、本体の電源を入れる
参考:Playstationサポート PS5に詰まったディスクを取り出す方法
取り外したディスクは誤って破損させないように、適切な保管場所に保管しましょう。
アカウントの登録情報を削除する
アカウントの登録情報削除は、個人情報保護のために重要です。今後Playstationネットワークサービスを利用しない場合は、アカウント登録情報を削除しましょう。
Playstationネットワークのアカウント情報を完全に削除するには、Playstationサポートの「チャットへのお問い合わせ」へ連絡しましょう。本人確認の情報を準備して、連絡しましょう。
アカウントを削除すると、今後同じIDを利用して別のアカウントを作成できなくなります。削除したアカウントで購入したコンテンツはすべて利用できなくなります。
PSNウォレットは使用できなくなり、返金もされないため、削除する前に使いきるなどしておきましょう。
本体をクリーニングする
PS5を売却する場合、本体をきれいな状態にしておくと評価が上がります。できるだけきれいにクリーニングしておきましょう。
本体の表面は、ウェットティッシュなどで汚れをふき取りましょう。ホコリが溜まりやすい排気口は、ブロアーなどでホコリを払っておくのがおすすめです。端子がある場所は、ショートしないように乾いた柔らかい布で汚れを取り除きましょう。
また、コントローラーやケーブル類などの付属品がそろっているかも確認しておきましょう。
PS5を初期化できない場合の対処法

PS5を初期化しようとしてもうまくできない場合があります。これまで紹介した方法で初期化できない場合には、以下2つの方法を試してください。
- セーフモードで初期化する
- Playstationサポートに問い合わせる
それぞれの対処法を詳しく紹介します。
セーフモードで初期化する
正常に初期化できない場合は、セーフモードで起動して、強制的に初期化しましょう。セーフモードとは、トラブルが起こった場合のトラブルシューティングのために最小の構成でPS5を起動させるモードのことです。
以下の手順でセーフモードに入り、本体を初期化しましょう。
- 電源ボタンを3秒間長押しして本体の電源を切る
- 本体の電源が切れたら電源ボタンを再び長押しする
- 2度目のビープ音が聞こえたらボタンから手を離す
- USBケーブルでコントローラーを接続しPSボタンを長押しする
- メニューから「6.PS5を初期化する」を選択する
- 初期化が完了するまで電源を切らない
参考:Playstationサポート セーフモードで本体を起動する方法
Playstationサポートに問い合わせる
セーフモードでも初期化できない場合は、Playstationサポートに問い合わせましょう。PS4やPS3ではHDDを取り外して処分できましたが、PS5は増設したM.2 SSDを取り外すことはできますが本体ストレージは取り外しできません。
初期化しないで売却すると個人情報が漏れるリスクもあるため、Playstationサポートに問い合わせるのがおすすめです。
まとめ:PS5を処分する際には必ず初期化しよう

PS5を処分する際には、必ず初期化しましょう。初期化することで、個人データの漏洩リスクを最小限に抑えられます。
初期化するとセーブデータなどは消えてしまうため、必ずバックアップを取っておきましょう。完全にPS5を手放す場合は、PS PLUSの解約やアカウントの登録情報なども忘れずに削除しましょう。
PS5を安全に処分するために、初期化が必要です。できない場合はセーフモードで強制的に初期化できることもあります。どうしてもできない場合は、Playstationサポートに連絡するのがおすすめです。
PS5を処分するなら、パソコン廃棄.comがおすすめです。一緒に送るパソコンがある場合には、送料も無料。事前連絡も不要で処分できるため、いつでも処分できることもメリットです。PlayStationの処分に困ったら、ぜひご利用ください。
パソコン廃棄.comでPlayStationの処分をする>>

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
Googleが開発した独自OS「chrome」を搭載したchromebookは、起動速度が速く、動作も軽い、さらに仕事や勉強に必要な基本的な機能を一通り兼ね備えていると人気のノート型パソコンです。
しかし、日常的に使用していると、「以前のようにサクサク動かない」と動作が重く感じることが多々あります。そこで今回は、chromebookが重くなる原因と対処法をご紹介します。「最近chromebookが重い気がする」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。
Chromebookが重い原因

chromebookが重いと感じる原因として、考えられる8つの理由を解説します。当てはまる項目はないか、チェックしてみてください。
Chrome OSのアップデート中
chromebook搭載OS「Chrome OS」がアップデート中の場合、動作が重くなることがあります。基本的にChrome OSでは、バックグラウンドでアップデートを行い、次回ログイン時にアップデートが適応される仕組みを取っているためです。
自宅のWi-Fiなど自由に通信ができる環境では、自動でアップデートが実行されます。アップデート中はバックグラウンドでディスクの書き込みや通信が行われるため、動作が重くなる場合もあるので覚えておいてください。
Chrome OSがアップデート中かどうかは、「設定」から「Chrome OSについて」を開くと確認できます。「アップデート中」と表示される場合は、Chrome OSのアップデート作業中です。多少動作が重くなるものの、特に対処する必要はないので完了するまで待つと良いでしょう。
インターネット回線が遅い
動作が重くなる原因は、chromebookだけにあるとは限りません。そもそもインターネット回線の接続が遅い場合、思うようにURLが開けず、時間がかかります。chromebookの設定を調整したり、ソフトウェアやハードウェアを変更したりしても高速化できません。
インターネット回線に原因がある場合は、ネットワーク設定を変更する必要があります。ネットワークの接続状況を確認してみましょう。
拡張機能を多分に使用している
chromebookではChromeの様々な拡張機能を使えます。便利な機能ですが、使い過ぎはchromebookが重くなる原因になるため注意が必要です。拡張機能の管理は、ブラウザのURLが表示される欄の隣にある拡張機能ボタンからできるので確認してみてください。
削除も可能ですが、動作が重い原因かどうかを判断するなら、一度OFFにしてみると良いでしょう。
アプリケーションが多い
アプリケーションのインストールのしすぎもchromebookが重くなる原因です。アプリは便利な一方で、メモリやシステムリソースの消費も多いです。
ほとんど使用していないものなどは、必要に応じてアンインストールすると良いでしょう。また、新しいアプリやソフトウェアのインストール後に動作の重さを感じるようになった場合には、一度アンインストールしてみることも大切です。
タブを開きすぎている
ブラウザで多くのタブを開いていると、動作が重くなることがあります。同時に何十ものタブを開くのは、chromebookのメモリを多く消費するからです。
特に、Googleドキュメントなど機能性の高いページは、通信量も多く、より多くのメモリを消費するため、動作が重くなりがちです。
バックグラウンドが実行されている
OSのアップデート以外にも、更新や同期、データ転送などのプロセスがバックグラウンドで実行されている場合、chrombookの動作が重くなる原因になります。特に、chromebookの作業中、YouTubeなど動画再生サイトをBGMにしている方は少なくありません。
しかし、YouTubeは常に読み込みながら再生します。複数の作業を同時に行うと、負担がかかり動作が重くなるため注意が必要です。
空き容量が少ない
chromebookのローカルディスクやSSDの容量不足も重くなる原因の1つです。基本的にchromebookのストレージは16~64GBとそれほど多くありません。そのため、空き容量が少なくなってくると、実行速度や応答速度が低下するなど影響が出ることがあります。
chromebookの動作が重いと感じた時は、一度どのくらい空き容量があるのか確認してみましょう。
ハードディスクが損傷している
ここまで紹介したどの項目にも当てはまらないのに動作が重い場合、chromebookのハードディスクが損傷している可能性があります。ハードディスクの状態を確認し、問題がないか確認しましょう。
Chromebookが重くなった時の対処法
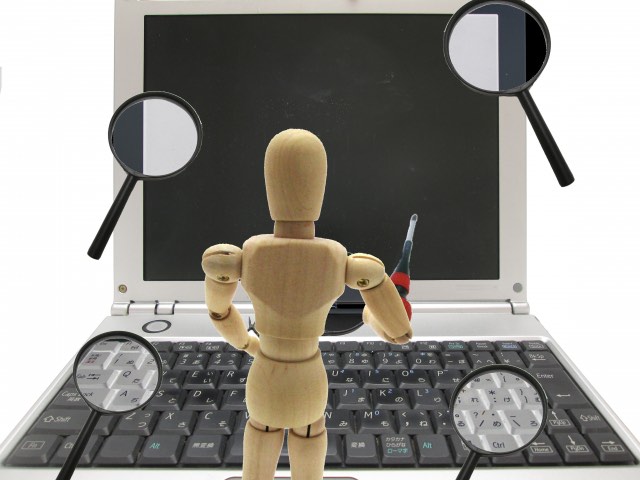
chromebookの動作が遅くなる原因がわかったところで、続いては重くなった時の対処法をご紹介します。どのように操作すれば良いのか、詳しく解説していくのでぜひchromebookの重さに悩んでいる方は、ぜひ試してみてください。
Chromebookを再起動する
chromebookを再起動するだけで、動作の遅さが改善できる場合があります。再起動はハードウェアリセットやハードリセットとも呼ばれており、chromebookは再起動すると持っているデータを一度開放するためです。
そして、データがない状態で再度起動するため、不具合の原因が情報だった場合は、再起動するだけで状態の改善が期待できるでしょう。ただし、ブラウザのタブを開いたまますると、再起動後も自動で開き、メモリを消費します。
再起動した意味がなくなる可能性があるため、再起動する際は全てのタブを閉じるよう気を付けましょう。
chromebookの再起動方法は以下の通りです。
①chromebookの電源を切る
②更新を長押ししながら、電源ボタンをタップ
③chromebookの起動後、更新を離す
chromebookはデザインによって、電源ボタンの有無や配置が変わります。
上記の方法が実行できない場合には、Googleの公式ページをチェックしてください。
なお、スリープでは解決しないため、間違えないように注意が必要です。
タスクマネージャーからプロセスを終了させる
タスクマネージャーとは、簡単にいうとパソコンの処理を管理するプログラムのことで、パソコン上で実行されているアプリを確認し、強制終了できる機能です。chromebookでは、「Everythingボタン+escボタン」を同時に押すと、タスクマネージャーを開けます。
また、chromeのブラウザの右上にある「Googlechromeの設定」→「その他のツール」からもタスクマネージャーを開けます。タスクマネージャーを起動すると、現在使用しているアプリやメモリのチェックが可能です。
必要のないものをクリックし終了させていくと、メモリが開放されるため、chromebookの重さが改善されます。メモリを多く使用しているアプリや拡張機能がある場合には、この一連の作業でchromebookが軽くなるケースが多いです。ぜひ試してみてください。
閲覧履歴を消去する
過去に見た閲覧履歴が溜まっていると、メモリを圧迫し、ブラウザの動作が重くなることがあります。ブラウザの動作が重い時は、履歴やキャッシュを削除しましょう。ちなみに、キャッシュとはアクセスしたWebサイトなどを一時的に保存する機能です。
2度目以降に表示する場合、キャッシュがあると早く開けて便利ですが、その反面、開いたページの分だけデータが溜まるため、負担がかかり動作が重くなります。閲覧履歴やキャッシュは、ブラウザ右上にある「Googlechromeの設定」から「その他ツール」→「閲覧履歴の消去」でできます。
使用していないアプリケーションを消去する
アプリがインストールされているだけでも、chromebookのストレージを使用しています。
容量のそれほど多くないchromebookでは、アプリによる負担は特に大きくなってしまうため、不要なアプリは消去すると良いでしょう。
不要なアプリは、アプリドロワーで右クリック→アンインストールで消去できます。アプリの多くはchromeブラウザから使用できるため、使用頻度の低いものや使っていないアプリはなるべく消去し、ストレージを節約しましょう。
アプリを最新の状態にする
androidアプリがchromebookの動作を重くし、速度を低下させることがあります。不要であれば消去するのが良いですが、どうしても消したくない、残しておきたい場合には、バグのない状態を維持できるよう、常に更新し、最新の状態を保ちましょう。
アプリが最新の状態かどうかは、playストアの「プロフィール」→「アプリとデバイスの管理」から確認できます。
パフォーマンス設定を最適化する
ハイパースレッディングの有効化も、chromebookの動作を軽くするために効果的な方法の1つです。ハイパースレッディングとは、アメリカのインテル社が自社製品に搭載している1つのコアを疑似的に2つに見せる技術です。
ハイパースレッディングに対応している場合、有効化すると並行した命令を実行できるため、パフォーマンスが向上する可能性があります。
パフォーマンス設定を最適化する方法は以下の通りです。
①Google chromeを開く
②アドレスバーに「chrome://flags#scheduler-configuration」と入力
③「Scheduler Configuration」で「Enables Hyper-Threading on relevant CPUs」を選択
④「Restart」を選択
なお、デフォルトの状態に戻したい時は、「Scheduler Configuration」で「Default」→「Restart」を選択してください。
chromebookでは、特にアプリやゲームが重い場合にハイパースレッディングを有効化すると、パフォーマンスの向上が期待できます。
空き容量を増やす
chromebookの空き容量が不足している場合、本体に保存してあるデータをSDカードやUSBメモリに移すのも効果的です。SDカードやUSBメモリに移せるものは移し、本体の空き容量を増やしましょう。
また、chromebookのファイルの保存先をSDカードやUSBメモリにするのも良いでしょう。ダウンロードフォルダの設定先は、以下の方法で変更できます。
①chromeブラウザの右上にある「Googlechromeの設定」を開く
②「ダウンロード」にある保存先を選択し設定
既にダウンロードしたファイルの移動も可能です。
Chrome OSをアップデートする
動作が重い原因がChrome OSにある場合、主に考えられるのは以下の理由です。
・Chrome OSのバージョンが古いまま使用している
・バグが発生している
古いバージョンのChrome OSをアップデートせずそのまま使用していると、動作が重くなる原因となります。Chrome OSは、基本的に自動で更新されますが、最新のバージョンになっているか、確認してみてください。
また、アップデートをしてから動作が重くなったと感じる時は、バグが発生している可能性があります。そのような時は、次のアップデートで修正されるため、新しいアップデートが利用可能ではないか確認してみてください。
なお、Chrome OSが最新かどうかの確認方法は以下の通りです。
①右下にあるステータストレイをクリック
②ポップアップウィンドウの上部にある「設定」をクリック
③左側のバーをスクロールし「Chrome OSについて」を選択
④Google Chrome OSの下にある「アップデートを確認」をクリック
⑤チェックプロセスを確認し、更新可能なプログラムがあればダウンロード
「お使いのchromebookは最新です」と表示される場合は、新しいバージョンが公開されていません。次の更新まで待ちましょう。更新可能なプログラムがあり、ダウンロードにデバイスの再起動が必要な場合は、指示にしたがって操作を完了してください。
拡張機能を消去する
動作の重さがインストールしすぎた拡張機能にある場合、消去によって改善が期待できることもあります。拡張機能を確認し、不要なものを削除しましょう。
拡張機能の削除方法は以下の通りです。
①chromeのブラウザを開く
②右上にあるGoogle chromeの設定を開く
③「その他のツール」→「拡張機能」を選択
もしくは、アドレスバーに「chrome://extensions」しても確認できます。
④表示された拡張機能から不要なものを選ぶ
削除するか、スイッチをオフにしても拡張機能を無効にできます。
Chrome OSを初期化する
ここまで紹介した方法を試してもchromebookが高速されない場合、最後の手段として挙げられるのはChrome OSの初期化です。初期化してもアカウントにログインすれば、アプリや設定は元通りに戻ります。しかし、ファイルが同期されないため、事前にバックアップしておきましょう。
chromebookの初期化する方法は以下の通りです。
①chromebookの「設定」を開き「詳細設定」をクリック
②「設定のリセット」から「Powerwash」を探す
③「リセット」→ポップアップで表示された「再起動」をクリック
④自動的に再起動がスタート
⑤「chromebookをリセット」→「Powerwash」をクリック
⑥「続行」をクリック
上記の流れで進めていけば、chromebookはリセットされます。
まとめ:Chromebookに負担がかからないように心がけよう!

今回は、chromebookの動作が重くなる原因と対処法をご紹介しました。
起動速度の速さや動作の軽さに定評のあるchromebookですが、使う中でどうしても重くなってしまうことがあります。もしも、chromebookの動作が重いと感じた時は、今回紹介した内容を参考に、原因を探り、対処法を実行してみてください。
なお、動作が重くなった原因は必ずしも1つとは限りません。いくつかの原因が組み合わさって重くなることもあるため、組み合わせて対処してみることをおすすめします。
また、不要なデータはこまめに削除し、chromebookの負担がかからないよう、普段から意識するようにしてください。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
Chromebookを使っている最中にフリーズすると焦ってしまうでしょう。仕事などに使える機能が揃っているなどの理由からChromebookを採用したのに、フリーズしてしまっては意味がありません。
今回は、Chromebookがフリーズする状況と自分でできる対処法を解説していきます。万が一のときに備えて対処法を把握していれば、焦らずに済むでしょう。
Chromebookがフリーズした時の状況

Chromebookがフリーズしてしまう状況はいくつか考えられます。まずは、どのような状況があるのかみていきましょう。
「Chrome OSが存在しないか破損しています」と表示される
「Chrome OSが存在しないか破損しています」と表示されるのは、そのままの意味です。Chrome OSが破損していたり、ストレージが故障していたりする可能性があります。このメッセージが表示されたら、Chrome OSのリカバリーツールを使ってOSの再インストールをしなければいけません。
リカバリーツールを使うとデータがすべて消えてしまいます。そのため、データが必要な場合は、データの復旧を行っている専門業者に依頼しましょう。
「He’s Dead, Jim!」というエラーメッセージが表示される
「He’s Dead, Jim!」というエラーメッセージが表示される場合は、システムのメモリが不足している可能性が高いです。メモリの空き容量を増やすためには、開いているタブやアプリ、使っていないそのほかのプロセスを閉じてみてください。
ChromeOSが反応しない
そもそもChromeOSが反応しないパターンもあります。そのようなときは、ハードリセットを行い、Chromebookのロックを解除しなければいけません。
正常に起動すれば問題ありません。起動しない場合は、「HP Chromebook – Chromebookオペレーティングシステムがロードされない (Chrome OS)」を確認してみてください。
ファンから異音がする
Chromebookがフリーズし、ファンから大きな音が鳴ったり、ずっと回り続けたりする場合は、パソコン自体が熱くなっている可能性が高いです。ハードウェアコンポーネントが故障している場合も、ファンから異音がします。
通気口に誇りが詰まっていないか確認し、取り除いて改善されるか試してみてください。改善されれば、熱暴走でフリーズしたと考えられます。その後も続く場合は、ハードウェアコンポーネントの故障を疑いましょう。
Chromebookがフリーズした際の対処法
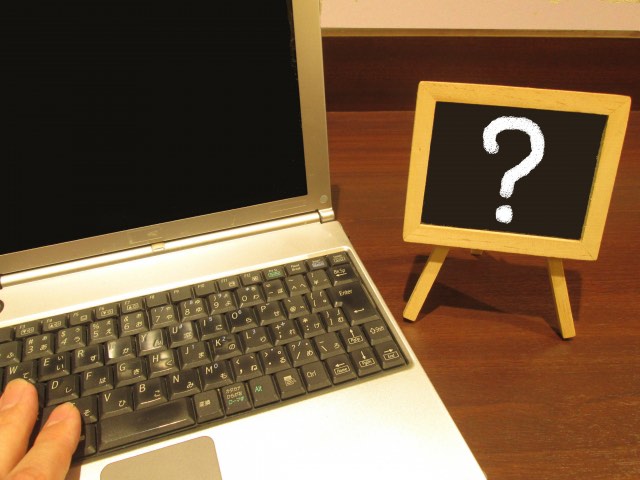
Chromebookがフリーズしたとき、自分でできる対処法を把握していれば再起動できる可能性が高くなります。具体的な対処法は以下の通りです。
タスクマネージャを起動する
1つ目は、タスクマネージャを起動する方法です。Windowsパソコンがフリーズしてしまったときと同じく、Chromebookでも有効な方法となっています。特定のアプリケーションがフリーズする場合は、タスクマネージャから終了させられるので、試してみてください。
タスクマネージャを起動する方法は以下の2つです。
・「Esc」キー+「検索」キー(虫眼鏡マーク)の同時押し
・Chromeブラウザ右上の「…」から「その他ツール」内の「タスクマネージャ」を起動
Windowsの「Ctrl + Alt + Delete」と違うので、間違えないようにしてください。
リカバリモードで再起動する
2つ目は、リカバリモードで再起動する方法です。電源ボタンを押しても反応がない場合は、この方法を試してみてください。やり方は以下の通りです。
・「Esc」キーと「更新」キーを押しながら「電源」ボタンを押し、「電源」ボタンを放す
・「ChromeOSが見つからないか破損しています」「Chrome OS is missing or damaged」などと表示されたら、「Esc」キーと「更新」キーも放す
・「電源」ボタンを再度押すと、再起動がスタートする
ハードウェアをリセットする
3つ目は、ハードウェアをリセットする方法です。ハードリセットで再起動すると、改善される場合があります。ハードリセットの手順は以下の通りです。
・Chromebookの電源を切る。
・「更新」キーを押しつつ「電源」ボタンを押す
・Chromebookが起動したら「更新」キーから指を放す
再起動する
4つ目は、再起動する方法です。これまでの方法を試しても改善されない場合は、しばらく放置し、バッテリーを0%にして強制終了させます。その後、電源アダプターを指した状態で再度起動してみましょう。
問題なく起動すれば大丈夫です。しかし、突然電源が落ちる、エラーが出るなどの場合は、内部に問題が生じている可能性があるので、修理に出すのがおすすめです。
chromebookのメーカーサポート

chromebookに何らかの不具合が生じ、自力での解決が難しい場合は、メーカーサポートを受けられます。続いては、各メーカーがどのようなサポートを行っているのかみていきましょう。
Acerの場合
Acerのサポート対象となるのは、以下の機器です。
・日本国内で日本エイサーが販売しているデスクトップPCまたはノートPC
・日本エイサーの保証書が添付された各種周辺機器
海外の製品やOEM製品、他社製品に関する質問には答えていません。問い合わせ方法は、オンラインサポートや電話サポート、メール・チャットによるサポートがあります。問い合わせ先は、日本エイサーカスタマーサービスセンターです。
ASUSの場合
ASUSでは、オンライン修理受付サービスや修理・お預かり品の状況確認などのサービスを提供しています。オンライン修理受付サービスを利用するには、製品のシリアル番号を入力しなければいけません。また、申し込みをする際に購入照明のコピーも必要になるので、忘れずに用意しておいてください。
また、ASUSアカウントにサインインすると、チャットでの問い合わせも可能となります。
富士通クライアント コンピューティングの場合
富士通クライアント コンピューティングの場合は、使い方や困りごとに関する相談をチャットやメール、電話で受け付けています。不具合が生じてどのように対応すべきかわからない場合は、このいずれかの方法でメーカーに問い合わせてみましょう。
故障や修理に関する窓口は別で用意されています。故障や修理に関する窓口を利用する際は、「ネットで故障診断」を行って本当に故障しているのか確認するようにしてください。また、保証期間や修理規定などにも目を通しておきましょう。
HPの場合
HPでは、Web修理受付を行っています。Web修理受付を依頼する場合は、サインインが必要です。そのほかに、預かり修理や出張修理、部品送付、消耗品購入などのサービスも提供しています。
Lenovoの場合
Lenovoの場合は、シリアル番号や製品を選択すると問い合わせや修理申し込みができるようになっています。Lenovo PC を使用している場合、「製品を検出する」ボタンでシリアル番号の検出ができるので、どこで確認すればいいのかわからない場合は活用してみてください。利用可能なサポートは、ラインチャットサポートやWebチャットサポート、eメールサポートなどです。
子どもが壊さないために指導すべきこと

chromebookは子どもが使用するケースも多くみられます。子どもはパソコンの扱い方に慣れていないため、壊してしまうリスクが高いです。そのため続いては、子どもが壊さないために指導すべきことをピックアップしてご紹介します。
机などから落とすなどしない
子どもがノートパソコンを使っていて壊す要因として多いのは、落下です。パソコンを使っていないとき、机の上にあるノートや教科書などの奥にあるパソコンを押してしまい、落下するなどのパターンも珍しくありません。落下による衝撃で基盤にダメージが加わったり、液晶パネルが割れてしまったりする可能性があります。
学校方持ち帰る際に壊す場合もないとは言い切れないでしょう。ノートパソコンを入れたままランドセルを放り投げるなどすると、落としたときのようにダメージが加わります。
水をこぼしてしまう
パソコンは電子機器なので、水をこぼしてしまうのは故障の原因になります。子どもは特に不注意などで水などの飲み物をこぼす可能性が高いです。こぼしてしまってからでは遅いので、パソコン作業をするときは水筒など蓋を締められるものに飲み物を入れるなどの工夫が必要になるでしょう。
コネクタに物を入れない
子どもが使っているパソコンで多い故障には、USB端子などのコネクタにシャープペンシルの芯や消しゴムを入れてしまうなどの原因もあります。端子口に鉛筆の芯が偶然入り、ショートや発煙するケースもあるので、注意が必要です。端子部に入り込んだごみを取るためにシャープペンで取ろうとして、同じような状況になった事例もあります。
また、端子の中に消しゴムなどを無理やり入れるなど、大人では考えられない行動をとる場合もあるので、油断は禁物です。
修理業者に依頼するメリットやメーカーとの違い

chromebookがフリーズするなどして使えなくなってしまった場合、修理が必要となります。修理はメーカーへの依頼も可能ですが、修理業者に依頼する場合もあるでしょう。続いては、修理業者に依頼するメリットやメーカーとの違いを解説していきます。
修理業者に依頼するメリット
修理業者に依頼すると、メーカーに依頼するよりも早く対応してもらえます。これは、メーカーとの大きな違いであり、修理業者ならではのメリットです。購入店やメーカーの保証書を紛失してしまった場合でも、修理業者なら対応してもらえます。
業者によっては、即日引き取りが可能なところもあるので、すぐに何とかしたいなどのニーズにも応えてもらえるでしょう。出張修理を行っている業者であれば、店舗に出向かなくても直してもらえます。
修理業者とメーカーの違い① 付帯サービス
修理業者とメーカーでは、付帯サービスが異なります。
修理業者は、データのバックアップや対象部分以外の修理、本体のクリーンアップなどに対応しているところが多いです。追加で費用は掛かってしまいますが、より使いやすい状態にしてもらえます。パソコンに関する専門知識を持つスタッフも在籍しているので、自作パソコンや複数のメーカーにも対応している業者が多いのも魅力の1つでしょう。
一方メーカーは、付帯サービスの提供を行っていないケースが多いです。自社製品しか取り扱っていないこと、対象部分以外の修理が行わないこと、なども業者との大きな違いとして挙げられます。修理時にはリカバリーをするので、データも消えてしまうでしょう。
バックアップなど付帯サービスを充実させたいのであれば、メーカーではなくパソコン修理業者に依頼するのがおすすめです。
修理業者とメーカーの違い② 安全性や信頼性
安全性や信頼性も大きな違いとして挙げられるでしょう。
パソコンの修理業者の中には、全国展開している大手企業もあり、サービスの質や信頼性などは向上しています。専門的なスキルを持つスタッフが在籍しているところもあり、安心してお任せできるケースが多いです。しかし中には、相場以上の修理費用を請求する悪徳業者もあるので注意しなければいけません。
メーカーでは、純正の部品を使った修理を行うので、安全性や信頼性は確実です。保証期間内であれば、無償修理の対象となる場合もあり、コストをかけずに直せる可能性もあります。安全性や信頼性を何よりも重視したいなら、メーカー一択でしょう。
フリーズ以外に多いトラブル

chromebookは、フリーズ以外にも多くみられるトラブルがあります。最後に、フリーズ以外に多いトラブルにはどのようなものがあるのかみていきましょう。
モバイル版のWebページが表示される
ChromebookにはGoogle ChromeのPC用ブラウザが搭載されているのですが、毎回モバイル版のWebページが表示される場合があります。これは、サイト側がスマートフォンからアクセスしていると誤って認識していることが原因です。
そのような場合は、「User Agent Switcher and Manager」を使ってみてください。サードパーティが提供している拡張機能で、パソコンからアクセスしているとサイト側に思わせます。この拡張機能はインストールするだけで簡単に使えるので、モバイル版のWebページが表示されると悩んでいる場合におすすめです。
ストレージを空けられない
Chrome OSは、クラウドを自分のものとして使用する前提になっています。そのため、出荷時のストレージは32GBもしくは64GBです。ウェブブラウザしか機能がない場合はそれでも十分ですが、AndroidのゲームやLinuxソフトウェア、Googleの開発プラットフォーム「Android Studio」などをインストールするのは難しいでしょう。
そのようなときは、Chromebookのファイルマネージャー「ファイル」で、クラウドストレージを設定しておくのがおすすめです。ストレージが足りないときのデータ移行がスムーズになり、必要なときに取り出しやすくなります。
まとめ:フリーズの原因がわからない際は各種サポートセンターに問い合わせよう!

Chromebookがフリーズしてしまったときの対処法を試しても改善されない、原因がどこにあるかわからないケースもあるでしょう。そのようなときは、サポートセンターに問い合わせてみてください。サポートセンターに問い合わせることで、ほかの対処法を教えてもらえる場合があります。
適切なアドバイスを受け、それに沿って再起動などを再度試してみると改善される可能性も考えられるでしょう。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
Dellのパソコンで作業しているときに突然フリーズして困った経験がある方も多いのではないでしょうか?Dell製品に限らず、パソコンはさまざまなことが原因でフリーズします。
今回は、Dellのパソコンがフリーズする原因と対処法、事前にできる対策をご紹介します。Dellのフリーズを解消したい方はもちろん、事前にフリーズ対策をしておきたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
Dellのパソコンがフリーズする原因

まずは、Dellのパソコンがフリーズする原因を見ていきましょう。
アップデートの不具合
WindowsのOSをアップデートしたタイミングでフリーズするケースがあります。特にWindows10、Windows11にアップデートをしたときに起こることが多いです。
OSのアップデートをすると、パソコンを動作させる役割を持つドライバーが大きく変化します。その大きな変化によってドライバーが正常に動作しなくなり、パソコンがフリーズしてしまう可能性があるでしょう。
電源関連の故障
パソコンを動かすために欠かせない電源が確保できていない場合もフリーズするケースがあります。電源ケーブルが断線していたり、電源タップが故障していたりすると、動作が安定しないほか、起動できないことも多いです。
メモリの不足
一度にたくさんのアプリやソフトなどを使うことでフリーズしてしまう場合は、メモリ不足が原因として考えられるでしょう。パソコンによって一度に行える処理の量が変わります。8GB以下だとExcelやWord、インターネットの利用であれば、問題なく動作します。
しかし、8GB以下のパソコンで動画編集やゲームなどを一度に動かそうとすると、メモリが足りず、フリーズしてしまう可能性が高いです。
アプリケーションのエラー
新しくアプリをインストールしたタイミングや、特定のアプリを起動するとフリーズが発生する場合は、アプリのエラーが原因かもしれません。アプリのエラーによるフリーズは、OSのアップデート後に起こることもあります。
理由としては、アプリのドライバーがパソコンの動作を妨げている、OSアップデート後アプリのバージョンが合わなくなってしまったなどが挙げられます。
ウイルス感染
ウイルス感染によってフリーズするケースも多いです。悪質なウイルスに感染した場合、パソコンが正常に動作するために必要なプログラムを壊されてしまい、最悪の場合、パソコンの起動すらできなくなるケースもあります。
フリーズさせるタイプのウイルスは、メモリや命令を処理するCPUにダメージを与えてくるでしょう。その結果、画面が固まって動かなくなってしまいます。
ハードディスクの故障
データ保存に欠かせないハードディスクが劣化したり、故障したりしている場合もフリーズが頻発します。特に毎日パソコンで作業している場合は、読みとる量と書きこむ量が膨大になるため、寿命よりも早く故障してしまうことがあります。
パソコンのフリーズに加え、本体から異音がしたり何度もアプリが落ちてしまったりするときは、ハードディスクの故障を疑ってみましょう。
マザーボードの不具合
パソコンの土台、中心パーツと言われるマザーボードの不具合も原因として考えられるでしょう。パソコンに欠かせないパーツとはいえ、マザーボードにも寿命があります。3~5年使い続けている場合は、マザーボードの劣化によるフリーズかもしれません。
ほかにも、マザーボードにまで水が入った、高温や低温が続いた、高い所から落としたなど、マザーボードが故障する原因はさまざまです。
オペレーションシステムの不具合
パソコンのシステム全体を管理するオペレーションシステムに不具合がある場合、フリーズケースがあります。オペレーションシステムとは、OSの正式名称です。OSのアップデートがうまくいかなかったときや、ソフトウェアに異常があるとき、OSに不具合が発生します。
ディスプレイ関連の故障
ディスプレイ自体が故障しており、画面が正常に動かないケースも少なくありません。特にデスクトップパソコンの場合は、映像を画面に反映させるためのケーブルが断線を起こしていたり、モニターが故障していたりすると、フリーズしているように見えることがあります。
デバイス接続の故障
突然文字が打てなくなったり、マウスを動かしても反応しなかったりする場合は、接続しているデバイスの故障が考えられます。パソコン自体がフリーズしている可能性は低いでしょう。電池を入れ替えてみたり、新しいキーボードやマウスに交換したりして、正常に動作するか確認してみてください。
DellのPCがフリーズしてしまった際にまずやること

パソコンがフリーズすると、焦って強制シャットダウンをしてしまう方は多いです。しかし、強制シャットダウンをする前にできることがあります。パソコンがフリーズしたときは、以下の方法を試してみてください。
デバイスの接続を確認する
デバイスが接続されていない、何かの拍子でパソコンがデバイスを認識できなくなっているなどのケースもあります。まずは、キーボードやマウスがパソコンと接続されているかをチェックしましょう。ケーブルなら抜き差し、ワイヤレス接続なら再接続をしてみてください。
しばらくの間待ってみる
デバイスの接続に問題がなくても、すぐに強制終了したり電源を抜いたりするのは危険です。フリーズした場合、3時間は待ってみましょう。6時間以上経っても状況が好転しない場合は、そのほかの対処法を試してみてください。
特にメモリが少ないパソコンの場合、アプリなどの処理に時間がかかってしまい、パソコンが重くなることは多いです。アプリの処理が原因であれば、5~10分で回復するでしょう。マウスを動かすと反応する、読み込み中のマークが動いているときはフリーズしているわけではないため、しばらくの間待ってみてください。
エラーコードの表示があれば調べてみる
Dellのパソコンは、フリーズするとエラーコードが表示されるケースがあります。画面に表示されるエラーコードを検索すると、フリーズの原因が特定できるだけでなく、対処法もチェック可能です。
公式サイトでチェックすればそのエラーコードが出たとき、どういった手順で改善できるのかも詳しく書かれているため、より適切な対処ができます。エラーコードによっては、パーツの交換やパソコンの修理が必要になることもあるので注意しましょう。
DellのPCがフリーズした際の対処法

次に、DellのPCがフリーズした際の対処法を見ていきましょう。
ハードウェア診断プログラムを起動させる
フリーズの原因が特定できない場合は、ハードウェア診断プログラムを起動させましょう。
Dellのパソコンにはソフトウェア「SupportAssist」が備わっています。これには、不具合や故障が起きたときに知らせてくれる機能が備わっており、フリーズしたときにも焦らず対処できることから、とても便利なものとして認知度も高いです。
しかし、より包括的にパソコンを診断したい場合は、ハードウェア診断プログラムを起動させてみましょう。ハードウェア診断プログラムは、下記の手順で起動できます。
①パソコンを再起動する
②ロゴ画面が表示されたら「F12」キーを押す
③矢印キーを操作して「Diagnostics(診断)」を選択し、「Enter」キーを押す
④表示された指示に従って回答していく
Dell製PCは、オンライン診断テストを実行できます。オンライン診断テストは、下記の手順に沿って実行してみましょう。
①Dellサポートサイトを開き、Dell製品を手動で選択またはタグやコード、シリアル番号で検索する
②「Diagnostics(診断)」を選択する
③「Run Full Test(フルテスト)」を実行する
強制シャットダウンをする
しばらく待ってみても状況が変わらない場合は、パソコンを強制シャットダウンしましょう。Dell製品の多くは電源ボタンを長押しすると強制シャットダウンできます。しかし「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Delete」キーの3つを同時に押してメニューが表示される場合は、そこからシャットダウンを選択してください。
電源ボタンの長押しによる強制シャットダウンは最終手段だと考えておくのがおすすめです。しかし、フリーズはパソコンの再起動によって改善するケースも多くあります。理由は、誤作動で起動したアプリや見えない場所で動作しているシステムをストップさせられるためです。
アプリやシステムを終了させることで、処理に追われていたメモリに余裕が生まれ、パソコンが正常に動作します。特に、パソコンを長時間使っていたときにフリーズした場合は、再起動で解決されることが多いです。
全てのデバイスを外す
パソコンの電源を切った後にマウスとキーボードだけでなく、USBドライブやプリンター、Webカメラ、SDカードなど、全てのデバイスをパソコンから外しましょう。パソコンのデバイスは正しく取り付けられていても、障害をもたらすケースがあります。
使っているデバイスが、パソコンのメモリやハードディスクなどに異常がないかを診断する「自己診断」に影響していることもあるでしょう。デバイスを取り外した後、再起動して正常に動作すれば、デバイスが自己診断の完了を妨げていた可能性があります。どのデバイスが原因となっているかを特定し、原因となるものは新しいものや相性がいいものに交換しましょう。
電源ケーブルから外し、バッテリーを取り外す
バッテリーを取り外すのもトラブル解決に有効です。接触不良などが原因で、動作が不安定になっている可能性があるからです。
バッテリーを取り外すときは、パソコンから電源ケーブルを外してから作業を行うようにしましょう。また、バッテリーの取り外し方はパソコンによって異なるため、安全に取り外せるよう、マニュアルなどで手順を確認してください。
放電する
パソコンの内部に電気が溜まり過ぎると、トラブルの原因になることがあります。帯電を解消するためには、放電を行う必要があります。フリーズ以外に突然電源が切れる、画面が真っ暗になるなどのトラブルが多い場合は、以下の手順で放電を行ってみてください。
①電源を切る
②ケーブルやデバイスを全て取り外す
③電源ボタンを15秒~20秒押し続ける
④1時間ほど放置する
Windowsのアップデートを行う
WindowsのOSアップデート後にフリーズするケースをご紹介しましたが、反対にOSをアップデートするとフリーズを改善できる場合もあります。OSのアップデートは、下記の手順で実行できます。
①「設定」を開く
②「更新セキュリティ」の「Windows Update」から「更新プログラムをチェック」を選択する
セーフモードで原因を調べる
セーフモードは、必要最低限の機能だけが使えるモードになります。不具合の原因を特定するための診断機能も使えるので、フリーズしたときにも便利です。セーフモードでの起動が可能であれば、ソフトウェアやアプリ、ハードウェアなど、どこに原因があるのかを調べてみましょう。
アプリケーションをアンインストール・再インストールする
セーフモードで診断した結果、特定のアプリに原因があれば、アンインストールや再インストールを試してみましょう。アンインストールで改善、再インストールで再度フリーズする場合は、そのアプリに不具合がある可能性が高いです。
マルウェアやウイルスの侵入を確認する
セキュリティ対策に特化したソフトを使い、マルウェアやウイルスの侵入を確認しましょう。ウイルスが見つかった場合、しっかりと除去すればフリーズが解消する可能性があります。
ここで注意したいのは、使用するセキュリティ対策ソフトを1種類に絞ることです。複数のセキュリティ対策ソフトを起動していると、動作が安定しづらくなり、トラブルが起きやすくなります。
通気孔のゴミを取り除く
パソコンの動作を不安定にする外的要因として挙げられるのは、浸水だけではありません。ホコリや異物が通気孔を塞いでしまうと、パソコンに熱がこもり、トラブルが起きやすくなってしまいます。しばらく掃除をしていない、どの方法を試しても改善しない場合は、通気孔のゴミを取り除いてみましょう。
DellのPCをフリーズさせない対策

ここからは、DellのPCをフリーズさせない対策方法をご紹介します。
定期的にシステムメンテナンスを行う
ファイルのクリーンアップやチェックディスクなどを定期的に行い、不要なファイルの削除・ドライブの修復を行いましょう。システムメンテナンスを行うことで、容量やメモリに余裕が生まれ、フリーズしにくい環境を作れます。
高湿・高温を避ける
パソコンに熱がこもるとトラブルが起きやすくなるため、高湿・高温が避けられる環境に設置しましょう。特に直射日光や通気口付近に物を置くのは厳禁です。結露による故障もあるため、寒暖差が生じないような環境づくりを心掛けてください。
使わないアプリケーションは消去する
使っていないアプリや、しばらく使う予定のないアプリは消去しておくのがおすすめです。メモリはもちろん、容量を圧迫してしまい、フリーズにつながる恐れがあります。定期的にアプリの整理を行うこともフリーズ対策として有効です。
ソフトウェアやドライバーを最新する
ソフトウェアやドライバーは、自動でアップデートされるものが多いことから、わざわざチェックしない方も多いでしょう。中には自動アップデートされないものもあるため、定期的に最新のものがないかチェックしてみてください。
ウイルス対策ソフトをインストールする
ウイルスに感染したらすぐに分かる・早急に駆除できるウイルス対策ソフトをインストールしておくことも対策の1つです。ウイルス対策ソフトの中には、体験版が用意されているものも多いため、好みのソフトを見つけやすいでしょう。インストールする前にメモリ不足にならないよう、チェックしておくことも大切です。
ドライブのデフラグと最適化を行う
同じパソコンを長期にわたって使用している場合、1つのデータが複数の場所に書き込まれてしまうことがあります。書き込まれる場所が分散されることによって、動作するまでに時間がかかってしまったり、フリーズしてしまったりするトラブルが起きやすくなります。これを改善してくれるシステムメンテナンスを「デフラグ」と言います。
デフラグを頻繁に行うとハードディスクに大きな負担がかかってしまうため、半年~1年に1回程度の頻度でメンテナンスを行うのがおすすめです。
メモリ容量を増設する
高いスペックが求められるアプリやソフトを使いたい、快適に作業したい場合は、メモリ容量の増設も視野に入れましょう。メモリが足りず、フリーズが頻発する場合は、増設によって改善できるかもしれません。
ただし、メモリの増設は知識や技術が求められるため、素人には難易度が高いです。安全に増設したい場合は、パソコンの修理業者に依頼するのがおすすめです。
まとめ:フリーズした際にはまず故障の原因を探ろう!

今回は、Dellのパソコンがフリーズする原因や対処法をご紹介しました。パソコンがフリーズしたときはまずその原因を特定し、適切に対処しましょう。間違った対応をしてしまうと、フリーズを解消できても大切なデータなどが消えてしまう可能性があります。
フリーズする原因によって適切な対処方法があるため、焦らずじっくり原因を見極めてみてください。また、突然のフリーズを防げるよう、普段から対策しておくことも重要です。ぜひ今回ご紹介した「DellのPCをフリーズさせない対策」を参考にして、フリーズ対策を行ってみてください。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
アメリカ発祥のDellは世界中にたくさんのユーザーがいるパソコンの有名メーカーです。動画編集やゲームなど、幅広い用途で使用でき、シーンや予算に合わせて自分に適したパソコンが選べ、なおかつコストパフォーマンスにも優れているなどの魅力的な特徴を持っています。しかし、使用していると不具合が発生するケースもあります。特に「起動せず画面が黒いまま動かない」「急に画面が真っ暗になった」など、ブラック画面による不具合が発生すると、故障したのかと不安になる方もいるはずです。
そこで今回は、Dellのパソコンの画面が真っ暗になる原因や画面が黒くなったまま動かないときに確認すべきポイントなどを解説していきます。対処法もご紹介していくので、画面が暗くなる症状でお悩みの方は、ぜひチェックしてみてください。
Dellの画面が真っ暗になる原因

Dellのパソコン画面が真っ暗になったまま動かない原因は以下の通りです。
・電気元の故障
・ハードウェアやアクセサリーの故障
・システムの破壊
それぞれの原因の詳細を確認していきましょう。
電源元の故障
パソコンの電源供給関連に問題があれば、ラップトップ画面が真っ暗になるケースもあります。新しい機器を使用した際にモニターがブラックアウトを起こす可能性もあるので注意してください。
また、ピープ音や電源ランプがオレンジ色に点滅していると電源元が故障している可能性があります。その場合、電源ユニットの故障や静電気の帯電などが原因です。
ハードウェアやアクセサリー故障
ディスプレイやマザーボード、グラフィックスカードやメモリなどのパーツが故障している場合も画面が黒くなり動かなくなる可能性があります。アクセサリーとマザーボードの接続が緩んでいるまたは不適切など状態でもブラックアウトを起こすケースがあるので確認してみましょう。
また、マザーボードの電解コンデンサの液漏れ、膨張が見られる場合は交換や修理が必要です。交換や修理を行えば復活するかもしれませんが、場合によっては機器そのものが交換されてしまい、データが初期化されてしまう危険性もあるので注意してください。
システム破損
パソコンの起動に関連するデータやプログラムが破壊された状態がシステム破損です。HDD内部のデータが異常をきたしている状態となり、「倫理障害」とも言われています。
・突然の電源遮断
・不適切な操作によるデータの削除
上記が原因でシステム破損は引き起こされます。アップデート中に電源を切る行為や不適切な手順によるパソコンの起動には十分に注意してください。システム破損は、ウイルスが原因となっているケースもあります。ウイルスに感染しウイルスシステムが破損する場合もあるので、自力での対処が難しいときには業者に依頼して対処してもらいましょう。
記憶装置破損
パソコンのデータを保存する記憶装置(HDD/SSD)に破損が起きている際も画面が真っ暗になる、画面が黒くなったまま動かないなどの症状を引き起こす可能性があります。
・パソコンやハードディスクを落とす
・落雷が原因の電力供給の異常
・熱や湿度
・HDDの経年劣化や寿命
上記のような物理障害によって引き起こされます。HDD/SSDの寿命は3年~5年です。長期間使用し続ければディスク部品に傷が付き、データが揮発するなどしてパソコンが起動しなくなる危険性もあります。
物理障害を起こしたHDD/SSDの修復は自力では難しく高度な技術が必要です。データが消失してしまう可能性もあるので、業者に相談した方が安全です。
Dellの画面が真っ暗の際に確認すること

Dellのパソコン画面が真っ暗になり動かなくなった場合は、パソコンの故障が原因の場合もありますが、違うことが原因かもしれません。以下を確認してパソコンの状態に問題がないか、まずは確認してみてください。
スリープモードの状態
パソコンの画面が真っ暗になっていれば不安を感じてしまいますが、一度「スリープモード」の状態でないか確認してみましょう。スリープモードは省電力機能の1つで、電力の消費を抑えるためにパソコンの動作を一時的に停止する機能です。スリープモードの状態であると画面が暗くなります。
解除する方法としては、マウスやキーボードを動かすだけなので試してみてください。もし、マウスの操作やキーボードの操作でも解除されない場合は、電源ボタンを押すと解除されるケースがあります。
スリープモードは、設定を変えると時間を調整できます。Windows10での調整方法は以下の通りです。
① 「スタート」をクリックして「設定」を選びます。
② 「システム」をクリックして移動してください。
③ 「電源とスリープ」を選択して「画面」で画面をオフにするまでの時間を選択してください。
④ 「スリープ」でパソコンを使用していないときにスリープモードの状態にするまでの時間を選択しましょう。
上記の方法で設定を変えられるので、スリープモードになるまでの時間が短いと感じた場合は調整してみましょう。
電源ランプの色
Dellのパソコンに不具合が起きたとき、電源ランプによって状態を確認できます。電源ランプの点灯パターンは、モデルによって異なるので画面が真っ暗のまま動かなくなった際には、説明書を確認してランプの色を確認してみてください。Dell OptiPlexシリーズの点灯パターンは以下の通りです。
・ランプが消灯している:電源がオフになっている
・ランプがオレンジ色に点滅している:初期状態もしくはエラーが発生している
・ランプがオレンジ色に点灯している:電源装置が正常な状態
・ランプが白色に点滅している:電源供給が少なくなっている
・ランプが白く点灯している:通常の電源状態
ランプが白く点灯しているなら、パソコンが正常に起動されている証拠です。それでも画面が黒くなっているときには、パネルやモニターの故障を疑ってください。白点滅の状態であれば、充電してから再び起動すると解消されるケースもあります。
Dellの画面が真っ暗な際の対処法

Dellのパソコン画面が真っ暗になる問題の対処法として9つの方法をご紹介していきます。スリープモードでもなく、再起動をしても問題が解消されない場合は、以下の方法を試して対処してみてください。
強制シャットダウンを行う
画面が黒くなり起動しない場合、まずは強制シャットダウンでブラック画面が解消されるか試してみましょう。
① ライトが消灯するまで電源ボタンを長押しします。
② 電源が完全にオフになったのを確認後、ACアダプターや電源コード、バッテリーなどを電源から外してください。
③ 再度電源ボタンを長押ししてコンピュータの残りの電力を使い果たしましょう。(約60秒)
④ メディアカードやUディスク、USBフラッシュドライブなど、接続されている外部デバイスや周辺機器を取り外してください。
⑤ バッテリーを元に戻して電源コードとACアダプターを再度差し込みます。
⑥ Dellの電源を入れて黒い画面が表示されるか確認してみてください。
普段通りに映るようであれば、そのまま使用してみましょう。
ディスプレイを新しいものにする
ディスプレイ不良であれば、新しいディスプレイに交換するだけで問題を解消できます。まずは、以下の方法でディスプレイに不具合がないか確認してみてください。
① 上記の強制シャットダウンをしてから再度Dellの電源を入れてください。
② 起動プロセス中に電源ボタンの上にあるLEDの表示があるかチェックしてみましょう。
③ 電源ボタンやCaps LockのLEDが点灯していない場合は、外付けモニターをWindowsに接続し、正常に表示されるかチェックしてください。
④ 正常に表示されない場合、ディスプレイに不具合があるので新しいものと交換しましょう。
セーフモードで立ち上げる
必要最低限の構成でパソコンを起動させる機能がセーフモードです。不具合の原因を見つける際にも役立てられます。
① パソコンの電源ボタンを長押しして電源を切ってください。
② パソコンの電源を入れます。
③ ロゴが表示される前に「Shift + F8キー」を押すと回復モードメニューに入ります。回復モードにならない場合は、再度上記手順を繰り返してみてください。
④ 「詳しい修復オプションを表示する」または「詳細オプション」を選択して「トラブルシューティング」に進んでください。
⑤ トラブルシューティング画面で「詳細オプション」をクリックします。
⑥ 「スタートアップ設定」「再起動」の順に進みましょう。
⑦ 起動したらキーボードの「4」もしくは「F4」を押してセーフモードで起動してみましょう。ネットワークに接続したい場合は、「5」または「F5」を押してください。
正常にセーフモードで起動した場合はMサードパーティのアプリケーションや古いグラフィックドライバー、ウイルスなどが原因で画面が黒くなっている可能性があります。対応の修正法をとって問題を解決しましょう。
Windowsシステムを再インストールする
Windowsを再インストールする対処法でも問題の解消が期待できますが、個人情報や設定などの必要なデータが削除されてしまうので、再インストールをする前にデータのバックアップを行いましょう。Windows10の再インストール方法は以下の通りです。
① BIOS設定を変更します。パソコンの電源を入れてロゴが表示されている間に「F2」を押してBIOSを起動させてください。
② Windows10インストールメディアから起動するように設定します。
③ Windows10のセットアップ画面が表示されたら言語や時刻、通貨の形式や入力方式、キーボードの種類などのセットアップ項目を確認し、「次へ」に進みます。
④ 「今すぐインストール」をクリックしてください。
⑤ Windows10のプロダクトキーを入力し、Windows10のエディション項目を選んで「次へ」に進み、ライセンス条項に同意します。
⑥ 「カスタム:Windowsのみをインストールする(詳細設定)(C)」を選択します。
⑦ 「新規」「次へ」「適用」の順にクリックしてください。
⑧ 「OK」をクリックしてWindows10をインストールするドライブ項目を選んで「次へ」に進みます。
放電を行う
画面が暗くてもカーソルのみ動く場合やカーソルが点滅している場合は帯電が原因の可能性があります。その場合は放電をして起動を促してみてください。
① パソコンの電源を切りましょう。
② ACアダプターとバッテリーを外してください。
③ 数分放置します。
④ 放置後、ACアダプターとバッテリーを再び取り付けます。
⑤ パソコンの電源を入れてください。
以上の方法で起動すれば帯電が原因の可能性が高いです。起動後、異常が無ければそのまま使用できます。
外部モニターに接続する
・電源ランプが白色に点灯している
・画面が突然真っ暗になった
などのケースでは、ディスプレイの故障が疑われるので、外部モニターに接続をして問題が解消するか確認してみてください。ディスプレイの不具合確認方法は前述した「ディスプレイを新しいものにする」を参考にチェックしてみてください。ディスプレイが原因であれば交換で解決しますが、そのほかの異常が原因の可能性もあります。詳しい原因を知りたい場合は、業者に確認してもらった方が部品交換もできるので、的確に対処できます。
グラフィックドライバを再起動させる
電源がオンになっても黒い画面のままであればグラフィックドライバーとシステムの接続で問題がある場合もあります。再起動をして問題解決できるか確認してみましょう。
① 「Windows + Ctrl + Shift + B」を同時に押してください。
② 再起動プロセスが完了するまで待機します。再起動後に解消される可能性がありますが、万が一解消されない場合は、以下の手順を実行してみましょう。
③ 「Win+R」を同時に押して実行ウィンドウを表示させます。
④ 編集ボックスに「msc」と入力してエンターキーを押してください。
⑤ デバイスマネージャ内の「ディスプレイアダプター」を選択して右クリックをして「ドライバーの更新」に進んでください。
⑥ 「ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索」オプションをクリックして画面の指示に沿って更新操作を完了させます。
h3:BIOSをリセットさせる
BIOSを工場出荷時の状態にリセットすれば問題が解消されるケースもあります。BIOSとは、マザーボードに搭載されたプログラムを指します。管理と制御を行う役割を持っています。
① パソコンの電源を入れてロゴが表示される前に「F2」キーを数回押します。
② BIOSが起動した後、「Restore Settings」もしくは「Load Defaults」をクリックしてください。機種によって表示項目に違いがあるので、表示された項目を選んで「Esc」キーを押して終了します。終了する際には「保存して終了」を忘れずにクリックしてください。
クリーンブートを実行させる
起動を鑑賞するプログラムや邪魔をするプログラムを特定する際に活用できます。
① 管理者権限でパソコンにログインして「スタート」をクリックしてください。
② 画面左下にある検索窓で「msconfig」と入力して「システム構成」を選択しダイアログを起動します。
③ 「スタートアップ」「タスクマネージャーを開く」の順に進んでください。
④ 一覧に表示されている項目の状態が「有効」なものを選択し、画面下にある「無効にする」をクリックします。
⑤ 「有効」な項目部分を「無効」にしたらタスクマネージャーを「×」で閉じてください。
⑥ 「システム構成」ダイアログの「スタートアップ」タグに戻り、「OK」を押してパソコンを再起動させます。
プログラムの有効・無効を判断できない場合は、安易に無効にしないよう注意してください。
まとめ:以上の対処法を試しても改善されない際は、業者に連絡しよう!

Dellのパソコンの画面が真っ暗になったときの対処法を解説してきました。上記の方法を試しても改善されない場合ややり方が分からない場合は、症状の悪化やデータの消失を防ぐためにも自力で回復せずに業者に相談してみてください。専門家による知識や技術があれば、大切なパソコンのデータを失わずに問題解決が望めます。どういった症状で悩んでいるのか問い合わせを行い、的確な方法で対処してもらいましょう。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
Dellのノートパソコンはコストパフォーマンスが高く、種類も豊富なのでビジネスシーンでも取り入れられています。ビジネスでも活躍するDellのパソコンですが、ずっと使っているとバッテリーの消費が早くなってしまうものです。そうなると充電の回数も増えてしまい、使っている側は手間に感じてしまいます。
バッテリーの消費が早くなったら、バッテリー交換をしたいと考える方もいるでしょう。そこで今回は、バッテリー交換のタイミングや劣化する原因、交換方法、交換する際の注意点、交換手順を解説していきます。Dellのノートパソコンを使っていて、バッテリー交換をしたいと考えている方は参考にしてみてください。
バッテリー交換のタイミング
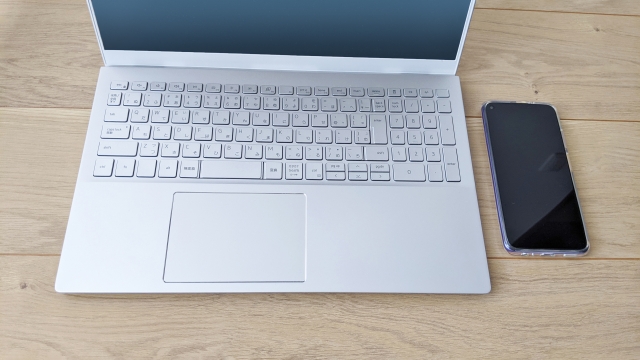
Dellのノートパソコンを使っている中で、バッテリー交換をどのようなタイミングですべきなのか迷ってしまうケースも少なくありません。そこでまずは、バッテリーの寿命や状態の確認方法から解説していきます。
バッテリーの寿命
パソコンのバッテリーは、寿命が約2~3年です。駆動時間が短くなってきたら新しいものと交換する必要性が出てきます。ただし、電源を確保できる環境でしかパソコンを使わないのであれば、そこまで気にする必要はありません。
Dellのノートパソコンを電源の確保ができない外出先でも使う場面があり、駆動時間を長くしたいのであれば、バッテリー交換を行うのがおすすめです。2年以上使っている場合は、バッテリーの寿命が近いと考えられます。
バッテリー状態の確認方法
Dellのノートパソコンは、バッテリーの状態を確認できるようになっています。オペレーティングシステム環境からチェックが可能です。Dellのノートパソコンでバッテリーの状態を確認する方法は以下のとおりです。
・Dellのノートパソコンの電源をOFFにする
・電源を入れ、Dellのロゴ画面で「F2」を押す
・左側の「General」下にある「Battery Information」を選択する
・バッテリー性能の情報を確認する
バッテリー性能の確認は、「F2」キーを押し、「Advanced」を選択する方法でも確認可能です。バッテリーの状態をチェックすれば、交換すべきか判断する指標になります。
バッテリーの劣化原因

Dellのノートパソコンに限った話ではありませんが、使い続けているとバッテリーは劣化してしまいます。続いては、ノートパソコンのバッテリーが劣化してしまう原因をみていきましょう。
経年劣化
使用年数が長くなると、経年劣化が起こります。経年劣化は、パソコンに良くない影響を及ぼします。具体的にはシステムエラーや内部パーツの破損、動作不良などの不具合です。
経年劣化を止めることはできません。しかし、ソフトウェアを最新のものにアップデートしたり、安定した動作環境を維持したりすると、安定化が可能です。メーカーや専門の業者の修理を依頼すれば、経年劣化が起こっても正常な状態を維持できます。
Dellのノートパソコンを使っていて経年劣化と思われる症状が出てきたら、早急に修理や交換を行うのがポイントです。
極度な温度変化
ノートパソコンに使われているリチウムイオン電池は、高温に弱い性質を持っています。そのため、真夏に暑い部屋の中で使ったり、持ち運び時に高温になる可能性がある車内に放置したりすると、本体が熱くなってバッテリーの劣化を早める可能性があります。デスクトップパソコンよりもパーツが詰まっているので、熱を溜め込みやすい特徴もあるので注意しなければいけません。
パソコンの頭脳とされるCPUは40~70度が適正温度とされていて、使用時の室温は16~25度が適温だと言われています。問題視されるのは高温ですが、低温過ぎるのもパソコンにとって負担となり、性能を低下させる原因になりかねません。暑過ぎず、寒過ぎない場所で使用・保管するのが望ましいです。
過度な充電
ノートパソコンのバッテリーは、充電可能回数が決まっています。Dellをはじめとした数々の製品だと、充電可能回数の目安は500回です。しかし中には、1,000回程度充電できるモデルもあるので、購入する際にバッテリーの性能も確認しておきましょう。
いずれにしても、決められた充電回数を超えると性能が低下し、最終的には充電不可となります。500回が充電可能回数だった場合、毎日充電すると約1年半で寿命を迎えるでしょう。残量が減っていないのにACアダプターにつないでおくなど、無意味に回数を増やすのは避けるのが無難です。
バッテリーの交換方法
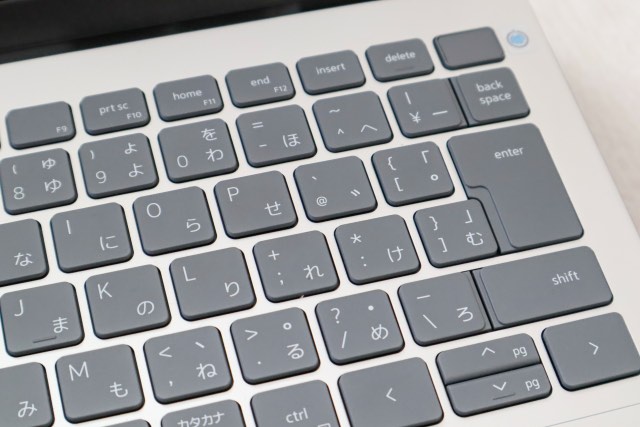
Dellのノートパソコンを使っていて、バッテリーの交換をしたいと考える場面でも出てきます。しかし、ノートパソコンのバッテリーを交換する機会はそこまで多くないので、どのようにすべきかわからない方もいるでしょう。そのため続いては、バッテリーの交換方法を解説していきます。
公式カスタマーサポートに依頼する
DELL公式サポートでは、Dellのノートパソコンを購入してから1年間の保証サポートを行っています。保証期間内なら、バッテリーの交換も無償でしてもらえるので、利用するようにしましょう。修理費用などもかかりません。
保証期間外であっても、オプションで3年間の保証サポートに加入できます。保証サポートでバッテリーの交換をしてもらう場合は、DELLの公式サイトから「サポートサービスと契約」で使っているノートパソコンの型番を入力し、手順に沿った対応をしてもらってください。
保証期間を過ぎている場合は、DELLの公式サイトから使っているノートパソコンに合うバッテリーを購入できます。
業者に依頼する
コストを抑えつつ早急にバッテリー交換をしたいなら、非正規店になりますが対応している業者に依頼する選択肢もあります。非正規店であってもパソコンに関する知識やスキルを持つプロなので、依頼しても問題ありません。メーカー保証の対象外になってしまいますが、短期間かつリーズナブルな修理をしてもらえます。
店舗によっては、即日対応も可能です。そのため、すぐにDellのノートパソコンを使わなければいけないなどの場合にも役立つでしょう。複数の業者から見積りを出してもらえば、より費用を抑えられます。
自分で交換する
Dellのノートパソコンは、ユーザー自身がバッテリーを取り外し、新しいものへと交換できるようになっています。自分で交換する場合は、使っているパソコンの型番に合うバッテリーとドライバーが必要です。メーカーや業者に依頼するわけではないので修理費用がかからないため、コストを抑えられる方法でもあります。
本体の裏に書かれている型番をチェックし、対応するバッテリーを公式サイトやネットショッピングサイトで購入します。届いたら古いバッテリーをノートパソコンから取り外し、新しいバッテリーを装着したら完了です。
自分でバッテリーを交換する際の注意点

ノートパソコンにはDellのモデルのように自分でバッテリー交換ができるものもあります。しかし、その際に注意すべきポイントもあるので、チェックしておかなければいけません。続いては、自分でバッテリーを交換する際の注意点をみていきましょう。
事前にバックアップを行う
ノートパソコンのバッテリー交換を行う際は、事前のバックアップを忘れないようにしてください。自分で交換する場合だけではなく、メーカーや業者に依頼する場合も例外ではありません。なぜなら、データを消失する可能性がゼロではないためです。
バックアップをしていないと、万が一データが消えてしまった場合、復元ができなくなります。Dellのノートパソコンのデータは、クラウドストレージや外付けのHDDやSSDに保存しておくのがおすすめです。複数の場所にバックアップを取っておくとより安心感が高まります。
作業前には放電を済ませる
バッテリーの交換を行う場合は、感電のリスクがあるので、バッテリーや電源ケーブルなどすべて外します。電源ケーブルをつないだまま作業をしてしまうと、より一層感電するリスクが高まるので注意が必要です。安全に作業するためにも、コード類をすべて外しておいてください。
バッテリー残量に関しては、25%まで減らしておくことをおすすめします。減らしておくことで、修理中に誤ってバッテリーを破損してしまったときに火災が発生するリスクを軽減できるためです。
外したネジは締め切る
バッテリー交換を行うなら、外したネジをしっかりと締め切ることも注意すべきポイントです。バッテリーを外す際に、ネジも外さなければいけないモデルがDELLのノートパソコンにはあります。ネジがしっかり締まっていないと、接続不良の原因になりかねません。
また、どこにネジが締まっていたか忘れないようにしましょう。交換する前に写真をスマホなどで撮影しておくのがおすすめです。
自分でバッテリーを交換する手順

自分でバッテリーを交換するのであれば、正しい手順を把握しておく必要があります。最後に、Dellのノートパソコンのバッテリー交換を自分で行う際の手順を解説していきましょう。
交換時に用意すべきものは以下のとおりです。
・新品のバッテリー
・パソコン本体
・精密ドライバー(星型と+ドライバー)
・静電気防止手袋(パソコンは精密機器で静電気に弱いため)
・マグネットトレイ(米粒ほどのネジを紛失しないようにするためにあると便利)
バッテリーを購入する
Dellのノートパソコンのバッテリーを交換する場合、まずは公式サイトやネットショッピングサイトで使っているモデルに対応するバッテリーを購入してください。公式サイトでは、使っているパソコンの型番を選ぶと専用のバッテリーが表示されるため、間違えることなく購入できます。
公式サイトからの購入が安心ですが、Amazonなどのネットショップでも購入可能です。「DELL バッテリー (型番)」などで検索すると、使用できるバッテリーを探せます。Amazonで普段から買い物をしている方は、探してみてください。
底面のネジを外す
購入したバッテリーが届いたら、交換作業に取り掛かりましょう。Dellのノートパソコンは、底面に8~10ヶ所ネジ止めされています。モデルによってはネジを外さずにバッテリーのつけ外しができるタイプもあるので、使っているのはどのようなタイプか確認してから作業を進めるようにしてください。
ネジを外す際は、星型と+ドライバーを使用しましょう。周辺は星型ドライバー、中央部は+ドライバーを使ってください。ネジを外せば、底面のカバーの取り外しが可能です。
外したネジはとても小さいので、なくさないようにマグネットトレイを用意しておくと安心です。
カバーを取る
ネジを外したら、カバーを取っていきます。この作業は神経を使うので、慎重に行ってください。意外としっかりはまっているので、外しにくいと感じてしまう場合もあるので注意が必要です。
なかなか外れない場合に備え、オープニングピックを用意しておく方もいます。オープニングピックがあれば、ドライバーなどで無理にこじ開けずに済むので、本体に傷がつきにくくなるためです。
バッテリーを取る
カバーを外すことができたら、バッテリーを取ります。カバーが付いているモデルのバッテリーを本体から取り外す際は、ネジやコードテープ、コネクタを外さなければいけません。コネクタ付近にあるネジはサイズが特に小さいので、慎重に作業する必要があります。
コードテープはカッターなどで切らないようにしてください。なぜなら、新しいバッテリーを取り付けたときに再度貼り付けなければいけないためです。
ネジなどを外した状態でバッテリー本体を手前に引っ張るようにして持ち上げると外せます。
新しいバッテリーを取り付ける
外したら、新しいバッテリーの取り付け作業を行います。取り付け方は外し方と逆の手順です。バッテリー本体をノートパソコンにつけ、コネクタからネジ、コードテープの順でつけていけば完了となります。
外したカバーを取り付ける
新しいバッテリーを取り付けたら、カバーを戻してください。戻すときは「パチン」と音が鳴るまでしっかりとはめるのがポイントです。
ネジを締める
外したカバーを取り付けたら、ネジを締めます。ネジは真ん中の+ネジ、周囲の星型ネジの順で締めるようにしてください。
バッテリーの放電・充電を行う
バッテリーの交換が完了したら、放電と充電を行ってください。放電は、パソコンの内部にある不要な電力を外に逃がすための作業です。放電しないままパソコンを起動した場合、エラーが発生しやすくなってしまいます。
放電する際は、電源ケーブルを接続せずにパソコンの電源を入れてください。しっかり放電ができたら、電源ケーブルを接続し、充電します。
まとめ:正しい手順に沿って、バッテリーを交換しよう!

Dellのノートパソコンを使っていて、電源を接続していないときのバッテリー持ちが悪くなったように感じる場合があります。それは、バッテリーが劣化している証拠です。劣化したまま使っていると、いずれ使えなくなってしまうので、交換する必要があります。
交換は、正しい手順を知っていれば自分でもできるでしょう。しかし、自分で交換したり、非正規店に依頼したりすると、保証対象外になってしまうケースが多くなっています。そのため、保証期間がある場合はメーカーに依頼するのが無難です。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
ヘッドホンを処分したいけど、手間がかかりそうで気が進まない方は多いでしょう。ヘッドホンは家電製品であることから、分別が難しそうなイメージです。しかし、処分方法を調べてみると、簡単に処分できるケースがあることをご存じでしょうか。
適切な業者やお店を使えば、処分料がかからないどころか、お金がもらえる可能性もあります。今回は、ヘッドホンの種類や寿命、処分方法や売却方法までご紹介します。ヘッドホンの処分を考えている方はもちろん、ヘッドホンの買い替えを考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
ヘッドホンのタイプ

ヘッドホンには、大きく分けて「ワイヤレスタイプ」と「有線タイプ」の2つがあります。どちらにもメリット・デメリットがあり、好みにバラつきが見られるのもヘッドホンの特徴でしょう。まずは、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
ワイヤレスタイプ
ワイヤレスタイプのヘッドホンは、無線で接続できるのが特徴です。Bluetoothなどの無線通信機能が搭載されているため、邪魔なケーブルを介さず、音が伝わる仕組みです。定期的に充電をしていれば、手軽にストレスなくヘッドホンが使えることから、ワイヤレスタイプを選ぶ方が増えています。
しかし、充電を忘れてしまうと使用できなかったり、電波や障害物によって音飛びが発生したりするデメリットもあります。このようなデメリットから、高級モデルの開発が少ないのもワイヤレスタイプの特徴です。
高音質を求める場合は、ワイヤレスタイプでは物足りなく感じるかもしれません。
有線タイプ
有線タイプのヘッドホンは、スマホやパソコン、ゲーム機にケーブルを差し込んで使います。ワイヤレスタイプとは異なり、直接つなげて使用するため、音質にもこだわれるのが特徴です。ほかにも、映像と音のズレが抑えられるなどのメリットがあります。
しかし、ケーブルに不具合が出ると、音が聞こえにくくなったり、途切れるようになってしまったりします。有線タイプのヘッドホンを使う場合は、ケーブルの扱いに細心の注意を払う必要があるでしょう。
ヘッドホンの寿命
では、ヘッドホンの平均的な寿命は一体どれくらいなのでしょうか。ヘッドホンの寿命は、ワイヤレスタイプと有線タイプで異なると言われています。
とはいえ、平均寿命以上に長く使えるヘッドホンも数多く存在します。扱い方やお手入れの頻度、保管などにも気を付けながら使用すると、長く愛用できるのがヘッドホンの魅力です。ここからは、ヘッドホンの平均的な寿命に加え、寿命がきてしまう原因を見ていきましょう。
ワイヤレスタイプは2~3年
ワイヤレスタイプの平均寿命は、2年~3年ほどと言われています。
ワイヤレスタイプは充電が必要なので、本体にはバッテリーが内蔵されています。
繰り返し充電をしていると、バッテリーが劣化していき、充電の減りが早くなってくることがほとんどです。
減りが早くなると、充電する頻度も増え、さらにバッテリーが劣化する悪循環に陥ります。
つまり、使用頻度が高いほど、バッテリーの劣化が早まってしまいます。
常に充電していないと使えない、充電できなくなってしまったときが、ワイヤレスタイプの寿命です。
有線タイプは3〜5年
有線タイプの寿命は、ワイヤレスタイプよりも長い3年~5年です。
有線タイプのヘッドホンが壊れる原因としては、ケーブルの断線が挙げられます。
ワイヤレスタイプとは異なり、本体だけでなく、ケーブルにも気を遣いながら使用しなければなりません。
ケーブルを雑に扱った、ねじれたまま放置したなどが原因で断線してしまうケースが多いです。
逆に言えば、ケーブルを丁寧に扱っていれば、平均寿命よりも長く使えます。
しかし、どれだけ大切に使っていても、断線や故障してしまうこともあるでしょう。
音が聞こえなくなったり、ブツブツ聞こえたりする場合は、有線タイプヘッドホンの寿命です。
ヘッドホンの処分方法

たかがヘッドホンとはいえ、壊れているにもかかわらず保管しておくと、邪魔になったり、ほかのものが収納できなくなったりと不便です。
今後快適に過ごしていくためにも、大切にしていたヘッドホンは、正しい方法で処分しましょう。
ここでは、ヘッドホンを処分する2つの方法をご紹介します。
自分に合った方法を見つけてみてください。
・自治体の可燃ゴミ・不燃ゴミで処分する
ヘッドホンは、可燃ごみ・不燃ごみとして処分できます。
家庭ごみとして処分できるため、各自治体のルールに従えば、手間をかけることなく処分可能です。
可燃ごみに分別されるのか、不燃ごみに分別されるのかは、自治体によって異なります。
捨て方を間違えると、回収してもらえないことがほとんどです。
ヘッドホンを家庭ごみとして処分する場合は、自治体が設けているゴミの分け方・出し方を事前に調べておきましょう。
不燃ごみの場合、回収日を月に2回ほどと少なく設定している自治体が多いため、速やかに処分したい場合はほかの方法を検討してみてください。
また自治体の中には、ヘッドホンを分解し、パーツごとに分別して処分するようにルールを設けているところもあります。
この場合、イヤーパッドは可燃ごみとして、本体・コードは不燃ごみとして回収してもらうケースが多いです。
ヘッドホンの分別で特に気を付けたいのが、ワイヤレスタイプのヘッドホンの分別です。
ワイヤレスタイプのヘッドホンには、バッテリーが内蔵されています。
バッテリーを家庭ごみとして扱っている自治体はほとんどなく、分解して処分しても、バッテリーだけが手元に残ってしまいます。
ワイヤレスヘッドホンの処分に手間をかけたくない方は、ほかの方法を検討しましょう。
自治体のリサイクルボックスで出す
ヘッドホンは、小型家電リサイクル法の対象であるため、リサイクルボックス(小型家電回収ボックス)を利用できます。
小型家電リサイクル法とは、鉄や貴金属、レアメタルなどの限りある資源をリサイクルするために定められた法律です。
小型家電リサイクル法の対象であれば、自治体が設置したリサイクルボックスに投入するだけで処分が完了するため、とても手軽です。
リサイクルボックス、モバイルバッテリーなどのバッテリー類も対象であるため、ワイヤレスヘッドホンを分解せずに処分できます。
とはいえ、リサイクルボックスで処分できる品目・サイズは自治体によって異なるため、事前の確認が必須です。
リサイクルボックスは、家電量販店やスーパー、地域のイベント開催地などに設置している自治体が多いです。
また、自治体の小型家電回収には、リサイクルボックス以外の方法も用意していることがあります。
家庭ごみの回収と同じように、小型家電回収専用の指定ゴミ袋に入れて収集所に出すことが可能な自治体もあります。
小型家電リサイクル法に基づいて処分したい場合は、リサイクルボックスがどこにあるのか、どのような回収方法が存在するのかなど、事前にチェックしておきましょう。
ヘッドホンの売却の仕方

ヘッドホンを新調したい、壊れる前に買い替えたいなどの理由でヘッドホンの処分を考えている人もいるでしょう。
ヘッドホンがまだ使える、きれいな状態で保管してある場合は、ヘッドホンを売却できるかもしれません。
もちろん、修理すれば直る・価値の高い製品などであれば、壊れている場合でも売却できる可能性があります。
では、実際にヘッドホンを売却したいときは、どのような方法を選べば良いのでしょうか。
ここからは、ヘッドホンの売却の仕方をご紹介します。
不用品回収業者に出す
不用品回収業者は、大型家具・家電をメインに取り扱っているイメージがあるかもしれませんが、ヘッドホンを対象品目として扱っている業者は多くあります。
不用品回収業者によっては、外へ運び出すなどの作業も請け負ってくれるため、処分のためにかける手間を削減できます。
リサイクルできるものはリサイクルに回してくれるなど、適切に処分してくれるのも不用品回収業者に出すメリットでしょう。
また、まだまだ使える、美品であると判断された場合は、買取してくれることもあります。
ここで注意したいのが、回収してもらいたい不用品がヘッドホンしかない場合です。
業者に不用品を回収してもらうためには、回収費用がかかります。
ヘッドホンのみの回収となると、回収費用が高くなり過ぎてしまう可能性があります。
たとえヘッドホンが売却できても、買取価格よりも回収費用が上回ってしまい、結果的に損をするおそれがあります。
不用品回収業者は、ヘッドホン以外にも回収希望の不用品があるときに利用するのがおすすめです。
リサイクルショップで売る
リサイクルショップでは、ヘッドホンをはじめとするありとあらゆるものを売却できます。
もちろん、状態によっては買取価格が安くなってしまうこともありますが、とにかく安く、速やかに処分したい方におすすめです。
手数料がかからないため、手間といえば店頭に持ち込まなければいけないことだけです。
その日のうちにその場でお金がもらえる点も、リサイクルショップならではのメリットでしょう。
ただし、製造年数が古かったり、傷や汚れが目立っていたりすると、買取してもらえないことがあるため注意が必要です。
リサイクルショップの中には、壊れていて音が聞こえないなどのジャンク品を扱っているところもあります。
ヘッドホンの状態を確認するだけでなく、持ち込む予定のリサイクルショップがどういったヘッドホンを扱っているかの確認も大切です。
家電量販店で売る
不用品の買取を行っているのは、リサイクルショップだけではありません。
家電であれば、家電量販店の買取サービスを利用できます。
買取サービスを扱っている家電量販店の中には、インターネットでできるセルフ査定を用意しているところがあります。
査定額の目安がすぐに分かるため、「店舗に持ち込んだが、査定額に納得できず、再度持ち帰る」などの面倒を避けられるのがメリットです。
ただし、リサイクルショップと同じで、ヘッドホンの状態によっては査定額が低かったり、買取不可となったりするケースもあるので注意してください。
売却にかかる手間を抑えたい場合は、セルフ査定などの便利なサービスが受けられる家電量販店を選びましょう。
フリーマーケットに出品する
フリーマーケットで売却するのも1つの方法です。
多くの自治体が行う人気イベントであるため、定期的に行われている可能性が高いです。
自治体のフリーマーケット以外にも、イベント業者が開催しているフリーマーケットがあります。
フリーマーケットでヘッドホンを売却したい場合は、イベント情報をチェックし、申し込みましょう。
フリーマーケットは、リサイクルショップや家電量販店の買取サービスとは異なり、自分で価格を設定できるメリットがあります。
査定してもらい、納得できずに嫌な思いをするなどのリスクを減らせることもフリーマーケットならではのポイントです。
ただし、フリーマーケットで出店するには、200円~1,000円程度の出店手数料を支払わなければなりません。
出品したいものがヘッドホンのみの場合は、出費がマイナスになってしまう可能性があります。
フリーマーケットでヘッドホンを売るときは、ほかにも売却したいものがあるか、どうすれば元が取れるかなどを考える必要があるでしょう。
オーディオ買取ショップで売る
ヘッドホンの売却は、オーディオ買取ショップも有効です。
オーディオ買取ショップは、オーディオ機器専門の買取ショップであるため、特に有名なブランドやメーカーのヘッドホンを適切な価格で売却したい場合におすすめです。
オーディオ買取ショップで売却するときの注意点には、ショップによって査定額が大きく異なることが挙げられます。
1店舗目よりも、2店舗目の方が高く査定してくれる可能性もあるため、複数のショップで査定してもらうと良いでしょう。
ヘッドホンの処分の際には売却できるかも視野にいれて考えよう!

今回は、ヘッドホンの種類、寿命、処分の仕方をご紹介しました。
ヘッドホンは、タイプによって処分にかかる手間が変わってくるため、処分方法をよく検討してください。
自治体によってはそれほど手間をかけずに処分できる可能性もあるため、しっかり確認してみましょう。
また、ヘッドホンは美品のもの、まだ使えるものであれば、売却も可能です。
中には壊れていても買い取ってくれるショップや業者もあるため、ヘッドホンの状態に合わせて売却先を検討するようにしてください。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
iPodは、Apple社製のオーディオプレイヤーです。音楽を聴くことはもちろんですが、機種によっては映像やネットを楽しむことも可能。そのため、愛用している方も多く見られます。
iPodが壊れてしまったり、使わなくなったりするケースも当然あります。そのような場合、どう処分すべきか悩んでしまう方もいるはずです。そこで今回は、iPodを処分する方法やデータを消す方法、売る方法などを詳しく解説していきます。
iPodを処分する方法

iPodを処分する方法はいくつかあります。使わなくなったものを持っていても仕方がないので、処分したいと考えているのであればここでご紹介する方法を取り入れてみてください。では、どのような処分方法があるのかみていきましょう。
アップルリサイクルプログラムを利用する
1つ目は、アップルリサイクルプログラムを利用する方法です。アップルリサイクルプログラムとは、iPodやiPhone、Apple WatchなどのApple製品をAppleが無料で回収してくれるプログラムを指します。画面が割れてしまっていたり、充電ができない状態になったりした商品でもすべて無料で回収してもらうことが可能です。
回収方法はAppleストアに直接持っていく方法と、インターネットで申し込んで回収してもらう方法の2パターンがあります。店舗が近くにある場合は持ち込んでも良いでしょう。店舗が近くにない場合でも、インターネットから回収を申し込めるので問題ありません。
家電量販店に持っていく
2つ目は、家電量販店に持っていく方法です。家電量販店の中には使わなくなった電化製品の回収を行っているところがあります。新しいiPodを購入する際に古いものを引き取ってくれる場合もあるので、家電量販店のスタッフに確認してみましょう。
ただし、すべての家電量販店で回収を行っているわけではありません。そのため、持っていく前に問い合わせて確認するようにしてください。また、回収してもらえるのは本体だけなので、付属品に関しては自分で処分しなければいけません。
自治体に持っていく
3つ目は、自治体に回収してもらう方法です。ゴミ回収の際にiPodも回収してもらえます。ただし、どのゴミに分類されるかは自治体によって異なるので、確認してからゴミとして出すようにしてください。
iPodのようなデジタルオーディオプレーヤーは、小型家電リサイクル法の対象家電になっています。そのため、住んでいる自治体で小型家電の回収を行っているのであれば、回収ボックスなどの決められた場所に入れてください。小型家電リサイクルを行っていない自治体の場合は、そのままゴミとして捨てても問題ありません。
iPodのデータを処分する方法

iPodを処分するには、データを消去する必要があります。続いては、どのような方法でデータを消去するのか見ていきましょう。iPodの処分を考えている方は必見です。
パソコンと接続して消去する
iPodのデータは、パソコンと接続して消去できます。方法は以下のとおりです。
・まずはUSBケーブルでiPodとパソコンをつなぎましょう。
・Macの場合は、FinderのサイドバーでiPodを選択し、ウィンドウの上にある「一般」、「iPodの復元」の順で選択します。工場出荷時の設定に復元するには、macOS 10.15以降が必要、それ以前のバージョンを使っている場合はiTunesを使用してください。
・Windowsの場合は、パソコンで最新バージョンのiTunesをインストールするか、最新バージョンのiTunesにアップデートしてからiTunesを開きます。
・iTunesウィンドウの左上にある「iPod」をクリックし、「概要」へと進み、「iPodの復元」をクリックしましょう。
・画面に表示される操作に従って進めると消去が完了します。
iPodを売る方法

使わなくなったiPodは、売ることも可能です。続いては、iPodを売る方法をピックアップしてご紹介します。売ることでお金にもなるので、まだ使えるiPodがある場合は参考にしてみてください。
リサイクルショップで売る
リサイクルショップでは、多岐にわたる品目を取り扱っています。家具や家電、ゲーム機、おもちゃ、衣類などを取り扱っているリサイクルショップでiPodも買い取ってもらえるところです。
ただし、リサイクルショップは動くことが確認できるもの、見た目がきれいなものでなければ買い取り不可と判断される場合もあります。買い取りができないと判断されると、引き取りをしてくれないリサイクルショップもあるので持ち帰らなければいけません。それでは無駄足になってしまうので、あらかじめ動くかどうかチェックしたり、見た目をきれいにしたりしておきましょう。
リサイクルショップの中には、出張買い取りサービスを行っているところもあります。出張買い取りサービスならわざわざ店舗まで足を運ばなくても、ショップのスタッフが取りに来てくれます。
また、宅配買取サービスを実施しているところもあるでしょう。宅配買い取りなら段ボールに詰めてショップに送ればいいので、自宅に店員を招きたくない場合や立ち会いの時間が取れない場合でも安心です。iPod以外にも処分したいものがたくさんある場合は、このようなサービスを活用してみましょう。
Apple Trade Inで下取りに出す
Apple Trade Inは、新しいApple製品を購入する際に古い端末を下取りに出せるサービスです。査定額が決まると、購入価格から差し引かれる仕組みになっています。
オンライン買い取りとオフライン買い取りに対応しているので、便利なサービスです。Appleの公式店舗などでApple Trade Inを利用する場合は買い取りを希望する端末を直接持っていかなければいけません。少し手間だと感じてしまうかもしれませんが、いずれの場合も規定に沿った価格査定が行われるので安心してお任せできます。
Apple Trade Inは下取りサービスしか行っていないと思われがちです。しかし実際は、買い取りにも対応してもらえます。買い取りは古い端末を買い取ってもらう方法になります。iPodを今後使う予定がない場合は、買い取り対応してもらえば問題ありません。
フリーマッケットに出品する
Yahoo!オークションやメルカリなどのフリーマーケットに出品できます。いずれも個人同士で簡単に取引ができます。この2つの大きな違いは、Yahoo!オークションは買う側がオークション形式で値段を決定する、メルカリは売る側がフリーマーケットと同じように値段を設定するなどです。
Yahoo!オークションに出品されている商品は、仕事や趣味で使う道具が多い傾向にあります。また、楽天市場やAmazonなどに出店するEC事業者が出品できるのもYahoo!オークションならではの特徴です。
メルカリに出品されている商品は、子ども服やベビー用品、使いかけの香水などの半端品など女性向けのアイテムが多くなっています。スマホを使って気軽に取引できるため、このような傾向になっていると考えられるでしょう。
どのサービスを利用するにしても、壊れていたり使えても傷だらけだったりする商品は、買い手が見つからない可能性が高いです。ジャンク品としてなら買い取ってもらえるかもしれませんが、値段はほとんどつかないでしょう。クレームなどを考慮すると、使えるもの、見た目がきれいなものでなければ割に合わないと感じてしまう可能性が高いです。
不良品回収業者に持っていく
iPodのほかに家具や家電もまとめて処分したいのであれば、不良品回収業者の利用もおすすめです。通信機器や家電製品に特化した業者であれば、iPodを高値で買い取ってくれる可能性が高いです。
ほかにも売りたい家電製品がいくつもある場合は、出張回収サービスを利用するのも良いでしょう。また、宅配に対応している業者もあります。iPodだけであれば宅配便で送っても問題ありません。店舗が近くになくて持っていけない場合は、宅配や出張買い取りなどのサービスの利用も検討してみてください。
回収業者に依頼する際の注意点

回収業者に依頼する際、いくつか注意すべきポイントがあります。次は、どのような注意点があるのかみていきましょう。
古物商の許可を持っている
中古品の売買を行う場合、「古物商」と呼ばれる許可が必要になります。古物商の許可なしで買い取りを行っている業者は違法なので、依頼しないようにしましょう。古物商の許可を得ているかどうかは、業者のホームページに書かれている会社概要などでチェックできます。
また、古物商許可には古物商許可番号が併記されているので、その番号をネットで検索すると本物か判断できるでしょう。怪しいと感じた場合は、検索してみてください。古物商許可番号の兵器がない業者は、許可を得ずに買い取りを行っている可能性が高いです。
複数社に見積もりを出す
依頼先の業者は、最初から1つに絞らないようにしましょう。いくつか候補となる業者をピックアップし、相見積もりを出してもらうことが重要になるためです。少なくとも3社くらいから見積もりをとるのがおすすめ。
複数者から見積もりを出してもらうと、抜群に良い条件で回収してくれる業者が見つかる場合があります。そのような業者は、実際に良い条件を提示している可能性ももちろんあるでしょう。しかし、好条件にしている詐欺業者のパターンもあるので、相場や平均よりも飛び抜けて良い条件だった場合は警戒するようにしてください。
訪問営業には気をつける
回収業者の中には、自宅に訪問営業するところもあります。しかし、しっかりとした運営を行っている業者の場合、訪問営業は基本的にありません。
わざわざ訪問してくる業者は、押し買いと呼ばれる悪徳商法を狙っている可能性もあるでしょう。押し買いは、貴金属や宝石などを強引に買い取る手法です。買取価格は法外な安値で、売る側に不利益が生じてしまいます。
押し買いをしている業者は、「完全に無料」などの謳い文句で家に上がり込み、「貴金属を売るまで帰りません」などと言い、強引な買い取りを行います。こうした悪質なやり方を行う業者もあるため、訪問営業には十分に注意しましょう。
中古のiPodを高く売る方法
中古のiPodを売る場合、少しでも高値が付いてほしいと考える方も多いはずです。最後に、中古のiPodを高く売る方法を解説していくので、売る際は参考にしてみてください。

ホコリなどのゴミを取り除く
ホコリなどのゴミを取り除くのは、iPodを売る場合に限らず重要です。なぜなら、見た目が少しでもきれいな方が高値で買い取ってもらえる可能性が高いから。しばらく使っていなかった場合、ホコリやゴミが付いていることが多いので、売る前にきれいにしておきましょう。
フィルムやケースが汚れている場合は、取り外すのがおすすめです。買ったときの状態に近づけることができれば、より高値がつきやすくなります。指紋すら付いていない状態にできるのが理想です。
購入時の付属品などを一緒に売る
iPodを購入したときの付属品も一緒に売るようにしましょう。付属品が1つでも欠けていると、買い取り金額は大幅に下がってしまいます。そのため、高く売りたいなら付属品もしっかりと揃えておいてください。
購入時には、イヤホンや USBケーブル、クイックスタートガイドなどの付属品が付いていたはずです。付属品込みで商品が完成するとみなされるため、これらも忘れずに準備しておきましょう。付属品がなくても買い取ってもらうことはできますが、金額は相場より低くなってしまうことを覚えておいてください。
水没などで故障させない
iPodは、iPhoneやAndroidスマホと同じように水没させるのは厳禁です。水没した機器は、内部にも水が浸入している可能性があり、すぐに電源を入れるとショートする恐れがあります。ショートすると電源が入らないなどの不具合が生じ、ジャンク品になるので注意しなければいけません。
故障しているジャンク品のiPodは、買い取ってもらうことができません。買い取りできるのは、きちんと動き、見た目がきれいな商品です。傷などがあるだけなら買値が下がるだけですが、動かないものは買い取りするメリットが業者にないので、買い取りできないと言われてしまうでしょう。
そのような事態を回避するためにも、水没などで故障させないように気をつける必要があります。
まとめ:iPodを売る際には、事前にデータを消去しておこう

適切な準備をしておけば、iPodを高値で売れるようになります。使えるのに処分するのはもったいないので、売ることもぜひ視野に入れておきましょう。
iPodを売る場合、あらかじめデータを消去する必要があります。また、使わなくなったiPodを自治体の回収などで処分する際にも、データを消去しておくと安心です。データを消去するときは、今回ご紹介した方法を参考にしてみてください。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。