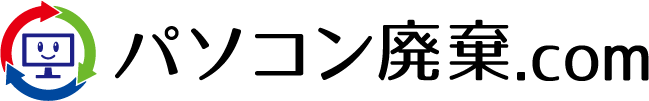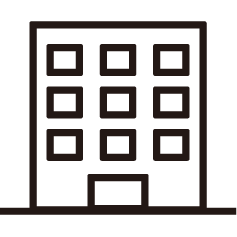404 Not Found
OPPOのスマートフォンを使っていて、急に電源が入らなくなったことはありませんか?あるいは、充電しようとしても反応がない…そんな経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
突然スマホの電源が入らなくなった時には焦ってしまいますが、実は解決方法があります。この記事では、OPPOの電源が入らないよくある原因と解決策を詳しく解説します。充電できない場合の対処法も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
【この記事でわかること】
- OPPOの電源が入らない原因派充電不足やバッテリーの劣化が多い
- まずは30分以上充電してみる
- 充電できない時は充電器をチェックする
- OPPOの電源が入らない場合は機種変更や修理も検討する
OPPOが電源入らない!考えられる原因

OPPOの電源が入らない原因は様々考えられますが、充電不足やバッテリー劣化が最も多い原因です。その他にも、以下のような原因があります。
- 充電不足
- バッテリーの劣化
- OPPOのフリーズ
- アプリやシステムの不具合
- 物理的な故障
それぞれの原因を詳しく解説します。
充電不足
OPPOの電源が入らない最も一般的な原因は、充電不足です。長期間充電していない場合や、バッテリー残量が少ない状態で使用を続けると、電源が入らなくなることがあります。
長時間スマホを使用していると、気づかないうちに充電が切れてしまい、電源が入らなくなることも。完全に充電がなくなってしまうと、電源ボタンを押しても反応しなくなります。
充電器を接続しても充電が開始されない場合は、充電器やケーブル自体の問題の可能性があります。充電器とケーブルを確認し、別の充電器に交換してみましょう。
バッテリーの劣化
バッテリーの劣化も電源が入らない一因として挙げられます。スマホのバッテリーは消耗品であり、時間が経つにつれて性能が低下します。劣化が進むと、充電しても電源が入らない場合があります。
特に2年以上同じデバイスを使用している場合、バッテリーの寿命が尽きている可能性があります。頻繁に完全放電させるとバッテリーの寿命が短くなることがあるため、注意が必要です。バッテリーが劣化すると、充電しても電源が入らない、あるいは充電がすぐに切れるといった症状が現れます。バッテリーが寿命の場合は、バッテリーの交換が必要になります。
OPPOのフリーズ
ソフトウェアの問題やアプリの不具合により、OPPOがフリーズしてしまい、反応しなくなることがあります。フリーズした状態では電源ボタンが反応しないため、電源を入れることができません。
また、画面が消えている状態でOPPOがフリーズすると、電源が入っていないように見える場合があります。画面が真っ暗になっている場合には、強制的に再起動することで改善する可能性があります。
スマホがフリーズした場合の原因や直し方は、下記記事でも詳しく解説しています。
スマホがフリーズ!iPhone・Androidでの直し方と原因を解説>>
アプリやシステムの不具合
インストールしたアプリやシステム自体の不具合も、OPPOの電源が入らない原因となり得ます。特に、最近インストールしたアプリがある場合は、そのアプリが原因でシステムに負荷がかかり、正常に起動しなくなることがあります。
また、システムアップデート後に不具合が生じることも。システムの不具合が考えられる場合は、セーフモードでの起動や、アプリのアンインストール、システムのリセットなどが解決策となります。
物理的な故障
スマホの落下や水没など、物理的なダメージが原因でOPPOスマホの電源が入らない場合もあります。長期間OPPOのスマホを使用している場合は、経年劣化によるパーツの故障も考えられます。
スマホの内部には多くのパーツが使用されており、外見上は問題なさそうに見えても、内部のコンポーネントが損傷している可能性があります。パーツが一つでも故障すると、スマホの電源がつかなくなります。
また、落下などの衝撃によってディスプレイが故障し、電源が入っていてもディスプレイに何も映らず、電源が入っていないように感じる場合もあります。
OPPOの電源が入らない場合の対処法
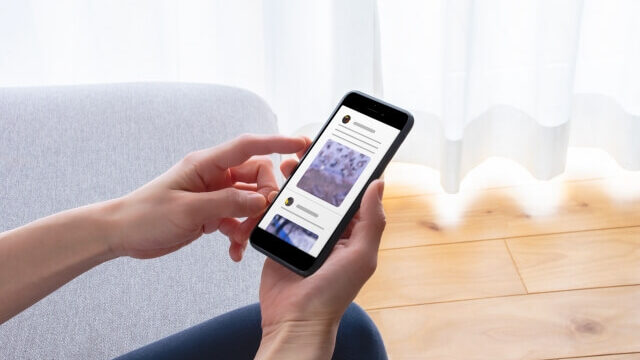
OPPOのスマホの電源が突然入らなくなると、焦ってしまいます。しかし、様々な対処法を試すことで、意外に簡単に解決できる可能性もあります。OPPOの電源が入らない場合にできる対処法は、以下の通りです。
- 30分以上充電する
- ディスプレイの故障を確認する
- フィルムを剥がす
- 電池パックやSIMカードを入れなおす
- 強制再起動する
- セーフモードで起動する
- 強制初期化する
- OPPOサポートへ問い合わせる
OPPOの電源が入らないと思っていたら、充電が切れていただけだったなど、単純な問題の可能性もあります。落ち着いて、順番に対処法を試していきましょう。
30分以上充電する
OPPOを充電器に接続し、少なくとも30分以上充電してみてください。充電することによってバッテリーに十分な電力が供給され、スマホが正常に起動する可能性があります。
バッテリーの充電が完全に切れている場合、即座には電源が入らないことがあります。充電中はスマホを触らないで、30分以上しっかりと充電してから、起動を試みましょう。バッテリーが劣化している場合は、十分に充電してもすぐに充電残量が減る場合があります。
ディスプレイの故障を確認する
OPPOスマホのディスプレイに故障がないかを確認しましょう。スマホを落とすなどで衝撃が加わったことでディスプレイが故障して、電源がついているにもかかわらず、電源がついていないように感じることがあります。
ディスプレイの故障を確認するには、電源を入れ、しばらく待ってから、別の電話から電話をかけてみましょう。着信音やバイブレーションがあれば、OPPO本体には問題ないことがわかります。ディスプレイの故障の場合は、早めに修理を依頼しましょう。
フィルムを剥がす
OPPOスマホの画面に貼った保護フィルムが原因で、スマホに搭載されている「近接センサー」が誤作動を起こし、画面が真っ暗になることがあります。保護フィルムを剥がして、問題なく起動すれば故障ではありません。他に原因が見当たらない場合は、保護フィルムを剥がしてみるのも良い方法です。
電池パックやSIMカードを入れなおす
電池パックやSIMカードの接触不良で、電源が入らなくなっている可能性があります。特に、OPPOスマホを落とした場合などに、接触不良を起こして不具合が起こっている可能性があります。OPPOのスマホの中には、OPPO A54のように電池パックが内蔵されており、取り外しできないタイプもあります。
電池パックが取り外しできない場合は、SIMカードだけを入れなおしましょう。カードスロットの汚れのために接触不良を起こしている可能性もあります。SIMカードを取り出した際には、カードスロットを掃除してから、入れなおしてみましょう。
強制再起動する
OPPOの電源が入らない場合で30分以上充電しても電源が入らない場合は、強制再起動もおすすめです。
画面が固まって全ての操作ができない場合や、電源を入れる途中で操作が止まった場合など、通常の再起動ができない場合に使用します。強制再起動の手順は、以下の通りです。
- 電源ボタンと音量小ボタンを同時に長押しする
- OPPOのロゴが画面に表示されるまで、約10秒間押し続ける
- デバイスが強制再起動する
強制再起動は、システムがフリーズしている場合に特に有効です。強制再起動は、一時的なエラーや不具合を解決できる方法。初期化とは異なり、内部データを消失することはありません。
セーフモードで起動する
特定のアプリをインストールした後に不具合が発生した場合には、アプリが問題の原因になっている可能性があります。セーフモードでの起動は、アプリが一時停止され、システムの基本的な部分のみが動作します。そのため、システムやアプリの問題を診断するのに役立ちます。
OPPOの機種によって、セーフモードへの入り方が異なります。一例として電源が切れた状態から電源ボタンを長押しし、OPPOのロゴが表示されたら電源ボタンから指を離し、音量下ボタンを長押しすることでセーフモードを起動できます。
セーフモードによって、電源が入らない問題の原因となったアプリが特定されたら、問題のアプリをアンインストールします。デバイスを再起動後に、不具合が解消していることを確認しましょう。OPPO一部の機種では、セーフモードが使用できません。セーフモードがない場合は、別の対処法を試してください。
強制初期化する
他のすべての対処法を試しても改善しない場合はOPPOスマホを初期化して、工場出荷時の状態に戻すことを検討してください。スマホの初期化は、スマホが重い場合やシステムに不具合がある場合に有効な方法です。OPPOスマホを初期化すると、デバイス内のデータは全て消去されるため、事前にデータをバックアップしましょう。
OPPOの電源が入らない場合は、リカバリーモードから強制的に初期化する必要があります。リカバリーモードへは、電源と音量ダウンボタンを同時に長押しすることで起動して、リカバリーモードが表示されます。リカバリーモード画面では、音量ボタンで選択カーソルを移動しますが、OPPOの場合はタッチパネルで操作できます。リカバリーモードから、強制初期化する手順は、以下の通りです。
- OPPOの電源を切る
- 「電源ボタン」と「音量ダウンボタン」を同時に長押し
- RECOVERY画面で「Wipe data」を選択
- 「Format data」を選択
- 4桁の認証コードを入力
- 確認画面が表示されたら「Format」を選択
- 「Wiped successfully」と表示されたら完了
完了後、自動的に再起動が始まり、工場出荷状態の画面になれば強制初期化が成功しています。なお、強制初期化は取り消しできません。デバイス内のデータは全て消去されるため、最後の手段として実行しましょう。
OPPOのスマホの初期化に関しては、下記記事でも詳しく紹介しています。
OPPOのスマホを初期化したい!事前準備や様々な初期化パターンも解説>>
OPPOサポートへ問い合わせる
ここまで紹介した対処法で問題が解決しない場合は、OPPOカスタマーサポートに問い合わせする方法もおすすめです。OPPOのサポート専門の技術者が、デバイスの診断と修理を行います。
OPPOカスタマーサポートサイトでは、デバイスの保証期間の確認も可能です。保証期間内の場合は、無料で修理できる可能性もあるため、事前に確認すると良いでしょう。ただし保証期間内の場合でも、画面割れや水濡れ、端末湾曲などの故障の場合は修理費用が発生します。
宅配で修理依頼ができ、修理期間の目安は5営業日です。費用は修理費のみで、代引き手数料や送料は発生しません。修理を依頼する場合は、事前に端末の初期化が必要です。データのバックアップを取り、端末を初期化してから修理を依頼しましょう。
充電できない場合の原因と対処法

OPPOの電源が入らず、充電もできない場合は、充電器の汚れや劣化、故障なども考えられます。充電器を変えて充電してみることで、充電器の故障か、OPPOのスマホの故障であるかを判断できます。
また、OPPOのスマホは0~45℃の環境で、正常に充電できるように設計されています。直射日光があたる場所など気温の高い場所は、室外など気温が低い場所では正しく充電できないことがあります。
OPPOのスマホには充電ランプがあり、充電中には赤色に、充電が完了すると緑色に点灯します。また充電中にはロック画面に「充電中」の表示やバッテリー残量も表示されます。充電されていることを確認するには、充電器を接続した後にランプを確認しましょう。
ここからは、OPPOのスマホが充電できない場合の対処法を解説します。
充電器が汚れている
OPPOが充電できない場合は、充電器に問題がある場合も多いです。まず充電器の端子にホコリや汚れが溜まっていると、充電がうまく行われないことがあります。
充電器の端子を柔らかい布で優しく拭き、汚れを取り除いてください。また、スマホの充電ポートも同様に清掃するのがおすすめです。充電器や充電ポートを掃除して挿しなおすことによって、接触不良が改善される可能性があります。
充電器やケーブルが劣化している
長期間同じ充電器やケーブルを使用していると、摩耗や損傷が生じることがあります。充電器やケーブルに見える損傷がある場合は、新しいものに交換してください。また、非正規品の充電器は充電できないことがあります。
充電器はスマホとの相性があり、メーカー純正の充電器を使用することで安全に充電できます。純正の充電器に変えて、充電してみてください。
バッテリーケア充電がオンになっている
OPPOには、バッテリーの寿命を延ばすための「バッテリーケア充電」機能が搭載されています。バッテリーケア充電とは、バッテリーの劣化を抑えるために充電しすぎない機能のことですが、オンになっていると充電速度が遅くなり、フル充電できなくなります。
「設定」メニューから、「バッテリー」を確認し、バッテリーケア機能をオフにしてください。バッテリーケアをオフにしてから、正しく充電できるかどうかを確認しましょう。
OPPOの電源が入らない場合は機種変更や修理!データ移行はできる?

あらゆる対処法を試してみてもOPPOの電源が入らない場合は、OPPOが故障している可能性が高くなります。OPPOが故障している場合は、機種変更する、修理するなどの選択肢があります。
一般的にAndroidスマホの寿命は、本体が3~4年程度、バッテリーは2~3年と言われています。使用期間が4年以上の場合は、寿命も考えられるため、機種変更するのがおすすめです。
スマホを機種変更するなら、データ移行が必要です。電源が入らない、壊れたOPPOからデータを取り出すには以下の方法があります。
- Googleアカウントにバックアップしたデータを復元する
- SDカードからデータを取り出す
OPPOのようなAndroid端末の場合は、Googleアカウントにバックアップしたデータがあれば、新しいデバイスから同じGoogleアカウントにログインし、クラウドからバックアップを選択することでデータを移行できます。
本体のSDカードにデータを保存している場合は、データの取り出しも簡単です。スマホの電源が切れている状態で、SDカードをOPPO端末から引き抜きます。データを移行したい新しいスマホにSDカードを差し込む、またはパソコンに差し込み、データを取り出しましょう。
データ復元ソフトは、電源が入っていない場合は利用できません。データを失うリスクもあるため、使用しないようにしましょう。
パソコンとUSBケーブルで接続してバックアップする方法もありますが、OPPOの電源が入らない状態ではデータを取り出すことができません。GoogleアカウントやSDカードにデータを保存していない場合には、OPPOサポートや修理専門業者に依頼しましょう。
OPPOのデータ移行方法は、下記記事でも詳しく解説しています。
OPPOのデータ移行方法とは?AndroidとiPhone別に解説>>
まとめ:OPPOの電源が入らない時には充電してみよう!

OPPOスマホの電源が入らない時には、焦らず冷静に対処することが重要です。OPPOの電源が入らない時に多い原因の一つが充電不足です。そのため、電源が入らない時には、まず30分以上充電してみましょう。
そもそも充電ができない場合は、デバイスの問題ではなく充電器の問題も考えられます。別の充電器に変えて充電してみてください。充電しても電源が入らない場合は、この記事で紹介した対処法を順番に試していくことで、問題の原因を特定し、適切な解決策が見つかるでしょう。
OPPOサポートへの問い合わせも選択肢の一つですが、その前に基本的な対処法を試してみるのがおすすめです。OPPOスマホの電源が入らないと故障かもと思ってしまいますが、簡単な対処法で解決することもあります。紹介した対処法を試して、OPPOのスマホを長持ちさせましょう。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
Lenovoのパソコンのキーボードが、突然反応しなくなり困っていませんか?Lenovoのキーボードが反応しないのは様々な原因がありますが、再起動や掃除、端子を抜き差しするなど簡単な方法で解決することもあります。
この記事では、Lenovoのキーボードが全く反応しない場合と一部だけ反応しない場合の原因と解決策を詳しく解説します。物理的な問題からソフトウェア的な問題まで、幅広い原因とそれぞれの解決策を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
【この記事でわかること】
- Lenovoのキーボードが反応しない原因は物理的な問題とソフトウェア的な問題がある
- 再起動や掃除、配線のチェックなどの簡単な方法で直ることもある
- キーボードの一部だけが反応しない時はNumLockなどの設定を確認する
Lenovoのパソコンが重い、起動しない場合の対処法は、下記記事で詳しく解説しています。
lenovoのパソコンが重い原因は?改善方法や不要なソフトを解説>>
Lenovoのパソコンが起動しない!ロゴから動かないときの対処法も>>
Lenovoのキーボードの故障を確かめる方法

Lenovoのキーボードが反応しない場合は、まず以下の方法で故障かどうかを確かめてみましょう。
別のキーボードに接続してみる
最初のステップとして、問題がキーボードに特有のものなのか、それともシステム全体に関わるものなのかを判断するために、別のキーボードを接続してみることが推奨されます。USBまたはBluetooth経由で別のキーボードをパソコンに接続し、問題が解消するか試してみてください。これにより、問題が元のキーボードに特有のものか、それともシステム側に原因があるかの判断材料となります。
Lenovoのハードウェア診断を利用する
Lenovoは、ハードウェアの問題を診断するためのLenovoのみが使用できる専用ツールがあります。このツールを利用することで、キーボードの故障をはじめとする様々なハードウェアの問題を特定できます。
Lenovo公式サイトからハードウェア診断ツールをダウンロードし、指示に従ってインストールしてください。Lenovo公式サイトでは、状況に合わせて診断ツールを選択できます。インストール後ツールを開き、「キーボードテスト」を選択し、画面の指示に従ってキーボードの各キーをテストしてください。
機種によっては、Lenovoの診断ツール「Lenovo Vantage」がインストールされている場合があります。「Lenovo Vantage」で診断する方法は、以下の通りです。
- 「Windows」ボタンをクリック
- プログラムの一覧から「Lenovo Vantage」をクリック
- 「Lenovo Vantage」が起動したら「次へ」をクリック
- 「操作性のカスタマイズ」が表示されたら、右下の「スキップ」をクリック
- 「操作性をカスタマイズしますか?」と表示されたら「不要」をクリック
- 「個人設定で使いやすくする」と表示されたら「スキップ」をクリック
- 「ようこそ、ユーザー」と表示されたら「ヘルスとサポート」をクリック
- 画面が切り替わったら「ハードウェア・スキャンを実行」をクリック
- 「簡易テストを実行」をクリック
- 「情報」が表示されたら、内容を確認し「OK」をクリック
- 診断が開始されたら100%になるまで待つ
- 100%になったらデバイスごとの結果が表示される
異常が見つかった場合は、キーボードが反応しない原因につながる不具合が考えられます。Lenovoサポート窓口へ相談しましょう。
参考:Lenovo サポート Lenovo Vantage – PC を更に使いやすく
Lenovoのキーボードが反応しない原因

Lenovoのキーボードが反応しない原因は、大きく分けて2つあります。
- 物理的な問題
- ソフトウェア的な問題
中でも最も多いのが、物理的な問題である接続不良です。それぞれの問題について、具体的な原因を詳しく説明していきます。
物理的な問題
物理的な問題はキーボードの故障や、故障以外の外部的な要因によって起こる問題です。主な原因は以下の4つです。
- 隙間に入ったゴミやホコリによる物理的障害
- 接続不良
- 静電気などの帯電
- キーボードの物理的故障
それぞれ解説します。
隙間に入ったゴミやホコリによる物理的障害
キーボードが反応しない一般的な原因のひとつは、隙間に入り込んだゴミやホコリです。日常的にキーボードを使用しているとホコリは避けられませんが、ホコリやゴミが隙間に入るとキーの動きを妨げ、正常な入力ができなくなることがあります。特に、キーボードの一部だけが入力できない場合はホコリが原因の可能性が高いでしょう。
定期的にエアダスターを使用してキーボードの隙間を清掃する、または専用のクリーニングツールを使って、こまめにゴミやホコリを除去することが重要です。定期的なメンテナンスによって、物理的な障害を防ぎ、キーボードの性能を維持できます。
接続不良
特に外付けキーボードを使用している場合、USBポートとの接続不良が原因でキーボードが反応しないことがあります。また、内蔵キーボードの場合は、キーボード自体とマザーボードとの接続不良も考えられます。接続不良の場合は、一度キーボードの接続を確認し、必要であれば接続端子を清掃することや、異なるUSBポートに差し替えてみることが有効です。
静電気などの帯電
パソコンは内部に電気を帯びやすく、想定以上に内部に帯電すると誤作動を起こすことがあります。パソコンの帯電は、キーボードやマウスが反応しないだけではなく、パソコン全体が動作不良を起こす原因にもなります。長時間使用したら、適度にパソコンをシャットダウンして、パソコン内部にたまった電気を放電することが大切です。
キーボードの物理的故障
長期間の使用や、落下などの物理的衝撃によって、キーボード自体が故障している可能性もあります。キーが押し込まれたまま戻らない、特定のキーが全く反応しないなど、物理的な故障の兆候が見られる場合、修理や交換が必要になることがあります。
ソフトウェア的な問題
次にソフトウェア的な問題は、キーボードの故障ではなく、パソコンのソフトウェア設定やアプリの問題によって起こる問題です。主な原因は以下の3つです。
- ドライバーの不具合
- アプリの干渉
- システム設定の問題
順番に解説します。
ドライバーの不具合
キーボードが反応しない原因として、ドライバーの不具合も考えられます。特にOSのアップデート後に、問題が発生することがよくあります。ドライバーの不具合が考えられる場合は、デバイスマネージャーからキーボードのドライバーを確認し、更新または再インストールすることで問題が解決することがあります。
アプリの干渉
特定のアプリケーションがキーボードの動作に干渉している可能性もあります。特に、キーボードのショートカット機能を拡張するアプリや、システムの動作を変更するようなアプリを使用している場合、これらが原因でキーボードが正常に動作しなくなることがあります。疑わしいアプリケーションを一時的に無効化またはアンインストールして、問題が解決するかどうかを確認しましょう。
システム設定の問題
時には、システムの設定変更がキーボードの反応しない原因となることがあります。たとえば、誤ってキーボードを無効にする設定をしてしまったり、言語設定が意図しないものに変更されてしまったりすると、キーボードが正常に機能しなくなることがあります。システムの設定を確認し、必要ならば元の状態に戻すことで問題が解決するでしょう。
Lenovoのキーボードが反応しない場合の対処法

Lenovoのキーボードが反応しない場合は、焦らずに以下の対処法を試してみてください。原因を特定し、適切な対処を行うことで、問題を解決できるでしょう。以下で具体的に解説します。
パソコンを再起動する
最も基本的な対処法で、簡単で効果的な方法がパソコンの再起動です。再起動することで、一時的な不具合やメモリ上の問題が解消されることがあります。再起動する手順は、以下の通りです。
- 「スタート」メニューを開く
- 電源ボタンをクリックする
- 「再起動」を選択する
なお、作業中のデータは保存されていない可能性があるため、再起動前に必ずデータを保存しておきましょう。
キーボードの配線をチェックする
外付けキーボードを使用している場合、配線が正しく接続されているかを確認しましょう。USBポートが損傷していないか、またはポートとキーボードの接続が緩んでいないかをチェックします。キーボードの接続端子が汚れている場合にもキーボードが反応しなくなることがあるため、汚れも確認しましょう。
確認後はケーブルを抜き差しする、接続端子を掃除するなどを試してみてください。改善しない場合は、別のUSBポートに差し替えてみるのも有効な方法です。万が一、ケーブルが断線している場合は、新しいケーブルに交換しましょう。
Windows Updateを実行する
Windows Updateには不具合の修正も含まれているため、システムを最新の状態に更新することで、問題が解決される場合があります。以下の手順で、Windows Updateを実行しましょう。
Windows Updateは、インターネットへ接続してから実行しましょう。また、時間がかかる可能性もあるため、余裕を持って実行するのがおすすめです。
- 「スタート」メニューを開く
- 「設定」を選択
- 「更新とセキュリティ」を選択
- 「Windows Update」選択
- 「更新の確認」を選択
更新プログラムがある場合は、自動的にダウンロードしてインストールされます。更新プログラムのインストール後には、パソコンを再起動しましょう。
アプリの状態を確認する
特定のアプリを使用しているときだけキーボードが反応しない場合は、そのアプリが原因の可能性があります。また、特定のアプリがキーボードの動作の妨げになっている場合もあります。アプリを一時的に終了する、アプリの更新や再インストールを試すなどを実行してください。アプリは、以下の手順で確認します。
- 「スタート」メニューを開く
- 「設定」を選択
- 「アプリ」を選択
- 最近インストールしたアプリを確認する
- 問題があると思われるアプリをアンインストールまたは無効化する
ドライバーを最適化する
キーボード用のドライバーが古くなっている、または破損している場合、キーボードが反応しなくなることがあります。以下の手順でドライバーを更新する、再インストールするなどで改善することがあります。
- 「スタート」メニューを開く
- 「デバイスマネージャー」を選択
- 「キーボード」を展開する
- 使用しているキーボードドライバーを右クリックする
- ドライバーの更新を選択
- ドライバーを自動的に検索を選択
最新のドライバーが見つからない場合は、Lenovoの公式サイトからダウンロードしてインストールする必要があります。オンラインで利用可能な更新がある場合は、自動的にダウンロードしてインストールされます。ドライバーを更新する前には、必ず現在のドライバーをアンインストールしてから新しいドライバーをインストールする点には注意しましょう。
放電して帯電を解消する
パソコン内に帯電しすぎると、パソコンが誤作動を起こすことがあります。特に、冬場など乾燥している時期には静電気が発生しやすいため、注意が必要です。以下の手順で放電しましょう。
- 起動中のアプリを終了する
- パソコンの電源を完全にシャットダウンする
- 周辺機器を取り外す(バッテリーが取り外しできる場合は取り外す)
- ノートパソコンは電源ボタンを1分間押す
- デスクトップは電源が切れた状態で1分間放置する
- 電源ケーブルやマウス、キーボード、バッテリーをパソコンに接続する
- パソコンの電源を入れる
BIOS設定を確認する
BIOS設定が間違っている場合、キーボードが反応しなくなることがあります。Lenovoのパソコンで起動中にBIOSに入る方法は、以下の通りです。
- 電源を入れる
- Lenovo、ThinkPad、ThinkStation、またはThinkCentreのロゴが表示されたら、「F1」キーを繰り返しタップする
- ビープ音が1回鳴り、BIOSのメニュー画面が表示される
一部の機種では、電源を入れてから「F1」ではなく「Enter」を押し続けます。「Startup Interrupt Menu」が表示されたら、「F1」を押して BIOS に入ります。BIOS画面でキーボードが反応する場合は、Windowsやシステムには問題がありません。BIOS画面でキーボードが反応しない場合は、キーボードやマザーボードが故障している可能性があります。
また、BIOSの設定が間違っている場合は、初期化することで問題が改善することもあります。BIOSのメニュー画面から、以下の手順で初期化してください。
- 「F9」キーを押す
- 「Setup Confirmation」の画面が表示されるため「Yes」を選択して「Enter」キーを押す
【非RAID構成の場合】
- 「F10」キーを押す
- 「OK」あるいは「YES」を選択して「Enter」キーを押す
- 再起動がかかりWindowsが起動する
【RAID構成の場合】
- 矢印キーを使用して「Devices」を選択
- 「Configure SATA as」で「Enter」キーを押す
- 矢印キーを使って値を「AHCI」から「RAID」に変更し「Enter」キーを押す
- 「F10」キーを押す
- 「OK」あるいは「YES」を選択して「Enter」キーを押す
- 再起動がかかりWindowsが起動する
セーフモードでのトラブルシューティング
Windowsのセーフモードを使用してパソコンを起動し、問題の原因を特定します。セーフモードでは、最小限のドライバーとサービスのみが起動するため、ソフトウェアの問題を切り分けやすくなります。
セーフモードは基本構成のみで起動する診断モードのため、セーフモードで問題なく動作する場合は、常駐アプリやあとからインストールするアプリなどがキーボードが反応しない原因になっている可能性が高くなります。以下の手順で、設定からセーフモードに入りましょう。
- 「スタート」から「設定」を選択
- 「 更新とセキュリティ>回復」を選択
- 「スタートアップ設定」で「今すぐ起動する」を選択
- PCが再起動したら画面のオプションを選択
- 「トラブルシューティング>詳細オプション>スタートアップ設定>再起動」から、ネットワークをセーフモードで起動する
- PCが再起動したらオプションの一覧が表示される
- 4 を選択、または「F4」を押してセーフモードでPCを起動
- インターネットを利用するには、「5」または 「F5」 を選択してネットワークをセーフモードで起動する
参考:Lenovoサポート セーフモードで起動する – Windows 7/8/8.1/10/11
キーボードを修理または買い替える
上記の手順で問題が解決しない場合、キーボード自体に物理的な故障がある可能性があります。Lenovoの公式サポートに連絡し、修理の手続きをしましょう。補償期間内であれば、無償で修理できる場合もあります。キーボードが寿命の場合は、別のキーボードへ買い替える方法も一つです。Lenovoサポートは、電話やチャット、メールなどの方法があるため、気軽に相談できるでしょう。
キーボードの一部だけが反応しない場合の対処法

Lenovoのキーボードが全てではなく、一部だけが反応しなくなることもあります。一部だけが反応しない場合は、ゴミが詰まる、ロックがかかっているなど単純な問題の可能性も高いです。焦らず順番に以下の対処法を試してみてください。
反応しないキーの周辺を清掃する
キーボードの一部が反応しない主な原因の一つは、キーの下に溜まったホコリやゴミです。電源を切り、キーボードの電源が切れていることを確認した上で、柔らかいブラシやエアーダスターを使って、反応しないキーの周辺を慎重に清掃してください。
また、無水エタノールをしみ込ませた綿棒で反応しないキー周辺を清掃するのもおすすめです。清掃の際には、力を入れすぎるとキーボードを破損する可能性があるため、注意しましょう。
「Num Lock」キーを確認する
特に数字のキーが反応しない場合は、「Num Lock」キーがオフになっていないかを確認してください。「Num Lock」キーは、キーボードのインジケーターランプで、オンオフを確認できます。多くのキーボードでは、「Num Lock」キーをオンにすることで数字キーが有効になります。もし、オフになっていた場合は、オンに切り替えてから再度キーの反応を確認してください。
マウスキー機能を無効にする
「マウスキー」機能を有効にすると、テンキーがマウスの操作に割り当てられマウスポインターを移動できるようになります。オンになっていると、テンキーが反応しなくなります。以下の手順で設定メニューから、マウスキー機能を無効にしてみてください。
- 「スタート」メニューから「設定」を選択
- 「簡単操作」を選択し「マウス」をクリック
- 「テンキーを使用するためにマウス キー機能をオンにして、マウスポインターを移動する」のオン・オフを切り替える
フィルターキー機能を無効にする
フィルターキーは、キーを短時間で連続して押したときの入力反応を抑えてご入力を防止する機能です。フィルターキー機能が有効になっていると、キーの反応が悪くなる場合があります。「Shift」キーを8秒間押し続けると切り替え画面が表示され、切り替えできるようになります。
まとめ:Lenovoのキーボードが反応しない時はゴミや接続不良の確認を!

Lenovoのキーボードが反応しない場合は、まず物理的な問題がないか確認しましょう。キーボードにゴミやホコリが溜まっていないか、接続不良がないか、静電気の影響を受けていないかなどを確認します。
物理的な問題がない場合は、ソフトウェア的な問題が考えられます。キーボード用のドライバーが古くなっている、または破損している可能性があります。また、特定のアプリがキーボードの動作を妨害している可能性もあります。
Lenovoのキーボードが反応しない原因がわかれば、紹介している解決策を試してみましょう。ゴミを掃除する、再起動するなど簡単な方法で改善する可能性もあります。
それでも問題が解決しない場合は、キーボードの故障も考えられます。Lenovoのサポートに連絡して、修理を依頼しましょう。キーボードが寿命の場合は、買い替えもおすすめです。Lenovoのキーボードが反応しなくて困った時には、この記事で紹介した解決策を試してみてください。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
PCから突然音が出なくなると様々な場面で支障を来してしまいます。
HPのパソコンから音が出なくなる原因は簡単な物から本体の故障、ドライバーの不具合など多岐にわたります。
この記事では
- HPのパソコンから音が出ない原因
- 音が出ないときの解決方法
について解説していきます。
HPのパソコンから音が出ない原因

HPのパソコンから音が出ない原因は以下のものが考えられます。
- ミュートになっている
- YouTubeや音楽プレーヤーの音量が0またはミュートになっている
- 接続しているスピーカーなどの音量が0になっている
- 正しくスピーカーに接続されていない
- スピーカーやヘッドホンの故障
- オーディオドライバーの不具合
ミュートになっている
パソコンから音が出ないときは音量がミュートになっている可能性があります。
ミュートにした覚えがない場合でも何かの弾みでクリックしてしまったり、忘れている場合もあるのでまずは音量設定を確認しましょう。
またキーボード上のキーでにミュートに入っている可能性もあります。
YouTubeや音楽プレイヤーの音量が0またはミュートになっている
YouTubeや音楽プレイヤーの音が聞こえないときはソフト自体の音量バーが0やミュートになっている可能性もあります。
Web上で動画を視聴しているときも同様で、大抵のサイトでは画面の下側に音量調節のアイコンがあります。
ここで音が出ない設定になっているとスピーカーなどが正常でも音は出なくなってしまいます。
接続しているスピーカーなどの音量が0になっている
接続しているスピーカーやヘッドホンが個別にボリューム調節可能な場合は音量が0またはミュートになっていると音が聞こえません。
ヘッドホンによってはミュートにするためのボタンなどが付いているものもあり、うっかり触ってしまっていることがあります。
正しくスピーカーに接続されていない
スピーカーやヘッドホンとパソコンが正しく接続されていない場合も音が聞こえません。
有線であれば正しいジャックに刺さっているか、Bluetooth接続であれば確実に接続されているか確認する必要があるでしょう。
スピーカーやヘッドホンの故障
音が聞こえないときはスピーカーやヘッドホンが故障している可能性もあります。
またワイヤレスの場合はバッテリーが切れているかもしれません。
スピーカーが故障する原因として多いのは
- ケーブルの断線
- 大音量での長時間使用
- コーンの経年劣化
などが挙げられます。
ケーブルを無理に引っ張ったりすると断線の原因となるので、注意が必要です。
オーディオドライバーの不具合
パソコンには音声を制御するためのドライバーがあり、そのドライバーが不具合を起こしていると音が聞こえないことがあります。
ドライバーは更新したり、再インストールをすることで正常に動作する可能性もあるので、さまざまな手法を試しても音が聞こえないときはドライバーを疑ってみましょう。
HPのパソコンから音が出ないときの解決法

HPのパソコンから音が出ないときは以下の解決法が有効です。
- ミュートを解除する
- スピーカーなどの音量設定を見直す
- スピーカーに正しく接続されているか確認する
- 別のスピーカーに接続してみる
- オーディオドライバーの更新または再インストール
- HPのパソコンを再起動する
- Windowsの更新を実行する
ミュートを解除する
音が出ないときはまずミュートまたは音量が0になっていないか確認しましょう。
音量は画面右下にあるスピーカーのアイコンから変更できます。
パソコンの種類やキーボードによってはキーで音量設定できるものもあるので、そこからも変更可能です。
スピーカーなどの音量設定を見直す
スピーカーやヘッドホン自体の音量が0になっている可能性もあるので、そちらも合わせて確認しましょう。
スピーカーであれば音量を調節するためのつまみやタッチパネルで調節できます。
ヘッドホンの場合はダイヤル式が多いのでお使いのヘッドホンを見ながら調節してください。
スピーカーに正しく接続されているか確認する
スピーカーやヘッドホンが正しくパソコンと接続されているかも確認しましょう。
有線接続であればイヤホンジャックや光デジタル出力、またはHDIMケーブルが正しく刺さっているかを見ます。
Bluetooth接続の場合は他の機器に接続されていないか、パソコンのBluetoothがオフになっていないかなどを確認します。
ヘッドセットやスピーカーによってはパソコンを起動する度に接続先がリセット(優先的に接続する)設定になっているものもあるので、ヘッドセットのコンパニオンアプリなどで設定を見直してみましょう。
別のスピーカーに接続してみる
スピーカーが壊れているかどうかを確かめるには別のヘッドセットなどに接続するとわかりやすくなります。
別のスピーカーに接続して音が出ない場合はそのスピーカーが故障しているか接続に問題がある可能性が高くなります。
どのスピーカーに繋いでも音が出ない場合はパソコン側に問題があることが多いので、次に解説するオーディオドライバーの更新を試してみましょう。
オーディオドライバーの更新または再インストール
パソコンのオーディオドライバーに何らかの問題が発生している場合はドライバーを更新または再インストールを実行します。
ドライバーの更新の方法は以下の手順で行います。
- Windowsキー + Xを同時に押し、表示されたメニューから「デバイスマネージャー」を選択するか、Windows検索ボックスに「デバイスマネージャー」と入力して開く
- 「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」セクションを展開して、オーディオドライバー(例: Realtek High Definition Audio)を探す
- 右クリックして「ドライバーの更新」を選択
- 「オンラインで検索してドライバーソフトウェアを更新する」を選ぶ
HPのパソコンを再起動する
特に設定を変えたりスピーカーの接続を変えたりしていないのに音が出なくなった場合はパソコンを再起動することで解決することがあります。
何らかの不具合が起きている場合も再起動は有効なのでとりあえず試してみるのもありです。
Windowsの更新を実行する
Windowsの更新プログラムが溜まったままになってはいませんか?
Windowsのプログラムを最新にすることは音が出ないなどの不具合の解消の他にもセキュリティを最新にするという重要な意味があります。
Windowsのプログラムを最新にするには以下の手順で行います。
- スタートメニューを開き、「設定」をクリック
- 「更新とセキュリティ」を選択
- 「Windows Update」タブをクリックし、「更新を確認」をクリック
- 利用可能なアップデートがあれば、ダウンロードとインストールを開始
全て試しても音が出ない場合

ここまで解説した方法を試しても音が出ない場合は少し手間がかかりますが、以下の方法があります。
- BOISを初期化する
- 調子が悪くなる前に復元ポイントで戻す
- メーカーに修理を依頼する
BOISを初期化する
どうしても音が出ない場合はBIOSを初期化することで解決する可能性があります。
ただしBIOSの初期化はパソコンに対する一定の知識が必要とされますし、BIOSをいじることは基本的に推奨されていないため、最後の手段として実行するようにしましょう。
またBIOSを初期化する前にしっかりとバックアップを取っておくことをおすすめします。
HPのパソコンのBIOSを初期化する方法は公式サイトで詳しく解説されています。
調子が悪くなる前に復元ポイントで戻す
パソコンの設定を音声が正常に出力されていたときの状態に戻すことで解決することがあります。
パソコンの設定を前に戻すには「復元ポイント」と呼ばれる機能で戻します。
- タスクバーの検索欄に「復元ポイント」と入力する
- 「復元ポイントの作成」をクリック
- タブから「システムの保護」を選択
- 「システムの復元」をクリックし、復元ポイントを選択する
メーカーに修理を依頼する
BIOSの初期化やシステムの復元を実行しても音が出ない場合はパソコン本体が故障している可能性が高くなります。
その場合は修理する以外に方法はないので、HPのサポートに連絡して修理が必要か相談してみましょう。
HP公式のサービス以外にも民間の修理業者でも対応してもらえることがあるので、近隣に修理業者を探してみるのもおすすめです。
まとめ

以上、HPのパソコンから音が出ない場合の原因と対処法を解説してきました。
修理に出す前に簡単に試せることが多いので、慌てずに対処法を一つずつ試してみましょう。
すぐにできる対処法は
- ミュートになっていないか確認する
- スピーカーやヘッドホンの音量を確認する
- 接続を確認する
- ソフトやアプリ側での音量がゼロになっていないか確認する
などがあります。
音が出ない場合はうっかりミュートになっていたり、音量が0になっていることがよくあるので、まずはここを確認してください。
また外部のスピーカーなどに接続している場合も接続やボリュームを調節して音が出るか試してみましょう。
どうしても音が出ない場合はオーディオドライバーの更新やBIOSの初期化などの方法を試すことで解決する可能性もありますが、それでも直らない場合は公式サポートに問い合わせてみることをおすすめします。
ノートPCは持ち歩けることがメリットの一つですが、充電できなくなるとそのメリットも活かすことができません。
パソコンが充電できない原因には充電器の故障やバッテリーの劣化などがあります。
この記事では
- HPのパソコンが充電できなくなる原因
- 充電できないときに確認するポイント
- 充電できないときの対処法
について解説していきます。
HPのパソコンが充電できなくなる原因

HPのパソコンが充電できない原因には以下のものが考えられます。
- 電源アダプターに接続されていない・電源アダプターの故障
- パソコンが帯電している
- 本体が熱すぎる
- バッテリーが劣化している・故障している
- 本体が故障している
電源アダプターに接続されていない・電源アダプターの故障
まず見落としがちなことですが、電源アダプターが確実に接続されているか確認しましょう。
延長コードなどに差している場合は特に確認が必要です。
延長コードの差し込み口が掃除の際に引っかかって抜けてしまったり、同居の家族や子供がいる場合は知らない間に抜かれていることもあります。
確実に接続されているのに充電されない場合は電源アダプター自体の故障やコードの断線も考えられます。
その場合は他の充電機やコードを利用して充電できるか確かめてみましょう。
パソコンが帯電している
パソコンは電気を溜め込んでしまうことがあり、その場合は充電できなくなることがあります。
帯電は主に静電気が原因で起こります。
乾燥した環境やホコリっぽい部屋などでノートPCを使うと静電気が起こりやすくなり、帯電する要因となります。
本体が熱すぎる
パソコン本体が熱すぎる場合も充電できないことがあります。
ノートPCの排熱が上手くいかずに熱くなったり、直射日光が当たる場所など高温下で使用していると、安全機能が働いて一時的に充電できない状態になります。
パソコンは人間が快適と思える環境で使用することが推奨されているので、極端に暑い部屋で使うことは避けて、エアコンなどを活用するようにしましょう。
バッテリーが劣化している・故障している
バッテリーが劣化していたり、故障している場合も充電できません。
ノートPCに使われているリチウムイオンバッテリーは300~500回程度の充放電を繰り返すと寿命を迎えるといわれています。
期間でいえばおおよそ2~3年ほどで寿命を迎えることになりますが、ハードに使っている人ほど充電回数が増えるので、よりバッテリーの寿命が短くなるといえます。
また過放電といって、使わずに放置したりバッテリー容量を極限まで使い切ってしまうと、二度と充電できない状態になることもあります。
しばらく使っていなかったときに充電できない場合は過放電を起こしてしまった可能性も考慮する必要があるでしょう。
本体が故障している
パソコン本体が故障している場合も当然ですが充電できません。
パソコン本体が壊れる要因はさまざまですが、パソコンに強い衝撃を与えてしまった、飲み物をこぼしてしまったなどのあとに充電できなくなった場合は本体の故障と考えてもよいでしょう。
充電できないときに確認するポイント

HPのパソコンが充電できないときは以下の項目を確認してみましょう。
- 電源アダプターが正しく接続されているか確認する
- 充電ランプが点灯しているか確認する
- 本体の温度が高すぎないか確認する
- 高負荷の作業をしていないか確認する
電源アダプターが正しく接続されているか確認する
パソコンが充電されないときはまず、電源アダプターが正しく接続されているか確認しましょう。
コンセントに挿したつもりでもゆるかったり、延長コードの差し込み口が抜けている可能性もあります。
またタコ足配線をしている場合は電力が足りなくなることもあるので、使っていない機器のコードを抜く、電源アダプターをコンセントに直接挿すなどして対処しましょう。
本体の温度が高すぎないか確認する
充電の前にパソコン本体が熱くなりすぎていないか確認しましょう。
パソコンが熱くなる原因としては
- 高負荷の作業をしている
- 放熱がうまくいっていない
- パソコンを使っている部屋が暑い
などが挙げられます。
高負荷の作業をした直後であればしばらく作業を中断して、温度が下がるのを待ちましょう。
また絨毯の上やホコリで吸排気口が詰まっていると適切な冷却を妨げることもあるので、机の上で使う、ホコリを取り除くなどの対処を行います。
パソコンを使っている部屋自体が暑い場合も本体温度の上昇に繋がるので、エアコンなどを活用して適切な室温を保つようにしましょう。
高負荷の作業をしていないか確認する
動画編集やゲームなどの負荷がかかる作業をしながらの充電は場合によっては充電が間に合わず、充電が進まないように見えることがあります。
電源アダプターを接続して動作しているようであれば問題はありませんが、その場合は普段よりも充電に時間がかかることもあります。
充電できないときの対処法

HPのパソコンが充電できないときは以下の方法を試してみてください。
- 別の電源アダプター・ケーブルを試す
- 放電する
- バッテリーを接続し直す
- パソコンを冷却する
- バッテリーを交換する
- パソコンの設定を見直す
別の電源アダプター・ケーブルを試す
今使っている電源アダプターを正しく接続しても充電されない場合は別のアダプターを試してみましょう。
タイプCのケーブルで充電するタイプの場合は家にある他のものを使ってみるのもよいでしょう。
パソコンの機種によっては専用のアダプターが用意されていることもあり、市販品が使えない場合もあるので、その場合はメーカーに修理を依頼した方が確実です。
放電する
パソコンが帯電している場合は放電作業をすることで解消する可能性があります。
パソコンを放電するには以下の方法が有効です。
- 電源アダプターを外して数分放置する
- 周辺機器を外す
- バッテリーが外せるモデルの場合は外す
バッテリーを接続し直す
バッテリーが外れるモデルの場合は一度外してから、再度取り付けてみましょう。
何らかの理由でバッテリーが接続不良になっている場合はこの方法で解決できることもあります。
パソコンを冷却する
パソコン本体が熱すぎる場合はいったん使用を中止して冷却しましょう。
またパソコンを使っている環境が暑い場合は部屋の温度を下げる、直射日光を避けるなどしてパソコンが熱くならないようにします。
冷却がスムーズにできなくてパソコンが熱くなっている場合は吸排気口を掃除し、ホコリなどを取り除きましょう。
バッテリーを交換する
バッテリーが寿命を迎えていたり、過放電してしまった場合は充電することができません。
その場合はバッテリーを交換するしか方法がないので、HPの問い合わせ窓口や民間の修理業者に依頼しましょう。
HP Care Pack ワンタイム内蔵バッテリー交換サービス
パソコンの設定を見直す
充電が進まないと感じるときはパソコンの設定を見直してみましょう。
画面の明るさを最大にしていたり、高パフォーマンス設定になっていると多くの電力を消費します。
また動画編集やゲームなどのCPU、GPUに多大な負荷がかかる作業をしながらの充電は満充電まで時間がかかることがあります。
高パフォーマンス設定を変更するには以下の方法で行います。
- コントロールパネルを開く
- システムとセキュリティー→電源オプションをクリック
- 電源プランの高パフォーマンスをバランスまたは省エネに変更
まとめ:充電できないときは電源周りから確認していこう
以上、HPのパソコンが充電できないときの対処法について解説してきました。
充電できないときはまず原因を突き止めることから始めましょう。
ポイントは以下の通りです。
- 電源アダプターが刺さっているか確認する
- バッテリーは劣化していないか
- パソコン本体が熱すぎないか
- 高負荷の作業をしていないか
以上を確認したらそれぞれに応じた対処法を実施しましょう。
ただしバッテリーや本体の故障の場合は修理に出すしか方法はないので、HPの公式サービスに申し込むか、民間の修理業者に依頼しましょう。
LenovoのThinkPadは、その高い耐久性と優れた性能で多くのビジネスパーソンから支持を受けています。しかし、長時間の使用など様々な原因によって異常に熱くなり、ファンがひっきりなしに回ることがあります。
パソコンの過熱は寿命を縮める原因となるため、早めの対策が重要です。この記事では、ThinkPadが熱くなる主な原因と対処法、さらにファンが止まらない場合の対処法について詳しく解説します。そもそもThinkPadが熱くならないためにできる対策も紹介しますので、参考にしてください。
【この記事でわかること】
- LenovoのThinkPadが熱くなる原因は高負荷やホコリ
- ThinkPadを熱いまま放置すると熱暴走のリスクがある
- ファンが回りっぱなしになるのは内部温度が高温になっているため
- 定期的なクリーニングが重要
Lenovoのパソコンが重い場合や起動しない場合の対処法は、下記記事でも詳しく解説しています。
lenovoのパソコンが重い原因は?改善方法や不要なソフトを解説>>
Lenovoのパソコンが起動しない!ロゴから動かないときの対処法も>>
Lenovo「ThinkPad」が熱くなる原因

LenovoのThinkPadが熱くなる原因は、以下があります。
- CPUやGPUへの高負荷
- 内部に溜まったホコリ
- ThinkPadを設置している環境
- 冷却ファンの不具合
順番に解説します。
CPUやGPUへの高負荷
LenovoのThinkPadが熱くなる原因の一つとして、CPUやGPUにかかる高負荷が挙げられます。特に動画編集ソフトの使用、大規模なデータベースの操作、高解像度のゲームのプレイなど、複雑な計算やデータを処理している時などにパソコンへかかる負荷が大きくなります。
負荷が高くなるプロセスを特定するには、タスクマネージャーなどを使用して、CPUやGPUの使用率を定期的にチェックすることが効果的です。どのプロセスが高負荷を引き起こしているのかを把握し、必要に応じて処理の優先度を調整する、使用を控えるなどで過熱を防止できます。
CPUやGPUへの高負荷の状態が続くと、パーツ内の温度が急速に上昇します。温度が上昇すると、性能を維持するためにより多くのエネルギーが消費され、さらなる熱が発生する悪循環に陥ることがあります。パソコンの高温は、ハードウェアの損傷や性能の低下を引き起こす可能性があります。
パソコンの温度が一定を超えると、故障を防ぐためにシステムが自動的にパフォーマンスを下げることがあります。最悪の場合は、急にシャットダウンする場合もあるため、高負荷の作業をする際には、パソコンを冷却する対策をすることが重要です。
内部に溜まったホコリ
パソコン内部にホコリが溜まる主な原因は、周囲の環境とパソコンの冷却システムにあります。パソコンのファンは、内部の熱を外に逃がすために空気を内部に取り込みますが、この過程でホコリなども一緒に取り込まれます。
特に、床に近い場所やホコリの多い環境でパソコンを使用している場合、内部にホコリが溜まりやすくなります。また、定期的に内部クリーニングしないことも、ホコリが溜まる一因となります。
さらにパソコン内部に溜まったホコリは、冷却システムの効率を低下させます。特に、CPUやGPUなどの熱を発するパーツ周辺にホコリが溜まると、熱が外部に逃げにくくなりパーツの温度が異常に高くなる原因となります。
CPU温度の上昇は、パフォーマンスの低下やシステムの不安定化、さらにはハードウェアの故障につながるため、パソコンにとってホコリは大敵です。定期的にクリーニングすることによって、ホコリによる冷却効果の低下を防ぎ、安定したパフォーマンスを維持できます。
ThinkPadを設置している環境
パソコンが熱くなる原因は、設置している環境の温度も大きく関係します。高温の環境下では、パソコン内部の温度が自然に上昇し、冷却システムが正常に機能しづらくなります。特に、夏季や直射日光が当たる場所での使用は、内部温度の急激な上昇を招きやすくなります。
環境温度が高いと、CPUやGPUなどの熱を発するパーツの冷却が追いつかず、パフォーマンスの低下やシステムの不安定化を引き起こすことがあります。したがって、パソコンは涼しい場所で使用し、適切な通気性を確保することが重要です。
ThinkPadを使用する上で、最適な温度環境は10℃から35℃で、湿度は35%から80%とされています(※)。最適な使用環境を実現するためには、直射日光を避け、良好な通気性を確保しましょう。エアコンや扇風機を使用して、室温を適切にコントロールすることもパソコンの過熱防止に役立ちます。適切な環境下でパソコンを使用することで、長時間の作業でも安定したパフォーマンスを維持できるでしょう。
冷却ファンの不具合
冷却ファンは、パソコン内部の熱を効率的に排出するために不可欠なパーツです。冷却ファンが正常に機能しない場合、内部の熱が適切に排出されず、過熱の原因となります。ファンの不具合は、ホコリの蓄積、故障、経年劣化など様々な要因で発生する可能性があります。
過熱によって、パソコンは性能の低下を招くだけでなく、ハードウェアの損傷やデータの損失、最悪の場合はシステム全体の故障につながることもあります。また、冷却ファンの異常はパソコンの動作音の増加として現れることもあり、パソコンから異音がする原因にもなります。
冷却ファンの不具合は、ホコリが原因で正常に回転しなくなっていることが多いです。まずはファン自体やその周辺のホコリを掃除しましょう。掃除をしても改善しない場合は、ファンが物理的に故障している、または寿命による劣化が考えられ、その場合はファンの交換が必要となります。
ソフトウェアを用いてファンの回転速度を調整することで、一時的に問題を緩和させることができる場合もありますが、あくまで一時的な対処法であり、根本的な問題解決にはなりません。また、内部の清掃やファンの交換は、パソコンの保証がなくなる可能性があるため、自信がない場合は専門業者に依頼するのがおすすめです。
ThinkPadを熱いまま放置すると起こること
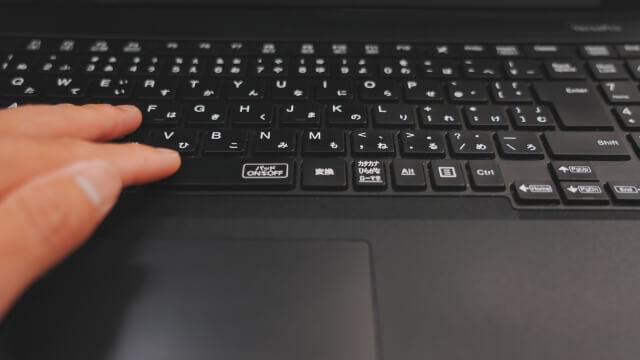
ThinkPadをはじめとするパソコンは、高度な計算処理をしているため熱くなることは避けられません。しかし、異常な高温になったまま放置すると、様々な問題が発生する可能性があります。ここでは、熱いまま放置することによって起こる主な問題とその対策について解説します。
熱暴走するリスクがある
熱暴走は、パソコン内部の温度上昇が制御不能になる現象を指します。パソコンが熱い状態が続くと、突然シャットダウンする、フリーズする、エラーが出るなど著しく性能が低下するだけでなく、最悪の場合は部品が焼けてしまうなどで発火を引き起こすリスクもあります。特に、CPUやGPUなどの主要な処理を担うパーツが故障すると、修理に高額な費用がかかる場合があります。
熱暴走を防ぐためには、パソコンの冷却システムが適切に機能していることを確認することが重要です。冷却ファンがきちんと動作しているかのチェックや、ホコリが溜まっていないかチェックするなど定期的なメンテナンスを実行しましょう。また、パソコンを使用する際は通気性の良い場所に置く、冷却パッドを使用するなど、パソコンが熱くならない工夫も大切です。
発火する危険がある
パソコンが発火する主な原因は、電池の過熱やショートです。特にリチウムイオンバッテリーは、内部温度が極端に高くなると暴走し、発火や爆発に至る危険性があります。また、内部の配線が損傷し、ショートが発生することも発火の原因となります。
パソコンの発火リスクを最小限に抑えるためには、バッテリーの劣化に注意し、定期的に交換するのがおすすめです。また、パソコンを長時間使用する際には、適切な休憩を挟むことで内部温度の上昇を抑えられます。さらに、使用しない時は電源を切る、またはスリープモードにすることで、不必要な発熱を避けられます。
故障するリスクがある
過剰な熱は、パソコンの内部パーツの大敵です。中でも半導体の素材であるシリコンは、一定の温度以上になると性能が劣化し始めます。継続的に高温状態にさらされることで、パーツが故障しやすくなり、ThinkPad全体の寿命が短くなる恐れがあります。
故障リスクを減らすためには、パソコンを適切な環境で使用し、定期的にメンテナンスすることが重要です。使用後はパソコンをシャットダウンする、通気性の良い場所に保管する、内部のホコリを定期的に清掃するなどの日常的なケアにより、長期間にわたって安定した性能を保てるでしょう。
Lenovo「ThinkPad」が熱い時にできる対処法

ThinkPadなどのノートパソコンは、長時間の使用や高負荷の作業によって過熱することがあります。
過熱はパフォーマンスの低下や内部パーツの故障につながることがあるため、適切な対処法を知っておくことが重要です。ここでは、ThinkPadが熱い時に試せる以下の9つの対処法について紹介します。
- 使用を中止する
- 通気を確認する
- ThinkPad内部のホコリを取り除く
- ThinkPadの置き場所を変える
- アプリやソフトを閉じる
- 省電力設定に変更する
- パソコン用の冷却グッズを使用する
- サポートに連絡する
それぞれ解説します。
使用を中止する
ThinkPadが熱い場合、最初にできる対処法は使用を一時的に中止することです。使用を中止し、休ませることで、内部の温度が自然に下がります。パソコン内部の温度を下げることによって、熱による故障のリスクを減らし、パフォーマンスの低下を防げます。
ThinkPadの使用を中止する際はただ閉じるだけではなく、適切にシャットダウンすることが重要です。また、パソコンが冷えるまで充電を避けることで、バッテリーへの負担を軽減できるでしょう。
通気を確認する
パソコンの通気性を向上させるには、底面や側面の通気口が空気を十分に取り込めるように、配置を工夫することが効果的です。例えば、パソコンを平らで硬い面に置く、または専用の冷却スタンドを使用することで、空気の流れが改善されます。
布やカーペットの上にパソコンを置くと、通気口が塞がれてしまい、内部の熱が逃げにくくなります。また、通気口の近くに物を置くことも避けましょう。
ThinkPad内部のホコリを取り除く
パソコン内部のホコリは、冷却能力を低下させる主な原因の一つです。専用のエアダスターを使用して、通気口やキーボードの隙間からホコリを吹き飛ばしましょう。ファンの排気口にエアダスターを吹きかけるとパソコン内部にホコリが侵入することがあります。そのため、吸引力の弱い掃除機でホコリを吸い取るのもおすすめです。
また使用していないUSBポートなどに専用のキャップをすると、ホコリの侵入を防げます。ただし、パソコン内部の掃除はリスクを伴うため、分解する場合は専門業者に依頼するのもおすすめです。
ホコリの蓄積を防ぐためには、定期的なクリーニングが不可欠です。特に、高温多湿の環境やペットがいる場合は、ホコリが溜まりやすいため、頻繁にクリーニングしましょう。
参考:ノートブックを掃除しよう!簡単にきれいにするコツや注意点
ThinkPadの置き場所を変える
パソコンの置き場所を変えることも、過熱問題の解決に役立ちます。例えば、直射日光が当たる場所や暖房器具の近くではなく、涼しい影のある場所にThinkPadを設置することで、熱が逃げやすくなります。エアコンや扇風機で、室内の温度を調整することも大切です。
また、ThinkPadを物で囲まない、柔らかい布の上に置かないなど、通気しやすい環境にThinkPadを設置するなど、設置場所に注意しましょう。
アプリやソフトを閉じる
ThinkPadが熱い時には、高い負荷がかかっていることが原因になっている場合があります。多くのアプリやソフトがバックグラウンドで動作していると、パソコンのメモリやCPUに負担がかかり、ThinkPadが高温になるため、システム全体のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。
特に、重いプログラムや複数のアプリケーションを同時に開いている場合には、パソコンの処理速度が著しく低下することがあります。不要なアプリやソフトを閉じることで、パソコンへの負荷を下げると温度が下がり、動作の改善も期待できます。
省電力設定に変更する
パソコンの消費電力が増えると、パソコンの温度も高温になります。パソコンの省電力設定は、パソコンの消費電力を抑制する機能。そのため、パソコンが熱いときにも設定を変更すると改善することがあります。ただし、パソコンのパフォーマンスが落ちるため、適度に切り替えることが重要です。
Windowsのパソコンでは、OSの機能によって省電力モードがあり、Windows11の場合は以下の手順で切り替えできます。
- 「スタート」ボタンから「設定」を選択
- 「システム」から「電源とバッテリー」を選択
- 「電源プランの選択」を選択
- 「電源モード」から「トップクラスの電源効率」を選択
以上で、ThinkPadの電力設定を最も省電力のモードに変更できます。なお、「バランス」は中程度の電力を消費してパソコン効率も中程度、「最適なパフォーマンス」はパソコンのパフォーマンスを最大にするために、消費電力も大きくなります。
また、ThinkPadには「省電力マネージャー」が標準搭載されており、節電効率重視の設定から、パフォーマンスと消費電力のバランスを重視した設定まで、簡単に切り替えできます。OSの電源オプションにはない機能があり、より高い省電力効果が期待できます。
パソコン用の冷却グッズを使用する
ThinkPadが熱い時には、パソコン用の冷却グッズを使用するのもおすすめです。冷却グッズは本来、予防のために使用することが多いのですが、パソコンが熱くなった時に本体を冷却するためにも使用できます。特にゲーミングパソコンや高負荷の作業の際に、有効な対策となります。
例えば、冷却パッドや冷却シートは、パソコンの底面に設置することで、効率的に熱を逃がし、適切な温度を維持するのに役立ちます。また、外付けファンは、パソコンの熱くなりやすい部分に風を送り込めるため、効率よくパソコンを冷却できます。
CPUやGPUが高温になっている場合は、熱を発生するパーツと冷却装置の間に新しい熱伝導性グリスを塗ることで、熱伝達効率を向上させ冷却性能を向上できます。このようにパソコン用の冷却グッズを適切に使用することで、パソコンの冷却を効果的に行い、本体の性能の維持や故障のリスクを低減できます。
サポートに連絡する
ここまで紹介した対処法を試してもThinkPadの問題が解決しない場合は、メーカーサポートに連絡することが最後の手段となります。
Lenovoサポートでは、製品名やシリアル番号を入力して、修理を依頼できます。ThinkPadのハードウェアの故障や複雑なソフトウェアの問題が疑われる場合、サポートに連絡することで解決することも多いでしょう。Lenovoサポートを利用する前には、パソコンの型番やシステム情報、発生している問題の詳細を準備しておくと、申し込みもスムーズです。
参考:Lenovo サポート
Lenovo「ThinkPad」のファンが回りっぱなしの場合の対処法
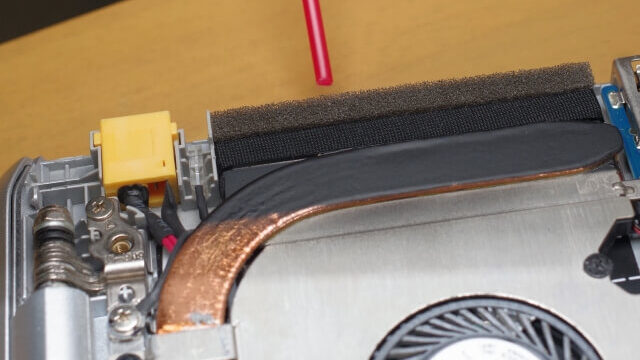
ThinkPadを長時間使用していると本体が熱くなり、さらにファンが回りっぱなしになることもあります。これはパソコンが高温になり、温度が下がらないために、ファンが回り続けている可能性があります。
通気口を掃除する、アプリを終了するなど紹介した対処法を試して、本体の温度が下がるとファンの回転が止まる可能性もあります。それでも、ファンの回転数や回転音が気になる場合は、以下の対処法を試してみてください。
- CPUの使用率を確認する
- BIOSをアップデートする
それぞれ解説します。
CPUの使用率を確認する
CPUの使用率が異常に高い場合、ファンが回転し続ける原因である可能性が高いです。以下の手順でタスクマネージャーを開き、CPUの使用率をチェックしましょう。
- 「Ctrl+Shift+ESC」を押してタスクマネージャーを開く
- ウィンドウの上の「プロセス」タブをクリック
- 「CPU」をクリック
- 全てのプロセスがCPU使用量の多い順から並べられる
- 終了したいプロセスを選び「タスクの終了」をクリック
- CPU使用量が通常になるまで繰り返す
参考:Lenovo 高 CPU 利用量(負荷)の問題を解決する
特定のアプリやプロセスのCPU使用量が多い場合は、そのアプリが原因の可能性が高いです。例えば、バックグラウンドで動作するアップデートプロセスや、重いグラフィックス処理を要求するアプリなどが考えられます。ただし、CPUの使用量が50%を超えている場合にファンが高速回転して異音がするのは、通常の動作です。
高CPU使用率の原因が特定できたら、そのプロセスを終了させることで、CPU負荷を軽減できます。CPUにかかる負荷を軽減することで、ThinkPad内部の温度が下がり、ファンの回転数が減少する可能性も高くなります。
BIOSをアップデートする
BIOSを最新の状態にアップデートすることで、システムの安定性が向上し、ファンの制御が最適化されることがあります。BIOSの冷却管理ロジックが間違っている場合には設定を変更しましょう。
BIOSのアップデートは、Lenovoサポートサイトから最新のBIOSバージョンをダウンロードして、指示に従ってインストールします。BIOSをアップデートしたら、BIOSに入り、「F9」を押して、デフォルト設定に戻してから「F10」を押して変更を保存します。ファンとCPUの最大パフォーマンスの設定によっては、ファンを高速で回転させ過ぎる原因となります。バランスの設定を選択すると、ファンが回り続けることを抑えられます。
Lenovo「ThinkPad」が熱くならないためにできる対策

LenovoのThinkPadは、使用し続けるとどうしても熱くなりやすくなります。本体が熱くなってから対策するよりも、事前に熱くならない対策をしておく方が、パソコンにかかる負担を軽減できます。ThinkPadを使用する際には、以下の対策を実行しましょう。
- 定期的に内部をクリーニングする
- 設置場所に注意する
- 長時間の使用を避ける
このように対策することで、ThinkPadの寿命を延ばすこともできます。それぞれ詳しく解説します。
定期的に内部をクリーニングする
ThinkPadのパフォーマンスを長期間維持するためには、内部のクリーニングが欠かせません。ホコリやゴミは冷却システムの効率を低下させ、結果として過熱を引き起こす可能性があります。
クリーニングは3~6ヶ月に1回を目安に行い、エアーダスターを使用してファンやヒートシンクからホコリを除去します。排気口のホコリは、吸引力の弱い掃除機で吸いだしましょう。
定期的に内部クリーニングすることで、内部にホコリが溜まりにくくなり、冷却効果が大幅に向上しThinkPadの過熱を防ぐことができます。
設置場所に注意する
ThinkPadなどのノートパソコンは、室内温度にも影響され、熱くなることがあります。直射日光があたる場所や高温多湿の場所などには、置かないようにしましょう。また、パソコンは温度が上がると冷却するために排熱する機能があります。機能を活かすために、通気性の良い場所に置くことも大切です。
パソコンの周りを物で覆わない、排気口をふさがない、柔らかい布の上に置かないなどに注意しましょう。また、ノートパソコンスタンドや冷却パッド、外部ファンなどの冷却グッズを使用して、パソコンが熱くならないように事前に対策しておくことのもおすすめです。
長時間の負荷のかかる使用を避ける
長時間にわたる高負荷作業は、ThinkPadの過熱の大きな原因となります。特に動画編集やゲームなど、リソースを大量に消費するタスクを実行する場合、適切な休憩を挟むことでパソコンの温度を管理できます。
また、高負荷の作業が続く場合は、よりスペックの高いパソコンへの買い替えもおすすめです。スペックが高くなると、負荷の高い作業も余裕を持って実行できるようになるため、パソコンが高温になるリスクを避けられます。
パソコンを使用しない時はスリープモードに設定するよりも、定期的にシャットダウンしましょう。パソコンは高温に弱く、長時間高温になり続けると、故障などのリスクもあります。あらかじめ過熱対策をすることで、ThinkPadの寿命を延ばせるでしょう。
まとめ:LenovoのThinkPadが熱い時には使用を中止するのがおすすめ

LenovoのThinkPadが熱いと感じたら、最初にできる対策は、使用を中止して休ませることです。パソコンを熱いまま放置すると、故障や発火のリスクがあるため、すぐに対策するのがおすすめです。
また、ThinkPadを健康な状態で長持ちさせるには、日頃から過熱対策しておくことも重要です。定期的なクリーニングと適切な設置場所、そして適切な使用法が鍵となります。適切に過熱対策をすることで、冷却システムの効率を高め、システムの安定性を保ち、結果的にThinkPadの寿命を延ばすことができるのです。
過熱は避けられない問題かもしれませんが、適切に対策することで最小限に抑えることも可能です。ThinkPadが熱いと感じたらただちに使用を中止して、この記事で紹介している対処法を実行し、ThinkPadを長持ちさせましょう。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
Let’s noteを使用していると、本体が熱いと感じることがあります。Let’s noteは軽くてコンパクトなボディながら高性能で、多くのビジネスマンに人気ですが、性能上オーバーヒートしやすいとも言われています。
Let’s noteを熱いままで放置すると熱暴走などの不具合が起こり、最悪の場合故障してしまうリスクも。そのため、本体が熱いと感じた時にはすぐに対処することが大切です。
この記事では、Let’s noteが熱くなる原因と、自分でできる対処法を解説します。パームレストが熱いと感じる場合の原因も解説しますので、参考にしてください。
【この記事でわかること】
- Let’s noteが熱い主な原因は高負荷やホコリ
- 対処法は掃除や室温調整、電源管理など
- Let’s noteが熱いまま放置するのは危険
Let’s noteが熱くなる原因は?パームレストが熱い原因も

パソコンの過熱は、長時間の使用による不具合や性能低下の可能性があります。
特にLet’s noteのようなノートパソコンは、コンパクトな設計のために熱がこもりやすく、過熱しやすい特性を持っています。Let’s noteが熱くなる原因は、主に次の6つがあります。
- 長時間使用している
- CPUに負荷がかかりすぎている
- 室温が熱い、高温の場所にLet’s noteを置いている
- Let’s note内部にホコリが溜まっている
- パームレストが熱いのは冷却ファンの故障の可能性
- 周辺機器が発熱している
まずは、Let’s noteが熱くなる原因を知り、対処しましょう。ここでは、Let’s noteが熱くなる原因をそれぞれ解説します。
長時間使用している
パソコンを使用していると、様々なパーツから熱が発生します。パソコン内部には、冷却ファンなどで熱を逃す機能がありますが、長時間使用し続けると排熱処理が追いつかなくなることがあります。その結果、結果本体が高温になってしまいます。
CPUに負荷がかかりすぎている
ノートパソコンが高温になる原因には、内部パーツに負荷がかかりすぎていることもあります。
CPUは、パソコンの「脳」とも言える部分で、計算やデータ処理を行います。複数のプログラムを同時に実行したり、動画編集やゲームといった高度な処理を要求するアプリケーションを使用すると、CPUに大きな負荷がかかります。CPUの稼働率は、以下の方法で確認できます。
- スタートボタンを右クリック
- 「タスクマネージャー」を選択
- 画面上部にある「パフォーマンス」を選択
- 「CPU」を選択
- 「使用率」欄に表示されるCPU使用率を確認
CPUに負荷をかけすぎないためには、最大限稼働しないで、最大でも99%以内の稼働に抑えるのがおすすめです。さらにCPUへの負荷を減らすためには、複数のアプリケーションを同時に開かない、バックグラウンドのプログラムを停止する、ゲームの設定を低くする、グラフィックボードの設定を変更するなどの方法もあります。
また作業内容に対してパソコンのスペックが低い場合にも、高い負荷がかかるため本体が熱くなる原因になります。特に動画編集や、高画質のオンラインゲームをプレイする場合などは、高いスペックのパソコンが必要なため、低スペックのパソコンでは負荷がかかりすぎて本体が熱くなりやすくなります。パソコンを購入するときには、作業内容にあったスペックのパソコンを選ぶことも大切です。
室温が熱い・高温の場所にLet’s noteを置いている
周囲の温度が高いと、パソコンの冷却が追いつかず内部温度も上昇します。パソコンはその周囲の環境にも敏感で、一般的にパソコンを使用する際の適正温度は5~35℃と言われています。Let’s noteの使用環境条件も温度は5~35℃、湿度は30~80%で、それ以上高温になると動作が不安定になることがあります。
高温の場所や直射日光が当たる場所で使用すると、内部の熱を効率よく放出できず、過熱しやすくなります。室温が高い場合や高温になる場所では、冷却システムが正常に機能していても、内部温度が安定しないことがあるため注意が必要です。
Let’s note内部にホコリが溜まっている
パソコン内部のホコリは、パソコンの冷却効率を低下させる原因のひとつです。特に、冷却ファンや排気口にホコリが溜まると、熱が外部に逃げにくくなります。
Let’s noteが熱い時に、排気口から暖かい空気が出ていない場合は、排気口がホコリでふさがれて排熱できない状態になっている可能性が高くなります。また、ホコリが内部コンポーネントに付着すると、ホコリが熱を帯びてパソコンの温度上昇を招くこともあります。
パームレストが熱いのは冷却ファンの故障の可能性
冷却ファンがうまく機能していないと、パームレストやキーボード付近が熱くなることがあります。冷却ファンは、パソコン内部の熱を外部に逃がす重要な役割を持っています。
このファンが故障すると、発生した熱が効率よく外部に排出されず、パームレストを含むパソコンの特定の部分が熱くなる原因となります。特にファンから異音がする場合や回転の不具合が見られる場合は、故障のサイン可能性もあるため、冷却ファンをチェックしましょう。
周辺機器が発熱している
充電中や接続している外部機器が原因で熱が発生することもあります。充電器は充電中にはノートパソコンへ電力を供給しつつ、充電器本体も熱くなります。充電器が熱くなることでノートパソコンの内部の温度が高温になります。
また、外付けHDDやUSBデバイスなどの周辺機器も使用中に発熱するため、これらの周辺機器が原因でパソコンが熱くなることもあります。特に電力消費の大きい機器を接続している場合、その熱がLet’s noteに伝わり内部温度が上昇することがあります。使用していない周辺機器を接続したままにしておくと、余計な熱が発生することもあるため、使用していない時には取り外しておくのがおすすめです。
Let’s noteが熱い時にできる10個の対処法

Let’s noteを使用していると、高負荷な作業や長時間の使用によって本体が熱くなることがあります。Let’s noteが熱い時にできる対処法は、以下の10個です。
- Let’s note内部のホコリを取り除く
- ファンをクリーニングする
- ファンを交換する
- CPU性能を抑制する
- 室温を調節する、置き場所を変える
- 使わないソフトを終了する
- 長時間使用しない
- 電源オプションから省電力設定にする
- 使わないときは電源を切る
- 冷却グッズを使用する
これらの対処法を試すことで、Let’s noteのパフォーマンス低下や故障のリスクを減らせます。順番に解説します。
Let’s note内部のホコリを取り除く
Let’s note内部にはホコリが溜まりやすいため、1か月に1回程度ホコリを掃除するお手入れをすることも大切です。Let’s note内部のホコリの清掃方法の手順は、以下の通りです。
- Let’s noteをシャットダウンする
- 電源ケーブルを抜く
- ディスプレイを閉じてパソコンを裏返す
- バッテリーパックを取り外す
- ねじを取り外してダストカバーを引き抜いて外す
参考:Panasonic Store レッツノートのお手入れ方法について
Let’s noteは裏蓋を開けることなく、ホコリを取り除くことができます。1か月に1回程度お手入れすることで、Let’s noteを快適に使い続けられるでしょう。排気口から正常に排気できれば、パソコン内部の温度上昇を防げるため、本体の温度も正常に戻る可能性があります。
ファンをクリーニングする
冷却ファンにホコリが溜まりすぎて、動きを阻害し、Let’s noteが熱くなっている可能性もあります。パソコン内部の掃除だけでなく、冷却ファンに溜まったホコリを取り除くことで、ファンの機能が回復し、うまく放熱することがあります。
ただし、ファンのクリーニングはLet’s noteを分解する必要があります。マザーボードやDVDドライブなどにも触れる必要があるため、失敗すると完全に故障するリスクもあります。パソコン修理に自信がない場合は、専門業者に依頼するのが安全です。
自分でファンをクリーニングする場合の手順は、以下の通りです。
- キーボードを慎重に取り外す
- 防水シートがある場合は取り外す
- DVDドライブを取り外す
- マザーボードを取り外す
- ファンブレードを取り外す
- ブレードの内側やローター部分を掃除する
- グリスを塗布しなおす
- すべての作業が完了したら、元通りに組み立てる
ファンを交換する
ファンが完全に故障して止まっている場合は、掃除ではなく交換を検討しましょう。ファンが回転していても、カラカラというような異音がする場合も交換がおすすめです。ファンを交換すれば冷却性能が向上し、Let’s noteが熱くなることも減ります。
冷却ファンは、使用しているLet’s noteにあった種類を購入する必要があります。また、本体の分解も必要なため、故障のリスクもあります。自信がない場合は専門業者に依頼しましょう。ファンを交換する手順は以下の通りです。
- ファンの型番を確認し、適合する新しいファンを購入する
- 裏蓋を取り外し古いファンを取り外す
- ファンが正しい向きであることを確認して新しいファンを取り付ける
- 電源を入れてファンが回ることを確認する
CPU性能を抑制する
Let’s noteは、Windowsの機能によってCPUのパフォーマンスを抑制できます。CPUのパフォーマンスを抑制しても、Let’s noteの動作に大きな影響は出ないため、発熱を抑えるためにパフォーマンスを変更しましょう。CPUのパフォーマンスを抑制する手順は、以下の通りです。
- タスクバーの検索欄で「電源」と入力
- 検索結果一覧から「電源プランの編集」を選択
- 「詳細な電源設定の変更」を選択
- 「プロセッサの電源管理」を展開
- 「最大のプロセッサの状態」を確認
- 「バッテリ駆動」と「電源に接続」が100%になっていれば99%以下に下げる
- 「OK」して完了
100%から1%下げるだけで、発熱を抑える効果がありますが、発熱が気になる場合は、様子を見ながら少しずつ下げてみましょう。
またLet’s noteは、「Panasonic PC設定ユーティリティ」によって、冷却ファンの回転数を切り替えできます。「標準」では、パソコン内部の温度に合わせて調節しますが、「高速」に設定すればCPUの使用率が高い場合にファンの回転数を上げて内部の温度を下げることができます。
室温を調節する、置き場所を変える
室温が28度を超えると、Let’s noteは熱くなりやすくなります。エアコンや扇風機を使って、室温を25度以下に保ちましょう。また、直射日光が当たることも、Let’s noteの内部温度が上がる原因です。風通しの良い机の上や、壁から少し離した場所にLet’s noteを設置し直してください。
Let’s noteを設置する際には、通気口をふさがないことも大切です。ノートパソコンスタンドを使用する、机や壁から少し離して設置するなどで、Let’s noteの周りの通気を良くすると本体の熱を逃しやすくなります。
使わないソフトを終了する
同時に多くのソフトを開いて作業をすると、パソコンに高い負荷がかかります。複数のソフトを同時に使用している場合は、Let’s noteも熱くなりやすいため、注意が必要です。
タスクバーを確認して、使用していないソフトやアプリが起動していないか確認しましょう。バックグラウンドで動作しているソフトやアプリも終了させると効果的です。日頃から、使い終わったソフトはその都度終了する習慣を付けておくことも大切です。
長時間使用しない
Let’s noteを長時間使用し続けると、CPUなどの内部パーツに負荷がかかり本体が熱くなることがあります。長時間使用している場合は、使用を中止してしばらくLet’s noteを休ませることで、長時間使用での過熱を防げます。例えば1時間使用したら10分休憩するなど、適度に使用しない時間を設けましょう。
電源オプションから省電力設定にする
パソコンの消費電力が増えると、パソコン本体が熱をもちやすくなります。Let’s noteは、「Panasonic PC設定ユーティリティ」によって省電力設定ができます。比較的新しいLet’s noteのモデルには、省電力設定がありませんが、ファンのモードやバッテリ残量の補正、照度センサーを利用した電源管理ができます。
また、Windowsの機能によって以下の手順で省電力設定にすることも可能です。省電力設定に変更することで、発熱を抑えられるでしょう。
- タスクバーの検索窓で「電源」と検索
- 「電源オプション」から「電源プランの選択またはカスタマイズ」にある「プラン設定の変更」を選択
- 「高パフォーマンス」になっている場合は「バランス」などに設定する
使わないときは電源を切る
Let’s noteを常に電源を切らないで使い続けていると、負荷がかかり続けて本体が熱くなることがあります。Let’s noteを使わない時には、電源を切って休ませることでパソコンにかかる負担を軽減できます。長時間使用しない時や、1日の作業が終わった時などには、Let’s noteの電源を切るようにしましょう。
冷却グッズを使用する
Let’s noteなどのノートパソコンは、冷却ファンの交換などの内部修理が難しくなります。そのため外部から、本体を冷却できる様々な冷却グッズが販売されています。例えば、ノートパソコンを置けるスタンドに冷却ファンが付属しており、通気性を良くするグッズや、複数のファンがついたノートパソコン用のクーラーなどのグッズもあります。
これらの冷却グッズを使えば、Let’s noteが高温になりすぎて熱暴走するリスクも軽減されます。冷却グッズには大きさや冷却性能に違いがあるため、使用する場所や用途に合わせて最適なものを選びましょう。
Let’s noteが熱い時の注意点

Let’s noteが熱い時には、すぐに対処することが最も大切ですが、以下の注意点もあります。
- 熱暴走を起こすことがある
- 放置するとLet’s noteが故障するリスクがある
- 氷を使って冷却しない
Let’s noteが熱い時には、放置することは危険です。以下で、注意点について詳しく解説します。
熱暴走を起こすことがある
パソコンの熱暴走とは、突然シャットダウンする、フリーズする、エラーが出るなどの不具合が起こることを言います。パソコンは高温になると危険を察知して、自動で電源を落とすことがあります。また、高温になりすぎるとCPUの機能が停止するため、フリーズやエラーが起こることがあります。
熱暴走が起こると、Let’s noteの寿命が短くなる、保存していないデータが失われるなどのリスクがあります。そのためLet’s noteが熱いと感じたら、熱暴走を起こす前に使用を中止しましょう。
Let’s noteが起動しない、重いなどの不具合がある場合は、下記記事でも対処法を解説しています。
レッツノートが起動しない!よくある症状と原因別の対処法を解説>>
放置するとLet’s noteが故障するリスクがある
Let’s noteを熱いまま放置すると、パーツが高熱になり、溶けて故障するリスクがあります。パソコンは高温に弱いため、高温のまま放置すると熱暴走を起こすなどで、ダメージが蓄積し故障するリスクもあります。
パソコン内部パーツが高温になると、内部のホコリに引火して発火するリスクもあります。パソコンが発火すると火災が起こる可能性もあるため、Let’s noteが熱いだけでなく、焦げ臭い、煙が出ているなどの兆候があったらすぐに使用するのをやめてください。
氷を使って冷却しない
Let’s noteが熱い場合には、すぐに冷やす必要がありますが、氷や保冷剤を使って冷やすのはやめましょう。氷や保冷剤を使用すると、溶けた時に水分がパソコン内部に入り込み、故障するリスクがあります。
また、急激に冷やすとパソコン内部に結露が発生する可能性もあり、故障の原因になることがあります。Let’s noteを冷却する際には、パソコン専用の冷却グッズを使用して、急激に冷やさないようにしましょう。
まとめ:Let’s noteが熱い時にはすぐに対処しよう!日頃の使い方も注意する

Let’s noteは人気のパソコンですが、コンパクトな設計のため排熱性能が低く、発熱しやすいともいわれています。しかし、日頃から定期的にホコリを取る、置き場所に注意するなどの発熱対策をすることで、快適に使い続けることも可能です。
Let’s noteが熱い時には、発火や熱暴走を起こし、最悪の場合は故障する可能性もあるため、Let’s noteが熱いと感じたら、すぐに対処することが大切です。室温を調整する、置き場所を変える、長時間使用しないなど、簡単な対処で改善する可能性もあります。
パームレストやキーボードが熱い場合は、冷却ファンに不具合が起きている可能性があるため、掃除や交換などで対処しましょう。Let’s noteは高価なパソコンのため、長く使い続けたいものです。この記事を参考に発熱対策をして、快適にLet’s noteを使い続けましょう。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。