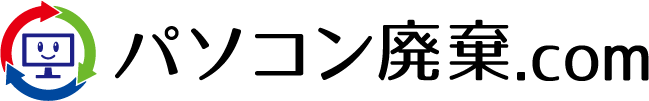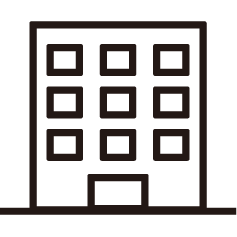404 Not Found
Galaxyを利用中に動画や音楽の音が聞こえないということはありませんか?
音が出ないときの多くは故障よりもミュートになっている、再生メディア側の音量が0になっているなどの簡単な原因であることがよくあります。
この記事では
- Galaxyの音が出ないときに確認すべき項目
- Galaxyの音が出ないときの対処法
- Galaxyの着信音が鳴らないときの対処法
について解説していきます。
Galaxyの音が出ないときに確認すべき項目

Galaxyの本体や接続したイヤホンから音が出ないときは以下の項目を確認しましょう。
- 音量がミュートになっている
- 再生しているメディアの音量がミュートになっている
- Bluetooth機器に接続されている
- マナーモードになっている
- 水没していないか確認する
音量がミュートになっている
意外と見落としがちなことですが、音量がミュートになってしまっていて音が出ないことがあります。
特に音量ボタンが知らないうちにポケットやカバンの中で押されてしまって、音量が0やミュートになってしまうことがあります。
音楽や動画を再生しても音が出ない場合はまずは音量設定を確認してみましょう。
再生しているメディアの音量がミュートになっている
Galaxy本体側の音量を調節しても音が出ないときは再生しているメディアのボリュームを確認しましょう。
アプリによっては本体の音量調節とは別に、アプリ側での音量が調節できるものがあります。
YouTubeやNetflixのアプリなどは独自に音量調節のアイコンがあるので、そこがミュートや0に近い状態になっていないか確認しましょう。
Bluetooth機器に接続されている
本体の音量は調節したし、アプリ側での音量も調節しても本体から音が聞こえないときはBluetooth機器に接続されていないか確認しましょう。
Galaxy で Bluetooth デバイスの設定を表示するには、次の手順に従います。
- 設定を開く
- 接続済みデバイスに移動
- ペアリング済みまたは 接続済みデバイスがないか確認
もしBluetooth機器に接続されている場合は接続を解除して音が出ないか確認してください。
マナーモードになっている
Galaxyがマナーモードになっていると本体から音が出ないことがあります。
マナーモード中はいったんボリューム調節キーを調節すると音が出るようになることもあるので、解除するかボリュームを上げてみましょう。
水没していないか確認する
Galaxy本体を水没させてしまったなどの思い当たる節がある場合は、スピーカー部分が濡れて音が聞こえないことがあります。
お風呂に落としたり、びしょ濡れになった後に音が出なくなった場合は下手にいじらずに乾くまでまってみてから再度音が出ないか確認してみましょう。
Galaxyから音が出ないときの対処法

Galaxyから音が出ないときは以下の対処法を試してみましょう。
- マナーモードを解除する
- Bluetooth機器を確認する
- 再起動する
- 本体を初期化する
マナーモードを解除する
Galaxyがマナーモードになっていて音が出ない場合はいったんマナーモードを解除してみましょう。
マナーモード中は音が一切でないということはありませんが、一時的にみゅーとに設定されていることがあります。
不意に音が出ないようにマナーモードがあるので、慌てずに設定を確認してみてください。
Bluetooth機器を確認する
Bluetoothのイヤホンやスピーカーに接続している場合はそちらから音が出るようになります。
特に複数のBluetooth機器と接続した後などは思わぬ機器に接続されていることがあり、本体はもちろん使っているイヤホンなどからも音が聞こえないことがあります。
Bluetoothにどの機器が接続されているかは設定から確認することができるので、不要な機器と接続している場合は切断して音が出るか確認しましょう。
再起動する
上記を試しても音が出ない場合はいったん再起動してみましょう。
音が出ないときに限らず、スマートフォンの調子が悪いときは再起動すると解決することが多いので、まずは試してみましょう。
本体を初期化する
ここまで解説した全てを試しても音が出ない場合はいったん本体を初期化してみるという方法もあります。
本体を初期化することは工場出荷時、買ってきたときと同じ状態に戻すことを意味しますが、初期化することで音が出ない原因となっている障害を元に戻すことができる可能性があります。
Galaxyを初期化するには以下の手順で行います。
- 設定アプリを開く
- 一般管理をタップ
- リセットをタップ
- 工場出荷状態に初期化をタップ
- 表示される内容を確認してリセットをタップ
- 全て削除をタップ
なお、初期化すると本体に保存されている全てのデータが失われます。
初期化する前に保存しておきたいデータはバックアップを取っておくことを忘れないようにしましょう。
Galaxyの着信音が鳴らないときの対処法

Galaxyの着信音が鳴らないことでお困りの方は以下の方法を実行しましょう。
- マナーモードを解除する
- 通知をミュートを解除
- 着信音の音量を上げる
マナーモード中は当然ですが、着信はならないように設定されています。
着信音を鳴らしたい場合はマナーモードを解除しましょう。
また着信を含めた通知自体をミュートしている場合も着信音は鳴りません。
さらに着信音の設定自体が0になっている可能性もあるので、通知や音量を再度確認してみましょう。
まとめ:音が出ないときはまずボリューム調節をしたりマナーモードを解除してみよう

以上、Galaxyで音が出ないときの対処法について解説してきました。
音が出ないときはまず以下のことを試してみてください。
- マナーモードを解除する
- Bluetooth機器を確認する
- 再起動する
- 本体を初期化する
上記を試しても音が出ない場合は残念ながら故障の可能性が高くなります。
故障したGalaxyを修理に出すのも一つの方法ですが、修理代金によっては買い換えてしまった方がよい場合もあるでしょう。
もしGalaxyを買い換えて古い機種が不要になった場合はパソコン廃棄.comの処分サービスはいかがでしょうか?
スマホは確実にデータを消去してから処分することがおすすめですが、本体を初期化したり、物理的に読み込めないようにするのは手間がかかります。
パソコン廃業.comなら、手間のかかるデータ消去や申し込みも不要で処分できます。
確実にデータを消去したい場合はぜひ検討してみてくださいね。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
富士通のパソコンを使用していると、突然音が出なくなり、困ることがあります。
パソコンから音が出ない原因は、音声がミュートになっている、イヤホンに接続されているなど単純なミスも多いです。まずは落ち着いて、簡単なことから順番に対処していきましょう。
この記事では、富士通のパソコンから音が出ない場合の原因や対処法を詳しく解説します。パソコンから音が出なくて困っている場合は、ぜひ参考にしてください。
【この記事でわかること】
- 富士通のパソコンから音が出ない場合は音量を確認
- スピーカーとの接続状況が原因のことも
- スピーカー設定やWindowsの更新などを調整してみる
- BIOSや本体を初期化する方法もある
- イヤホンからは音が出る場合は既定のデバイスの確認を
富士通のパソコンがフリーズした場合の対処法は、下記記事で詳しく解説しています。
富士通のパソコンがフリーズする原因と対処法!パソコン操作をスムーズに>>
富士通のパソコンから音が出ない!最初に確認すること

富士通のパソコンから音が出ない場合、簡単な方法で直ることもあります。まずは、以下を確認しましょう。
- 音量を確認
- 音量ミキサーで本体から音が出ていることを確認
- 本体の再起動
「パソコンから音が出ないと思ったら、ミュートになっていただけだった」ということもよくあることです。まずは音量の確認をしてみましょう。
パソコンに不具合がある場合、再起動することで解消することもあります。音量に問題がない場合は、試してみるのもおすすめです。それぞれ順番に解説します。
音量を確認
画面右下のスピーカーアイコンをクリックし、音量がミュートになっていないか、音量が小さくなっていないか確認します。
音量アイコンがグレーになっている、または✕がついている場合は、ミュート状態です。スピーカーアイコンをクリックして、ミュートを解除しましょう。音量バーが低い場合は、バーをドラッグして音量を上げてください。
スピーカーアイコンの横にある∧をクリックすると、出力デバイスのリストが表示されます。使用しているスピーカーが選択されていることを確認しましょう。
音量ミキサーで本体から音が出ていることを確認
スピーカーアイコンを右クリックし、「音量ミキサーを開く」を選択します。音量ミキサーでは、各アプリの音量を個別に調整できます。
- すべてのアプリの音がミュートになっていないか確認する
- システム音の音がミュートになっていないか確認する
- スピーカーのバーが動いているか確認する
特定のアプリから音が出ない場合は、そのアプリの設定を確認する必要があります。また、イヤホン端子にイヤホンが挿しこまれている場合は本体から音が出ません。イヤホンが挿し込まれていないことも確認しましょう。
本体の再起動
パソコンは一時的な問題であれば、再起動で解決する場合があります。富士通のパソコンは、以下の4つの方法で再起動できます。Windows11の場合の手順は、以下の通りです。
【スタートメニューから再起動】
- スタートメニューを開く
- 電源ボタンをクリック
- 再起動を選択
【タスクバーから再起動】
- タスクバーの電源ボタンをクリック
- 再起動を選択
【キーボードショートカット】
- Ctrlキー + Altキー + Delキーを同時に押す
- 画面右下の電源ボタンをクリック
- 再起動を選択
【電源ボタンによる強制再起動】
上記の方法で再起動できない場合は、電源ボタンによる強制再起動を試してください。
- 電源ボタンを長押しして、パソコンを強制終了する
- 数秒待ってから、電源ボタンを押してパソコンを起動する
再起動する前には、編集中の文書などのデータを保存しておきましょう。強制再起動は、データ損失などのリスクがあるため、最後の手段として使用してください。
参照元:FMVサポート [Windows 11] 電源を切る方法または再起動する方法を教えてください
以上の方法で再起動できない場合は、Windowsキー+Rキーを押して ファイル名を指定して実行を開き、「shutdown /r /t0」と入力して Enterキー を押します。
コマンドプロンプトを開き、「shutdown /r /t0」と入力して Enterキーを押す方法でも、再起動できます。
富士通のパソコンから音が出ない原因

富士通のパソコンから音が出ない原因は、以下の5つが考えられます。
- パソコンとスピーカーが正しく接続されていない
- サウンドドライバーの不具合
- Windowsシステムの不具合
- ハードウェアの故障
- ウイルス感染
それぞれ順番に解説します。
パソコンとスピーカーが正しく接続されていない
スピーカーやイヤホンが正しく接続されていないことが原因で、音が出ないことがあります。まずは、接続端子が緩んでいないか確認しましょう。挿し直して音が出るか確認します。
ヘッドホンやイヤホンは、しっかりと挿し込まれていない場合、音が出ない、片耳しか聞こえない場合があります。プラグを抜き挿しして、音が出るかを確認しましょう。
サウンドドライバーの不具合
サウンドドライバーとは、パソコンとスピーカー間の音声データをやり取りするソフトウェアです。サウンドドライバーが古くなっていたり、破損したりしていると、音が出ないなど不安定になる場合があります。
デバイスマネージャーから、サウンドドライバーのバージョンを確認しましょう。バージョンが古い場合は最新版に更新すると解消する場合があります。
Windowsシステムの不具合
Windowsシステムのファイルが破損したり、不具合が発生したりしていると、音が出ないことがあります。
Windows Updateを実行し、システムファイルを更新しましょう。システムファイルの破損を修復するコマンドを実行することもできます。
ハードウェアの故障
富士通のパソコンから音が出ない場合は、スピーカーやイヤホンなどのハードウェアが故障している可能性があります。
まずは、目視で故障している箇所がないかを確認しましょう。明らかな故障がない場合は、別のスピーカーやパソコンで音が出るか確認することで、ハードウェアの故障を特定することもできます。
ウイルス感染
ウイルス感染によって、音が出なくなる場合があります。Windows標準の「Windows Defender」でウイルススキャンを実行して、ウイルスが検出された場合は駆除しましょう。
富士通のパソコンから音が出ない場合の対処法【Windows11】

富士通のパソコンから音が出ない原因は、故障やシステムの不具合など様々です。音が出ない場合に自分でできる対処法は、以下10個があります。
- 音声出力を外部ディスプレイに変更する
- 音楽の再生に関するアプリをアンインストールする
- パソコンとスピーカーを再接続する
- スピーカーが有効になっていることを確認する
- サウンドドライバーを更新・再インストールする
- WindowsUpdateを実行する
- 放電する
- Windowsのトラブルシューティングを実行する
- BIOSを初期化する
- パソコンを初期化する
それぞれの対処法を詳しく解説します。
音声出力を外部ディスプレイに変更する
スピーカーアイコンを右クリックし、「音量ミキサー」を選択します。「出力デバイス」で、使用したいスピーカーまたはヘッドホンをクリックして終了します。設定が完了したら、パソコンから音が出ることを確認しましょう。
音楽の再生に関するアプリをアンインストールする
音楽再生アプリをインストールしたことが原因で、音が出なくなることがあります。問題が発生した後にインストールしたアプリをアンインストールして、音が出るか確認します。アプリをアンインストールする手順は、以下の通りです。
- 「スタート」から「すべてのアプリ」をクリック
- 一覧からアンインストールするアプリを選択
- 右クリックして「アンインストール」をクリック
参照:Microsoftサポート Windows でアプリとプログラムをアンインストールまたは削除する
パソコンとスピーカーを再接続する
スピーカーやイヤホンをパソコンから取り外し、再度接続します。プラグが抜けていたり、緩んでいたりすると音が出ない場合があります。再接続しても音が出ない場合は、ケーブルが断線している可能性も。見た目は断線していなくても、ケーブルに違和感を感じる場合は交換しましょう。
スピーカーが有効になっていることを確認する
接続しているスピーカーなどの出力デバイスが無効の場合は、有効に設定し直せば改善する可能性があります。スピーカーを有効にするには、以下の手順で操作します。
- 「スタート」から「設定」を選択
- 「システム」から「サウンド」をクリック
- 「サウンドの詳細設定から「サウンドコントロールパネル」を開く
- 「再生」タブにある再生デバイスを確認
- 再生デバイスを「有効」にする
再生デバイス一覧にあるデバイスから音が出ていることは、プロパティから詳細タブを選択し、「テスト」ボタンを押せば確認できます。
サウンドドライバーを削除・再インストールする
「デバイスマネージャー」でサウンドドライバーを更新または再インストールすると、音声に関するトラブルを改善できる可能性があります。
まずは、以下の手順でサウンドドライバーを一度アンインストールしてから、再度インストールし直しましょう。
- 「スタート」メニューを開く
- 「デバイスマネージャー」を開く
- サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラーを展開する
- 問題のあるサウンドデバイスを右クリックして、デバイスのアンインストールを選択
- 「このデバイスのドライバーソフトウェアを削除します。」にチェックがついていないことを確認する
- アンインストールをクリック
- 本体を再起動する
次に、最新版のサウンドドライバーをダウンロードする手順は以下の通りです。
- 富士通のダウンロードページを開く
- 使用中の機種に応じたドライバーを見つける(例えば、「Realtek High Definition Audio オーディオドライバー (プレインストール版)」など。)
- 「ダウンロード」アイコンをクリック
- ダウンロードが完了したら、ダウンロードしたファイルを実行してインストールする
以上の手順で、富士通のパソコンのサウンドドライバーの最新版をダウンロードできます。なお、ドライバーの更新はパソコンの動作に影響を及ぼす可能性があるため、十分注意して実行しましょう。
Windows Updateを実行する
Windows Updateにはバグを修正するプログラムも含まれています。そのため最新の状態に更新することで、音声に関する不具合も修正される可能性があります。
富士通のWindows11のパソコンでWindows Updateを実行する方法は以下の通りです。
- 作業中のアプリケーションをすべて終了する
- 作成中のファイルは保存する
- 「スタート」ボタン→「設定」の順にクリック
- 「Windows Update」をクリック
- 「Windows Update」で、「更新プログラムの確認」をクリック
- 利用可能な更新プログラムがある場合、自動的にダウンロードされ、インストールの準備が始まる
- 更新プログラムのインストールが完了したら、パソコンを再起動する
参照:FMVサポート [Windows 11] Windows Updateの実行方法を教えてください。
放電する
パソコンは帯電すると正常に動作しないことがあります。そのため、パソコンから音が出ない場合も放電することで、改善する可能性があります。
- 作業中ファイルを保存しアプリを終了
- 電源を切る
- 電源ケーブルなどをすべて抜き、パソコン本体からACアダプターを取り外す
- バッテリーを取り外す
- ディスプレイケーブルやLANケーブルなどの周辺機器を取り外す
- 1~ 2分放置する
- パソコン本体にACアダプターや電源ケーブルを接続
- キーボードやマウスなどパソコンに付属していた機器だけを接続
- 電源プラグをコンセントに接続
- パソコンの電源を入れる
以上でパソコンの放電は完了です。電源ケーブルについているアースを接地すると帯電しにくくなります。
参考:富士通 FMVユーザーサポート パソコンを放電する方法を教えてください。
Windowsのトラブルシューティングを実行する
Windowsのトラブルシューティングを実行すれば、音声に問題が発生している場合に自動で不具合を修正してくれます。
- 「スタート」から「設定」を選択
- 「システム」 から「トラブルシューティング」、「その他のトラブルシューティングツール」 に進む
- 「オーディオの再生」 で「実行する」をクリック
- 問い合わせが表示される
- 「 音声の問題を解決するために自動診断を実行することに同意がありますか? 」と表示されたら「はい」をクリック
- しばらく待つ
- 対話形式でトラブルシューティングが続ける
BIOSを初期化する
BIOS 設定を初期化することで、問題が解決する場合があります。BIOSとは、パソコンの起動時にハードウェアを初期設定するソフトウェアです。
BIOSが破損したり、不具合が発生したりしていると、パソコンの起動や音声出力などの問題が発生することがあります。BIOSを初期化する手順は以下の通りです。
BIOSの初期化は、パソコンの起動や音声出力などの問題を解決するために行うものです。BIOSの設定を変更したい場合は、富士通のサポートページなどの情報を参考にして、慎重に操作しましょう。
- パソコンの電源を切り、電源ケーブルを抜く
- パソコンの電源ボタンを押しながら、電源ケーブルを挿し込む
- F2キーまたはDeleteキーを押して、BIOS設定画面を表示する
- BIOS設定画面で、「Load Optimized Defaults」または「Load Setup Defaults」を選択して、Enterキーを押す
- BIOS設定画面から、Exitを選択して、Enterキーを押す
- 「Save Changes and Exit」または「Save and Exit Setup」を選択して、Enterキーを押す
- パソコンが再起動される
パソコンを初期化する
ここまで紹介した方法を試しても音が出ない場合は、最終手段として初期化もおすすめです。初期化する場合は、以下の手順で実行しましょう。
【初期化前の準備】
- データをバックアップする
- デバイスの暗号化の回復キーを取得する
- Microsoftアカウントをメモする
- 周辺機器を取り外しACアダプターを接続する
【初期化の手順】
- 「スタート」ボタンから「設定」の順にクリック
- 「システム」をクリック
- 「回復」をクリック
- 「PCをリセットする」ボタンをクリック
- 「オプションを選択してください」と表示されたら「すべて削除する」、または「個人用ファイルを保持する」をクリック
- 「Windowsを再インストールする方法を選択します。」と表示された場合は、「ローカル再インストール」をクリック
- 表示されない場合は、次の手順に進む
- 「追加の設定」と表示されたら内容を確認し、問題がなければ「次へ」ボタンをクリック
- 「このPCをリセットする準備ができました」と表示されたら内容を確認し「リセット」ボタンをクリック
- リカバリが開始される
「すべて削除する」を選択すると、パソコンが購入時の状態に戻るため、初期化するのに数時間かかることがありますが、パソコンを譲渡したり、処分したりする場合におすすめです。
一方、個人用ファイルを保持するを選択すると、Windows、ドライバー、アプリの状態は「すべて削除する」と同じ状態に戻りますが、ユーザーアカウントや個人用ファイルなどを保持します。一部データが保持されるため、不具合が完全に修正されない可能性があります。
参照:FMVサポート [Windows 11] 「このPCを初期状態に戻す」(リカバリ)の実行方法を教えてください。
パソコンから音が出ないがイヤホンから音が出る場合はどうする?

パソコン本体から音が出なくても、イヤホンからは音が出る場合もあります。イヤホンから音が聞こえて、本体から音が聞こえない場合は単純な設定ミスの可能性もあります。以下の対処法を試してみましょう。
- 既定のデバイスをスピーカーに設定する
- 音量ミキサーを確認する
- スピーカーの設定を調整する
順番に解説します。
既定のデバイスをスピーカーに設定する
パソコンの初期設定では、本体のスピーカーが出力デバイスに設定されていますが、一度他のデバイスに設定して再生すると既定のデバイスが自動的に変更されることがあります。
既定のデバイスが本体のスピーカーではない場合は、パソコンから音が出なくなることがあります。Windows11でスピーカーを既定のデバイスに設定する手順は、以下の通りです。
- メニューバーの「スピーカーのアイコン」を右クリック
- 「サウンドの設定」を開く
- 「サウンドの詳細設定」を開く
- 「再生」タブを開く
- 再生したい機器を右クリックして「既定のデバイスとして設定」を選択
音量ミキサーを確認する
既定のデバイスに設定しても、音が出ない場合は、音量に問題がある可能性があります。Windows11の場合は、タスクバーの音量アイコンを右クリックして「音量ミキサー」をクリックし、ボリュームを調整しましょう。
スピーカーの設定を調整する
スピーカーの設定によっては、スピーカーから音が出ないことがあります。スピーカー設定から、ミュートの状態や音量を調整することで、改善することがあります。手順は以下の通りです。
- 「設定」内の「システム」から「サウンド」を選択
- 「詳細設定」から「すべてのサウンドデバイス」をクリック
- 「スピーカー」など「出力デバイス」に表示されている項目をクリック
- プロパティで「オーディオ」の横にあるボタンが許可になっている場合はクリック
- 「出力の設定」のスピーカーミュートの確認し再生する音量を調整する
参照:FMVサポート [Windows 11] スピーカーから音が出ません。
それでも音が出ない場合の対処法

ここまで紹介した方法を試してみても富士通のパソコンから音が出ない場合は、修理や買い替えが必要な可能性があります。以下で詳しく解説します。
スピーカーやイヤホンの修理
様々な対処法を試しても、富士通のパソコンから音が出ない場合は、故障していることも考えられます。
富士通には会員同士のコミュニティサイトがあり、質問することで問題が解決できる可能性もあります。24時間問い合わせできるチャットサポートもあり、写真などを使ってパソコンの状態を相談可能。LINEでも相談できるため、使いやすい方法でまずは相談してみましょう。
パソコンを修理する場合は「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」から修理を依頼しましょう。
問い合わせ前には富士通のパソコンの品名・型名の確認方法から使用しているパソコンの型番などを確認しておくとスムーズです。
富士通の問い合わせ相談は、パソコンに電源を入れてから1年以内は無料で利用できますが、2年目以降は有料になります。問い合わせの方法や料金は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」から確認しましょう。
パソコンの買い替え
パソコンの修理には時間がかかり、費用が高くなることもあります。パソコンはどんどん進化しているため、購入から数年経過している場合は修理してもスペックが追いつかない場合もあります。
パソコンが古い場合は思い切って古いパソコンを処分して、買い替えを検討しましょう。
古いパソコンは小型家電リサイクル法によって、粗大ごみなどで簡単に処分できず、処分費用がかかることもあります。
パソコンを手軽に処分したいなら、パソコン廃棄.comがおすすめです。無料で古いパソコンを処分可能。データ消去も無料のため、安心してパソコンを処分できます。
まとめ:富士通のパソコンから音が出ない原因は音量のことも!

富士通のパソコンから音が出ない場合は、原因は単純なミスのことも多いです。まずは、パソコンの音量や出力などの設定を確認してみましょう。問題がない場合は、本体を再起動すると簡単に直ることがあります。
それでも音が出ない場合は、イヤホンやスピーカーなどのハードウェアの故障や、システムトラブルなどソフトウェアの不具合も考えられます。サウンドドライバーを確認する、Windows Updateの実行、放電などの対処法がおすすめです。
あらゆる対処法を試しても、音が出ない場合は、パソコンが故障している可能性もあるため、買い替えがおすすめです。パソコンを買い替えた場合は、古いパソコンは無料で簡単に処分できるパソコン廃棄.comをぜひご利用ください。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
この記事をご覧になっているということはGalaxyが突然反応しなくなって非常にお困りの状態ですよね。
Galaxyに限らずですが、スマホのタッチパネルが反応しないともはや何もできない状態になってしまいます。
タッチパネルが反応しない原因はフリーズやキャッシュの溜まりすぎ、画面の汚れなどさまざまなことが考えられます。
この記事では
- Galaxyのタッチパネルが反応しない原因
- Galaxyのタッチパネルが反応しないときの対処法
について解説していきます。
Galaxyのタッチパネルが反応しない原因

タッチパネルが反応しない原因は主に以下のものがあります。
- 一時的にフリーズしている
- アプリが固まった
- 画面が汚れている
- 極度に指が乾燥している
一時的にフリーズしている
スマホの処理に負荷がかかったり、メモリが不足している場合はスマホがフリーズしてしまうことがあります。
フリーズしたスマホは一定時間操作を受け付けないので、タッチパネルが反応しないように見えることがあります。
頻繁にフリーズする場合はスマホのスペックが不足している可能性も考慮して、原因となるアプリのアンインストールなどの対策が必要となります。
アプリが固まった
Google Chromeなど使用しているアプリが固まってしまうとタッチ操作を受け付けないことがあります。
アプリが固まる大きな理由としてはメモリ不足です。
メモリは
- 複数のアプリを起動している
- アプリのキャッシュが溜まっている
- アプリのメモリ消費量が大きい
といったときに起こりがちです。
またアプリ自体の不具合やバグなどでも固まったりすることもあります。
画面が汚れている
画面が通常以上に汚れていると指の操作を読み取ることができず、タッチパネルが反応しないことがあります。
これは画面に付着した汚れがタッチパネルのセンサーを覆い、指の動きが認識できなくなるためです。
タッチパネルは指の静電気を利用して動作しており、指の静電気が画面に触れると、画面のセンサーが指の位置を認識し、タッチ操作を実行します。
しかし画面に汚れやゴミが付着していると、指の静電気がうまく伝わらず、センサーが指の位置を認識できなくなります。
そのため、タッチ操作が正しく実行されず、反応しないことがあります。
また、画面に付着した汚れやゴミが、タッチパネルの表面を傷つけたり、ゆがませたりすると、タッチ操作が不安定になることもあります。
極度に指が乾燥している
指が極度に乾燥している場合もタッチパネルが反応しなくなる原因となります。
指が乾燥しているとスマホの画面が反応しないのは、指の静電気がうまく伝わらないためです。
先述の通り指の静電気を利用して動作しており、指の静電気が画面に触れると、画面のセンサーが指の位置を認識し、タッチ操作を実行します。
指が乾燥していると、指の表面に水分が少なく、静電気がうまく発生しないため、センサーが指の位置を認識できなくなり、タッチ操作が反応しないことがあります。
Galaxyのタッチパネルが反応しないときの対処法

タッチパネルが反応しないときは以下の方法を試してみてください。
- アプリを終了させる
- 強制的に再起動する
- 画面をきれいにする
- 指を適度に湿らせる
アプリを終了させる
アプリを使用中にタッチパネルが反応しなくなった場合はいったん強制的にそのアプリを終了させましょう。
Galaxyでアプリを強制終了させるには以下の手順で行います。
- ホーム画面やアプリ利用中の画面で画面下部中央の四角のアイコンをタップ
- 反応しなくなったアプリをスワイプして終了させる
もしアイコンをタップしても反応がない場合は次に説明する強制再起動を実行します。
強制的に再起動する
アプリを終了させる画面が出せない、どこを触っても一切反応がないという場合は強制的に再起動することで解消する可能性があります。
Galaxyを強制的に再起動するには以下の方法で行います。
- 電源ボタンと音量下げるボタンを同時に 7 秒以上長押しする
- 電源メニューが表示されても、電源ボタンと音量下げるボタンは押し続けたままにする
- 電源メニューが消えたら電源ボタンと音量下げるボタンから指を離す
- 自動的に再起動する
一部の機種では上記の方法以外にも電源ボタンを7秒以上長押しすることで再起動できる場合があります。
手持ちのGalaxyの再起動方法は公式HPも参考にしてみてください。
画面をきれいにする
画面の汚れが原因と思われる場合は画面を不織布やマイクロファイバーなどで拭いてきれいにしてみてください。
汚れの種類はさまざまですが、保護シートの劣化など拭いても改善しない場合は、古くなった保護シートを剥がして動作するか試してみましょう。
指を適度に湿らせる
冬場などに手が極度に乾燥している場合は少し湿らせてからタッチパネルが反応するか試してみてください。
水洗いやエアコンなど手が乾燥しがちな季節はハンドクリームなどを適度に使用して皮膚が乾燥しすぎないようにすることが重要です。
ただしハンドクリームをつけすぎると画面が汚れる原因ともなるので、塗りすぎないように少量ずつこまめに塗るようにしましょう。
それでも反応しないときは?

ここまで解説した対処法を試してもタッチパネルが反応しない場合は残念ながら本体の故障の可能性があります。
本体が故障したと思われる場合は修理に出すほかありません。
Galaxyを修理するには以下の方法があります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 正規修理店に依頼 | ・純正パーツで修理してもらえる ・修理後もキャリアの保証期間が適用される | ・修理料金が高い |
| 民間の修理業者に依頼 | ・修理料金が正規店よりも安い ・当日に修理が完了する | ・保証がつかない、なくなる ・純正パーツではない |
| 自力で修理 | ・知識さえあれば最も安く直せる | ・失敗すると壊れてしまう可能性がある |
正規修理店に依頼
Galaxyを修理する方法の一つは正規修理店に依頼することです。
正規修理店は
- 原宿の「Galaxy Harajuku」
- ドコモショップ「Galaxyリペアコーナー」
の2つがあります。
「Galaxy Harajuku」は1店舗のみとなっており、東京近郊に在住であれば直接赴いて修理を受けることができます。
どちらも事前に予約が必要となりますが、最短60分で修理が完了するなどのメリットがあり、純正パーツを利用して直してもらえるため、画面の色味や操作性に違和感を感じることもありません。
ただし修理料金は民間の修理業者に比べると高めになる傾向にあるのはデメリットといえるでしょう。
民間の修理業者に依頼する
スマホ全般の修理を請け負っている民間の業者に依頼することでも修理を受けることができます。
民間の修理業者は修理代金が安いのがメリットです。
その代わりに純正パーツではないものを使われる可能性もあり、画面の色味などが純正と若干異なることがあるのがデメリットといえます。
自力で直す
パーツだけを購入して自分で直すという方法もないわけではありません。
ただしよほど知識と経験がないとGalaxyそのものを破損してしまうリスクがあり、おすすめできる方法とはいえません。
パーツ代のみで済むので、うまくいけば最も安く修理することができますが、デメリットを上回るとは言い難いものがあります
スマホの修理に精通している方以外は素直に修理に出すことをおすすめします。
まとめ:タッチパネルが反応しないときはまず再起動やアプリを終了してみよう

以上、Galaxyのタッチパネルが反応しないときの対処法について解説してきました。
タッチパネルが反応しないときはフリーズやメモリ不足が原因となることが多いので、アプリの終了や強制再起動を試してみてください。
また画面が汚れていたり、手が乾燥しすぎているときも反応が悪くなります。
原因に応じた対処法をまずは試してみましょう。
今回紹介した対処法を試しても改善しない場合は残念ながら本体の故障の可能性が高くなります。
修理に出すことも選択肢の一つですが、場合によっては買い換えを検討することもあるかもしれません。
もし買い換えで旧機種が不要となった場合はパソコン廃棄.comの処分サービスはいかがでしょうか?
スマホは確実にデータを消去してから処分することがおすすめですが、本体を初期化したり、物理的に読み込めないようにするのは手間がかかります。
パソコン廃業.comなら、手間のかかるデータ消去や申し込みも不要で処分できます。
確実にデータを消去したい場合はぜひ検討してみてくださいね。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
富士通のパソコンを使用していると、パソコンから異音がすることがあります。パソコンで作業していると、ハードディスクの動作音やファンの回転音など、なんらかの音がするものですが、いつもと違う異音が聞こえた場合には、注意が必要です。
パソコンから異音がする場合、そのまま使用し続けると、故障する可能性もあるため、原因を解明し対策しましょう。この記事では、富士通のパソコンを使用中に異音が聞こえた場合の種類や原因、対処法を詳しく解説します。
【この記事でわかること】
- 富士通のパソコンから異音がする場合は音をよく聞く
- いつもと違う音やうるさい音には注意が必要
- 置き場所を変える、掃除するなどで改善することも
- 故障ならメーカー修理や買い替えを検討
富士通のパソコンから出る異音とは?

富士通のパソコンは、使用中に音が聞こえることがあります。これらの音は、多くの場合異音ではなくパソコンを使用していると聞える通常の動作音です。その場合は故障ではないため、まずは音の種類をよく聞いてみましょう。
ただし、パソコンから聞こえる音で故障などを判断することは非常に難しいです。判断するポイントは、いつもとは違う音がするか、あまりにもうるさい音ではないかなど。このような場合はなんらかの不具合が起きている可能性があります。ここでは、富士通のパソコンから出る異音の種類について解説します。
ポツなどのパソコンを起動するときのノイズ音
パソコン本体の電源を入れたときや、Windowsを起動・終了するとき、省電力状態へ移行・復帰するときに「プチッ」「ポツ」などのノイズ音が発生することがあります。
これらの音は、電源状態が切り替わるときにオーディオ回路の出力信号が不安定になる、オーディオ回路を初期化する場合などに出力信号が変動するために発生する音です。
正常な音のため、使い続けて問題ありませんが、気になる場合は、サウンドドライバーを最新にすることで、ノイズ音が減ることがあります。
ハム音
パソコンのハム音とは、パソコンの内部から聞こえる低い音で、唇を閉じてハミングしているように聞こえるためハム音と呼ばれています。音の周波数は、50Hzまたは60Hzの交流電源の周波数に近いことが多いため、ハム音と呼ばれています。
ハム音の種類は大きく分けて電源ノイズと磁気ノイズの2種類。電源ノイズによるハム音はパソコン内部に搭載した電源やファンなどの電子機器から発生するノイズがスピーカーから聞えるもので、故障ではないため使い続けても問題ありません。気になる場合はアースを取る、パソコンの置き場所を見直すことで解消することもあります。
一方、磁気ノイズによるハム音はハードディスクやSDDの故障が原因のことがあります。ハードディスクやSSDが故障している場合は交換などで改善する可能性があります。
キーン、ジーなど電子回路の操作音(コイル鳴き)
パソコン使用中に聞こえる「キーン、ジー」などの高周波音はコイル鳴きと呼ばれます。電子回路の操作音(コイル鳴き)とは、電子回路のスイッチやリレーなどの接点が開閉する際に発生する音のことです。音の周波数は、接点の開閉速度に比例して高くなります。
コイル鳴きの原因は、接点の開閉時に発生する電磁誘導です。接点が開くと、接点間に流れていた電流が急激に遮断され、コイルに電磁誘導が発生します。この電磁誘導により、コイルに電流が流れて振動します。この振動が音となって聞こえるためコイル鳴きと呼ばれます。
コイル鳴きは、電子回路の動作に影響を与えることはありません。音が気になる場合は、接点の開閉速度を遅くする、振動を吸収するスポンジやゴムなどを取り付けるのも有効です。
ブーンなど光学ドライブ等ディスク類からの異音
光学ドライブは、ディスクを高速回転させて、レーザー光で読み取りを行います。このとき、ディスクが高速回転して「ブーン」という回転する音が発生します。
この音は、ディスクの種類や読み取り速度によって異なりますが、正常な動作音のため問題ありません。しかし、ディスクに傷や汚れがある場合には、音が大きくなることがあります。
また対応していないディスクをセットすると、通常よりも大きな音がしたり、音が停止するまでに時間がかかったりすることがあります。ドライブが破損する原因にもなるため、対応していないディスクを使用しないようにしましょう。
ピーピー、カシャカシャなどハードディスクからの異音
LIFEBOOK「CH75/W」、「WA3/W」の一部機種を使用している場合、ハードディスクから「ピーピーピー」と警告音のように一定時間鳴り続けることがあります。この場合は、ハードディスク用のファームウェアを更新することで改善します。
また富士通のノートパソコンの場合、パソコン操作終了後にカシャカシャと鳴ることがあります。ノートパソコンにはハードディスクにアクセスしていないときに、ヘッドを安全な場所に退避させる機能があり、その時に発生する音です。使用上問題ないため、そのまま使い続けてください。
ガッガッなどフロッピーディスクからの異音
古いパソコンの中には、フロッピーディスクドライブを搭載している機種もあります。フロッピーディスクドライブを搭載していると、起動時などに「ガッガッ」と音がする場合があります。
フロッピーディスクドライブが起動ドライブに指定されていたり、ファイル使用履歴にフロッピーディスクが残っている時に発生する音で、正常な動作音です。使い続ける上で問題はありません。
ブーンなどファンなどの回転音
パソコン内部には、CPUファンなどパソコン使用時に内部で発生する熱を排熱するためのファンがあります。パソコンは熱に弱いため、高温になって不具合を起こさないためにも排熱処理は重要です。
パソコンが高温になりすぎると、ファンが高速回転し、「ブーン」などの音が大きくなることがあります。また、ファンの周りにほこりがたまっている場合もファンの音が大きくなります。
また、パソコン内部のハードディスクにも操作に応じて回転するパーツが搭載されています。回転する度合いによっては、大きな回転音が聞えることがありますが、通常の動作音のため、使用を続けて問題ありません。
バチッなどのナノイー放出音
富士通のパソコンでナノイー発生ユニットを搭載した機種は、パソコンの動作中にnanoe(ナノイー)を放出します。ナノイーの放出中は、「バチッ」という放電音や、パソコンのファンの回転音とは別に「ブーン」というモーター音が鳴ることがあります。ナノイー発生ユニットの正常な動作音のため、使用を続けて問題ありません。
参照:FMVサポート パソコン本体から異音がします。故障でしょうか。
問題のある異音の種類と原因

パソコンから異音がする場合は、問題ない場合もありますが、音の種類によっては故障の可能性もあります。以下の音は、故障の可能性がある音です。
- ジージー
- ブーン
- カラカラ
- カタカタ
- ガラガラ
- キュルキュル
- ピーピーピーなどのビープ音
- 無音
以上のような異音がする場合は、以下の種類と原因を参考にして、適切に対処しましょう。
冷却ファンからのジー、ブーン、カラカラなどの音
冷却ファンからのジー、ブーン、カラカラなどの音は、ファンの故障や、ファンにほこりやゴミが溜まっていることが原因で発生することがあります。
ファンにほこりやゴミが溜まると、ファンの回転が悪くなり、異音が発生することがあります。パソコンの内部を掃除してほこりを取り除くことで、異音が改善する場合があります。
また、ファンのモーターやベアリングなどの部品が故障した場合にも、異音が発生することがあり、故障した場合には交換が必要です。
HDDからのシャーシャー、カタカタ、ガタガタ、キュルキュルなどの音
HDDから発生する異音でシャーシャー、カタカタ、ガタガタ、キュルキュルなどの音は、HDDの故障が原因で発生することがあります。
HDDはディスクが回転して磁気ヘッドによってデータを読み書きするため、通常動作音がします。カリカリ、ジーなどの音はシーク音と言い、HDDの動作音で問題ありません。
HDDのディスクやヘッドなどの部品が故障すると、HDDから以下のような音が発生することがあり、HDDの交換が必要になります。一方、まったくの無音の場合も故障の可能性があるため、注意しましょう。
| 異音の種類 | HDDの症状 |
|---|---|
| シャーシャー | 擦ったような音がする場合はHDD内部のパーツが接触している |
| カチカチ、カタカタ、ガタガタタ、キュルキュル、カコンカコン | データを読み書きする部品が故障している |
| カチャカチャ、カックンカックン | 激しい音がする場合はHDDが完全に故障する寸前になっている |
| 無音 | HDDのモーターが故障している |
HDDから異音がする場合は、使い続けると完全に故障する恐れがあります。異音がする場合は、すぐに使用をやめて修理などの対応をしましょう。
HDDの異音については下記記事でも詳しく解説しています。
HDDから異音がする!カチカチなど音の種類と対処方法を解説>>
ピッピッなどのビープ音
パソコンから発生するピーなどのビープ音は、パソコンの起動や動作に何らかの問題が発生していることを示す警告音です。BIOSがパソコンに異常があることを検知して鳴らしており、パソコンに深刻な不具合が起きている可能性があります。
電源を入れた時に発生するビープ音は、「ピッ」「ピッピッ」など、1回または連続したビープ音の組み合わせによって原因と対処法がわかります。
ビープ音が鳴る場合は、メモリの不良や、CPUやマザーボードの故障などが原因のか旺盛があります。メモリを抜き差ししたり、CPUやマザーボードなどの修理または交換が必要です。富士通のパソコンで発生する、ビープ音の種類は以下の通りです。
| ビープ音の回数 | 原因と対処法 |
|---|---|
| 1-2(1回目のビープ音は「ピーッ」と長めに鳴る) | PCIデバイス上のROMでエラーが発生している。正しく取り付けられていることを確認する。 |
| 1-1-1-11-3-3-11-3-3-21-3-4-11-3-4-31-4-1-1 | メモリのテストエラー。メモリが正しく取り付けられていることを確認する。 |
| 1-1-1-….(長めに鳴り続ける) | W630のカスタムメイドで選択したグラフィックカードに電源ケーブルが接続されていない。 画面上には、赤字で次の文字が点滅。「YOU HAVE NOT CONNECTED THE POWER CABLE TO YOUR VIDEO CARD.PLEASE REFER TO THE ‘GETTING STARTED GUIDE’ FOR PROPER HARDWARE INSTALLATION.」 電源ボタンを4秒以上押して電源を切り、グラフィックカードに電源ケーブルを接続し、10秒以上待ってから電源を入れ直す。 |
全く音がしない(無音)
パソコンは、通常なんらかの動作音がするものです。いつも聞こえているはずの動作音が全く聞こえない場合も、不具合が起こっている可能性が考えられます。パソコン内部を開けて、ファンが回転しているか、HDDが正常に動作しているかなどを確認しましょう。
また、パソコンから音が出ない場合は、以下が原因となっていることもあります。
- 音量がミュートになっている
- スピーカーやヘッドフォンが接続されていない
- スピーカーやヘッドフォンの故障
- パソコンの故障
富士通のパソコンから異音がする場合の注意点

パソコンの異音は故障の可能性もあるため、放置せずに早めに対処することが大切です。富士通のパソコンから異音がした場合は、以下の点に注意しましょう。
異音を放置しない
異音がするままパソコンを使い続けると、故障が悪化したり、他の部品に影響を与えたりする可能性があります。
ファンの故障の場合は、パソコンの熱によって内部から発火する可能性があります。HDDやCPUの故障の場合は、パソコンが使えなくなり、データを消失する可能性もあります。富士通のパソコンから異音がしたら、すぐに原因を調べて対処しましょう。
何度も再起動しない、電源のオンオフを繰り返さない
異音がしてパソコンが正常に動作しない場合は、何度も再起動したり、電源のオンオフを繰り返したりすると、故障を悪化させる可能性があります。
特にハードディスクやマザーボードは、通電する時に起こる電圧変化に弱いため故障するリスクが高まります。ハードディスクが完全に故障すると、データ消失のリスクもあります。
またで電源のオンオフを繰り返すと電源ユニットにも負荷がかかります。電源ユニットの故障にもつながるため、やたらとオンオフを繰り返さないようにしましょう。
パソコンに衝撃を与えない、分解しない
異音がするからといって、パソコンに衝撃を与えたり、分解したりするのは危険です。パソコン内部の部品が破損したり、ショートしたりする可能性があるためです。異音の原因を調べる場合は、パソコンの電源を切ってから専門業者に依頼するのがおすすめです。
急激にパソコンを冷やさない、氷などを使わない
パソコンを長時間使用した後に、保冷剤などで急激に冷やすと内部の部品に結露が発生して故障の原因になることがあります。
また、氷を使って冷却することも厳禁です。氷が溶けてパソコン内部に水が侵入して、ショートしたり、故障したりとさらに症状が悪化する可能性があります。パソコンを冷やすときは、エアコンや扇風機を使って徐々に冷やしていくようにしましょう。
富士通のパソコンから異音がする場合の対処法

まずは、異音がしている箇所を特定しましょう。富士通のパソコンから異音がする場合は、以下の対処法が考えられます。異音の種類によって、簡単なものから順番に試してみてください。
パソコンの設置場所を変える
パソコンを通気性の悪い場所や直射日光があたる場所、高温になる場所などに設置すると、内部に熱がこもりやすくなります。パソコンを以下の環境で使用すると異音が改善する場合があるため、見直してみましょう。
- 風通しの良い場所(接地面にすき間を作るなど)
- 周囲に物がない場所
- 涼しい場所
- 直射日光があたらない場所
ファンの掃除をする
パソコン内部にほこりが溜まっていると、ファンの回転が悪くなり、異音が発生することがあります。パソコンの内部を掃除するには、専用の掃除機やエアダスターなどを使用して、ほこりを吸い取ったり、吹き飛ばしたりします。
以下の手順で、まずはパソコンの外側からファンの掃除を行いましょう。
- パソコンの電源を切って、電源コードやプラグ類を抜く
- 乾いた布などで排気口を拭く
- 排気口に掃除機をあててほこりを吸いだす
パソコンの外側からほこりを吸い取っても異音が改善しない場合は、以下手順でパソコンのカバーを開けて内部のほこりを掃除することもできます。しかし、カバーを開けるとメーカー保証が使えなくなる可能性もあるため、パソコンに詳しくない場合はやめましょう。
- パソコンの電源を切って、電源コードやプラグ類を抜く
- パソコンの底面にあるネジを外し、底面カバーを取り外す
- ファンの周辺に溜まっているほこりを、専用の掃除機やエアダスターで取り除く
- ファンに傷や汚れがある場合は、清掃用アルコールで拭き取る
- 底面カバーを元に戻し、ネジを締める
- パソコンの電源を入る
パソコンを冷却する
パソコンが高温になっている場合は、ファンが過剰に動作して音がうるさくなることがあります。パソコンを冷却するには、以下の方法を試してみてください。
- エアコンなどを使いパソコンの周囲の温度を下げる
- パソコンの冷却性能を上げる
- パソコンの負荷を減らす
パソコンが熱い場合の対処法は下記記事でも詳しく解説しています。
パソコンが熱い原因は?音がうるさい時や起動しない時の対処法を解説>>
パソコンの負荷を減らす
パソコンの負荷を減らすことで、ファンの回転を抑えることができます。パソコンの負荷を減らすには、以下の方法を試してみてください。
- 起動しているプログラムやサービスを減らす
- 不要なファイルを削除する
- 不要なタスクを停止する
パソコンが重い場合の対処法は下記記事でも詳しく解説しています。
Windows11が重いときはどうするの対応は?原因と対処法を紹介!>>
HDDの状態を確認する
HDDの状態が悪いと、異音が発生することがあります。デフラグを実行したり、エラーチェックでHDDの状態を確認したりすることで、改善する可能性があります。
デフラグとは、HDD上のデータを連続した領域にまとめることで、読み書きの効率を高める作業です。エラーチェックとは、HDDのデータを読み込んで、エラーを検出する作業です。
デフラグは、以下の方法で実行できます。
- 「スタート」ボタンをクリック
- 検索ボックスに「デフラグ」と入力
- 検索結果の「デフラグと最適化」をクリック
- 「デフラグと最適化」ウィンドウで、デフラグを実行したいドライブを選択し、「最適化」をクリック
- デフラグが完了すると、完了メッセージが表示される
なおデフラグは、スケジュールを決めて自動で実行できます。デフラグのスケジュールを設定するには、以下の手順で行います。
- 上記の手順で「デフラグと最適化」を開く
- 「スケジュール」タブをクリック
- 「スケジュールに従って最適化する」にチェックを入れる
- 「最適化する曜日」と「最適化する時間」を設定する
- 「保存」をクリック
デフラグは、HDDのパフォーマンスを向上させるために重要な作業です。定期的にデフラグを実行して、パソコンのパフォーマンスを維持しましょう。
エラーチェックは、以下の手順で実行可能です。
- タスクバーの「エクスプローラー」アイコンをクリック
- 「PC」をクリック
- エラーチェックをしたいドライブを選択
- 右クリックして「プロパティ」をクリック
- プロパティ画面で「ツール」タブをクリック
- 「エラーチェック」の「チェック」を選択
- 「ドライブのスキャン」で確認
参照:FMVサポート [Windows 11] ハードディスクやSSDのエラーをチェックする方法を教えてください。
富士通のメーカーアップデートを実行する
パソコンのドライバが古いと異音が発生する場合があり、パソコンのドライバを最新バージョンに更新することで異音が改善するケースも。
富士通から提供されているメーカーアップデートを実行することで、パソコンのパフォーマンスや安定性が向上する場合があります。富士通のパソコンは、「アップデートナビ」を起動しておけば、最新情報をお知らせしてくれます。
アップデートナビを使用すれば簡単な操作でアップデートできるため、起動しておくのがおすすめです。
参照:FMVサポート アップデートナビの使い方を教えてください。(Windows 11)
異音の原因がわからない、鳴りやまない場合の対処法

上記の対処をしても異音が改善しない場合は、パソコンの故障が考えられます。この場合は、パソコンを修理または買い替えがおすすめです。
メーカーへ相談
富士通のパソコンから発生する異音が改善しない場合、サポートへ相談すれば、原因や対処法についてアドバイスを受けられます。富士通のサポートは、電話だけでなくチャットやメールサポートを受けられます。他のユーザーに相談できるQ&Aコミュニティもあり、Web上での相談も可能です。
さらにネットで診断できる故障診断があり、故障と判断された場合にそのまま修理に出す方法もあります。富士通サポートへは、下記サイトから申し込みできます。
パソコンを買い替え
富士通のパソコンの故障が原因で異音が発生している場合は、パソコンを買い替えるのもおすすめです。異音が鳴りやまない場合は、深刻な不具合が起こっており、修理不可能なこともあるためです。
パソコンの平均寿命はノートパソコンで3~5年、デスクトップパソコンで5~10年と言われており、それ以上使用している場合は寿命の可能性も。寿命の場合は、一か所修理しても次々と他の部品が壊れることもあります。
富士通のパソコンの異音が鳴りやまない場合は、買い替えも検討しましょう。パソコンを買い替えたら、古いパソコンを処分する必要があります。しかし、パソコンを処分するにはデータを消去したり処分料がかかったりと手間や費用がかかります。
パソコン廃棄.comなら、完全無料でパソコンを処分できます。データ消去も専門の資格を持ったスタッフが行うため安全です。
まとめ:富士通のパソコンから異音がしたら音を良く聞こう

富士通のパソコンから異音がする場合は、まず、音の種類をよく聞きましょう。パソコンから発生する音は、通常の動作音で問題ないケースもあります。
音が大きい、いつもとは違う音がする場合は、パソコンの設置場所やファンの掃除など、簡単にできる対処法から試してみましょう。それでも改善しない場合は、メーカーに相談したり、パソコンを買い替えたりするなどの対処が必要となります。
パソコンを買い替えたら、古いパソコンの処分はパソコン廃棄.comにおまかせください。送料やデータ消去料、処分料、すべて無料のため、手軽に利用できます。事前の申し込みも不要のため、パソコンを処分したいときにいつでもご利用できます。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
Googleが開発した独自OS「chrome」を搭載したchromebookは、起動速度が速く、動作も軽い、さらに仕事や勉強に必要な基本的な機能を一通り兼ね備えていると人気のノート型パソコンです。
しかし、日常的に使用していると、「以前のようにサクサク動かない」と動作が重く感じることが多々あります。そこで今回は、chromebookが重くなる原因と対処法をご紹介します。「最近chromebookが重い気がする」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。
Chromebookが重い原因

chromebookが重いと感じる原因として、考えられる8つの理由を解説します。当てはまる項目はないか、チェックしてみてください。
Chrome OSのアップデート中
chromebook搭載OS「Chrome OS」がアップデート中の場合、動作が重くなることがあります。基本的にChrome OSでは、バックグラウンドでアップデートを行い、次回ログイン時にアップデートが適応される仕組みを取っているためです。
自宅のWi-Fiなど自由に通信ができる環境では、自動でアップデートが実行されます。アップデート中はバックグラウンドでディスクの書き込みや通信が行われるため、動作が重くなる場合もあるので覚えておいてください。
Chrome OSがアップデート中かどうかは、「設定」から「Chrome OSについて」を開くと確認できます。「アップデート中」と表示される場合は、Chrome OSのアップデート作業中です。多少動作が重くなるものの、特に対処する必要はないので完了するまで待つと良いでしょう。
インターネット回線が遅い
動作が重くなる原因は、chromebookだけにあるとは限りません。そもそもインターネット回線の接続が遅い場合、思うようにURLが開けず、時間がかかります。chromebookの設定を調整したり、ソフトウェアやハードウェアを変更したりしても高速化できません。
インターネット回線に原因がある場合は、ネットワーク設定を変更する必要があります。ネットワークの接続状況を確認してみましょう。
拡張機能を多分に使用している
chromebookではChromeの様々な拡張機能を使えます。便利な機能ですが、使い過ぎはchromebookが重くなる原因になるため注意が必要です。拡張機能の管理は、ブラウザのURLが表示される欄の隣にある拡張機能ボタンからできるので確認してみてください。
削除も可能ですが、動作が重い原因かどうかを判断するなら、一度OFFにしてみると良いでしょう。
アプリケーションが多い
アプリケーションのインストールのしすぎもchromebookが重くなる原因です。アプリは便利な一方で、メモリやシステムリソースの消費も多いです。
ほとんど使用していないものなどは、必要に応じてアンインストールすると良いでしょう。また、新しいアプリやソフトウェアのインストール後に動作の重さを感じるようになった場合には、一度アンインストールしてみることも大切です。
タブを開きすぎている
ブラウザで多くのタブを開いていると、動作が重くなることがあります。同時に何十ものタブを開くのは、chromebookのメモリを多く消費するからです。
特に、Googleドキュメントなど機能性の高いページは、通信量も多く、より多くのメモリを消費するため、動作が重くなりがちです。
バックグラウンドが実行されている
OSのアップデート以外にも、更新や同期、データ転送などのプロセスがバックグラウンドで実行されている場合、chrombookの動作が重くなる原因になります。特に、chromebookの作業中、YouTubeなど動画再生サイトをBGMにしている方は少なくありません。
しかし、YouTubeは常に読み込みながら再生します。複数の作業を同時に行うと、負担がかかり動作が重くなるため注意が必要です。
空き容量が少ない
chromebookのローカルディスクやSSDの容量不足も重くなる原因の1つです。基本的にchromebookのストレージは16~64GBとそれほど多くありません。そのため、空き容量が少なくなってくると、実行速度や応答速度が低下するなど影響が出ることがあります。
chromebookの動作が重いと感じた時は、一度どのくらい空き容量があるのか確認してみましょう。
ハードディスクが損傷している
ここまで紹介したどの項目にも当てはまらないのに動作が重い場合、chromebookのハードディスクが損傷している可能性があります。ハードディスクの状態を確認し、問題がないか確認しましょう。
Chromebookが重くなった時の対処法
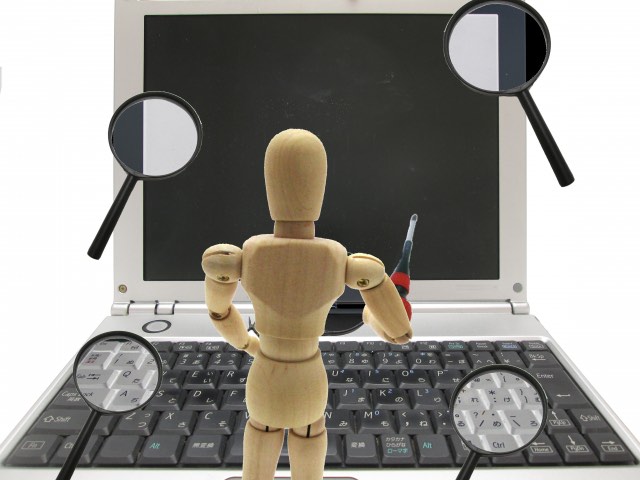
chromebookの動作が遅くなる原因がわかったところで、続いては重くなった時の対処法をご紹介します。どのように操作すれば良いのか、詳しく解説していくのでぜひchromebookの重さに悩んでいる方は、ぜひ試してみてください。
Chromebookを再起動する
chromebookを再起動するだけで、動作の遅さが改善できる場合があります。再起動はハードウェアリセットやハードリセットとも呼ばれており、chromebookは再起動すると持っているデータを一度開放するためです。
そして、データがない状態で再度起動するため、不具合の原因が情報だった場合は、再起動するだけで状態の改善が期待できるでしょう。ただし、ブラウザのタブを開いたまますると、再起動後も自動で開き、メモリを消費します。
再起動した意味がなくなる可能性があるため、再起動する際は全てのタブを閉じるよう気を付けましょう。
chromebookの再起動方法は以下の通りです。
①chromebookの電源を切る
②更新を長押ししながら、電源ボタンをタップ
③chromebookの起動後、更新を離す
chromebookはデザインによって、電源ボタンの有無や配置が変わります。
上記の方法が実行できない場合には、Googleの公式ページをチェックしてください。
なお、スリープでは解決しないため、間違えないように注意が必要です。
タスクマネージャーからプロセスを終了させる
タスクマネージャーとは、簡単にいうとパソコンの処理を管理するプログラムのことで、パソコン上で実行されているアプリを確認し、強制終了できる機能です。chromebookでは、「Everythingボタン+escボタン」を同時に押すと、タスクマネージャーを開けます。
また、chromeのブラウザの右上にある「Googlechromeの設定」→「その他のツール」からもタスクマネージャーを開けます。タスクマネージャーを起動すると、現在使用しているアプリやメモリのチェックが可能です。
必要のないものをクリックし終了させていくと、メモリが開放されるため、chromebookの重さが改善されます。メモリを多く使用しているアプリや拡張機能がある場合には、この一連の作業でchromebookが軽くなるケースが多いです。ぜひ試してみてください。
閲覧履歴を消去する
過去に見た閲覧履歴が溜まっていると、メモリを圧迫し、ブラウザの動作が重くなることがあります。ブラウザの動作が重い時は、履歴やキャッシュを削除しましょう。ちなみに、キャッシュとはアクセスしたWebサイトなどを一時的に保存する機能です。
2度目以降に表示する場合、キャッシュがあると早く開けて便利ですが、その反面、開いたページの分だけデータが溜まるため、負担がかかり動作が重くなります。閲覧履歴やキャッシュは、ブラウザ右上にある「Googlechromeの設定」から「その他ツール」→「閲覧履歴の消去」でできます。
使用していないアプリケーションを消去する
アプリがインストールされているだけでも、chromebookのストレージを使用しています。
容量のそれほど多くないchromebookでは、アプリによる負担は特に大きくなってしまうため、不要なアプリは消去すると良いでしょう。
不要なアプリは、アプリドロワーで右クリック→アンインストールで消去できます。アプリの多くはchromeブラウザから使用できるため、使用頻度の低いものや使っていないアプリはなるべく消去し、ストレージを節約しましょう。
アプリを最新の状態にする
androidアプリがchromebookの動作を重くし、速度を低下させることがあります。不要であれば消去するのが良いですが、どうしても消したくない、残しておきたい場合には、バグのない状態を維持できるよう、常に更新し、最新の状態を保ちましょう。
アプリが最新の状態かどうかは、playストアの「プロフィール」→「アプリとデバイスの管理」から確認できます。
パフォーマンス設定を最適化する
ハイパースレッディングの有効化も、chromebookの動作を軽くするために効果的な方法の1つです。ハイパースレッディングとは、アメリカのインテル社が自社製品に搭載している1つのコアを疑似的に2つに見せる技術です。
ハイパースレッディングに対応している場合、有効化すると並行した命令を実行できるため、パフォーマンスが向上する可能性があります。
パフォーマンス設定を最適化する方法は以下の通りです。
①Google chromeを開く
②アドレスバーに「chrome://flags#scheduler-configuration」と入力
③「Scheduler Configuration」で「Enables Hyper-Threading on relevant CPUs」を選択
④「Restart」を選択
なお、デフォルトの状態に戻したい時は、「Scheduler Configuration」で「Default」→「Restart」を選択してください。
chromebookでは、特にアプリやゲームが重い場合にハイパースレッディングを有効化すると、パフォーマンスの向上が期待できます。
空き容量を増やす
chromebookの空き容量が不足している場合、本体に保存してあるデータをSDカードやUSBメモリに移すのも効果的です。SDカードやUSBメモリに移せるものは移し、本体の空き容量を増やしましょう。
また、chromebookのファイルの保存先をSDカードやUSBメモリにするのも良いでしょう。ダウンロードフォルダの設定先は、以下の方法で変更できます。
①chromeブラウザの右上にある「Googlechromeの設定」を開く
②「ダウンロード」にある保存先を選択し設定
既にダウンロードしたファイルの移動も可能です。
Chrome OSをアップデートする
動作が重い原因がChrome OSにある場合、主に考えられるのは以下の理由です。
・Chrome OSのバージョンが古いまま使用している
・バグが発生している
古いバージョンのChrome OSをアップデートせずそのまま使用していると、動作が重くなる原因となります。Chrome OSは、基本的に自動で更新されますが、最新のバージョンになっているか、確認してみてください。
また、アップデートをしてから動作が重くなったと感じる時は、バグが発生している可能性があります。そのような時は、次のアップデートで修正されるため、新しいアップデートが利用可能ではないか確認してみてください。
なお、Chrome OSが最新かどうかの確認方法は以下の通りです。
①右下にあるステータストレイをクリック
②ポップアップウィンドウの上部にある「設定」をクリック
③左側のバーをスクロールし「Chrome OSについて」を選択
④Google Chrome OSの下にある「アップデートを確認」をクリック
⑤チェックプロセスを確認し、更新可能なプログラムがあればダウンロード
「お使いのchromebookは最新です」と表示される場合は、新しいバージョンが公開されていません。次の更新まで待ちましょう。更新可能なプログラムがあり、ダウンロードにデバイスの再起動が必要な場合は、指示にしたがって操作を完了してください。
拡張機能を消去する
動作の重さがインストールしすぎた拡張機能にある場合、消去によって改善が期待できることもあります。拡張機能を確認し、不要なものを削除しましょう。
拡張機能の削除方法は以下の通りです。
①chromeのブラウザを開く
②右上にあるGoogle chromeの設定を開く
③「その他のツール」→「拡張機能」を選択
もしくは、アドレスバーに「chrome://extensions」しても確認できます。
④表示された拡張機能から不要なものを選ぶ
削除するか、スイッチをオフにしても拡張機能を無効にできます。
Chrome OSを初期化する
ここまで紹介した方法を試してもchromebookが高速されない場合、最後の手段として挙げられるのはChrome OSの初期化です。初期化してもアカウントにログインすれば、アプリや設定は元通りに戻ります。しかし、ファイルが同期されないため、事前にバックアップしておきましょう。
chromebookの初期化する方法は以下の通りです。
①chromebookの「設定」を開き「詳細設定」をクリック
②「設定のリセット」から「Powerwash」を探す
③「リセット」→ポップアップで表示された「再起動」をクリック
④自動的に再起動がスタート
⑤「chromebookをリセット」→「Powerwash」をクリック
⑥「続行」をクリック
上記の流れで進めていけば、chromebookはリセットされます。
まとめ:Chromebookに負担がかからないように心がけよう!

今回は、chromebookの動作が重くなる原因と対処法をご紹介しました。
起動速度の速さや動作の軽さに定評のあるchromebookですが、使う中でどうしても重くなってしまうことがあります。もしも、chromebookの動作が重いと感じた時は、今回紹介した内容を参考に、原因を探り、対処法を実行してみてください。
なお、動作が重くなった原因は必ずしも1つとは限りません。いくつかの原因が組み合わさって重くなることもあるため、組み合わせて対処してみることをおすすめします。
また、不要なデータはこまめに削除し、chromebookの負担がかからないよう、普段から意識するようにしてください。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
Chromebookを使っている最中にフリーズすると焦ってしまうでしょう。仕事などに使える機能が揃っているなどの理由からChromebookを採用したのに、フリーズしてしまっては意味がありません。
今回は、Chromebookがフリーズする状況と自分でできる対処法を解説していきます。万が一のときに備えて対処法を把握していれば、焦らずに済むでしょう。
Chromebookがフリーズした時の状況

Chromebookがフリーズしてしまう状況はいくつか考えられます。まずは、どのような状況があるのかみていきましょう。
「Chrome OSが存在しないか破損しています」と表示される
「Chrome OSが存在しないか破損しています」と表示されるのは、そのままの意味です。Chrome OSが破損していたり、ストレージが故障していたりする可能性があります。このメッセージが表示されたら、Chrome OSのリカバリーツールを使ってOSの再インストールをしなければいけません。
リカバリーツールを使うとデータがすべて消えてしまいます。そのため、データが必要な場合は、データの復旧を行っている専門業者に依頼しましょう。
「He’s Dead, Jim!」というエラーメッセージが表示される
「He’s Dead, Jim!」というエラーメッセージが表示される場合は、システムのメモリが不足している可能性が高いです。メモリの空き容量を増やすためには、開いているタブやアプリ、使っていないそのほかのプロセスを閉じてみてください。
ChromeOSが反応しない
そもそもChromeOSが反応しないパターンもあります。そのようなときは、ハードリセットを行い、Chromebookのロックを解除しなければいけません。
正常に起動すれば問題ありません。起動しない場合は、「HP Chromebook – Chromebookオペレーティングシステムがロードされない (Chrome OS)」を確認してみてください。
ファンから異音がする
Chromebookがフリーズし、ファンから大きな音が鳴ったり、ずっと回り続けたりする場合は、パソコン自体が熱くなっている可能性が高いです。ハードウェアコンポーネントが故障している場合も、ファンから異音がします。
通気口に誇りが詰まっていないか確認し、取り除いて改善されるか試してみてください。改善されれば、熱暴走でフリーズしたと考えられます。その後も続く場合は、ハードウェアコンポーネントの故障を疑いましょう。
Chromebookがフリーズした際の対処法
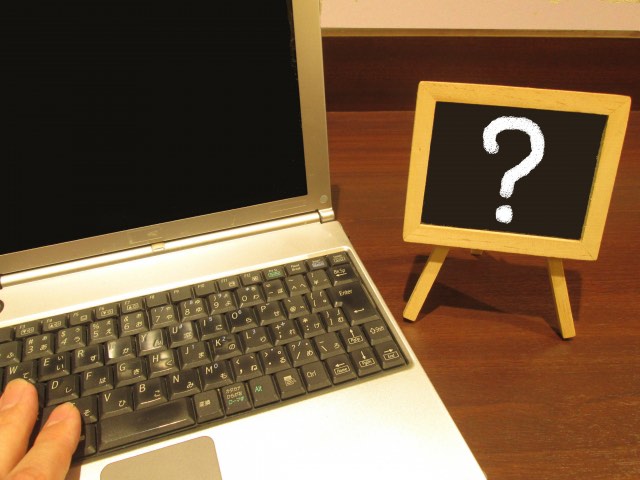
Chromebookがフリーズしたとき、自分でできる対処法を把握していれば再起動できる可能性が高くなります。具体的な対処法は以下の通りです。
タスクマネージャを起動する
1つ目は、タスクマネージャを起動する方法です。Windowsパソコンがフリーズしてしまったときと同じく、Chromebookでも有効な方法となっています。特定のアプリケーションがフリーズする場合は、タスクマネージャから終了させられるので、試してみてください。
タスクマネージャを起動する方法は以下の2つです。
・「Esc」キー+「検索」キー(虫眼鏡マーク)の同時押し
・Chromeブラウザ右上の「…」から「その他ツール」内の「タスクマネージャ」を起動
Windowsの「Ctrl + Alt + Delete」と違うので、間違えないようにしてください。
リカバリモードで再起動する
2つ目は、リカバリモードで再起動する方法です。電源ボタンを押しても反応がない場合は、この方法を試してみてください。やり方は以下の通りです。
・「Esc」キーと「更新」キーを押しながら「電源」ボタンを押し、「電源」ボタンを放す
・「ChromeOSが見つからないか破損しています」「Chrome OS is missing or damaged」などと表示されたら、「Esc」キーと「更新」キーも放す
・「電源」ボタンを再度押すと、再起動がスタートする
ハードウェアをリセットする
3つ目は、ハードウェアをリセットする方法です。ハードリセットで再起動すると、改善される場合があります。ハードリセットの手順は以下の通りです。
・Chromebookの電源を切る。
・「更新」キーを押しつつ「電源」ボタンを押す
・Chromebookが起動したら「更新」キーから指を放す
再起動する
4つ目は、再起動する方法です。これまでの方法を試しても改善されない場合は、しばらく放置し、バッテリーを0%にして強制終了させます。その後、電源アダプターを指した状態で再度起動してみましょう。
問題なく起動すれば大丈夫です。しかし、突然電源が落ちる、エラーが出るなどの場合は、内部に問題が生じている可能性があるので、修理に出すのがおすすめです。
chromebookのメーカーサポート

chromebookに何らかの不具合が生じ、自力での解決が難しい場合は、メーカーサポートを受けられます。続いては、各メーカーがどのようなサポートを行っているのかみていきましょう。
Acerの場合
Acerのサポート対象となるのは、以下の機器です。
・日本国内で日本エイサーが販売しているデスクトップPCまたはノートPC
・日本エイサーの保証書が添付された各種周辺機器
海外の製品やOEM製品、他社製品に関する質問には答えていません。問い合わせ方法は、オンラインサポートや電話サポート、メール・チャットによるサポートがあります。問い合わせ先は、日本エイサーカスタマーサービスセンターです。
ASUSの場合
ASUSでは、オンライン修理受付サービスや修理・お預かり品の状況確認などのサービスを提供しています。オンライン修理受付サービスを利用するには、製品のシリアル番号を入力しなければいけません。また、申し込みをする際に購入照明のコピーも必要になるので、忘れずに用意しておいてください。
また、ASUSアカウントにサインインすると、チャットでの問い合わせも可能となります。
富士通クライアント コンピューティングの場合
富士通クライアント コンピューティングの場合は、使い方や困りごとに関する相談をチャットやメール、電話で受け付けています。不具合が生じてどのように対応すべきかわからない場合は、このいずれかの方法でメーカーに問い合わせてみましょう。
故障や修理に関する窓口は別で用意されています。故障や修理に関する窓口を利用する際は、「ネットで故障診断」を行って本当に故障しているのか確認するようにしてください。また、保証期間や修理規定などにも目を通しておきましょう。
HPの場合
HPでは、Web修理受付を行っています。Web修理受付を依頼する場合は、サインインが必要です。そのほかに、預かり修理や出張修理、部品送付、消耗品購入などのサービスも提供しています。
Lenovoの場合
Lenovoの場合は、シリアル番号や製品を選択すると問い合わせや修理申し込みができるようになっています。Lenovo PC を使用している場合、「製品を検出する」ボタンでシリアル番号の検出ができるので、どこで確認すればいいのかわからない場合は活用してみてください。利用可能なサポートは、ラインチャットサポートやWebチャットサポート、eメールサポートなどです。
子どもが壊さないために指導すべきこと

chromebookは子どもが使用するケースも多くみられます。子どもはパソコンの扱い方に慣れていないため、壊してしまうリスクが高いです。そのため続いては、子どもが壊さないために指導すべきことをピックアップしてご紹介します。
机などから落とすなどしない
子どもがノートパソコンを使っていて壊す要因として多いのは、落下です。パソコンを使っていないとき、机の上にあるノートや教科書などの奥にあるパソコンを押してしまい、落下するなどのパターンも珍しくありません。落下による衝撃で基盤にダメージが加わったり、液晶パネルが割れてしまったりする可能性があります。
学校方持ち帰る際に壊す場合もないとは言い切れないでしょう。ノートパソコンを入れたままランドセルを放り投げるなどすると、落としたときのようにダメージが加わります。
水をこぼしてしまう
パソコンは電子機器なので、水をこぼしてしまうのは故障の原因になります。子どもは特に不注意などで水などの飲み物をこぼす可能性が高いです。こぼしてしまってからでは遅いので、パソコン作業をするときは水筒など蓋を締められるものに飲み物を入れるなどの工夫が必要になるでしょう。
コネクタに物を入れない
子どもが使っているパソコンで多い故障には、USB端子などのコネクタにシャープペンシルの芯や消しゴムを入れてしまうなどの原因もあります。端子口に鉛筆の芯が偶然入り、ショートや発煙するケースもあるので、注意が必要です。端子部に入り込んだごみを取るためにシャープペンで取ろうとして、同じような状況になった事例もあります。
また、端子の中に消しゴムなどを無理やり入れるなど、大人では考えられない行動をとる場合もあるので、油断は禁物です。
修理業者に依頼するメリットやメーカーとの違い

chromebookがフリーズするなどして使えなくなってしまった場合、修理が必要となります。修理はメーカーへの依頼も可能ですが、修理業者に依頼する場合もあるでしょう。続いては、修理業者に依頼するメリットやメーカーとの違いを解説していきます。
修理業者に依頼するメリット
修理業者に依頼すると、メーカーに依頼するよりも早く対応してもらえます。これは、メーカーとの大きな違いであり、修理業者ならではのメリットです。購入店やメーカーの保証書を紛失してしまった場合でも、修理業者なら対応してもらえます。
業者によっては、即日引き取りが可能なところもあるので、すぐに何とかしたいなどのニーズにも応えてもらえるでしょう。出張修理を行っている業者であれば、店舗に出向かなくても直してもらえます。
修理業者とメーカーの違い① 付帯サービス
修理業者とメーカーでは、付帯サービスが異なります。
修理業者は、データのバックアップや対象部分以外の修理、本体のクリーンアップなどに対応しているところが多いです。追加で費用は掛かってしまいますが、より使いやすい状態にしてもらえます。パソコンに関する専門知識を持つスタッフも在籍しているので、自作パソコンや複数のメーカーにも対応している業者が多いのも魅力の1つでしょう。
一方メーカーは、付帯サービスの提供を行っていないケースが多いです。自社製品しか取り扱っていないこと、対象部分以外の修理が行わないこと、なども業者との大きな違いとして挙げられます。修理時にはリカバリーをするので、データも消えてしまうでしょう。
バックアップなど付帯サービスを充実させたいのであれば、メーカーではなくパソコン修理業者に依頼するのがおすすめです。
修理業者とメーカーの違い② 安全性や信頼性
安全性や信頼性も大きな違いとして挙げられるでしょう。
パソコンの修理業者の中には、全国展開している大手企業もあり、サービスの質や信頼性などは向上しています。専門的なスキルを持つスタッフが在籍しているところもあり、安心してお任せできるケースが多いです。しかし中には、相場以上の修理費用を請求する悪徳業者もあるので注意しなければいけません。
メーカーでは、純正の部品を使った修理を行うので、安全性や信頼性は確実です。保証期間内であれば、無償修理の対象となる場合もあり、コストをかけずに直せる可能性もあります。安全性や信頼性を何よりも重視したいなら、メーカー一択でしょう。
フリーズ以外に多いトラブル

chromebookは、フリーズ以外にも多くみられるトラブルがあります。最後に、フリーズ以外に多いトラブルにはどのようなものがあるのかみていきましょう。
モバイル版のWebページが表示される
ChromebookにはGoogle ChromeのPC用ブラウザが搭載されているのですが、毎回モバイル版のWebページが表示される場合があります。これは、サイト側がスマートフォンからアクセスしていると誤って認識していることが原因です。
そのような場合は、「User Agent Switcher and Manager」を使ってみてください。サードパーティが提供している拡張機能で、パソコンからアクセスしているとサイト側に思わせます。この拡張機能はインストールするだけで簡単に使えるので、モバイル版のWebページが表示されると悩んでいる場合におすすめです。
ストレージを空けられない
Chrome OSは、クラウドを自分のものとして使用する前提になっています。そのため、出荷時のストレージは32GBもしくは64GBです。ウェブブラウザしか機能がない場合はそれでも十分ですが、AndroidのゲームやLinuxソフトウェア、Googleの開発プラットフォーム「Android Studio」などをインストールするのは難しいでしょう。
そのようなときは、Chromebookのファイルマネージャー「ファイル」で、クラウドストレージを設定しておくのがおすすめです。ストレージが足りないときのデータ移行がスムーズになり、必要なときに取り出しやすくなります。
まとめ:フリーズの原因がわからない際は各種サポートセンターに問い合わせよう!

Chromebookがフリーズしてしまったときの対処法を試しても改善されない、原因がどこにあるかわからないケースもあるでしょう。そのようなときは、サポートセンターに問い合わせてみてください。サポートセンターに問い合わせることで、ほかの対処法を教えてもらえる場合があります。
適切なアドバイスを受け、それに沿って再起動などを再度試してみると改善される可能性も考えられるでしょう。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
Dellのパソコンで作業しているときに突然フリーズして困った経験がある方も多いのではないでしょうか?Dell製品に限らず、パソコンはさまざまなことが原因でフリーズします。
今回は、Dellのパソコンがフリーズする原因と対処法、事前にできる対策をご紹介します。Dellのフリーズを解消したい方はもちろん、事前にフリーズ対策をしておきたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
Dellのパソコンがフリーズする原因

まずは、Dellのパソコンがフリーズする原因を見ていきましょう。
アップデートの不具合
WindowsのOSをアップデートしたタイミングでフリーズするケースがあります。特にWindows10、Windows11にアップデートをしたときに起こることが多いです。
OSのアップデートをすると、パソコンを動作させる役割を持つドライバーが大きく変化します。その大きな変化によってドライバーが正常に動作しなくなり、パソコンがフリーズしてしまう可能性があるでしょう。
電源関連の故障
パソコンを動かすために欠かせない電源が確保できていない場合もフリーズするケースがあります。電源ケーブルが断線していたり、電源タップが故障していたりすると、動作が安定しないほか、起動できないことも多いです。
メモリの不足
一度にたくさんのアプリやソフトなどを使うことでフリーズしてしまう場合は、メモリ不足が原因として考えられるでしょう。パソコンによって一度に行える処理の量が変わります。8GB以下だとExcelやWord、インターネットの利用であれば、問題なく動作します。
しかし、8GB以下のパソコンで動画編集やゲームなどを一度に動かそうとすると、メモリが足りず、フリーズしてしまう可能性が高いです。
アプリケーションのエラー
新しくアプリをインストールしたタイミングや、特定のアプリを起動するとフリーズが発生する場合は、アプリのエラーが原因かもしれません。アプリのエラーによるフリーズは、OSのアップデート後に起こることもあります。
理由としては、アプリのドライバーがパソコンの動作を妨げている、OSアップデート後アプリのバージョンが合わなくなってしまったなどが挙げられます。
ウイルス感染
ウイルス感染によってフリーズするケースも多いです。悪質なウイルスに感染した場合、パソコンが正常に動作するために必要なプログラムを壊されてしまい、最悪の場合、パソコンの起動すらできなくなるケースもあります。
フリーズさせるタイプのウイルスは、メモリや命令を処理するCPUにダメージを与えてくるでしょう。その結果、画面が固まって動かなくなってしまいます。
ハードディスクの故障
データ保存に欠かせないハードディスクが劣化したり、故障したりしている場合もフリーズが頻発します。特に毎日パソコンで作業している場合は、読みとる量と書きこむ量が膨大になるため、寿命よりも早く故障してしまうことがあります。
パソコンのフリーズに加え、本体から異音がしたり何度もアプリが落ちてしまったりするときは、ハードディスクの故障を疑ってみましょう。
マザーボードの不具合
パソコンの土台、中心パーツと言われるマザーボードの不具合も原因として考えられるでしょう。パソコンに欠かせないパーツとはいえ、マザーボードにも寿命があります。3~5年使い続けている場合は、マザーボードの劣化によるフリーズかもしれません。
ほかにも、マザーボードにまで水が入った、高温や低温が続いた、高い所から落としたなど、マザーボードが故障する原因はさまざまです。
オペレーションシステムの不具合
パソコンのシステム全体を管理するオペレーションシステムに不具合がある場合、フリーズケースがあります。オペレーションシステムとは、OSの正式名称です。OSのアップデートがうまくいかなかったときや、ソフトウェアに異常があるとき、OSに不具合が発生します。
ディスプレイ関連の故障
ディスプレイ自体が故障しており、画面が正常に動かないケースも少なくありません。特にデスクトップパソコンの場合は、映像を画面に反映させるためのケーブルが断線を起こしていたり、モニターが故障していたりすると、フリーズしているように見えることがあります。
デバイス接続の故障
突然文字が打てなくなったり、マウスを動かしても反応しなかったりする場合は、接続しているデバイスの故障が考えられます。パソコン自体がフリーズしている可能性は低いでしょう。電池を入れ替えてみたり、新しいキーボードやマウスに交換したりして、正常に動作するか確認してみてください。
DellのPCがフリーズしてしまった際にまずやること

パソコンがフリーズすると、焦って強制シャットダウンをしてしまう方は多いです。しかし、強制シャットダウンをする前にできることがあります。パソコンがフリーズしたときは、以下の方法を試してみてください。
デバイスの接続を確認する
デバイスが接続されていない、何かの拍子でパソコンがデバイスを認識できなくなっているなどのケースもあります。まずは、キーボードやマウスがパソコンと接続されているかをチェックしましょう。ケーブルなら抜き差し、ワイヤレス接続なら再接続をしてみてください。
しばらくの間待ってみる
デバイスの接続に問題がなくても、すぐに強制終了したり電源を抜いたりするのは危険です。フリーズした場合、3時間は待ってみましょう。6時間以上経っても状況が好転しない場合は、そのほかの対処法を試してみてください。
特にメモリが少ないパソコンの場合、アプリなどの処理に時間がかかってしまい、パソコンが重くなることは多いです。アプリの処理が原因であれば、5~10分で回復するでしょう。マウスを動かすと反応する、読み込み中のマークが動いているときはフリーズしているわけではないため、しばらくの間待ってみてください。
エラーコードの表示があれば調べてみる
Dellのパソコンは、フリーズするとエラーコードが表示されるケースがあります。画面に表示されるエラーコードを検索すると、フリーズの原因が特定できるだけでなく、対処法もチェック可能です。
公式サイトでチェックすればそのエラーコードが出たとき、どういった手順で改善できるのかも詳しく書かれているため、より適切な対処ができます。エラーコードによっては、パーツの交換やパソコンの修理が必要になることもあるので注意しましょう。
DellのPCがフリーズした際の対処法

次に、DellのPCがフリーズした際の対処法を見ていきましょう。
ハードウェア診断プログラムを起動させる
フリーズの原因が特定できない場合は、ハードウェア診断プログラムを起動させましょう。
Dellのパソコンにはソフトウェア「SupportAssist」が備わっています。これには、不具合や故障が起きたときに知らせてくれる機能が備わっており、フリーズしたときにも焦らず対処できることから、とても便利なものとして認知度も高いです。
しかし、より包括的にパソコンを診断したい場合は、ハードウェア診断プログラムを起動させてみましょう。ハードウェア診断プログラムは、下記の手順で起動できます。
①パソコンを再起動する
②ロゴ画面が表示されたら「F12」キーを押す
③矢印キーを操作して「Diagnostics(診断)」を選択し、「Enter」キーを押す
④表示された指示に従って回答していく
Dell製PCは、オンライン診断テストを実行できます。オンライン診断テストは、下記の手順に沿って実行してみましょう。
①Dellサポートサイトを開き、Dell製品を手動で選択またはタグやコード、シリアル番号で検索する
②「Diagnostics(診断)」を選択する
③「Run Full Test(フルテスト)」を実行する
強制シャットダウンをする
しばらく待ってみても状況が変わらない場合は、パソコンを強制シャットダウンしましょう。Dell製品の多くは電源ボタンを長押しすると強制シャットダウンできます。しかし「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Delete」キーの3つを同時に押してメニューが表示される場合は、そこからシャットダウンを選択してください。
電源ボタンの長押しによる強制シャットダウンは最終手段だと考えておくのがおすすめです。しかし、フリーズはパソコンの再起動によって改善するケースも多くあります。理由は、誤作動で起動したアプリや見えない場所で動作しているシステムをストップさせられるためです。
アプリやシステムを終了させることで、処理に追われていたメモリに余裕が生まれ、パソコンが正常に動作します。特に、パソコンを長時間使っていたときにフリーズした場合は、再起動で解決されることが多いです。
全てのデバイスを外す
パソコンの電源を切った後にマウスとキーボードだけでなく、USBドライブやプリンター、Webカメラ、SDカードなど、全てのデバイスをパソコンから外しましょう。パソコンのデバイスは正しく取り付けられていても、障害をもたらすケースがあります。
使っているデバイスが、パソコンのメモリやハードディスクなどに異常がないかを診断する「自己診断」に影響していることもあるでしょう。デバイスを取り外した後、再起動して正常に動作すれば、デバイスが自己診断の完了を妨げていた可能性があります。どのデバイスが原因となっているかを特定し、原因となるものは新しいものや相性がいいものに交換しましょう。
電源ケーブルから外し、バッテリーを取り外す
バッテリーを取り外すのもトラブル解決に有効です。接触不良などが原因で、動作が不安定になっている可能性があるからです。
バッテリーを取り外すときは、パソコンから電源ケーブルを外してから作業を行うようにしましょう。また、バッテリーの取り外し方はパソコンによって異なるため、安全に取り外せるよう、マニュアルなどで手順を確認してください。
放電する
パソコンの内部に電気が溜まり過ぎると、トラブルの原因になることがあります。帯電を解消するためには、放電を行う必要があります。フリーズ以外に突然電源が切れる、画面が真っ暗になるなどのトラブルが多い場合は、以下の手順で放電を行ってみてください。
①電源を切る
②ケーブルやデバイスを全て取り外す
③電源ボタンを15秒~20秒押し続ける
④1時間ほど放置する
Windowsのアップデートを行う
WindowsのOSアップデート後にフリーズするケースをご紹介しましたが、反対にOSをアップデートするとフリーズを改善できる場合もあります。OSのアップデートは、下記の手順で実行できます。
①「設定」を開く
②「更新セキュリティ」の「Windows Update」から「更新プログラムをチェック」を選択する
セーフモードで原因を調べる
セーフモードは、必要最低限の機能だけが使えるモードになります。不具合の原因を特定するための診断機能も使えるので、フリーズしたときにも便利です。セーフモードでの起動が可能であれば、ソフトウェアやアプリ、ハードウェアなど、どこに原因があるのかを調べてみましょう。
アプリケーションをアンインストール・再インストールする
セーフモードで診断した結果、特定のアプリに原因があれば、アンインストールや再インストールを試してみましょう。アンインストールで改善、再インストールで再度フリーズする場合は、そのアプリに不具合がある可能性が高いです。
マルウェアやウイルスの侵入を確認する
セキュリティ対策に特化したソフトを使い、マルウェアやウイルスの侵入を確認しましょう。ウイルスが見つかった場合、しっかりと除去すればフリーズが解消する可能性があります。
ここで注意したいのは、使用するセキュリティ対策ソフトを1種類に絞ることです。複数のセキュリティ対策ソフトを起動していると、動作が安定しづらくなり、トラブルが起きやすくなります。
通気孔のゴミを取り除く
パソコンの動作を不安定にする外的要因として挙げられるのは、浸水だけではありません。ホコリや異物が通気孔を塞いでしまうと、パソコンに熱がこもり、トラブルが起きやすくなってしまいます。しばらく掃除をしていない、どの方法を試しても改善しない場合は、通気孔のゴミを取り除いてみましょう。
DellのPCをフリーズさせない対策

ここからは、DellのPCをフリーズさせない対策方法をご紹介します。
定期的にシステムメンテナンスを行う
ファイルのクリーンアップやチェックディスクなどを定期的に行い、不要なファイルの削除・ドライブの修復を行いましょう。システムメンテナンスを行うことで、容量やメモリに余裕が生まれ、フリーズしにくい環境を作れます。
高湿・高温を避ける
パソコンに熱がこもるとトラブルが起きやすくなるため、高湿・高温が避けられる環境に設置しましょう。特に直射日光や通気口付近に物を置くのは厳禁です。結露による故障もあるため、寒暖差が生じないような環境づくりを心掛けてください。
使わないアプリケーションは消去する
使っていないアプリや、しばらく使う予定のないアプリは消去しておくのがおすすめです。メモリはもちろん、容量を圧迫してしまい、フリーズにつながる恐れがあります。定期的にアプリの整理を行うこともフリーズ対策として有効です。
ソフトウェアやドライバーを最新する
ソフトウェアやドライバーは、自動でアップデートされるものが多いことから、わざわざチェックしない方も多いでしょう。中には自動アップデートされないものもあるため、定期的に最新のものがないかチェックしてみてください。
ウイルス対策ソフトをインストールする
ウイルスに感染したらすぐに分かる・早急に駆除できるウイルス対策ソフトをインストールしておくことも対策の1つです。ウイルス対策ソフトの中には、体験版が用意されているものも多いため、好みのソフトを見つけやすいでしょう。インストールする前にメモリ不足にならないよう、チェックしておくことも大切です。
ドライブのデフラグと最適化を行う
同じパソコンを長期にわたって使用している場合、1つのデータが複数の場所に書き込まれてしまうことがあります。書き込まれる場所が分散されることによって、動作するまでに時間がかかってしまったり、フリーズしてしまったりするトラブルが起きやすくなります。これを改善してくれるシステムメンテナンスを「デフラグ」と言います。
デフラグを頻繁に行うとハードディスクに大きな負担がかかってしまうため、半年~1年に1回程度の頻度でメンテナンスを行うのがおすすめです。
メモリ容量を増設する
高いスペックが求められるアプリやソフトを使いたい、快適に作業したい場合は、メモリ容量の増設も視野に入れましょう。メモリが足りず、フリーズが頻発する場合は、増設によって改善できるかもしれません。
ただし、メモリの増設は知識や技術が求められるため、素人には難易度が高いです。安全に増設したい場合は、パソコンの修理業者に依頼するのがおすすめです。
まとめ:フリーズした際にはまず故障の原因を探ろう!

今回は、Dellのパソコンがフリーズする原因や対処法をご紹介しました。パソコンがフリーズしたときはまずその原因を特定し、適切に対処しましょう。間違った対応をしてしまうと、フリーズを解消できても大切なデータなどが消えてしまう可能性があります。
フリーズする原因によって適切な対処方法があるため、焦らずじっくり原因を見極めてみてください。また、突然のフリーズを防げるよう、普段から対策しておくことも重要です。ぜひ今回ご紹介した「DellのPCをフリーズさせない対策」を参考にして、フリーズ対策を行ってみてください。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
アメリカ発祥のDellは世界中にたくさんのユーザーがいるパソコンの有名メーカーです。動画編集やゲームなど、幅広い用途で使用でき、シーンや予算に合わせて自分に適したパソコンが選べ、なおかつコストパフォーマンスにも優れているなどの魅力的な特徴を持っています。しかし、使用していると不具合が発生するケースもあります。特に「起動せず画面が黒いまま動かない」「急に画面が真っ暗になった」など、ブラック画面による不具合が発生すると、故障したのかと不安になる方もいるはずです。
そこで今回は、Dellのパソコンの画面が真っ暗になる原因や画面が黒くなったまま動かないときに確認すべきポイントなどを解説していきます。対処法もご紹介していくので、画面が暗くなる症状でお悩みの方は、ぜひチェックしてみてください。
Dellの画面が真っ暗になる原因

Dellのパソコン画面が真っ暗になったまま動かない原因は以下の通りです。
・電気元の故障
・ハードウェアやアクセサリーの故障
・システムの破壊
それぞれの原因の詳細を確認していきましょう。
電源元の故障
パソコンの電源供給関連に問題があれば、ラップトップ画面が真っ暗になるケースもあります。新しい機器を使用した際にモニターがブラックアウトを起こす可能性もあるので注意してください。
また、ピープ音や電源ランプがオレンジ色に点滅していると電源元が故障している可能性があります。その場合、電源ユニットの故障や静電気の帯電などが原因です。
ハードウェアやアクセサリー故障
ディスプレイやマザーボード、グラフィックスカードやメモリなどのパーツが故障している場合も画面が黒くなり動かなくなる可能性があります。アクセサリーとマザーボードの接続が緩んでいるまたは不適切など状態でもブラックアウトを起こすケースがあるので確認してみましょう。
また、マザーボードの電解コンデンサの液漏れ、膨張が見られる場合は交換や修理が必要です。交換や修理を行えば復活するかもしれませんが、場合によっては機器そのものが交換されてしまい、データが初期化されてしまう危険性もあるので注意してください。
システム破損
パソコンの起動に関連するデータやプログラムが破壊された状態がシステム破損です。HDD内部のデータが異常をきたしている状態となり、「倫理障害」とも言われています。
・突然の電源遮断
・不適切な操作によるデータの削除
上記が原因でシステム破損は引き起こされます。アップデート中に電源を切る行為や不適切な手順によるパソコンの起動には十分に注意してください。システム破損は、ウイルスが原因となっているケースもあります。ウイルスに感染しウイルスシステムが破損する場合もあるので、自力での対処が難しいときには業者に依頼して対処してもらいましょう。
記憶装置破損
パソコンのデータを保存する記憶装置(HDD/SSD)に破損が起きている際も画面が真っ暗になる、画面が黒くなったまま動かないなどの症状を引き起こす可能性があります。
・パソコンやハードディスクを落とす
・落雷が原因の電力供給の異常
・熱や湿度
・HDDの経年劣化や寿命
上記のような物理障害によって引き起こされます。HDD/SSDの寿命は3年~5年です。長期間使用し続ければディスク部品に傷が付き、データが揮発するなどしてパソコンが起動しなくなる危険性もあります。
物理障害を起こしたHDD/SSDの修復は自力では難しく高度な技術が必要です。データが消失してしまう可能性もあるので、業者に相談した方が安全です。
Dellの画面が真っ暗の際に確認すること

Dellのパソコン画面が真っ暗になり動かなくなった場合は、パソコンの故障が原因の場合もありますが、違うことが原因かもしれません。以下を確認してパソコンの状態に問題がないか、まずは確認してみてください。
スリープモードの状態
パソコンの画面が真っ暗になっていれば不安を感じてしまいますが、一度「スリープモード」の状態でないか確認してみましょう。スリープモードは省電力機能の1つで、電力の消費を抑えるためにパソコンの動作を一時的に停止する機能です。スリープモードの状態であると画面が暗くなります。
解除する方法としては、マウスやキーボードを動かすだけなので試してみてください。もし、マウスの操作やキーボードの操作でも解除されない場合は、電源ボタンを押すと解除されるケースがあります。
スリープモードは、設定を変えると時間を調整できます。Windows10での調整方法は以下の通りです。
① 「スタート」をクリックして「設定」を選びます。
② 「システム」をクリックして移動してください。
③ 「電源とスリープ」を選択して「画面」で画面をオフにするまでの時間を選択してください。
④ 「スリープ」でパソコンを使用していないときにスリープモードの状態にするまでの時間を選択しましょう。
上記の方法で設定を変えられるので、スリープモードになるまでの時間が短いと感じた場合は調整してみましょう。
電源ランプの色
Dellのパソコンに不具合が起きたとき、電源ランプによって状態を確認できます。電源ランプの点灯パターンは、モデルによって異なるので画面が真っ暗のまま動かなくなった際には、説明書を確認してランプの色を確認してみてください。Dell OptiPlexシリーズの点灯パターンは以下の通りです。
・ランプが消灯している:電源がオフになっている
・ランプがオレンジ色に点滅している:初期状態もしくはエラーが発生している
・ランプがオレンジ色に点灯している:電源装置が正常な状態
・ランプが白色に点滅している:電源供給が少なくなっている
・ランプが白く点灯している:通常の電源状態
ランプが白く点灯しているなら、パソコンが正常に起動されている証拠です。それでも画面が黒くなっているときには、パネルやモニターの故障を疑ってください。白点滅の状態であれば、充電してから再び起動すると解消されるケースもあります。
Dellの画面が真っ暗な際の対処法

Dellのパソコン画面が真っ暗になる問題の対処法として9つの方法をご紹介していきます。スリープモードでもなく、再起動をしても問題が解消されない場合は、以下の方法を試して対処してみてください。
強制シャットダウンを行う
画面が黒くなり起動しない場合、まずは強制シャットダウンでブラック画面が解消されるか試してみましょう。
① ライトが消灯するまで電源ボタンを長押しします。
② 電源が完全にオフになったのを確認後、ACアダプターや電源コード、バッテリーなどを電源から外してください。
③ 再度電源ボタンを長押ししてコンピュータの残りの電力を使い果たしましょう。(約60秒)
④ メディアカードやUディスク、USBフラッシュドライブなど、接続されている外部デバイスや周辺機器を取り外してください。
⑤ バッテリーを元に戻して電源コードとACアダプターを再度差し込みます。
⑥ Dellの電源を入れて黒い画面が表示されるか確認してみてください。
普段通りに映るようであれば、そのまま使用してみましょう。
ディスプレイを新しいものにする
ディスプレイ不良であれば、新しいディスプレイに交換するだけで問題を解消できます。まずは、以下の方法でディスプレイに不具合がないか確認してみてください。
① 上記の強制シャットダウンをしてから再度Dellの電源を入れてください。
② 起動プロセス中に電源ボタンの上にあるLEDの表示があるかチェックしてみましょう。
③ 電源ボタンやCaps LockのLEDが点灯していない場合は、外付けモニターをWindowsに接続し、正常に表示されるかチェックしてください。
④ 正常に表示されない場合、ディスプレイに不具合があるので新しいものと交換しましょう。
セーフモードで立ち上げる
必要最低限の構成でパソコンを起動させる機能がセーフモードです。不具合の原因を見つける際にも役立てられます。
① パソコンの電源ボタンを長押しして電源を切ってください。
② パソコンの電源を入れます。
③ ロゴが表示される前に「Shift + F8キー」を押すと回復モードメニューに入ります。回復モードにならない場合は、再度上記手順を繰り返してみてください。
④ 「詳しい修復オプションを表示する」または「詳細オプション」を選択して「トラブルシューティング」に進んでください。
⑤ トラブルシューティング画面で「詳細オプション」をクリックします。
⑥ 「スタートアップ設定」「再起動」の順に進みましょう。
⑦ 起動したらキーボードの「4」もしくは「F4」を押してセーフモードで起動してみましょう。ネットワークに接続したい場合は、「5」または「F5」を押してください。
正常にセーフモードで起動した場合はMサードパーティのアプリケーションや古いグラフィックドライバー、ウイルスなどが原因で画面が黒くなっている可能性があります。対応の修正法をとって問題を解決しましょう。
Windowsシステムを再インストールする
Windowsを再インストールする対処法でも問題の解消が期待できますが、個人情報や設定などの必要なデータが削除されてしまうので、再インストールをする前にデータのバックアップを行いましょう。Windows10の再インストール方法は以下の通りです。
① BIOS設定を変更します。パソコンの電源を入れてロゴが表示されている間に「F2」を押してBIOSを起動させてください。
② Windows10インストールメディアから起動するように設定します。
③ Windows10のセットアップ画面が表示されたら言語や時刻、通貨の形式や入力方式、キーボードの種類などのセットアップ項目を確認し、「次へ」に進みます。
④ 「今すぐインストール」をクリックしてください。
⑤ Windows10のプロダクトキーを入力し、Windows10のエディション項目を選んで「次へ」に進み、ライセンス条項に同意します。
⑥ 「カスタム:Windowsのみをインストールする(詳細設定)(C)」を選択します。
⑦ 「新規」「次へ」「適用」の順にクリックしてください。
⑧ 「OK」をクリックしてWindows10をインストールするドライブ項目を選んで「次へ」に進みます。
放電を行う
画面が暗くてもカーソルのみ動く場合やカーソルが点滅している場合は帯電が原因の可能性があります。その場合は放電をして起動を促してみてください。
① パソコンの電源を切りましょう。
② ACアダプターとバッテリーを外してください。
③ 数分放置します。
④ 放置後、ACアダプターとバッテリーを再び取り付けます。
⑤ パソコンの電源を入れてください。
以上の方法で起動すれば帯電が原因の可能性が高いです。起動後、異常が無ければそのまま使用できます。
外部モニターに接続する
・電源ランプが白色に点灯している
・画面が突然真っ暗になった
などのケースでは、ディスプレイの故障が疑われるので、外部モニターに接続をして問題が解消するか確認してみてください。ディスプレイの不具合確認方法は前述した「ディスプレイを新しいものにする」を参考にチェックしてみてください。ディスプレイが原因であれば交換で解決しますが、そのほかの異常が原因の可能性もあります。詳しい原因を知りたい場合は、業者に確認してもらった方が部品交換もできるので、的確に対処できます。
グラフィックドライバを再起動させる
電源がオンになっても黒い画面のままであればグラフィックドライバーとシステムの接続で問題がある場合もあります。再起動をして問題解決できるか確認してみましょう。
① 「Windows + Ctrl + Shift + B」を同時に押してください。
② 再起動プロセスが完了するまで待機します。再起動後に解消される可能性がありますが、万が一解消されない場合は、以下の手順を実行してみましょう。
③ 「Win+R」を同時に押して実行ウィンドウを表示させます。
④ 編集ボックスに「msc」と入力してエンターキーを押してください。
⑤ デバイスマネージャ内の「ディスプレイアダプター」を選択して右クリックをして「ドライバーの更新」に進んでください。
⑥ 「ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索」オプションをクリックして画面の指示に沿って更新操作を完了させます。
h3:BIOSをリセットさせる
BIOSを工場出荷時の状態にリセットすれば問題が解消されるケースもあります。BIOSとは、マザーボードに搭載されたプログラムを指します。管理と制御を行う役割を持っています。
① パソコンの電源を入れてロゴが表示される前に「F2」キーを数回押します。
② BIOSが起動した後、「Restore Settings」もしくは「Load Defaults」をクリックしてください。機種によって表示項目に違いがあるので、表示された項目を選んで「Esc」キーを押して終了します。終了する際には「保存して終了」を忘れずにクリックしてください。
クリーンブートを実行させる
起動を鑑賞するプログラムや邪魔をするプログラムを特定する際に活用できます。
① 管理者権限でパソコンにログインして「スタート」をクリックしてください。
② 画面左下にある検索窓で「msconfig」と入力して「システム構成」を選択しダイアログを起動します。
③ 「スタートアップ」「タスクマネージャーを開く」の順に進んでください。
④ 一覧に表示されている項目の状態が「有効」なものを選択し、画面下にある「無効にする」をクリックします。
⑤ 「有効」な項目部分を「無効」にしたらタスクマネージャーを「×」で閉じてください。
⑥ 「システム構成」ダイアログの「スタートアップ」タグに戻り、「OK」を押してパソコンを再起動させます。
プログラムの有効・無効を判断できない場合は、安易に無効にしないよう注意してください。
まとめ:以上の対処法を試しても改善されない際は、業者に連絡しよう!

Dellのパソコンの画面が真っ暗になったときの対処法を解説してきました。上記の方法を試しても改善されない場合ややり方が分からない場合は、症状の悪化やデータの消失を防ぐためにも自力で回復せずに業者に相談してみてください。専門家による知識や技術があれば、大切なパソコンのデータを失わずに問題解決が望めます。どういった症状で悩んでいるのか問い合わせを行い、的確な方法で対処してもらいましょう。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
Dellのノートパソコンはコストパフォーマンスが高く、種類も豊富なのでビジネスシーンでも取り入れられています。ビジネスでも活躍するDellのパソコンですが、ずっと使っているとバッテリーの消費が早くなってしまうものです。そうなると充電の回数も増えてしまい、使っている側は手間に感じてしまいます。
バッテリーの消費が早くなったら、バッテリー交換をしたいと考える方もいるでしょう。そこで今回は、バッテリー交換のタイミングや劣化する原因、交換方法、交換する際の注意点、交換手順を解説していきます。Dellのノートパソコンを使っていて、バッテリー交換をしたいと考えている方は参考にしてみてください。
バッテリー交換のタイミング
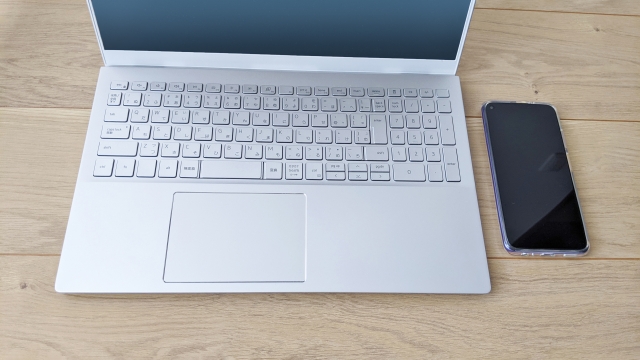
Dellのノートパソコンを使っている中で、バッテリー交換をどのようなタイミングですべきなのか迷ってしまうケースも少なくありません。そこでまずは、バッテリーの寿命や状態の確認方法から解説していきます。
バッテリーの寿命
パソコンのバッテリーは、寿命が約2~3年です。駆動時間が短くなってきたら新しいものと交換する必要性が出てきます。ただし、電源を確保できる環境でしかパソコンを使わないのであれば、そこまで気にする必要はありません。
Dellのノートパソコンを電源の確保ができない外出先でも使う場面があり、駆動時間を長くしたいのであれば、バッテリー交換を行うのがおすすめです。2年以上使っている場合は、バッテリーの寿命が近いと考えられます。
バッテリー状態の確認方法
Dellのノートパソコンは、バッテリーの状態を確認できるようになっています。オペレーティングシステム環境からチェックが可能です。Dellのノートパソコンでバッテリーの状態を確認する方法は以下のとおりです。
・Dellのノートパソコンの電源をOFFにする
・電源を入れ、Dellのロゴ画面で「F2」を押す
・左側の「General」下にある「Battery Information」を選択する
・バッテリー性能の情報を確認する
バッテリー性能の確認は、「F2」キーを押し、「Advanced」を選択する方法でも確認可能です。バッテリーの状態をチェックすれば、交換すべきか判断する指標になります。
バッテリーの劣化原因

Dellのノートパソコンに限った話ではありませんが、使い続けているとバッテリーは劣化してしまいます。続いては、ノートパソコンのバッテリーが劣化してしまう原因をみていきましょう。
経年劣化
使用年数が長くなると、経年劣化が起こります。経年劣化は、パソコンに良くない影響を及ぼします。具体的にはシステムエラーや内部パーツの破損、動作不良などの不具合です。
経年劣化を止めることはできません。しかし、ソフトウェアを最新のものにアップデートしたり、安定した動作環境を維持したりすると、安定化が可能です。メーカーや専門の業者の修理を依頼すれば、経年劣化が起こっても正常な状態を維持できます。
Dellのノートパソコンを使っていて経年劣化と思われる症状が出てきたら、早急に修理や交換を行うのがポイントです。
極度な温度変化
ノートパソコンに使われているリチウムイオン電池は、高温に弱い性質を持っています。そのため、真夏に暑い部屋の中で使ったり、持ち運び時に高温になる可能性がある車内に放置したりすると、本体が熱くなってバッテリーの劣化を早める可能性があります。デスクトップパソコンよりもパーツが詰まっているので、熱を溜め込みやすい特徴もあるので注意しなければいけません。
パソコンの頭脳とされるCPUは40~70度が適正温度とされていて、使用時の室温は16~25度が適温だと言われています。問題視されるのは高温ですが、低温過ぎるのもパソコンにとって負担となり、性能を低下させる原因になりかねません。暑過ぎず、寒過ぎない場所で使用・保管するのが望ましいです。
過度な充電
ノートパソコンのバッテリーは、充電可能回数が決まっています。Dellをはじめとした数々の製品だと、充電可能回数の目安は500回です。しかし中には、1,000回程度充電できるモデルもあるので、購入する際にバッテリーの性能も確認しておきましょう。
いずれにしても、決められた充電回数を超えると性能が低下し、最終的には充電不可となります。500回が充電可能回数だった場合、毎日充電すると約1年半で寿命を迎えるでしょう。残量が減っていないのにACアダプターにつないでおくなど、無意味に回数を増やすのは避けるのが無難です。
バッテリーの交換方法
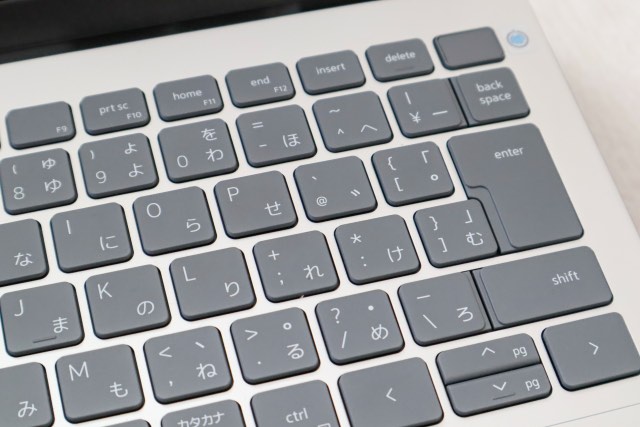
Dellのノートパソコンを使っていて、バッテリーの交換をしたいと考える場面でも出てきます。しかし、ノートパソコンのバッテリーを交換する機会はそこまで多くないので、どのようにすべきかわからない方もいるでしょう。そのため続いては、バッテリーの交換方法を解説していきます。
公式カスタマーサポートに依頼する
DELL公式サポートでは、Dellのノートパソコンを購入してから1年間の保証サポートを行っています。保証期間内なら、バッテリーの交換も無償でしてもらえるので、利用するようにしましょう。修理費用などもかかりません。
保証期間外であっても、オプションで3年間の保証サポートに加入できます。保証サポートでバッテリーの交換をしてもらう場合は、DELLの公式サイトから「サポートサービスと契約」で使っているノートパソコンの型番を入力し、手順に沿った対応をしてもらってください。
保証期間を過ぎている場合は、DELLの公式サイトから使っているノートパソコンに合うバッテリーを購入できます。
業者に依頼する
コストを抑えつつ早急にバッテリー交換をしたいなら、非正規店になりますが対応している業者に依頼する選択肢もあります。非正規店であってもパソコンに関する知識やスキルを持つプロなので、依頼しても問題ありません。メーカー保証の対象外になってしまいますが、短期間かつリーズナブルな修理をしてもらえます。
店舗によっては、即日対応も可能です。そのため、すぐにDellのノートパソコンを使わなければいけないなどの場合にも役立つでしょう。複数の業者から見積りを出してもらえば、より費用を抑えられます。
自分で交換する
Dellのノートパソコンは、ユーザー自身がバッテリーを取り外し、新しいものへと交換できるようになっています。自分で交換する場合は、使っているパソコンの型番に合うバッテリーとドライバーが必要です。メーカーや業者に依頼するわけではないので修理費用がかからないため、コストを抑えられる方法でもあります。
本体の裏に書かれている型番をチェックし、対応するバッテリーを公式サイトやネットショッピングサイトで購入します。届いたら古いバッテリーをノートパソコンから取り外し、新しいバッテリーを装着したら完了です。
自分でバッテリーを交換する際の注意点

ノートパソコンにはDellのモデルのように自分でバッテリー交換ができるものもあります。しかし、その際に注意すべきポイントもあるので、チェックしておかなければいけません。続いては、自分でバッテリーを交換する際の注意点をみていきましょう。
事前にバックアップを行う
ノートパソコンのバッテリー交換を行う際は、事前のバックアップを忘れないようにしてください。自分で交換する場合だけではなく、メーカーや業者に依頼する場合も例外ではありません。なぜなら、データを消失する可能性がゼロではないためです。
バックアップをしていないと、万が一データが消えてしまった場合、復元ができなくなります。Dellのノートパソコンのデータは、クラウドストレージや外付けのHDDやSSDに保存しておくのがおすすめです。複数の場所にバックアップを取っておくとより安心感が高まります。
作業前には放電を済ませる
バッテリーの交換を行う場合は、感電のリスクがあるので、バッテリーや電源ケーブルなどすべて外します。電源ケーブルをつないだまま作業をしてしまうと、より一層感電するリスクが高まるので注意が必要です。安全に作業するためにも、コード類をすべて外しておいてください。
バッテリー残量に関しては、25%まで減らしておくことをおすすめします。減らしておくことで、修理中に誤ってバッテリーを破損してしまったときに火災が発生するリスクを軽減できるためです。
外したネジは締め切る
バッテリー交換を行うなら、外したネジをしっかりと締め切ることも注意すべきポイントです。バッテリーを外す際に、ネジも外さなければいけないモデルがDELLのノートパソコンにはあります。ネジがしっかり締まっていないと、接続不良の原因になりかねません。
また、どこにネジが締まっていたか忘れないようにしましょう。交換する前に写真をスマホなどで撮影しておくのがおすすめです。
自分でバッテリーを交換する手順

自分でバッテリーを交換するのであれば、正しい手順を把握しておく必要があります。最後に、Dellのノートパソコンのバッテリー交換を自分で行う際の手順を解説していきましょう。
交換時に用意すべきものは以下のとおりです。
・新品のバッテリー
・パソコン本体
・精密ドライバー(星型と+ドライバー)
・静電気防止手袋(パソコンは精密機器で静電気に弱いため)
・マグネットトレイ(米粒ほどのネジを紛失しないようにするためにあると便利)
バッテリーを購入する
Dellのノートパソコンのバッテリーを交換する場合、まずは公式サイトやネットショッピングサイトで使っているモデルに対応するバッテリーを購入してください。公式サイトでは、使っているパソコンの型番を選ぶと専用のバッテリーが表示されるため、間違えることなく購入できます。
公式サイトからの購入が安心ですが、Amazonなどのネットショップでも購入可能です。「DELL バッテリー (型番)」などで検索すると、使用できるバッテリーを探せます。Amazonで普段から買い物をしている方は、探してみてください。
底面のネジを外す
購入したバッテリーが届いたら、交換作業に取り掛かりましょう。Dellのノートパソコンは、底面に8~10ヶ所ネジ止めされています。モデルによってはネジを外さずにバッテリーのつけ外しができるタイプもあるので、使っているのはどのようなタイプか確認してから作業を進めるようにしてください。
ネジを外す際は、星型と+ドライバーを使用しましょう。周辺は星型ドライバー、中央部は+ドライバーを使ってください。ネジを外せば、底面のカバーの取り外しが可能です。
外したネジはとても小さいので、なくさないようにマグネットトレイを用意しておくと安心です。
カバーを取る
ネジを外したら、カバーを取っていきます。この作業は神経を使うので、慎重に行ってください。意外としっかりはまっているので、外しにくいと感じてしまう場合もあるので注意が必要です。
なかなか外れない場合に備え、オープニングピックを用意しておく方もいます。オープニングピックがあれば、ドライバーなどで無理にこじ開けずに済むので、本体に傷がつきにくくなるためです。
バッテリーを取る
カバーを外すことができたら、バッテリーを取ります。カバーが付いているモデルのバッテリーを本体から取り外す際は、ネジやコードテープ、コネクタを外さなければいけません。コネクタ付近にあるネジはサイズが特に小さいので、慎重に作業する必要があります。
コードテープはカッターなどで切らないようにしてください。なぜなら、新しいバッテリーを取り付けたときに再度貼り付けなければいけないためです。
ネジなどを外した状態でバッテリー本体を手前に引っ張るようにして持ち上げると外せます。
新しいバッテリーを取り付ける
外したら、新しいバッテリーの取り付け作業を行います。取り付け方は外し方と逆の手順です。バッテリー本体をノートパソコンにつけ、コネクタからネジ、コードテープの順でつけていけば完了となります。
外したカバーを取り付ける
新しいバッテリーを取り付けたら、カバーを戻してください。戻すときは「パチン」と音が鳴るまでしっかりとはめるのがポイントです。
ネジを締める
外したカバーを取り付けたら、ネジを締めます。ネジは真ん中の+ネジ、周囲の星型ネジの順で締めるようにしてください。
バッテリーの放電・充電を行う
バッテリーの交換が完了したら、放電と充電を行ってください。放電は、パソコンの内部にある不要な電力を外に逃がすための作業です。放電しないままパソコンを起動した場合、エラーが発生しやすくなってしまいます。
放電する際は、電源ケーブルを接続せずにパソコンの電源を入れてください。しっかり放電ができたら、電源ケーブルを接続し、充電します。
まとめ:正しい手順に沿って、バッテリーを交換しよう!

Dellのノートパソコンを使っていて、電源を接続していないときのバッテリー持ちが悪くなったように感じる場合があります。それは、バッテリーが劣化している証拠です。劣化したまま使っていると、いずれ使えなくなってしまうので、交換する必要があります。
交換は、正しい手順を知っていれば自分でもできるでしょう。しかし、自分で交換したり、非正規店に依頼したりすると、保証対象外になってしまうケースが多くなっています。そのため、保証期間がある場合はメーカーに依頼するのが無難です。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
富士通のパソコンを使用していると、急に画面が動かなくなり、操作できなくなることがあります。この症状をフリーズといい、パソコンがフリーズするのには複数の原因があります。フリーズは、作業中のデータ消失や、パソコンの故障などにつながる可能性があるため、早急な解決が必要です。
この記事では、富士通のパソコンがフリーズする原因と対処法を解説します。今後フリーズさせないために、パソコン操作をスムーズにする方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
【この記事でわかること】
- 富士通のパソコンがフリーズする原因はハードウェアとソフトウェアの問題がある
- フリーズした場合にはまずしばらく待つ
- アプリやパソコンの強制終了もおすすめ
- どうしても修正できないなら初期化する
- フリーズしないためにできる対策
富士通のパソコンがフリーズする原因

富士通のパソコンがフリーズする原因には、以下があります。
- 処理に時間がかかっている
- マウスやキーボードの故障
- 熱暴走
- ハードディスクやメモリ、マザーボードなどの故障
- OSやシステムファイルの不具合
- パソコンの設定問題
- ウイルス感染
パソコンがフリーズする原因は、大きく分けて2つに分類されます。
本体やメモリ、マザーボードなどの故障や不具合、熱暴走などのハードウェアの問題と、OSやシステムファイルの不具合や設定の問題など、ソフトウェアの問題です。
それぞれの原因について、詳しく解説します。
処理に時間がかかっている
パソコンがフリーズしているように見えても、実は処理に時間がかかっているだけで、フリーズしていないことがあります。カーソルが動かなくなる、アプリの操作ができなくなる、画面が固まるなどの場合は、処理に時間がかかっている可能性があります。
富士通のパソコンが動かなくなったら、まずはアクセスランプを確認しましょう、アクセスランプが点灯中の場合は、パソコンが処理をしています。アクセスランプ点灯中に強制終了や再起動すると、処理中のデータを消失する可能性もあるため、処理が終わるまでしばらく待ちましょう。
マウスやキーボードの故障
マウスやキーボードの故障が原因で、パソコンがフリーズしているように見える場合があります。マウスやキーボードの動作がおかしい、クリックやキー入力を受け付けない場合は、マウスやキーボードの故障を疑いましょう。
まずは、別のUSBポートに差し替えて、動作を確認します。デバイスマネージャーで、マウスやキーボードのドライバを確認して、ドライバを再インストールするのも有効です。それでも動作しない場合は、別のマウスやキーボードに付け替えてみましょう。
熱暴走
パソコンが異常に熱い、ファンが頻繁に高速回転するなどの症状がある場合は、熱暴走によってフリーズしている可能性があります。
熱暴走とは、パソコン内部が高温になり、冷却機能が追いつかなくなること。高温の状態が続くと故障を防ぐために、パソコンは事故保護機能を発動し機能の制限やフリーズ、強制終了などが起こります。
長時間の作業を避ける、パソコンを定期的に清掃する、通気性の良い環境でパソコンを使うなどの対策が有効です。
ハードディスクやメモリ、マザーボードなどの故障
ハードディスクやメモリ、マザーボードなどのハードウェア故障が原因でフリーズすることもあります。
ハードウェアの故障があると、頻繁にフリーズが起こり、パソコンが起動しない、異音がすることもあります。ハードウェアが故障した場合は、交換や修理等が必要です。
OSやシステムファイルの不具合
OSやシステムファイルに不具合がある場合も頻繁にフリーズが起こり、ブルースクリーンエラーが発生することがあります。
OSとは、WindowsやMacなどを動作するために必要なシステムのこと、システムファイルとはOSを動作させるために必要なファイルのことで、破損や欠損、設定が不正になる、ウイルス感染するなどで不具合を起こすことがあります。
Windows Updateで最新の状態にアップデートするとバグが修正される可能性があります。また、システムファイルチェッカー(sfc /scannow)のコマンドを実行すると、システムファイルの破損や欠損を検出して修復できます。
パソコンの設定問題
特定のアプリを使う、特定操作を行う場合にフリーズする場合は、パソコンの設定の問題が疑われます。パソコンは様々なプログラムやデバイスを管理・制御していますが、それぞれの設定を誤ると正常に動作しなくなり、フリーズや動作が遅くなる原因になります。
具体的な設定例は、以下の通りです。
- 電源設定:省電力設定が過度に設定されている
- メモリ設定:仮想メモリの設定が適切でない
- システム設定:パフォーマンス設定が過度に設定されている
- デバイス設定:デバイスドライバが古い、または破損している
- アプリケーション設定:特定のアプリ(WordやExcelなど)の設定が原因でフリーズする
- BIOS設定:パソコンが起動するときに最初に読み込むプログラムでハードウェアの設定を行うが設定を間違えるとパソコンが起動しなくなる
パソコンの設定の確認や、問題のあるアプリの特定が必要です。競合しているデバイスドライバを特定し更新したり、不要なソフトウェアをアンインストールしたり、設定値をデフォルト(初期設定)に戻したりすると、問題が改善する場合があります。
ウイルス感染
富士通のパソコンにフリーズが頻繁に起こる、パソコンの動作が遅い、Windowsのロゴ画面で固まっている、デスクトップ画面で固まって動かない場合などは、ウイルス感染が疑われるケースもあります。
ウイルス感染が疑われる場合は、ウイルスソフトなどでウイルスチェックをしてみましょう。ウイルスが検出されない場合は、システムの不具合の可能性もあります。
富士通パソコンがフリーズした場合の対処法

富士通パソコンがフリーズした場合、以下の対処法を試してください。
- しばらく待つ
- タスクマネージャーでアプリを強制終了する
- Windowsを強制終了する
- アプリケーション/プログラムのアンインストールと再インストール
- 再起動する
- ウィルスチェックする
- 初期化する
それぞれの手順をわかりやすく解説します。
しばらく待つ
富士通のパソコンのアクセスランプが点灯中の場合は、焦らずにしばらく待ちましょう。処理が完了すれば、通常通り操作できるようになります。
待ち時間の目安は、5分程度です。アクセスランプが消えたら、正常に動作する可能性があります。
またフリーズした原因が一時的な高負荷の場合には、数分で自己修復する可能性もあるため、しばらく待つだけで動作するケースもあります。
タスクマネージャーでアプリを強制終了する
特定のアプリが原因でフリーズしている場合は、タスクマネージャーでアプリを強制終了することで解決する場合があります。タスクマネージャーは、パソコンのパフォーマンスを監視し、アプリケーションやプロセスを管理するために使用できるWindowsのツールです。
- タスクバーを右クリック、またはCtrl + Alt + Deleteキーを押して「タスクマネージャー」を起動する(タッチ操作の場合は「スタート」を長押し)
- 「プロセス」タブをクリックする
- アプリ一覧から終了したいアプリをクリックする
- 「タスクの終了」をクリックする
タスクマネージャーが起動しない場合は、Ctrl + Shift + Escキーを押して開くこともできます。
参照:FMVサポート [Windows 11] アプリやパソコンを強制終了する方法を教えてください。
Windowsを強制終了する
富士通のパソコンのフリーズが改善しない場合は、以下の手順でWindowsを強制終了しましょう。
- 「Ctrl」キーと「Alt」キーを押しながら、「Delete」キーを押す
- 黒い画面に「ロック」や「ユーザーの切り替え」などが表示される
- 画面右下の電源ボタンのマークをクリックする
- 表示されるメニューから「シャットダウン」をクリックする
- Windowsが終了しパソコンの電源が切れる
- そのまま10秒待つ
- パソコンの電源ボタンを押しWindowsを起動する
Windowsが強制終了できない場合は、本体の電源ボタンを長押しして強制終了します。
- 電源ボタンを4~10秒以上長押しする
- 電源ランプが消灯したら、指を離す
- そのまま10秒以上待つ
- パソコンの電源ボタンを押しWindowsを起動する
パソコンを強制終了すると、データが消失する可能性があります。しかし、フリーズが改善しない場合には有効な方法です。
富士通のノートパソコンやタブレットパソコンの一部の機種には、電源ボタンで電源が切れないときに使用する強制終了スイッチが搭載されています。パソコン本体下面の直径2〜3ミリ程度の穴の中にあるスイッチで、スイッチの近くに「RESET」や「OFF」、「REPAIR」と刻印されています。
使用する場合は、パソコン本体からACアダプターと周辺機器を取り外し、パソコン本体を静かに裏返します。強制終了スイッチにクリップの先などを差し込んで、スイッチを押してください。
参照:FMVサポート 強制終了スイッチについて教えてください。(2015年9月・10月・12月発表モデル以降)
アプリケーション/プログラムのアンインストールと再インストール
問題のあるアプリケーション/プログラムをアンインストールして再インストールすることで、解決する場合があります。
- コントロールパネルを開く
- 「プログラムと機能」を選択する
- 問題のあるアプリケーション/プログラムを選択し、「アンインストール」をクリックする
- アプリケーション/プログラムをダウンロードしてインストールする
アンインストールする前には、アプリやプログラムの設定のバックアップがおすすめです。
再起動する
富士通のパソコンは再起動することで、フリーズなどの問題が解決する場合があります。
- スタートメニューを開く
- 電源ボタンをクリックし、「再起動」を選択する
ウィルスチェックする
ウイルス感染が原因でフリーズしている場合は、ウイルスチェックを行い、ウイルスを駆除する必要があります。
Windows10およびWindows11には、ウイルス対策ソフト「Windows Defender」がデフォルトで入っています。Windows Defender は、リアルタイムの保護、クラウドベースの保護、高度な脅威からの保護など、さまざまな機能をもつセキュリティソフトです。
Windows Defenderでウイルスをチェックして削除する手順は、以下の通りです。
- スタートメニューから「設定」、「更新とセキュリティ」、「Windowsセキュリティ」を選択する
- 「ウイルスと脅威の防止」を選択する
- 「クイックスキャン」を実行する
- さらに詳しくスキャンする場合は「フルスキャン」を選択する
- スキャン結果を確認する
- ウイルスなどの脅威がある場合は、「許可」、「削除」、「隔離」のいずれかを選択する
- ウイルスを削除する
Windows Defenderは、常に最新の状態に保つようにしましょう。Windowsを使用している場合は、他のウイルス対策ソフトを導入する必要はありません。別のウイルス対策ソフトを導入する場合は、Windows Defenderを無効にしましょう。
初期化する
ここまで紹介した方法を試しても、フリーズが改善しない場合は、最終手段として初期化もおすすめです。初期化すると、パソコンが工場出荷状態に戻るため、パソコン内のデータは消失してしまいます。
ここでは、Windows11の富士通のパソコンを初期化する手順を紹介します。初期化する前には、デバイスの暗号化の回復キーを取得して、保管しておきましょう。データのバックアップができる場合は、しておきましょう。バックアップできない場合、必要な情報をメモしておくのもおすすめです。
初期化後には再度ログインが必要になるため、Microsoftアカウントなどのアカウント情報もメモしておきましょう。
周辺機器を取り外し、ACアダプターを接続し、準備が整ったら、以下の手順で初期化します。
【Windowsが起動できる場合】
- 「スタート」ボタンから「設定」の順にクリック
- 「システム」をクリック
- 「回復」をクリック
- 「PCをリセットする」ボタンをクリック
- 「オプションを選択してください」と表示されたら「すべて削除する」、または「個人用ファイルを保持する」をクリック
- 「Windowsを再インストールする方法を選択します。」と表示された場合は、「ローカル再インストール」をクリック
- 表示されない場合は、次の手順に進む
- 「追加の設定」と表示されたら内容を確認し、問題がなければ「次へ」ボタンをクリック
- 「このPCをリセットする準備ができました」と表示されたら内容を確認し「リセット」ボタンをクリック
- リカバリが開始される
すべて削除するを選択すると、パソコンが購入時の状態に戻るため、初期化するのに数時間かかることがあります。パソコンを譲渡する、処分するなどで手放す場合におすすめです。
一方、個人用ファイルを保持するを選択すると、Windows、ドライバー、アプリの状態は「すべて削除する」と同じ状態に戻りますが、ユーザーアカウントや個人用ファイルなどを保持します。一部データが保持されるため、フリーズした状態が修正されない可能性があります。
【Windowsが起動できない場合】
Windowsを起動できない場合は、以下の手順で「Windows 回復環境」を実行してから、「このPCを初期状態に戻す」を実行します。
- キーボードの上部にある「SUPPORT(サポート)」と記載されたボタンを押す
- サポートボタンがない場合は「F12」キーを押しながら、パソコンの電源を入れ、音がなったら指を離す。(音が鳴らない場合でも起動メニューが現れたら「F12」キーから指を離す。)
- 「起動デバイスを選択してください」、「アプリケーションメニュー」、「Application Menu」が表示された場合は、そのまま次の手順に進む
- 「起動メニュー」、「Boot Menu」が表示された場合は、「Tab」キーを押してメニューを切り替える
- 「↓」キーを押して「Windows 回復環境」または「Windows Recovery Environment」にカーソルをあわせて、「Enter」キーを押す
- 「オプションの選択」が表示されたら「トラブルシューティング」をクリック
- 「このPCを初期状態に戻す」を1回クリック
- 「オプションを選択してください」と表示されたら「すべて削除する」、または「個人用ファイルを保持する」をクリック
- 「Windowsを再インストールする方法を選択します。」と表示された場合は、「ローカル再インストール」をクリック
- 表示されない場合は、次の手順に進む
- 「追加の設定」と表示されたら内容を確認し、問題がなければ「次へ」ボタンをクリック
- 「このPCをリセットする準備ができました」と表示されたら内容を確認し「リセット」ボタンをクリック
- リカバリが開始される
参照:FMVサポート [Windows 11] 「このPCを初期状態に戻す」(リカバリ)の実行方法を教えてください。
富士通パソコンがフリーズしないための高速化テクニック

富士通のパソコンがフリーズする原因は様々ありますが、以下の方法を実践することでフリーズを防げる可能性があります。
- パソコン周りの作業環境に注意する
- パソコンの清掃
- 使わないアプリは終了する
- パソコンの設定を変更する
- メモリを増設する
- HDDからSSDへの交換
- OSやアプリケーションのアップデート
- デフラグをする
パソコン操作をスムーズにするためにも、実行してみましょう。順番に手順を解説します。
パソコン周りの作業環境に注意する
パソコンの周りに物が多く置かれていると、通気性が悪くなり、パソコン内部の温度が上がってフリーズの原因になります。パソコンは平らで安定した場所に置き、周囲に十分なスペースを確保しましょう。
ファンや通気口に埃が詰まっていると、熱がこもりやすくなり、フリーズの原因になります。定期的に掃除機などで埃を取り除きましょう。
パソコンの清掃
パソコン内部の埃を清掃するとパソコン内部に熱がこもりにくくなります。そのため動作が改善し、フリーズしにくくなります。
- パソコンをシャットダウンし、電源ケーブルを抜く
- ケースを開けて、埃を掃除機で吸い取る
パソコンは精密機械のため取扱いには注意が必要です。静電気は厳禁のため、静電気防止手袋の使用がおすすめです。掃除機を使う場合は、小さなパーツを吸い込まないように注意しましょう。心配な場合は、エアーダスターで埃を飛ばすのもおすすめです。
使わないアプリは終了する
複数のアプリを同時に起動していると、メモリやCPUの使用率が高くなり、フリーズの原因になります。使わないアプリは終了して、メモリやCPUの使用率を減らしましょう。
パソコンの設定を変更する
パソコンの設定を変更することで、フリーズしにくくなる場合があります。パソコンを高速化するためには、Windows11の場合電源の動作モードを高パフォーマンスにするのがおすすめです。
- コントロールパネルを開く
- 「ハードウェアとサウンド」を選択する
- 「電源オプション」を選択する
- 「高パフォーマンス」プランにチェックを入れる
その他にも、Windows11の設定を以下に変更すると、高速化が期待できます。
- スタートアップアプリを無効にする
- ストレージセンサーを起動する
- 視覚効果を無効にする
- 通知とアラートを無効にする
メモリを増設する
パソコンに搭載したメモリが少ないと、パソコンの動作が遅くなり、フリーズの原因になるため、増設することで、パソコンの動作を高速化できます。
頻繁にフリーズする場合は、作業内容に対してメモリが足りない可能性があります。パソコンのメモリは増設も可能です。メモリを増設する場合は、パソコンの取扱説明書を参照して、対応するメモリの種類と容量を確認しましょう。
パソコンのメモリ増設後に不具合が起こった場合の対処法は、下記記事でも詳しく紹介しています。
メモリ増設後にパソコンが起動しなくなった!よくある原因と対処法を解説>>
HDDからSSDへの交換
HDDはSSDよりも読み書き速度が遅いため、HDDを搭載しているパソコンはフリーズしやすい傾向があります。HDDをSSDに交換することで、パソコンの起動速度やアプリケーションの読み込み速度を高速化することができます。
SSDへの交換は、専門知識がない場合は故障の原因となる場合もあります。パソコン修理専門店などに依頼することをおすすめします。
HDDの交換方法は、下記記事でも詳しく解説しています。
HDDの交換は自分でもできる!デスクトップ・ノートPCでの手順を解説>>
OSやアプリケーションのアップデート
OSやアプリケーションが古いバージョンだと、不具合や脆弱性があり、フリーズの原因になることがあります。
OSやアプリケーションを最新の状態にアップデートすることで、不具合や脆弱性を修正することができます。
デフラグをする
HDDは使用していくうちに、データが断片化して読み書き速度が遅くなり、フリーズの原因になることがあります。デフラグを行うことで、データの断片化を解消し、読み書き速度を高速化できます。以下の手順で、デフラグを実行しましょう。
- タスクバーの「エクスプローラー」アイコンをクリック
- 「PC」をクリック
- 「ローカルディスク(C:)」を右クリック
- 表示されるメニューから「プロパティ」をクリック
- 「ツール」タブをクリック
- 「最適化」ボタンをクリック
- 「ドライブの最適化」が表示されたらデフラグを実行するドライブをクリック
- 「最適化」ボタンをクリック
- 「最後の実行」に「実行中」と表示され、ディスクデフラグが実行される
参照:FMVサポート [Windows 11] ディスクデフラグを実行する方法を教えてください。
フリーズが改善しない場合の対処法

ここまで紹介した方法を試しても改善しない場合は、サポートへ相談、買い替えなどがおすすめです。
サポートへ相談する
富士通のパソコンがフリーズして、対処できない場合はサポートへ相談するのがおすすめです。富士通のサポートは、電話だけでなくチャットやメールサポートもあります。また、他のユーザーに相談できるQ&Aコミュニティもあり、Web上での相談も可能。
さらにネットで診断できる故障診断があり、故障と判断された場合にそのまま修理に出す方法もあります。富士通サポートへは、下記サイトから申し込みできます。
パソコンを買い替える
富士通のパソコンが頻繁にフリーズする場合は、寿命を迎えている可能性もあります。寿命を迎えている場合は、どのような対処法を試しても、フリーズを繰り返す可能性があります。
頻繁にフリーズする場合は、パソコンの買い替えを検討しましょう。パソコンを買い替えたら、古いパソコンは処分する必要があります。しかし、パソコンは小型家電リサイクルの対象のため、費用がかかってしまいます。
パソコン廃棄.comなら不要になったパソコンを無料で処分可能です。データ消去も無料で行うため、パソコンを処分する手間もかかりません。


監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。