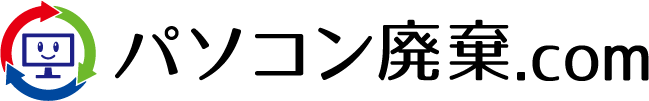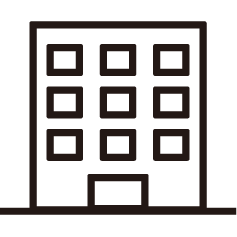404 Not Found
SSDは、パソコンの内部記録媒体としてHDDの代わりに使われることが多くなってきました。HDDよりも書き込みのスピードが速く、小型で軽量、衝撃に強いなどのメリットがあります。そのため、導入するケースが多くなってきました。
しかし、衝撃に強いSSDでもデータが消えてしまうなどのトラブルをなくすことはできません。そこで今回は、SSDが故障する原因やデータを復旧させるための方法、専門業者にデータの復旧を依頼する方法などを解説していきます。
SSDが故障する原因

SSDが故障する原因は、大きく分けると論理的障害と物理的障害の2種類があります。どのような原因なのか解説していきましょう。
論理的障害
論理的障害は、SSDに保存されているデータの破損によって起きる障害です。SSDをフォーマットする操作を誤って行ったり、必要なデータをうっかり消してしまったりなどの誤操作も論理的障害の原因として挙げられます。また、OSに不具合が生じたことによる影響で、SSDの内部にあるデータが破損してしまうケースも考えられるでしょう。
OSが正常に機能していない
OSは、パソコンの司令塔のような役割を担っている部分です。起動に必要なブートシステムも格納されています。OSが正常に機能していないと、パソコン自体も正常に起動できません。
ブルースクリーンが表示される場合もあります。パソコンを起動したときにブルースクリーンになってしまう場合は、OSが正常に機能していない可能性を疑いましょう。
システムファイルに異常がある
システムファイルは、データを管理する本棚のような場所です。パソコンの起動に関わる情報も含まれています。システムファイルに異常が生じて引き起こされるのは、保存してあるデータの位置情報が壊れてしまうので、どこに何があるのかわからなくなってしまうなどのトラブルです。
少しでもおかしいと感じたら、障害が悪化する前に電源を落としてください。再起動も行わないようにしましょう。そして、データの復旧を専門的に行っている業者に相談してみてください。
物理的障害
物理的障害は、その名のとおりパソコン自体が破損していることを指します。HDDと比較するとSSDが破損するケースは少ないですが、破損しないわけではありません。破損の原因として多く見られるのは、静電気によって引き起こされるショートや書き込み回数の上限などです。
複数のSSDで構成されているパソコンの場合は、1つ破損するだけですべて使えなくなってしまうこともあります。そのため、静電気くらい大丈夫だろうと侮るのは禁物です。
物理的な障害による不具合を復旧する技術はまだそこまで進んでいないため、復旧できる業者も多くありません。データ復旧を依頼する業者探しに苦労してしまう可能性があります。
ファームウェアが故障している
ファームウェアは、SSDのコントローラーにある物理的な動きを制御するプログラムです。ファームウェアが故障してしまうと、物理的障害が生じてしまうので使えなくなってしまうでしょう。障害が発生する原因には、パソコンの強制終了や経年劣化が挙げられます。
ファームウェアは年々進化しており、複雑化しています。そのため、障害が起こっても対応できない業者もあるので注意してください。データを取り戻したい場合は、物理的障害の復旧実績がある業者に相談しましょう。
書き込み回数が上限を達した
SSDには書き込みの上限回数が設定されています。上限を超えてしまうと、突然動かなくなってしまうので注意しなければいけません。しかし、HDDのように異音が鳴ることはないので、予兆に気付きにくいです。
障害が起こる前に対処するには、OS関連のファイル書き換え頻度が低く、代替の効くデータをSSDに保存するようにしましょう。書き換え頻度が高いファイルはHDDに保存するのがおすすめです。
自分でSSDに保存したデータを修復する方法

SSDに保存したデータは、自分で復旧できる場合もあります。続いては、自分でSSDに保存したデータを修復する方法をご紹介します。
データ復旧用ソフトが対応できる状態
SSDを誤ってフォーマットした場合やSSDのデータを誤って消してしまった場合は、データ復旧用ソフトで対応できる可能性が高いです。しかし、SSDの記憶容量を確保するためにデータの自動削除を行うコマンド・Trimが有効になっている場合は、復旧が難しくなる可能性も考えられます。
基本的には自分でやろうと思えばできますが、成功するとは言い切れません。データ復旧ソフトを使ったからと言って復旧できるとは限らないことを念頭に置いておきましょう。
SSDの復旧に使えるソフトにはいくつか種類があるので、状況に合わせたものを選んでください。無料で使えるソフトはファイル破損など簡単な症状だけに対応できます。利用料金が1万円ほどの有料ソフトであればフリーソフトより復旧性能が高いです。
データ復旧用ソフトが対応できない状態
物理的な障害やファームウェアの障害が発生してしまった場合は、データ復旧ソフトを使っても対応が難しいと考えられます。ソフトを使って復旧できても、データを元どおりに復元できるとは限りません。
そのようなケースでSSDのデータを復旧したいのであれば、専門業者に依頼するのが無難です。SSDのデータ復旧専門業者なら、自力で復旧しようとする場合よりも幅広い状況に対応できます。ただし、障害の原因や状況によっては、復旧が難しい場合もあるので過信はしないようにしてください。
データ復旧ソフトの利用手順
データ復旧ソフトの利用手順は以下のとおりです。
1.SSDのデータ復旧ができるソフトを選定する
2.パソコンにデータ復旧ソフトをインストールする
3.SSDのスキャンを行い、復元可能なデータを探す
4.データを復元したいファイルを選ぶ
5.データ復元ボタンをクリックする
6.データの復元が完了するまで待機する
データ復旧ソフトによって認識されたSSDは、復旧できる可能性が高いものになります。認識したデータから復旧したいものを選び、復元をソフトにお任せするだけなので簡単です。SSDのデータ破損や誤操作によって削除されたデータの復旧ならソフトでできる可能性が高いですが、データの容量が大きいと復旧作業に時間がかかる場合もあります。
データの復旧中に注意すること
SSDの復旧作業中に注意すべき点も把握しておく必要があります。
・電源の入り切りや再起動、通電の継続はしない
SSDはHDDよりも繊細な精密機器なので、より気を使って作業しなければいけません。内臓でも外付けでもトラブルが起こったら、まずは電源を切るようにしましょう。電源の入り切りを繰り返したり、再起動を行ったりすると、データの消失につながる可能性があります。
電源が入っていて通電されている状態だと、バックグラウンドでシステムが動いているので、状況を悪化させるリスクが高まってしまうので要注意です。SSD内のデータを守りたいなら、まず電源を切るのは鉄則だと覚えておきましょう。
・フォーマットをしない
SSDが認識できなくなってしまうと、「フォーマットする必要があります」などのエラーが出るケースもあります。焦って「はい」を押したくなってしまうかもしれませんが、押してはいけません。フォーマットしてしまうと、工場出荷時の状態に戻るため、中のデータがすべて消えてしまうためです。
・内蔵されているSSDを取り出す
パソコンに内蔵されているSSDなどの機器を個人で取り出すリスクは大きいです。状態を悪化させてしまうだけではなく、メーカーの保証も外れてしまいます。通電するだけでも新たなトラブルに発展しかねないので、ほかのパソコンにつないでみるなどの行為は危険です。
・分解しない
SSDは多くのパーツで構成されています。パソコン自体にも言えますが、クリーンルーム環境外での分解は避けるようにしましょう。小さなほこりなどが付着するだけでも大きなトラブルにつながる可能性があります。
また、精密機器なので分解して状況が悪化する可能性もないとは言い切れません。しかし分解してしまうと、メーカーの保証対象外となってしまうので諦めるしかなくなります。何とか自分で復旧したいなら、プロに相談した上で進めるのが無難です。
・無理に自力で復旧作業を行わない
SSDの復旧作業は、取り扱っていない業者もあるほど繊細で難しいです。ハイレベルな技術が必要になります。そのため、自分で復旧作業を進めようとしたり、いつものようにパソコンを使ったりすると、逆効果になってしまう可能性も考えられるでしょう。
SSDの復旧で少しでも対応を間違えてしまうと、取り返しがつかない状況になる恐れもあります。何らかのトラブルが起こると慌ててしまいますが、落ち着いて対応するようにしてください。自分自身での復旧を考えたときは、プロに相談した上で作業を進めると後悔するリスクも回避しやすいでしょう。
専門業者にデータ復旧を依頼する方法

自力での復旧はリスクもあるので、できればプロにお願いしたいと考えるケースも少なくありません。業者に依頼する場合は、ホームページなどにあるお問い合わせフォームや電話番号から問い合わせてみてください。専門業者に依頼すると得られるメリットもあるので、依頼する価値は大いにあります。
最後に、専門業者にSSDデータの復旧を依頼するメリットや、専門業者を選ぶ際のポイントを解説するので参考にしてみてください。
専門業者にSSDデータの復旧を依頼するメリット
専門業者にSSDデータの復旧を依頼するメリットには、以下のような点が挙げられます。
・SSDの復元を行うための環境が整っている
専門業者であれば、データを復旧するための専門的な設備が整っています。また、専門的な技術を持つスタッフも在籍しているので、SSDの復元に精通したサービスを提供していることになるでしょう。
・料金保証がある
SSDのデータ復旧を行っている専門業者では、復旧に成功したデータだけに料金がかかるなどの保証を行っているケースが多いです。ただし、中には悪質な業者もあり、法外な金額を請求される可能性もゼロではないので注意しなければいけません。
・無料サービスが充実している
無料診断を行っている業者も多く見られます。専門的な技術を持つスタッフが、SSDの症状をチェックし、原因を診断してくれるものです。どのような対応が必要なのか、などのアドバイスもしてもらえます。
専門業者を選ぶ際のポイント
SSDのデータ復旧を行っている専門業者はいくつもあります。その中でどこに依頼すべきか迷ってしまうケースも少なくありません。
迷わないようにするには、専門業者を選ぶ際のポイントを把握しておくことが重要です。専門業者を選ぶ際のポイントには、以下のような点が挙げられます。
・高度な技術力を有しているか
SSDの復旧には、高度な技術が必要です。そのため、依頼先の業者もハイレベルな技術を持つスタッフが在籍している必要があります。独自技術やAI技術を持っている場合も、適切な対応をしてもらえる可能性が高いです。
・復旧料金をホームページで確認できるか
いくらくらいかかるのか、依頼するときは気になるでしょう。ホームページをチェックしたときに料金が記載されている業者なら、安心して相談できます。しかし書かれていない場合は、そのときの言い値になってしまい、適正な価格なのか判断が難しくなってしまうので要注意です。
・復旧にはどのくらい時間がかかるか
復旧にかかる時間がどの程度か、気になる方もいるでしょう。復旧にかかる時間は、問い合わせをする際に確認すべきポイントです。曖昧にされてしまう場合などはそこまで実績がない可能性も考えられます。
・情報の管理を徹底しているか
SSDもパソコンの一部で、大切な情報が入っているケースも多いです。そのため、情報管理を徹底している業者に依頼した方が安心でしょう。守秘義務やセキュリティ管理を徹底的に行っている業者への依頼がおすすめです。
・クリーンルームが整っているか
SSDの復旧作業を行うには、クリーンルームなど適切な設備が必要です。適切な設備がなければ、自宅で作業するのと何ら変わりません。トラブルのリスクを軽減するためにも、クリーンルームなどの設備が整っている業者に依頼しましょう。
・復旧事例や実績はあるか
過去の復旧事例や実績も依頼前に確認すべきポイントです。実績がある業者であれば、安心して依頼できます。しかし、過去の事例や実績を公開していないと、本当に安心できる業者なのかわかりません。
大切なデータを適切に復旧してもらうには、過去の実績なども確認しておきましょう。そして、実績が豊富な業者を選ぶようにしてください。
まとめ:自分でSSD復旧作業をする際にはさらなるダメージを与えないよう気をつけて行おう!

SSDの復旧作業は、適切な手順を把握していれば自分でもできます。しかし、繊細なので静電気などでダメージを与えないように細心の注意を払わなければいけません。注意点などを把握した上で作業を進めるようにしましょう。
自分での作業に少しでも不安がある場合は、業者に依頼するのが無難です。業者に依頼するときは、専門業者を選ぶ際のポイントを参考にしてみてください。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
PS3に内蔵されるHDDの容量には限界があり、ゲームソフトやアプリ、スクショ画像・動画などがいっぱいになると容量不足になってしまいます。そこで、HDDを交換して容量を増やしたいと思っていませんか?
正しい手順を踏めば、PS3のHDDは個人でも交換が可能です。今回は、PS3のHDD交換にあたって知っておきたい規格や必要なもの、交換の手順まで解説しています。PS3のHDD交換を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
PS3で使用できるHDDの規格

PS3で使えるHDDの規格は決まっています。規格に合わないHDDを用意してしまうと交換できなくなるので、注意しましょう。PS3に対応したHDD規格は以下のとおりです。
2.5インチ
内蔵HDDのサイズには、3.5インチと2.5インチの2種類があります。PS3の場合、ノートパソコンや省スペースのデスクトップPCなどでも使われる、2.5インチのものを用意してください。
また、HDDだけでなくSSDへの交換も可能です。SSDは読み書きの速度が速く、動作音が小さいなどのメリットがあります。
ただし、HDDに比べて最大容量が少ない欠点もあるので注意が必要です。さらに、ニコニコ動画やYouTube動画などの視聴、オートセーブなどでストレージを頻繁に書き換える必要がある場合、書き込み回数に寿命があるSSDよりもHDDを選んだ方がいいでしょう。
9.5mm SATA インターフェイス
SATAインターフェイスの規格は、Serial ATAとなっています。かつて主流だったパラレルATAには対応していないので気をつけてください。
HDDのサイズだけではなく、厚さ9.5mm以内かどうかも確認しましょう。これ以上に厚さがあると、スロットに入らないためHDDを内蔵できなくなります。
最大容量1.5TB
対応しているHDDの最大容量は1.5TBです。PS3(CECH-4000シリーズ)の購入時の容量は250GBと500GBとなっています。たまにゲームを買ってプレイするぐらいならば、容量不足になることは少ないでしょう。
反対にたくさんゲームを買ってプレイしたり、画像や動画、音楽データなどを保存したりしている人はあっという間に容量オーバーとなってしまいます。1.5TBもあれば、容量を気にせずゲームの購入やデータ保存が可能です。
しかし、容量が大きいHDDほど価格は高くなるので、自分に必要だと思う容量を選ぶようにしましょう。
HDDの交換に必要なもの

PS3のHDD交換するために、揃えておくものがいくつかあります。続いては、HDD交換に必要なものをご紹介しましょう。
プラスドライバー
PS3の分解やHDDの取り付けにドライバーが必要です。ドライバーにはプラスとマイナスがありますが、PS3のHDD交換ではプラスドライバーH型を用意しましょう。
また、ドライバーのサイズは「1番」となっているので、サイズ違いに注意してください。サイズの合わないドライバーを無理に使うとネジ穴をつぶしてしまい、HDDや本体の外装を固定できなくなってしまいます。
ソフトウェアをダウンロードしたUSBメモリ
新しいHDDに交換するにあたって、元々内蔵されていたHDDに保存されているPS3のソフトウェアやデータを移動させる必要があります。交換する前にUSBメモリにソフトウェアのダウンロードや画像や動画などのファイルを移動させておきましょう。
システムソフトウェアのダウンロードは、パソコンからPlayStationの公式サイトを経由して行います。手順は以下のとおりです。
1.USBメモリの中に「PS3」と名前を付けたフォルダを作っておきます。
2.PS3フォルダ内に、さらに「UPDATE」と名付けたフォルダを作成しましょう。
3.PlayStation公式サイトの「PlayStation3システムソフトウェアアップデート」ページへ移動してください。
4.「PS3アップデートをダウンロードする」を右クリック、「名前を付けてリンク先を保存…」を左クリックします。
5.パソコンに「PS3UPDAT.PUP」がダウンロードされたら、USBメモリ内の「UPDATE」フォルダへ移動させます。
なお、USBメモリはデータのバックアップをとるときにも活用できることから、なるべく新品のメモリを用意するといいでしょう。ただし、PS3専用として販売されている「CECHA00(60GB)」と「CECHB00(20GB)」は、すでにシステムソフトウェアが入っている状態のため、USBメモリは別途用意する必要はありません。
PS3と互換性のあるHDD
PS3のHDD交換を行うには、PS3と互換性のあるHDDを用意する必要があります。互換性に関しては、上記でご紹介したように、2.5インチかつ9.5mm のSATA インターフェイスであればほとんどの製品はPS3と互換性を持っています。
PS3にはSATA1(150MB/s)のインターフェイスが搭載されているため、SATA1の購入を検討されている方も多いでしょう。しかし、SATA2(300MB/s)でも利用できるため、コストを抑えたい方はSATA2を選ぶのがおすすめです。
また、PS3に活用したあとでハードディスクを別の製品に活用しようと考えているのであれば、SATA3(600MB/s)のハードディスクを購入した方がいいでしょう。
HDDの交換の手順

PS3のHDD交換に必要なものが準備できたら、実際に交換を行っていきましょう。PS3のHDD交換は大きく5つのステップで行います。
1.データをバックアップする
まずは、PS3内に保存されているデータのバックアップを取ります。もしPS3内にデータを保存していないのであれば、次のステップへ移行しましょう。
データをバックアップするためには、保存するためのUSBメモリが必要です。以下の手順にしたがって、HDD内にあるデータをUSBメモリに移動させてください。
1.USBメモリをPS3本体にあるUSBコネクタに接続します。
2.PS3を起動させ、メニュー画面にある「設定」→「本体設定」を選びます。
3.さらに「バックアップユーティリティ」にある「バックアップ」を選択してください。
4.バックアップを選択するとトロフィーデータに関する注意書きが表示されます。注意書きを読んだら「はい」を選択してください。
5.「はい」を選ぶと保存先の選択画面が表示されます。その中から「USB機器」を選択するとバックアップが行われ、完了画面が表示されれば終了です。
上記の方法はデータをまとめてバックアップするための方法です。一部データのみバックアップしたい場合は、オプションメニューから「コピー」「ムーブ」「バックアップ」のいずれかを選んで、必要なデータだけをバックアップさせましょう。
なお、トロフィーデータに関する注意書きでは、ゲーム内で取得したトロフィーデータはバックアップができないことを説明しています。トロフィーデータも残しておきたい場合は、Sony Entertainment Networkのアカウントを作ってオンラインサーバーに保存しなくてはなりません。
トロフィーデータを保存するには、PSN℠にサインインをしてからPlayStation™Networkに接続してください。次に、トロフィーコレクションを選択して△ボタンを押すと、オプションメニューが表示されます。「サーバーと同期」を選べばトロフィーデータがPSN℠サーバーに保存されます。
2.古いHDDを取り外す
データのバックアップが完了したら、いよいよ交換作業に移ります。まずはPS3を分解して、HDDを取り外しましょう。HDDの取り外しとなると難しそうに思えるかもしれませんが、実際にはプラスドライバーさえあれば誰でも簡単に取り外しが可能です。
1.PS3の電源を切り、本体に接続しているケーブルをすべて取り外してください。
2.本体を裏返すとネジを隠しているカバーがあります。カバーをずらしてネジを取り外しましょう。
3.ネジを取り外したら、次は本体の前面にあるカバーを取り外します。カバーは正面から見て右方向にスライドさせると外せます。
4.カバーを取り外すとHDD交換のマウンタが見えるので、取っ手の箇所を手前に引き出すと外れます。ただし、手前に引き出す際には力が入り過ぎないように気をつけてください。
5.HDDはトレイに固定されているため、ドライバーを使って固定金具4ヶ所をすべて取り外します。
これでPS3から古いHDDを取り外せます。早ければ5分程度で取り外すことが可能です。
3.新しいHDDを取り付ける
次に、新しいHDDを取り付けていきます。基本的には古いHDDを取り外したときと逆の手順で行えば取り付けが可能です。
1.新しいHDDをトレイにのせ、四隅をネジで固定させます。
2.固定させたHDDをPS3本体に差し込み、カバーをはめてください。
3.本体裏側のネジを1本付け直したら、ネジを隠していたカバーをはめます。
4.あとはPS3に電源コードなどを接続させれば完了です。
4.システムソフトウェアを再インストールする
新しいHDDに交換したからと言ってもすぐにゲームができるわけではありません。新しいHDDへシステムソフトウェアを再インストールさせる必要があります。再インストールする手順は以下のとおりです。
1.PS3にシステムソフトウェアをダウンロードしておいたUSBメモリを差し込みます。
2.PS3を起動させると「システムソフトウェアが正しく動作できません。PSボタンを押して再起動してみてください。」と書かれた画面が表示されます。画面が表示されたらスタートボタンとセレクトボタンを同時押ししましょう。
3.次に「本体ストレージのシステム領域をフォーマットします。~」と書かれた画面が表示されます。表示に従って、スタートボタンとセレクトボタンを5秒以上同時押ししてください。同時押しをするとフォーマットが開始されます。
4.あとは自動的にシステムソフトウェアのインストールが行われます。インストールがすべて完了するとPS3が再起動し、初めてPS3を起動した際の画面が表示されます。
ここからさらに初期設定を行います。初期設定の流れは以下のとおりです。
1.「コントローラをUSBケーブルで接続して、PSボタンを押してください」と表示されるため、指示にしたがってPSボタンを押します。
2.表示言語は「日本語」を選択しましょう。
3.HDMIで接続している場合、初期設定で「HDMIが検出されました。映像と音声をHDMIから出力しますか?」と聞かれます。HDMIで出力する際は「はい」を選択してください。
4.次にタイムゾーンを設定します。日本国内の場合は「GMT+09:00 東京」を選びましょう。
5.現在の日付・時刻を設定します。
6.ログインするユーザー名を設定してください。
7.次にインターネット接続設定を行います。今すぐに設定しなくてもいい場合は×ボタンを押しましょう。
8.そのまま接続設定を行う場合は、まず接続方法を選択します。有線か無線を選び、有線で接続する場合はLANケーブルを本体に接続してください。
9.次にPPPoEユーザーIDとPPPoEパスワードを入力する画面が表示されます。しかし、PPPoEのIDとパスワードはルーターなどで設定されているため「中止」の×ボタンを押して終了しましょう。
これで初期設定は完了し、いつものメニュー画面へと移行します。
5.バックアップデータを復元する
初期設定が完了すればいつもどおりにPS3を使って遊べるようになりますが、バックアップしたデータを戻したい場合はここから復元作業に入ります。復元する際はPS3に接続しているUSBメモリを取り外さないように注意してください。バックアップデータを復元する手順は以下のとおりです。
1.まず、PS3のメニュー画面から「設定」→「本体設定」を選びます。
2.次に「バックアップユーティリティ」を選択し、「リストア(復元)」を選びましょう。
3.リストアを選択すると「リストアする前に本体ストレージ内のデータがすべて削除します。」と表示されます。この画面が表示されたら「はい」を選択してください。
4.「はい」を選ぶと保存先の選択画面に移ります。「USB機器」を選択し、復元したいバックアップデータを選びます。
5.最終確認画面が表示されるので、「はい」を選択すればデータが復元されます。
なお、場合によってはリストアが失敗してしまう可能性もあります。リストアが失敗する原因として考えられるのは、以下の項目です。
・PS3本体とHDDの相性が悪い
・新しいHDDが不良製品だった
・PS3本体に不具合がみられる
PS3と互換性のあるHDDを使っていても、相性の悪さからリストアが失敗するケースもあります。別のHDDで解決する可能性もありますが、それでも解決しない場合は外付けのメモリにセーブデータを1つずつ手動でコピーする方法を試してみてください。コピーができないものに関しては削除となるため、注意が必要です。
まとめ:正しい手順でHDDの取り扱いに気をつけて交換しよう!

今回は、PS3のHDD交換の手順をご紹介しました。PS3のHDD交換はデータをきちんとバックアップしておけば意外と簡単にできます。今回ご紹介した正しい手順にしたがって、HDDの取り扱いに注意しつつ交換を行ってみましょう。
PS3のHDD交換は自分で行うことも可能ですが、正しい手順どおりに行わないと故障するリスクもあります。特に初期型のPS3はPS2のソフトと互換性があることから、現在は価格が高騰しており手に入りづらくなっています。交換作業によって貴重な初期型PS3を壊したくない場合には、PS3のHDD交換にも対応している修理業者に相談してみましょう。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
SSDが認識しないために、データの読み込めず困ったことはありませんか?SSDは近年主流のストレージであり、高速でデータの読み書きができることから大切なデータを保存するために使っている人は多いでしょう。
そんなSSDが認識しなくなったとき、対処法を知っていれば解決できるかもしれません。そこで今回は、SSDを認識しない原因から対処法まで詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
パソコンがSSD認識しない時の原因

SSDが認識しない原因は、論理障害と物理障害の2つに大きく分けられます。ここで、論理障害と物理障害に分けて、SSDが認識されない原因をご紹介しましょう。
論理障害
システムやデータの不具合・破損が原因で起こる障害を論理障害と呼びます。システム上でSSDが認識されていないのであれば、論理障害の可能性が高いです。SSDが認識しない論理障害には、以下の6つのケースがあります。
Windows10/11システムの不具合
Windows10/11システムで不具合が起きていると、正常にSSDが認識されない可能性があります。OSは機器全体の管理や抑制を行うソフトウェアのため、不具合が起きるとさまざまな障害が起きてしまうかもしれません。
しかし、OSの不具合であれば修復やアップデートを行うことで改善され、SSDも正常に読み込まれる可能性があります。
デバイスドライバーの不具合
デバイスドライバーとは、パソコン内部の装置や外部から接続された機器を動作させるためのソフトウェアです。SSDもデバイスドライバーを通じて動作するため、何かしら不具合が起きていると正常に認識してくれません。
一時的なエラーもあれば、ドライバーのバージョンが古いことで正常に機能していないケースもあります。また、Windows Updateが行われたことでドライバーが対応しなくなり、SSDを含む周辺機器が認識されなくなるケースも少なくありません。
フォーマット時の不具合
SSDのフォーマットとは、SSDを初期化して使用可能な状態にすることです。フォーマットすればSSDに保存していたデータがすべて消去されるため、データを読み込めない状態になってしまいます。
また、フォーマット中にエラーや時間がかかるからと強制終了させ、正常に完了しなかった際もSSD内のデータが破損する可能性があり、正常に開けない状態となってしまいます。
キャッシュファイルの破損
キャッシュファイルとは、頻繁に使うデータを取り出しやすくするために一時的に保存されるデータのことです。SSDのデバイスドライバーが正常であっても、ドライバーのキャッシュファイルが損傷していることで認識してくれないことがあります。
ウイルスの感染
パソコンがウイルスに感染すると、内部のデータが破壊されることがあります。そのため、ウイルスの影響でSSD内部のデータやシステムが壊れ、正常に認識されないこともあるでしょう。
また、ウイルスに侵入するとパソコン自体の動作が重くなり、それによりSSDの接続を含み、システム上でさまざまな不具合が発生するケースもあります。ウイルスは不具合だけではなく、ファイルや個人情報を流出させるリスクもあるため、セキュリティ対策はとても重要です。
データ読み込みの上限
SSDの空き容量が減ると、読み書きの処理速度が低下してしまいます。その影響で、データが上手く読み込めなくなってしまうことがあります。この場合、不要なデータを削除して容量を減らすことでパソコンのパフォーマンスが改善され、SSD内のデータを正常に読み取れるようになる可能性が高いです。
物理障害
物理障害は、経年劣化や直接的な衝撃、水没などが原因でSSDが故障した状態です。SSDが認識されない以外に、エラーメッセージの表示や異音、異臭などの症状が出ることがあります。SSDが認識されている状態でも、頻繁にエラー表示や異音・異臭がすれば注意が必要です。
SSDの破損
SSDは物理的に動作する部品がないためHDDと比べて衝撃に強く、寿命も長いとされています。しかし、強い衝撃を受けると、本体が故障してしまう可能性が高いです。
また、寿命は5~10年とされていますが、頻繁に書き込みやデータ削除などアクセスを繰り返していると早々に劣化が進み、故障してしまう可能性があります。そのため、定期的な交換が必要です。
SSD自体が壊れてしまった場合、個人でデータを復旧するのは難しいでしょう。素人がデータ復旧やSSDを分解して直そうとするとなると、かえって状況を悪化させてしまう恐れがあるので注意してください。
USBケーブルの不具合
外付けSSDとパソコンを繋ぐUSBケーブルに問題がある場合も、正常に認識されません。たとえば、USBポートが破損していたり、ケーブルが断線したりすると、機器とパソコンを正常に接続させることができません。
USBケーブルが原因の場合、SSD本体が故障しているわけではないので、ケーブルを新しいものに変えれば問題は改善されます。
水没による電気障害
外付けSSDを誤って水没させたり、雨漏りや浸水によりSSDに水がかかってしまったりすると、電気障害によってSSDが故障します。水分が内部に入った状態で電源を入れるとショートしてしまうのが原因です。
また、濡れたからといって間違った方法で乾かすと内部の腐食を進行させ、状態を悪化させる恐れがあります。水没した際は正しい対処法をとることでデータを復旧できる可能性があるため、専門業者に相談するのがおすすめです。
パソコンがSSDを認証しない時の対処法

SSDが認識しない原因が論理障害にあれば、復旧が見込めます。ここからは、SSDが認識しないときに試してほしい対処法をご紹介しましょう。
パソコンを再起動させる
一時的なシステムやドライバー、ファイルなどのエラーであれば、パソコンを再起動させてください。再起動によってシステムやメモリなどの動作がリセットされ、不具合が解消されます。再起動してもSSDが認識されないのであれば、ほかに原因があると考えられるでしょう。
トラブルシューティングを起動させる
トラブルシューティングとは、何か問題があった際に原因を見つけ、解決策を導き出してくれるプロセスです。「ハードウェアとデバイス」のトラブルシューティングを実施すると、SSDが認識されない問題を突き止め、修復してくれる可能性があります。
トラブルシューティングを実行させる流れは以下のとおりです。
①スタートボタンを右クリックして、「ファイル名を指定して実行」を選ぶ
②ウィンドウのボックスに「msdt.exe -id DeviceDiagnostic」と入力して、実行ボタンをクリック
③トラブルシューティングのウィンドウが表示されたら「次へ」をクリックし、チェックを始める
④問題箇所が発見されたら、「修復を適用」の選択肢をクリックして修正を実行
トラブルシューティングの場合、SSD本体やBIOSの不具合であれば解決できないので注意してください。
ケーブルを再接続する
外付けSSDが認識されない場合、USBケーブルを抜いて、再度差し込んでみてください。一時的なエラーであれば、ケーブルの再接続によって解決する可能性があります。
また、ケーブルの故障が原因で認識されないことがあります。再接続しても改善しないときは、別のケーブルを使って接続を試してみてください。
BIOSで再設定する
BIOSとは、パソコンのメイン基板となるマザーボードに搭載されるプログラムで、役割の一つがハードウェアの抑制です。BIOSを再設定し、SSDの接続をやり直すことで問題が解決する可能性があります。
BIOSの再設定のやり方は以下のとおりです。
①パソコンの起動時、メーカーのロゴが表示されている間に特定のキーを入力して、設定画面に切り替える
②Advancedタブに移り、SATA Controller ModeをIDEに変更する
③F10キー押して設定を保存し、OS画面に移動する
BIOS画面の移動はメーカーによって異なるので、確認した上で実行してください。また、設定画面が基本的に英語での表示となり、むやみに変更するとSSD以外のハードウェアの設定まで変わってしまいます。
パソコンの知識がないと設定ミスを起こす可能性があるので、難しいと感じたら個人で再設定するのは避けましょう。
デバイスドライバーを最新する
SSDのデバイスドライバーを最新版にアップデートすると改善されることがあります。最新版になっているか確認し、古いバージョンであれば更新してみてください。デバイスドライバーの更新の流れは以下のとおりです。
①タスクバーの検索ボックスで「デバイスマネージャー」と入力し、プログラムを起動します
②表示される項目から対象のSSDを選び、右クリックして「ドライバーの更新」を選択
③「ドライバーを自動的に検索する」を押し、最新版があれば自動的に更新
SSDのメーカーのWebサイトから最新のデバイスドライバーをダウンロードし、手動で更新する方法もあります。ドライバーをダウンロードする際は、bitバージョン(32bitか64bitか)は使っているパソコンにあったものを選びましょう。
bitバージョンを間違えてインストールを行うと、SSDのトラブルが改善されないので注意してください。
ドライブ文字を変更する
エクスプローラーで接続されたSSDを見ると、ドライブ名に(C:)や(E:)が表記されています。この表記はドライブ文字と呼び、これを変更するとSSDが認識される可能性があります。ドライブ文字の変更手順は以下のとおりです。
①スタートボタンを右クリックして「ディスク管理」をクリック
③変更するSSDを選択して右クリックし、「ドライブ文字とパスの変更」を選ぶ
④変更したいドライブ文字を選び、変更(ドライブ文字の表示がないときは追加)をクリック
⑤「次のドライブ文字を割り当てる」から好きな文字を選び、「OK」をクリック
他のハードディスクを外す
SSDとは別に外付けハードディスクを接続している場合、それが干渉してSSDが認識されないことがあります。一度ハードディスクを外した上で、SSDを接続してみてください。
この方法で改善された場合、ハードディスクのデバイスドライバーの更新も試してみてください。ドライバーの更新によって、同時接続しても正常に認識されるようになる可能性があります。しかし、再発に不安があれば、SSDとほかのハードディスクを同時に接続するのは避けたほうがいいでしょう。
ウイルスに感染しているかチェックする
ウイルスが原因になっていることもあるので、セキュリティソフトを使って感染していないかチェックしてください。セキュリティソフトを導入していれば、感染チェック以外にウイルスの排除・感染防止も行ってくれます。
原因となっているウイルスを排除すれば、SSDが正常に認識される可能性があります。また、セキュリティソフトの導入だけではなく、怪しいサイトへのアクセスや怪しいファイルのダウンロードも避けることも大切です。
更新プログラムをアンインストールする
Windowsの更新プログラムがSSDを認識しない原因になっていることがあります。その場合、直近にダウンロードした更新プログラムをアンインストールすると改善されるでしょう。アンインストール方法は以下のとおりです。
①スタートメニューから設定を開き、更新とセキュリティ→Windows Updateに移動
②更新履歴の表示に移動し、「更新プログラムをアンインストールする」をクリック
③直近の更新プログラムを選び、アンインストールを実行
「フォーマットしてください」という表示が出た際の対処法

SSDを使うために、「フォーマットしてください」のアラートが表示されることがあります。そのまま「ディスクのフォーマット」を選択すると、SSDに保存しているデータが消去され、初期化されてしまいます。フォーマットの表示が出た際は、以下の対処法を試してみましょう。
パソコンを再起動させる
システム上のエラーによるアラートであれば、再起動させることで改善される可能性があります。まずは再起動で改善されるか試してみてください。再起動しても直らないときは、ほかの方法を試してみましょう。
デバイスドライバーを更新する
SSDのデバイスドライバーが古いことで、エラーが発生していることもあります。再起動で改善されない際は、上記で解説した流れでデバイスドライバーを新しいバージョンに更新してみてください。
SSDの問題を診断する
上記でも解説したように「ハードウェアとデバイス」のトラブルシューティングを実施すると、SSDに起きている問題の診断が可能です。診断により問題が見つかった際は修復され、改善につながる可能性があります。
「S・M・A・R・T」を使用する
「S・M・A・R・T」は、SSDやHDDなどストレージに内蔵される自己診断機能です。「CrystalDiskInfo」と呼ばれるフリーソフトを使うことで、SSDの健康状態を確認できます。注意と表示されている場合、SSDが不具合を起こしている可能性が高いので、完全に故障してしまう前に早期に交換を検討してみましょう。
まとめ:以上の対処法でも直らない際には、専門業者に問い合わせよう

今回は、SSDを認識しない原因から対処法まで解説しました。大事なデータを保存しているSSDに突然接続できなくなると、データの読み書きに支障が出てしまいます。
一時的なシステムエラーやケーブルの故障などであれば、比較的対処しやすいのでそれほど心配はいらないでしょう。しかし、ご紹介した対処法を実践しても改善されないときは、専門業者への相談がおすすめです。また、個人での対処に不安があるときも専門業者に相談すれば、早期に問題を改善できます。
パソコンが壊れてしまったとき、マザーボードの交換が必要になる場合があります。マザーボードの交換をしなければいけない状況になったとき、自分で作業を行っても大丈夫なのか気になる人もいるでしょう。パソコンにとって重要な部分なので、そのような不安を抱くのも当然です。
そこで今回は、そもそもマザーボードとは何か、交換のタイミングはいつか、故障した樋の対処法、交換の手順などを解説していきます。マザーボードの交換を自分でしようと考えているのであれば、ぜひ参考にしてみてください。
マザーボードの交換時期

マザーボードを交換する時期は、使用している時間や使用方法によって異なります。故障してしまったときに交換するケースが多いです。マザーボードの交換は、通常の使い方だと3年くらいが交換の目安となっていますが、10年以上使っている人もいるのであくまでも交換時期は目安だと考えておきましょう。
マザーボードは、電気を蓄えたり、放出したりする電子部品であるコンデンサが故障してしまうケースが特に多いです。部屋の温度が高温な状態が続く環境で使用したり、ほこりが溜まったりしていると、冷却性能が落ちてマザーボード自体の温度も高くなってしまいます。マザーボードのコンデンサを含むパソコンの部品は熱に弱い傾向があるので、室温やほこりには細心の注意を払ってください。
また、CPUのアップグレードもマザーボードを交換するタイミングとなります。新しい世代のCPUが出たら、新世代のCPUに対応したマザーボードとセットで購入するのが一般的です。マザーボードとCPUの関係性を理解しておくと、マザーボード交換の時期を見極めやすくなります。
交換のメリット

マザーボードを交換すると、最新のパーツを使える、インテリアとして楽しめる、などのメリットを享受できるでしょう。
最新のマザーボードは、パーツが持つ性能を発揮できるような中身になっています。つまり、マザーボードを新しくしておけば、新たなパーツが出たときに導入しやすくなります。パソコンのスペック向上にもつながるので、メリットは大きいです。
また、ゲーミングパソコンに多く見られる仕様としてLEDのライティングができるマザーボードもあります。本格的にLEDライティングを楽しむにはケースやファンも交換する必要がありますが、これまで以上に楽しめるようになるのは魅力的です。インテリアとしてパソコンを楽しみたいと考えている人にとっても、マザーボードを交換するメリットは大きいです。
マザーボードが故障している際の対処法

マザーボードが故障してしまったら、何とかしなければパソコンを使えない状態が長引いてしまいます。続いては、マザーボードが故障している際の対処法をみていきましょう。
自分でマザーボードを換える
パソコンに関する知識やスキルがあれば、自分でマザーボードを換えることができます。しかし、マザーボードはメーカー独自の規格で作られているので、簡単に交換できないケースも少なくありません。ノートパソコンの場合だと、モデル毎に専用の設計になっているので、交換用のマザーボードが市販されていないことも往々にしてあります。
デスクトップパソコンであれば市販のマザーボードで対応できるケースが多いです。それでも、マザーボードの形状に合うようにケースの一部を加工しなければいけないなど、手間がかかります。
このことから、パソコンに関する専門的な知識やスキルがない限り、マザーボードの交換を自分でするのは難しいです。もちろんこれまでに自作パソコンを作った経験がある人、周りにパソコンに関する豊富な知識を持つ知り合いがいる人であれば、できないわけではありません。
業者に依頼する
マザーボードの交換は、自分でやろうと思えばできる作業です。しかし、とても精神を使う作業なので、専門的な知識を持つ業者に依頼するのが無難だと考える人も少なくないでしょう。手間がかかる作業でもあるので、パソコンについてそこまで詳しくない人、自作パソコンを作ったことはあるけどどちらかというと初心者に分類される人は、修理業者に依頼するのが無難です。
場合によっては、不具合の原因が本当にマザーボードなのかわからない場合もあります。どこに原因があるのかわからない場合なども、修理業者に相談し、原因を究明してもらうべきです。修理業者に依頼すればスムーズに問題が解決する場合もあります。
PCごと買い替える
マザーボードが寿命を迎えてしまったパソコンは、電源が入らない状態になってしまうケースも多いです。そうなってしまうと、下取りに出すこともできません。修理に出すと費用も高額になってしまうため、パソコンの買い替えを検討する必要があります。
パソコンの買い替えを行ったら、古いパソコンは処分しなければいけません。パソコンは、小型家電リサイクル法の対象になっていて、処分費がかかります。ただし、パソコンの無料処分サービスを利用すると無料で処分できるので、利用してみるのもいいでしょう。
パソコンの無料処分サービスを使えば、処分費用がかからないだけではなく、送料もかかりません。パソコンの中にあるデータも無料で消してくれるので、安心して利用できるサービスです。
マザーボードを選ぶ際に注意すること

マザーボードを選ぶ際、いくつか把握しておきたい注意点があります。次は、マザーボードを選ぶ際の注意点をみていきましょう。
CPUとの相性
マザーボードには、ソケットと呼ばれるCPU用の穴があります。しかし、マザーボードによってソケット数が異なるので注意してください。。CPUも端子の数が異なるので、互換性があるかどうかは確認しなければいけません。
マザーボードの対応メモリの規格も、確認しておかなければいけないポイントです。DDR3とDDR4ではメモリの規格が違うので互換性がありません。DDR3メモリに対応するマザーボードからDDR4メモリに対応するマザーボードの交換をした場合、交換前に使っていたDDR3メモリの搭載は不可となります。
PCケースサイズ
マザーボードのケースは、サイズが統一されていません。メーカーによってサイズの規格はある程度決まっていますが、すべてのメーカーが同じ企画ではないので注意してください。
たとえばIntel社のATXは、縦が最大244ミリメートル、横が最大305ミリメートルの規格になっています。このサイズが今使っているマザーボードと同じくらいならケースに収まるでしょう。しかし、ケースがそれ以下の規格だったら上手く入らなくなってしまいます。
したがって、マザーボードのサイズとケースのサイズに問題がないかも確認しておかなければいけないポイントです。場合によっては、ケースの一部を加工しなければいけないこともあります。手間を省くためにも、サイズはチェックしておきましょう。
チップセットのグレード
チップセットは、マザーボードを選ぶ際に重要視されているポイントです。性能を決める要素になります。新しいマザーボードであればチップセットの性能も高いですが、ソケット数やメモリの対応数は製品によるので、最新モデルを買っておけば問題ないというわけでもありません。
マザーボードのチップセットだけに注目して選んでしまうと、既存のパーツが使えなくなってしまう場合もあります。マザーボードのスペックはチップセットのグレードを含め、網羅的にチェックしておきましょう。
マザーボードの交換前にしておくこと

マザーボードを交換するのであれば、その前にしておくことがあります。交換前に準備すべきことも把握しておけば、スムーズに作業を進められるでしょう。では、マザーボードの交換前にしておくことを解説していきます。
ローカルアカウントからMicrosoftアカウントに変更する
アカウントの紐づけは、マザーボードを交換する前にやらなければいけない作業です。Windows10やWindows11をローカルアカウントからMicrosoftアカウントに変更しておきましょう。変更をしないと、OSの継続利用ができなくなってしまいます。
つまり、Microsoftアカウントを取得すれば、マザーボードを交換に関係なくWindows10やWindows11を使えるので、取得しておくメリットは大きいです。既にアカウントを持っている人の場合は、そのまま切り替え作業ができます。まだアカウントを持っていない人は、Microsoftの公式サイトから無料登録をしておきましょう。
ローカルアカウントからMicrosoftアカウントに切り替える手順は以下の通りです。
・スタートメニューから「設定」に進む
・「Microsoftアカウントでのサインインに切り替える」をクリックする
・「自分用にセットアップする」へ進む
・Microsoftのアカウントとパスワードを入力し、「サインイン」をクリックする
・画面が替わったら「ローカルアカウント」のパスワードの設定を行う
※設定を行っていない場合は空欄のままで次に進んで問題ありません。
・PINの設定画面になるが、特に設定をする必要はない
・Microsoftアカウントへの紐づけが完了となる
PC内部の配置を記録する
パソコン内部の配置も、あらかじめ記録しておくのがおすすめです。写真に残しておくといいでしょう。なぜかと言うと、マザーボードを交換してからケーブルの配線などがわからなくなってしまう可能性があるからです。
作業をスムーズに進めるためにも、内部の配置記録と管理が重要になります。起動しないなどのトラブルを回避するためにも、交換前の配置を把握し、その通りに戻すことが重要です。
交換に必要な道具を準備する
マザーボードを交換する前に、必要な道具の準備も忘れてはいけません。必要な道具は以下の通りです。
・新品のマザーボード
・プラスドライバー
・ライト
・軍手
・グリス
軍手を要しておくと、手の保護ができるだけではなく、静電気対策にもなります。静電気が発生すると、パソコンのパーツが壊れてしまう恐れがあるので、静電気対策は必要です。軍手がない場合は、金属製のものに先に触っておくといいでしょう。
また、作業中にCPUクーラーを外します。そのため、グリスも用意しておくと塗布できるのでおすすめです。
マザーボードの交換手順

マザーボードの交換は、適切な手順で行わなければいけません。そのため続いては、マザーボードの交換手順を解説していきます。自分で交換しようと考えているのであれば、この手順に則って作業を進めてください。
電源を落とす
まずは、パソコンの電源を落とします。電源ケーブルもコンセントから抜いてください。
しばらく放電させる
電源ケーブルをコンセントから抜いたら、しばらく放置します。パソコンの内部に溜まった電気を放電させ、作業を安全に進めるためです。
PCを開け、マザーボードを固定しているネジを外す
放電が完了したらパソコンを開け、マザーボードを固定しているネジを外していきます。外す際はドライバーを使ってください。
ケーブルを抜き、マザーボードを取り外す
ネジを外し終わったら、ケーブルを抜いてマザーボードを外します。ケーブルをすべて抜いたら、マザーボードをケースから出しましょう。
I/Oパネルを取り換える
次は、I/Oパネルを取り替えます。I/Oパネルは、パソコンの内部にゴミやほこりが入り込むことを防ぐために取り付けられています。I/Oパネルはマザーボードによって異なるので取り替えなければいけません。
新しいI/Oパネルは、マザーボードの付属品として同梱されています。箱の中身を確認し、同梱されているものを使うようにしましょう。
メモリ・CPU・CPUクーラーを取り外す
続いては、メモリやCPU、CPUクーラーの取り替えを行います。
マザーボードに刺さっているメモリは、マザーボードの本体から取り外しておいてください。CPUはとても繊細なパーツです。取り扱いは慎重に行うようにしましょう。CPUクーラーにほこりが溜まっていたら、使ってきれいにしておくのがおすすめです。
新しいマザーボードにCPUとCPUクーラーを取り付ける
メモリ・CPU・CPUクーラーを取り外したら、新しいマザーボードに取り付けます。取り付ける際、CPUとCPUクーラーの間にはグリスを塗っておきましょう。グリスが潤滑剤になり、CPUの熱を効率的にCPUクーラーに伝えられるようになり、冷やしやすくなるためです。
グリスはCPUクーラーとセットになっています。パソコンを自作したことがある人なら持っているケースが多いでしょう。自宅にない場合は、マザーボードと一緒に購入しておくのがおすすめです。
CPUクーラーにグリスを塗ったら、CPUと一緒に新しいマザーボードに取り付けてください。
PCケースにマザーボードを取り付ける
CPUクーラーとCPUをマザーボードに付けたら、ケースに取り付けましょう。先ほど取り付けたI/Oパネルの形に合わせ、セットしてください。
外したネジを元通りに固定する
次に外したネジを元通りに固定していきます。写真で撮影した画像を元に、元々あった位置に固定してください。
メモリやケーブルを接続する
メモリやケーブルも忘れずに新しいマザーボードに取り付けましょう。ケーブルなどの位置も、写真を見ながら確認すると間違えずに済みます。
電源をつけて起動するかを確認する
すべて取り付け終わったら、電源ケーブルをコンセントに差し、電源を入れてください。無事に起動すれば作業は完了となります。
マザーボードが交換できた後の認証方法

マザーボードに交換が完了したら認証を行います。認証方法は、Microsoftアカウント認証と電話を使ったアカウント認証の2種類です。それぞれの方法も確認しておきましょう。
Microsoftアカウント認証
Microsoftアカウント認証の方法は以下の通りです。
・「設定」から「更新とセキュリティ」、「ライセンス認証」を開く
・「トラブルシューティング」をクリックし、「このデバイス上のハードウェアを最近変更しました」を選択する
・Microsoftアカウントとパスワードを入力し、サインインが完了したらリンクされているデバイスの一覧が表示されることを確認する
・「現在使用中のデバイスは、これです」にチェックを入れ、「ライセンス認証」をクリックすると認証完了となる
電話を使ったアカウント認証
OEMライセンスの場合、購入したパソコン本体だけに使用できます。マザーボードなどを交換するとライセンスがなくなってしまうので、電話認証が必要です。リテールライセンスとボリュームライセンスは、マザーボードとCPUを交換しても問題なく使えるので、インターネットに接続すると自動的に認証されます。
ライセンスを確認する方法は以下の通りです。
・「エクスプローラー」を開き「PC」を右クリックして「プロパティ」を開く
・「Windows ライセンス認証」内に書いてあるプロダクトIDを確認する
※「***-OEM-******-*****」というプロダクトIDであればOEMライセンス
マザーボードの交換にかかる費用
マザーボードの交換費用は、マザーボード代やドライバー代、グリス代などです。マザーボードは、7,000~30,000円程度、ドライバー・グリス代は2,000円程度が目安になります。業者に依頼する場合は、これらのコストに加えて工賃が12,000円程度かかることを念頭に置いておきましょう。
まとめ:マザーボードを自分で換える際には正しい手順を守って交換しよう!
マザーボードは、自分で交換できます。しかし、専門的な知識が必要です。また正しい手順で作業を行わないとせっかくのパソコンが使えなくなってしまう可能性もあります。
自分で交換するなら適切な方法をきちんと理解しておきましょう。自信がない場合は、パソコン修理業者などの専門家に依頼すると安心です。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
PS4本体は起動しているのに、コントローラーを操作しても反応を示さない場合、コントローラー側に何らかの不具合が生じている可能性があります。ただし、反応しないからといって必ずしも故障しているとは限りません。
ここでは、PS4コントローラーが反応しないときの診断方法や、原因と対処法を解説します。PS4コントローラーが突然反応しなくなり、困っている方はぜひ参考にしてみてください。
PS4コントローラーのライトバーを確認

コントローラーが故障しているのか、それとも別の原因によって反応を示さないのかは、ライトバーから確認が可能です。ライトバーはLボタンとRボタンの間に設置されています。
ただし、新しいモデルのCUH-ZCT2だとLボタンとRボタンの間だけでなく、タッチパッド部分も光る仕様です。ライトバーが光っているときの色を確認すると、コントローラーの状態を簡単に診断できます。
ホワイト
白く光っているときはコントローラーが起動準備をしている段階です。また、本体とペアリングが完了していない状況でも白く光ります。
ブルー、レッド、グリーン、ピンク
ブルー、レッド、グリーン、ピンクに光っている場合はペアリングが完了している状態なので、正常な状態だと判断できるでしょう。ちなみにコントローラーの順番によって光る色が変化しています。
プレイヤー1:ブルー
プレイヤー2:レッド
プレイヤー3:グリーン
プレイヤー4:ピンク
オレンジ
オレンジ色に光っている場合、コントローラーが充電中にあることを示しています。ゆっくりと明滅を繰り返しているのが特徴的です。
消灯
コントローラーの電源がオフになっている、充電不足、ペアリングが未実装などの場合、ライトバーは消灯します。起動中、またはペアリングが済んでいるにも関わらず消灯している場合は故障の可能性があります。
PS4コントローラーが反応しない原因

PS4コントローラーが反応しないときは、以下の原因が考えられます。どのような原因があるのか確認していきましょう。
コントローラーが故障している
コントローラーにあるPSボタンを押してもライトバーが反応しない場合、コントローラー自体が故障している可能性が高いです。コントローラーが故障しているとボタンを押しても反応しないだけでなく、特定のボタンが入力しっぱなしの状態になったり、ケーブルをつないでも充電されなかったりします。
コントローラーが充電できていない
単純に充電不足で反応しないケースもあります。充電不足が原因の場合、USBケーブルを接続して充電させれば不具合も解消されるでしょう。
コントローラーと本体がペアリングされていない
PS4の本体をアップデートした場合、時折コントローラーとのペアリングが解除される場合もあります。そのため、きちんとペアリングがされているかどうか確認してみてください。
ケーブルが故障している
コントローラーではなく、接続するケーブルが故障している可能性も考えられます。ケーブルは長年使用していると断線を起こしたり、接続端子が変形したりするなどの不具合が見られることもあるため、注意が必要です。
本体のUSB接続口が故障している
PS4の本体側にはコントローラーのペアリングに利用するUSB端子が備わっています。本体側のUSB接続口が変形しているなどの不具合が見られた場合、コントローラーのペアリングがうまくいかず、反応しない可能性が高いです。
PS4コントローラーが反応しない時の対処法

PS4コントローラーが反応しなかった場合、以下の対処法を試してみてください。対処法を実践すれば改善する場合もあります。
本体を再起動させる
本体とコントローラーが故障していなくても、一時的なエラーによって反応しないケースもあります。そのため、まずは一度本体を再起動させてみましょう。PS4の再起動方法は以下のとおりです。
1.PS4本体にある電源ボタンを10秒ほど押し続け、強制終了させる
2.もう一度PS4本体の電源ボタンを押し、起動させる
再起動を行ったことでコントローラーが反応するようになれば、問題解決となります。もし再起動しても反応しなかった場合は、別の方法を試してみましょう。
コントローラーを充電する
次にコントローラーが充電されているか確認します。充電用ケーブルを使ってフル充電が完了するまで放置してください。
なお、充電したままPS4を操作したいと考える方もいるかもしれませんが、充電中は本体とのペアリングが行えないため操作できません。そのため、フル充電が終わってからPS4への接続を行いましょう。
フル充電したのにすぐ充電が切れてしまい反応しなくなった場合は、バッテリーが寿命を迎えている可能性があります。長年使用しているコントローラーだとバッテリーの劣化が進んでいるため、新品への交換も検討してみてください。
コントローラーと本体の接続を確認する
次に、コントローラーと本体がきちんとペアリングされているか確認します。ペアリングはコントローラーとPS4本体をUSBケーブルでつなぐだけで完了します。ライトバーの色も確認しつつ、ペアリングができているか確認してみてください。
ただし、一度に複数のコントローラーを接続しようとすると失敗する恐れもあります。複数のコントローラーを接続したい場合でも、慌てず1つずつペアリングできるかチェックしていきましょう。
コントローラー裏面のリセットボタンを押す
PS4コントローラーの裏面、L2ボタンの左下あたりにリセットボタンが備わっています。リセットボタンを押すことで改善される場合もあるでしょう。具体的なリセットのやり方は以下のとおりです。
1.本体の電源を切り、電源ケーブルを外す
2.コントローラーの背面にある小さな穴に、爪楊枝やピンなどの先が細くなっているものを入れて5秒以上長押しする
3.再度コントローラーとPS4本体をUSBケーブルで接続する
4.PS4本体の電源を入れ、コントローラーにあるPSボタンをビープ音が鳴るまで押す
セーフモードから設定をリセットする
PS4のセーフモードを起動し、設定をリセットすると不具合の解消につながる場合もあります。セーフモードの起動方法は以下のとおりです。
1.本体の電源を切る
2.電源ボタンを7~11秒ほど押し続ける
3.いつもと違う起動音が鳴ったら反応するコントローラーを接続する
反応しないコントローラーを接続しても操作できない場合があるため、反応する別のコントローラーを使用する必要があります。
また、セーフモードから設定をリセットすると、本体が初期化されてデータを失ってしまいます。アプリを再インストールしなくてはならないため、時間があるときに試してみてください。
セーフモードからペアリングする
セーフモードから反応しないコントローラーを使ってペアリングによっても不具合が解消されるケースがあります。セーフモードを起動する際、画面に「DUALSHOCK4をUSBケーブルで接続して、PSボタンを押してください」と表示されます。この画面の指示に従って、反応しないコントローラーを接続すると解消されるでしょう。
ただし、接続する際に注意したいのが使用する接続ケーブルです。給電力の低いケーブルを使用しても改善されない場合があります。そのため、この対処法を試す際は給電力の高いPS4の純正ケーブルを活用しましょう。
コントローラーのケーブルを変える
コントローラーを有線接続にするとなぜか反応しなくなる場合、ケーブルに問題がある可能性が考えられます。ケーブルの根元などで断線が起きていないか確認し、もし断線していたら別のケーブルと交換しましょう。
コントローラーを接続するUSBケーブルは、PS4に付属している純正のケーブルが給電力も高いためおすすめです。しかし、純正ケーブル以外にも各メーカーからさまざまなケーブルが販売されているため、すぐに純正ケーブルが手に入らない状況であれば、ほかのメーカーの商品も試してみてください。
別のコントローラーで試す
コントローラーが故障して動かない場合は、別のコントローラーだと接続できるか確認してみてください。もし別のコントローラーだと反応する場合、反応しなかったコントローラーが故障していると考えられます。
しかし、別のコントローラーを試しても反応しなかった場合は、本体側に問題がある可能性もあるでしょう。現在SONYストアではPS4用のワイヤレスコントローラーが販売されています。中古のコントローラーだと同様に故障している可能性もあるため、試す際にはできるだけ新品で行うようにしてください。
コントローラーをBluetooth接続から削除する
PS4のコントローラーはBluetooth接続によって本体とペアリングを行うことで、ワイヤレスでゲームをプレイできます。しかし、Bluetooth接続がうまくいかないことでコントローラーが反応しない可能性もあるため、その際は一旦Bluetooth接続を解除し、有線接続に切り替えてみましょう。
なお、この方法は有線接続のままコントローラーを使用できるCUH-ZCT2Jで試せる方法です。他のモデルだと有線接続をしたままでの操作はできないため、注意してください。
Bluetooth接続を解除する方法は2つあります。
①コントローラーにあるPSボタンとSHAREボタンを10秒間同時押しする
②コントローラーの背面にあるリセットボタンを押す
Bluetooth接続を再設定する
一度Bluetooth接続を解除してから再設定を行うと、不具合が解消されるケースもあります。Bluetooth接続を行う際は、本体の電源を入れてから本体とコントローラーをUSBケーブルで接続し、コントローラー側にあるPSボタンを押してください。
接続する際、近くに別のBluetooth機器が起動していると混線して、うまく接続できない可能性もあります。接続がうまくできない場合や認識しているのに動かない場合は、別のBluetooth機器の電源を落としてから試してみましょう。
それでもコントローラーが反応しない際の対処法

ここまでさまざまな対処法をご紹介してきましたが、それでもコントローラーが反応しない可能性もあります。もしさまざまな方法を試した上で故障が改善されない場合は、以下の方法を試してみてください。
オンライン受付サービスに問い合わせる
PlayStationサポートでは、PS4を含むPS関連製品のオンライン修理受付サービスを実施しています。2023年11月現在はPS4の修理にも対応しているため、困ったときはこちらのサービスを活用してみてください。なお、オンライン受付サービスを使用してコントローラーの修理・交換を行う場合、価格は4,950円(税込み)です。
オンライン受付サービスから修理を依頼する際の流れは以下のとおりです。
1.「修理を申し込む」ページにアクセスし、指示に従いながら必要事項を入力し、申し込み手続きを進める
2.メールに書かれた送付先へ製品を発送する
3.修理品が到着してから数日~7日ほどで修理を実施
4.修理完了後、自宅へ発送(元払い)
5.修理代金を宅配業者に支払って製品を受け取る
なお、コントローラーが修理拠点に到着してから修理が完了するまで基本的に数日~7日ほどかかりますが、年末年始・夏休み期間などの繁忙期には日数がさらにかかってしまうかもしれません。また、修理代金の支払いは現金・電子マネー・クレジットカード・デビットカードから選択できます。
業者に修理を依頼する
SONYのオンライン受付サービスを活用すれば修理は可能です。しかし、「もっと安い料金で修理に出したい」「早く修理してほしい」などの場合には、修理専門の業者に依頼すると解決できる場合があります。
専門業者は料金の安さと修理までのスピードを売りにしていることも多いため、料金とスピードを重視したい方は業者への依頼がおすすめです。また、オンライン受付サービスだと発送する手間がありますが、近くに専門業者がある場合は持ち込んで修理を依頼できます。
まとめ:PS4コントローラーが反応しない際はライトバーの色から状態を確認しよう!

PS4コントローラーが反応しないときは、まずはライトバーの色から状態の確認が大切です。その後、どこに原因があるのか確認し、ご紹介してきた対処法を試してみましょう。
それでも解決しない場合は、新しいコントローラーに買い替えるか、もしくはSONYのオンライン受付サービスや専門業者への相談も検討してみてください。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
国内製のノートパソコンで、画質の良さなどから人気の元東芝「dynabook」。突然dynabookがフリーズして、仕事やレポートなどの作業ができなくなり、困っている方もいるのではないでしょうか。
dynabookは、さまざまな原因で突然フリーズして動かなくなることがあります。この記事では、dynabookがフリーズする原因や、対処法を詳しく紹介します。フリーズした場合の注意点や、今後フリーズしないために気を付けることなども紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
【この記事でわかること】
- dynabookのフリーズの症状
- dynabookがフリーズする原因
- dynabookがフリーズした場合の対処法
- dynabookがフリーズしないための対処法
dynabookのフリーズとはどんな症状?

dynabookが動かなくなることを、フリーズと言います。症状には違いがあり、原因も異なります。dynabookに起こっている症状を確認し、対処法を実行しましょう。
主に次のような症状が現れたら、dynabookがフリーズしたと考えられます。
- 電源が入らない・起動できない
- 真っ黒な画面に白い文字が表示される
- ブルースクリーンになり動かない
- 「自動修復を開始しています」を繰り返す
それぞれ、確認していきましょう。
電源が入らない・起動できない
dynabookを起動しようとしても真っ黒の画面のまま、電源が入らない、起動できない場合があります。dynabookは起動時にロゴマークが表示されますが、起動しても表示されない場合は、メモリに不具合が起こっている、パーツの故障などが考えられます。
また全く電源が入らない場合は、電源周りの故障やバッテリーの充電不足の可能性もあるため、バッテリーの充電残量やケーブルの接続状況も確認してみましょう。
真っ黒な画面に白い文字が表示される
真っ黒な画面に白いエラーメッセージが表示される場合は、周辺機器のトラブルやディスクの抜き忘れなどの場合もありますが、ハードディスクの故障やシステムの不具合の可能性もあります。
ハードディスクの故障やシステムの不具合など重大なトラブルの場合は、強制終了するとハードディスクに負担がかかりデータ復旧が難しくなる場合があります。
ブルースクリーンになり動かない
dynabookがブルースクリーンと呼ばれる青い画面になり、フリーズすることもあります。ブルースクリーンの場合は、電源を5秒以上長押ししてWindowsを強制終了し、電源を入れなおしてみましょう。
ブルースクリーンになる原因はさまざまですが、頻繁に起こる場合はシステムの不具合やストレージの故障、ウイルス感染など重大なトラブルの可能性もあり、修復できないこともあります。
「自動修復を開始しています」を繰り返す
dynabookの画面に「自動修復を開始しています」と繰り返し表示され、フリーズしている場合は、dynabookがトラブルの修復をしている状態です。強制終了などで、正常に終了しなかった場合などに表示されることがあります。
基本的には修復が終われば、自動で起動するため、そのまましばらく待つのがおすすめです。
dynabookが起動しない場合の原因と対処法は、下記記事でも詳しく解説しています。
dynabook(ダイナブック)が起動しない時はどうすればいい?原因と対処法>>
dynabookが突然フリーズする原因は?

dynabookが突然フリーズした場合は、以下の原因が考えられます。
- ストレージの故障
- 熱暴走
- メモリ不足
- ウイルス感染
- マザーボードの故障
- Windows Update
それぞれの原因を、順番に解説します。
dynabookを使っていると、フリーズしてはいないけれど動作が重いと感じることもあります。dynabookが重い場合の原因と解消方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
dynabookのパソコンが重い原因と解消方法は?アンインストールするソフトはこれ!>>
ハードディスクの故障
ハードディスクが故障している場合は、dynabookがフリーズすることがあります。ハードディスクとは、パソコンのデータを保存するストレージの一種で、膨大な量のデータの読み取りや書き込みを繰り返しています。
ハードディスクの寿命は3~4年と言われており、寿命を迎えると異音がしたり、突然フリーズしたりする症状が現れます。
熱暴走
dynabookに限らずパソコンは熱に弱いため、内部にある冷却ファンでパソコン本体の温度が上がらないようにしています。しかし、冷却ファンの寿命やホコリが溜まるなどでパソコン内部がうまく冷却できなくなると本体が高温になり、熱暴走を起こしフリーズすることがあります。
また、直射日光があたる場所や高温の室内、ファンの通気孔をふさぐような場所にdynabookを置くなどで、うまく排熱ができず熱暴走が起こる場合もあります。熱暴走は、dynabookの寿命を縮めるため、冷却対策をして使用する環境にも注意しましょう。
メモリ不足
dynabookを含むパソコンは、メモリ不足になると動作が不安定になります。メモリとは、パソコンの作業机のようなもので大きいほど、同時に複数の作業ができます。
複数のアプリを同時に起動する、動画閲覧しながら動画編集するなど、一度に容量の大きな作業をすると処理速度が追いつかず、フリーズする原因になります。メモリ不足の場合は、メモリを増設することで、改善する可能性が高いでしょう。
ウイルス感染
dynabookがウイルス感染した場合に、フリーズすることがあります。ウイルスの種類はさまざまで、パソコンのバックグラウンドでひそかに動き、メモリやCPUを圧迫するウイルスや、プログラムを破壊するウイルスなどがあり、負荷がかかることでdynabookの動きが重くなり頻繁にフリーズするようになります。
プログラムを破壊するタイプのウイルスに感染すると、dynabookを全く起動できないケースもあります。ウイルス感染した場合は、ウイルスの駆除やdynabookの初期化が必要です。
マザーボードの故障
パソコン内部の重要なパーツが故障して、フリーズしている可能性もあります。特にマザーボードはパソコンを動かす電子回路を搭載した基盤で、故障するとフリーズなどのさまざまな不具合が起こります。
マザーボードの電池切れの場合は電池交換で改善することがありますが、故障個所を特定することは難しく自分で修理するのは難しいでしょう。
また、マザーボードを修理するにはdynabookを分解するため、ある程度の知識が必要です。メーカー保証の対象外にもなるため、自分で分解するのはやめましょう。
Windows Update
Windowsのアップデート中は、大量のデータがダウンロードされるため、dynabookがフリーズして動かなくなることがあります。
Windows Updateが正常に終われば、再起動して動くようになるため、しばらく待ちましょう。あまりにも動きが遅い場合は、dynabookのスペックが不足している可能性があります。メモリ増設やハードディスクをSSDに換装するなどの対処法も試してみましょう。
Windows11など大型のメジャーアップデートの場合は、特にフリーズが頻発することがあります。メジャーアップデートの後にはドライバーが不具合を起こすことがあり、Windows Updateの実施やグラボの更新、高速スタートアップの無効などで解決することがあります。
dynabookがフリーズした場合の9つの対処法

dynabookがフリーズした場合には、次の対処法を試してみましょう。
- しばらく待つ
- dynabookを放電する
- F1キーを押す
- タスクマネージャーからアプリを強制終了する
- 再起動する
- セーフモードを起動する
- 自動修復を繰り返す場合はシステムを復元する
- 強制終了する
- リカバリーする
順番に解説します。
しばらく待つ
dynabookがフリーズしたら、まずはしばらく待ってみましょう。アクセスランプが点灯している場合は、データの書き込み中のため強制終了するとデータを消失する可能性もあります。アクセスランプが消え、データの読み書きが終わると、フリーズが解消することもあるため、そのまましばらく待ちましょう。
また、「自動修復を準備しています」や「検査しています」などのメッセージが表示されている場合は、修復などの処理中です。完了するのを待ちましょう。処理中に再起動などをすると、再び修復が始まるため、正常に処理が完了するまでそのまま待つしか方法はありません。
ただし、エラー処理が全く終わらない場合や、何度も繰り返す場合は、dynabookの故障も考えられます。
dynabookを放電する
dynabookなどのパソコンは、使用しているうちに内部に電気が帯電します。パソコン内部に不要な電気が溜まりすぎると、動作が不安定になり、フリーズが起こることがあります。
以下の方法で、dynabookを放電してみましょう。
- 起動中のアプリやソフトウェアを全て終了する
- CDドライブやSDカードが入っていれば取り出す
- 電源を長押ししてシャットダウンする
- ACアダプターやマウス、キーボード、バッテリーなどの機器類を全て取り外す
- そのまま5~10分ほど放置する
- 再びバッテリーや電源コードを元通りにしてから電源ボタンを押す
F1キーを押す
真っ黒な画面に以下のような白い文字が表示された場合は、「F1」キーを押すだけで改善します。
- Press F1 to Resume
- Strike the F1 Key to continue
黒い画面に表示される白いメッセージは、どのような行動を取るのかを表しています。これらのメッセージは、F1を押して続行するという意味のため、F1キーを押せば改善するでしょう。
タスクマネージャーからアプリを強制終了する
アプリを複数立ち上げている場合には、メモリ不足によってdynabookがフリーズすることがあります。使用していないアプリを終了しましょう。
特定のアプリがフリーズしている場合は、プログラムの右上の「✕」ボタンを押してアプリを終了します。「✕」を押してもアプリが終了しない場合は、タスクマネージャーを使用してアプリを強制終了させましょう。
タスクマネージャーを起動するには、マウスを使える場合は、スタートボタンを右クリックします。キーボードしか使えない場合は、「Ctrl」+「Alt」+「Del」キーを同時に押して起動します。
- タスクマネージャーが起動する
- 閉じたいアプリを選択して右クリック
- 「タスクの終了」を選択
- アプリが終了する
以上の手順で不要なアプリを終了して、dynabookが正常に動くことを確認しましょう。
再起動する
dynabookがフリーズして動かない場合、再起動することで、改善する場合があります。フリーズして動かない場合は、以下の方法で強制的に再起動が可能です。
- 「Ctrl」キーと「Alt」キーを押しながら「Del」キーを押す
- 「Tab」キーを数回押して画面右下の「電源」を選択し「Enter」キーを押す
- 「↑」「↓」キーを押して「再起動」を選択し「Enter」キーを押す
- 再起動される
以上の方法で、再起動ができない場合は、電源スイッチを5秒以上押してWindowsを強制終了してください。強制終了したあとに、電源を入れなおしてdynabookが正常に動作するかを確認しましょう。
参考:dynabookサポート パソコンがフリーズして応答しない場合の対処方法<Windows 10>
セーフモードを起動する
セーフモードとは、必要最小限の構成でパソコンを起動する診断モードのことです。セーフモードでは、簡単なトラブルであれば回避して起動できるため、トラブルの原因となっているソフトウェアやプログラムを特定し、削除することで問題が解決することがあります。
セーフモードで起動できない場合は、重大な傷害が起こっている可能性があります。その場合は、無理に起動しようとするとdynabookが完全に故障する可能性もあります。dynabookを修理するためには、メーカーサポートや専門の修理業者への依頼がおすすめです。
以下の手順で、セーフモードを起動してみましょう。
【手順1】
【「自動修復」画面が表示されている場合】
「自動修復」画面から[詳細オプション]をクリックして、手順2へ進みます。
【dynabookの電源が入るが操作できない場合】
- 電源スイッチを長押しして強制終了する
- dynabookの電源が切れたら、電源スイッチを押してすぐにキーボードの「0」(ゼロ)キー(かな入力の「わ」)を数回押す(dynabookのロゴが表示される前に素早く押す)
- 「HDDリカバリーをスタートします。」または「The Hard Drive Recovery Process has been selected.」などから始まるメッセージが表示されたら「はい」または「Yes」を選択し「ENTER」キーを押す(メッセージ画面が表示されない場合は手順2に進む)
- 「Please wait」メッセージが表示されたら画面が切り替わるまでしばらく待つ
- 「キーボードレイアウトの選択」画面が表示される場合は[Microsoft IME]をクリック(手順2へ進む)
【手順2】
- 「オプションの選択」画面が表示されたら「トラブルシューティング」をクリック
- 「詳細オプション」をクリック
- 「スタートアップ設定」をクリック
- 「再起動」ボタンをクリック
- 「スタートアップ設定」画面でキーボードの[4]キーを押し「4)セーフモードを有効にする」を選択
- WindowsまたはMicrosoftアカウントのサインイン画面が表示される
- 設定しているパスワードを入力してサインインする
- セーフモードで起動する(画面の4隅に「セーフモード」と表示される)
- セーフモード上でトラブルシューティングを実行する
最近インストールしたプログラムなど、Windowsが正しく起動できなくなる前にインストールしたプログラムなどを削除しましょう。完了したら、dynabookを再起動し正常に動作することを確認してください。
参考:dynabookサポート セーフモード(Safe Mode)で起動する方法(Windows上で操作ができない状態)<Windows 10>
自動修復を繰り返す場合はシステムを復元する
dynabookが自動修復が正常に終わらない場合に、「PCが修復できませんでした」「PCが正常に起動しませんでした」とメッセージが表示されたら、システムの復元を実行しましょう。
システムの復元をすれば、不具合が起こる前に作成している復元ポイントまで、dynabookの状態を戻せます。復元ポイントが作成されていない場合は、実行できないため別の方法を試しましょう。
【手順1】
【「自動修復」画面が表示されている場合】
[再起動]をクリックしても繰り返し「自動修復」画面が表示されてしまう場合は[詳細オプション]をクリックして、手順2へ進みます。
【dynabookの電源が入るが操作できない場合】
電源スイッチを長押しして強制終了します。dynabookの電源が切れたら、電源スイッチを押してすぐにキーボードの「0」(ゼロ)キー(かな入力の「わ」)を数回押します。
パスワードを設定している場合は、キーボードでパスワードを入力して「ENTER」キーを押します。「HDDリカバリーをスタートします。」または「The Hard Drive Recovery Process has been selected.」などから始まるメッセージが表示された場合は、「はい」または「Yes」を選択し、「ENTER」キーを押します。メッセージ画面が表示されない場合は、次の手順2に進みましょう。
【手順2】
- 「オプションの選択」画面から「トラブルシューティング」をクリック
- 「詳細オプション」をクリック
- 「システムの復元」をクリック
- 「システムの復元 続けるにはアカウントを選んでください。」画面が表示されたら復元するアカウント名をクリック
- 「システムの復元 こんにちは (選択したアカウント名)さん このアカウントのパスワードを入力してください。(キーボードレイアウト:日本語)」画面が表示されたらキーボードからパスワードを入力して「続行」ボタンをクリック
- 「システムファイルと設定の復元」画面が表示されたら[次へ(N)>]ボタンをクリック
- 「選択したイベントの前の状態にコンピューターを復元します。」画面が表示されたら日時を確認して「復元ポイント」を選択する
- 復元内容を確認して[完了]ボタンをクリック
- システムの復元が開始される
- 「再起動」をクリックする
以上でシステムの復元は完了です。dynabookが正常に起動することを確認しましょう。
強制終了する
dynabookがフリーズして、何をしても動かない場合は、電源ボタンを押して強制終了しましょう。ただし、強制終了はパソコンに負担をかける上に、データを消失する可能性もあります。フリーズ以外のトラブルが起こる可能性もあるため、万が一のための最終手段として実行しましょう。
リカバリー(初期化)する
dynabookをリカバリーすると、工場出荷状態に戻ります。dynabookに保存されているデータは消去されるため、データのバックアップが必要です。フリーズしてデータを取り出せない場合は、リカバリーする前にデータ復旧業者などへの依頼が必要です。
dynabookをリカバリーする方法は、2つの方法があります。通常は、ハードディスクからリカバリーするのがおすすめですが、ハードディスクの故障などでリカバリーできない場合は、リカバリーメディアを使い実行しましょう。
指紋センサー搭載モデルは、工場出荷状態に戻すと指紋を削除できなくなります。ユーザー(アカウント)ごとに、指紋データを消去しましょう。購入後にインストールしたアプリやプリンターなどの周辺機器は、リカバリー後に再度インストールが必要です。アカウントやIDなどの情報を控えておきましょう。
操作の途中で、デバイスの暗号化の回復キーの入力を求められることがあります。リカバリー操作を行う前に、デバイスの暗号化の回復キーを確認してください。
リカバリーする前には、プリンターなどの周辺機器を全て外します。リカバリーには時間がかかることがありますが、途中で電源を切らないようにしましょう。
【ハードディスクからリカバリーする方法】
まずは、ハードディスクからリカバリーする方法を紹介します。
- データを保存してタスクバーの「スタート」ボタンをクリック「電源」をクリック
- 「Shift」キーを押しながら「シャットダウン」をクリックして電源を切る
- 電源コードとACアダプターを接続する
- 電源スイッチを押してキーボードの「0」(ゼロ)キー(かな入力の「わ」)を数回押す
- 「The Hard Drive Recovery Process has been selected.」などから始まるメッセージが表示された場合は「YES」または「はい」を選択して「Enter」キーを押す
- 「オプションの選択」から「トラブルシューティング」をクリック
- 「dynabook Maintenance Utility」をクリック
- 回復キーを入力する画面が表示された場合は、あらかじめ確認した回復キーを入力して「続行」をクリック
- [◎dynabook Recovery Wizard]をチェックし「次へ」をクリック
- 画面の内容を確認し「はい」をクリック
- [◎初期インストールソフトウェアの復元]をチェックし「次へ」をクリック
- 「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」のメッセージが表示されたら「次へ」をクリック
- リカバリー処理が開始され、「しばらくお待ちください。」のメッセージが表示される
- しばらく待つ
- 「初期インストールソフトウェアの復元は完了しました。」のメッセージが表示されたら[終了]をクリック
パソコンが自動的に再起動し、セットアップ画面が表示されたらWindowsのセットアップを行います。これで、dynabookが初期状態に戻りました。
dynabookが正常に動作することを確認したら、周辺機器の接続やウイルス対策ソフトの設定や更新を実行します。その他、必要なアプリなども再度インストールして、設定しなおしましょう。
参考:dynabookサポート ハードディスクからパソコンを初期状態に戻す方法<Windows 10 dynabook リカバリーメディアクリエーター搭載モデル>
【リカバリーメディアからパソコンを初期状態に戻す方法<Windows 10 dynabook リカバリーメディアクリエーター搭載モデル>】
まずは、リカバリーメディアを用意して、周辺機器を取り外します。
- 電源コードとACアダプターを接続する
- リカバリーメディアをセットする
- データを保存したら、タスクバーの「スタート」をクリック
- キーボードの「Shift」キーを押しながら「シャットダウン」をクリックして電源を切る
- 電源スイッチを押してすぐに「F12」キーを数回押す
- 「Boot Menu」画面が表示されたら[↑]または[↓]キーで起動ドライブを選択
- [◎dynabook Recovery Wizard]をチェックし、「次へ」をクリック
- 警告メッセージ画面が表示されたら画面の内容を確認し「はい(Y)」をクリック
- [◎初期インストールソフトウェアの復元]をチェックし「次へ」をクリック
- 「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」のメッセージが表示され、よければ「次へ」をクリック
- しばらくお待ちください。のメッセージが表示されたらしばらく待つ
- 処理が完了すると「初期インストールソフトウェアの復元は完了しました。」のメッセージが表示される
パソコンが自動的に再起動し、セットアップ画面が表示されたらWindowsのセットアップを行います。以上で、dynabookのリカバリー完了です。
参考:dynabookサポート リカバリーメディアからパソコンを初期状態に戻す方法<Windows 10 dynabook リカバリーメディアクリエーター搭載モデル>
dynabookがフリーズした場合の注意点

dynabookがフリーズした場合には、注意点もあります。慌てて誤った対処法を実行すると、dynabook内のデータを消失する、故障するなどのリスクがあります。dynabookがフリーズした場合は、以下の注意点を守りましょう。
電源のオン・オフを繰り返さない
dynabookが突然フリーズしても、何度も電源をオン・オフしてはいけません。電源のオン・オフを繰り返すと、HDDやSSDに負担がかかります。
ストレージに不調がある場合は症状を悪化させ、最悪の場合は故障するリスクもあります。通電するとデータが上書きされるため、データの復旧が難しくなる場合もあります。
何度も強制終了しない
パソコンを強制終了すると、保存していない作業中のデータを失うリスクがあります。強制終了はHDDやSSDに負担がかかるため、ストレージが故障する可能性や、システムファイルが破損するリスクもあります。
システムファイルが破損すると、dynabookは完全に故障します。dynabookがフリーズすると強制終了が必要な場合もありますが、リスクがあることも覚えておきましょう。
知識がない場合は分解しない
dynabookがフリーズして動かない場合、故障個所がわかれば分解してパーツ交換すれば、直る可能性もあります。メーカー修理や修理業者に依頼するよりも、安価で修理できることが多いです。
ただし、dynabookを自分で分解すると、メーカー保証の対象外になります。分解して、さらに症状が悪化し、完全に故障した場合にはメーカーの保証を受けられません。メーカーの保証期間内の場合は、メーカーサポートに問い合わせるのがおすすめです。保証期間外で合ってもパソコンに詳しくない場合は、分解しないようにしましょう。
dynabookがフリーズしないための対処法

dynabookがフリーズしないために、できることもあります。普段から少し注意するだけで、dynabookがフリーズして作業が中断されるリスクが低くなります。それぞれ、順番に確認していきましょう。
通気性の良い場所でdynabookを使う
パソコンは熱を発しているため、長時間使用しているとパソコン内部が高温になることがあります。パソコンが高温になり、熱暴走するとフリーズなどのトラブルが起こり、パソコンの寿命を縮める原因にもなります。
熱暴走を起こさないために、パソコンには冷却ファンなどの冷却機能があります。冷却ファンによって、パソコン内部から排熱され、パソコンを最適な温度に保ちます。
パソコンを熱暴走させないためには、通気性の良い場所にdynabookを置くことが大切です。壁に囲まれた場所や、通気孔をふさぐものがある場所には置かないようにしましょう。
また直射日光があたる場所や、真夏の車内など高温になる場所には、dynabookを置くのもやめましょう。
不要なアプリを削除する
dynabookに大量のアプリをインストールすると、メモリ不足になる可能性があります。不要なアプリがある場合は、削除しましょう。定期的にdynabook内にあるアプリを確認し、不要なアプリを整理しましょう。
用途のあったメモリ容量を確保する
dynabookがフリーズして、不要なアプリやデータもない場合は、そもそもメモリが足りてない可能性が高いです。dynabookがメモリ不足で頻繁にフリーズする場合は、メモリの増設がおすすめです。
用途に合わせてメモリを増設することで、dynabookがフリーズするリスクが少なくなります。必要なメモリ容量の目安は、メールやWebサイトの閲覧だけなら4GB程度、文書作成などでは8GB程度、動画編集やゲームなどをする場合は16GB程度です。新しくパソコンを購入する場合は、用途を考慮して必要なメモリ容量があるものを選びましょう。
OSやソフトウェアを常に最新にする
OSやソフトウェアをアップデートすると、不具合が修正されます。常に最新に保つことでフリーズなどのトラブルを回避できるでしょう。Windowsには自動更新機能もありますが、常に最新の状態であることを確認しましょう。
ウイルス感染対策をする
ウイルス感染もdynabookがフリーズする原因の1つ。悪質なウイルスに感染した場合は、パソコンが完全に故障することもあります。
ウイルスは、さまざまな方法や経路で感染するため対策が必須です。ウイルス感染対策には、対策ソフトを利用しましょう。また、Windowsに標準で備わっている「Windows Defender」を有効にするのもおすすめです。
定期的にディスククリーンアップを実行する
ディスククリーンアップを実行すると、HDDやSSDに溜まった不要なデータを削除して、ディスクの空き容量を増やせます。ディスククリーンアップを実行すれば、パソコンの反応速度が速くなり、フリーズすることも少なくなるでしょう。
【dynabookのディスククリーンアップの手順】
- タスクバーの検索ボックスをクリック
- 検索ボックスに「ディスククリーンアップ」と入力
- ディスククリーンアップをクリック
- ディスククリーンアップを実行した場合の空き領域と増加するディスク領域の合計が表示される
- 「削除するファイル(F)」の一覧でチェックが付いている項目を確認する
- システムファイルもクリーンアップしたい場合は「システムファイルのクリーンアップ」をクリック
- 不要なシステムファイルを検索して再計算される
- 削除したくないファイルがある場合はチェックを外す
- 「OK」をクリック
- 「これらのファイルを完全に削除しますか?」が表示されたら「ファイルの削除」をクリック
- クリーンアップが終わるまで待つ
ディスククリーンアップが完了すると、自動的に画面が閉じます。定期的に実行することで、dynabook内の不要なデータを整理できます。
参考:dynabookサポート 「ディスククリーンアップ」不要なファイルを削除し、ディスク領域を解放する方法<Windows 10>
初期化しても直らない場合は買い替えもおすすめ

dynabookがフリーズしたら処理が遅れているだけの場合もあるため、慌てないでまずはしばらく待ちましょう。しばらく待ってもフリーズが解消しない場合は、この記事で紹介している対処法を試してみるのがおすすめです。あらゆる方法を試しても、改善しない場合は初期化しましょう。
フリーズが頻繁に起こる場合は、dynabookが故障している可能性もあります。メーカーサポートへ修理に出しましょう。保証期間を過ぎている場合は、費用が発生し、直るまでに時間がかかる可能性もあります。dynabookを5年以上使用している場合は、寿命を迎えている可能性があるため買い替えるのもおすすめです。


監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。