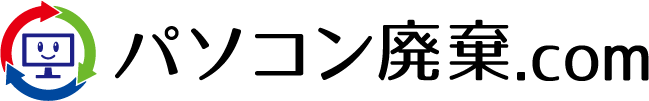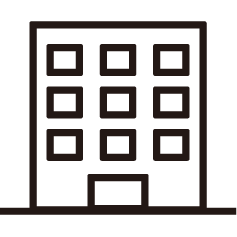404 Not Found
Macはウイルス感染しないと言われることがありますが、Macユーザーなら本当にMacはウイルス感染しないのか気になるのではないでしょうか?
結論、Macもウイルス感染します。Macはユーザーが少なく、ウイルス感染しにくい時期もありましたが、Macユーザーが増えた今となっては、Macにもウイルス対策が必須です。
この記事では、Macがウイルス感染した場合の確認方法や対処法について、わかりやすく紹介します。Macの動きがおかしいと感じる方は、最後まで読んでみてください。
【この記事でわかること】
- Macもウイルス感染する!対策は必須
- Macのウイルスの確認方法はアクティビティモニタの利用が最適
- ウイルスを除去するためには怪しいアプリやソフトを削除する
Macはウイルス感染しない?セキュリティ対策が必須

マックはウイルス感染に強い、ウイルス感染しないなどと言われてきましたが、今となっては昔の話であり、Windowsと同じようにMacもウイルスに感染します。
Macはウイルス感染しないと言われていた原因は、ビジネスシーンにおいてのシェアの低さにあります。
Windows用とMac用のウイルスは、使用するOSが異なるため、異なるプログラムの開発が必要。世界的に見ると、MacよりもWindowsのシェアが圧倒的であり、ウイルスを仕掛けるハッカーにとって、シェア率の低いMacをターゲットにすることは非常に効率が悪いため狙われなかったと言われています。
しかし、iPhoneがヒットした2007年ごろからMacユーザーが増えており、Macを狙ったウイルスも増加傾向です。Macはウイルス感染しないと認識しているユーザーも多く、セキュリティ対策が甘いことも原因の1つです。
また、技術の進歩によってWindowsと、Macで共有できるデバイスやソフトも増えており、Windowsとの接点が増えたことにより感染経路が増えたことも指摘されています。
さらにWindowsやMacなどのOSに関係なく動作するウイルスも確認されており、利用しているOSに関係なくセキュリティ対策が必須となっています。
Macには強固なセキュリティシステムがあるとはいえ、完全に対策できることはなく、Macもウイルス感染する可能性があることを認識しておく必要があります。
Macの主なウイルス感染経路

Macがウイルスに感染する主な経路は、次の3つです。
- 閲覧しているWebサイト
- USBメモリやSDカード、外付けハードディスクなどの記録媒体
- 受信メール
例えば、Webサイトを閲覧するだけで感染するウイルスや、Webサイトにあるゲームや広告などをクリックするだけで感染するウイルスもよくあります。
Webサイトを閲覧中にウイルス感染を警告する偽物のメッセージが表示されるケースも。Macはブラウザ上でウイルスチェックを実行することはないため、表示されたら強制終了がおすすめです。また、運営元がわからないアプリやソフトはダウンロードせず、AppStoreからダウンロードしましょう。
記録媒体にあらかじめウイルスを感染させ、Macに接続すると感染するものもあります。多いのはMacでは何も起こらないウイルスが、Macを通じてWindowsパソコンに被害をもたらすケースです。
また受信メールにも注意が必要。受信元がわからないメールを開き、本文にあるURLや添付ファイルを開くとウイルスに感染することもよくあるパターンです。大手通販サイトや自治体を装い、一見すると怪しいメールに見えないものも増えています。発信元を良く見て、覚えのないメールは開封せず削除しましょう。
Macがウイルスに感染したかも?事例を紹介

Macがウイルス感染した場合は、次のような症状が起こる場合があります。
- Macの動きが重くなる
- よくわからない広告やポップアップが表示される
- フォルダやファイルが開かず勝手に再起動する
- 頻繁にフリーズする
これらの症状が起こり、Macが正常に動作しない場合は、ウイルス感染している可能性があります。それぞれの症状を詳しく解説します。
Macの動きが重くなる
Macがウイルスに感染すると、Macの動きが重くなり、動作が遅くなります。マルウェアの中には、ボットネットと呼ばれるものがあります。ボットネットとは、ロボットとネットワークの造語で、第三者の指示通りに動くロボットにするマルウェアのことです。
それらに感染するとMacが乗っ取られ、他のユーザーに仮想通貨のマイニングやスパムメールの配信などのウイルス攻撃などに勝手に利用されます。CPUを大量に消費するため、Macが極端に重くなるのです。
よくわからない広告やポップアップが表示される
アドウェアと呼ばれるウイルスによって感染すると、見たことがないような広告やポップアップが頻繁に表示されるようになります。
大きな被害は少なく、広告のクリックを収益化して、サイバー犯罪者の利益になります。ただし中には、Appleや大企業の名前を使い、クレジットカードや銀行口座の番号など個人情報を抜き取るなど悪質なケースもあります。アドウェアはスパイソフトとして動作してユーザーの情報やファイルを不正に盗むなど、さまざまなケースがあるため注意しましょう。
ウイルス感染を示す表示が出る
突然、Appleのマークが付いた「お使いのMacはウイルスに感染しています」と警告が表示されたら注意が必要です。Appleのロゴが入っていると信頼してしまいそうですが、Appleはブラウザ上でウイルスをスキャンすることはないため、Mac向けの不正プログラムと考えられます。
警告の指示に従いスキャンをクリックすると、ウイルスに感染する可能性が高くなります。Macからウイルス感染を示すメッセージが表示されることはないので、警告を無視して画面を閉じましょう。
頻繁にフリーズする
ウイルスに感染することで、極端に動作が重くなり、頻繁にフリーズすることがあります。場合によっては、フリーズして一切動作ができなくなり、Macが使えなくなる場合もあります。
正常に動作していたMacが、突然フリーズを繰り返すようになったら、ウイルス感染の可能性が高いです。
Macがウイルス感染した場合に起こる被害

Macがウイルスに感染した場合に起こる被害は、以下の通りさまざまなパターンがあります。
- アカウントの乗っ取り
- メールのやり取りや写真などの個人情報流出
- クレジットカードや銀行の口座情報が盗まれる
- Macが使用できない
- Windows向けのウイルスを周りに拡散する
いずれにしても、Macが正常に動作できなくなったり、周りに迷惑を掛けたりします。あらかじめ、Macのウイルス感染の被害を知り、セキュリティ対策を強化しましょう。順番に詳しく紹介します。
SNSアカウントの乗っ取り
Macがウイルスに感染すると、個人情報を抜き取られます。個人情報は、ダークWebの闇市場では個人情報が高く売買されるため、盗まれるケースが多いです。
個人情報の中には、SNSアカウントも含まれています。万が一乗っ取られると、身に覚えのないことを投稿される被害やつながりのある人にDMを送るなどで、さらにウイルスを拡大してしまうのです。
メールのやり取りや写真などの個人情報流出
キーボードの入力内容ではなく、画面のスクリーンショットを勝手に撮影し、外部へ送信するウイルスもあります。キーボードの入力履歴を記録されるほどの被害はありませんが、メールの内容やプライベートな写真が流出するのは、気持ちのいいものではありません。仕事用のメールアドレスで、社外秘のメールなどを流出されると莫大な被害にもなりかねません。
Macに保存しているファイルが流出するのもよくあるケースの1つ。大切な情報が外部へ流出すると、信用を失う問題にもなりかねません。
クレジットカードや銀行の口座情報が盗まれる
Macがウイルス感染すると、クレジットカードや銀行の口座情報が盗まれることがあります。盗まれたクレジットカードや銀行口座は、預金が引き出される、不正利用されるなどの被害に合うことがほとんどです。
情報が盗まれたことに気付かず、被害が大きくなってから発覚することもあります。盗まれたお金が戻ることはほとんどなく、悪用された銀行口座やクレジットカードは再発行する必要があります。
Macが使用できない
Macがウイルスに感染すると、フリーズして一切使用できなくなることがあります。
悪質なケースでは、Macを人質に身代金が要求され、Macユーザーがお金を支払っても操作できず、情報だけを抜き取られることもあるのです。直接お金を請求されるだけでなく、ウイルスを駆除するためのソフトの購入を促すケースもあります。
いずれにしても、フリーズしてお金を要求されるウイルスに感染すると、Macを使用できなくなるため対応が困難になります。
Windows向けのウイルスを周りに拡散する
Macに直接的な被害はなく、Macを介してWindowsパソコンへウイルスを拡散するウイルスも存在します。
このウイルスに感染すると、アドレス帳にあるメールアドレスに自動で添付ファイルを送信する、USBメモリーなどの記録媒体からファイル共有するなどによって、Windowsパソコンにウイルスを感染させてしまいます。自分自身が被害に合うのではなく、周りに迷惑をかける加害者になってしまうのです。
Macのウイルス感染を確認する方法

Macがウイルスに感染したかも?と思ったら、感染を確認する必要があります。Macのウイルス感染は、以下の方法で確認可能です。
- アクティビティモニタを使用する
- ダウンロードしたフォルダーを確認する
それぞれの方法を、詳しく解説していきます。
アクティビティモニタを使用する
Macのアクティビティモニタとは、MacにインストールされているアプリケーションごとのCPUの使用率やメモリ使用量を確認できるアプリケーションのことです。Windowsで言うと、タスクマネージャーと同様の働きをします。
応答しないプロセスを強制終了させる、Macが重くなっている原因を探ることもでき、ウイルス検出にも役立ちます。アクティビティモニタを使用してウイルスを検出する手順は、以下の通りです。
- Finderを起動する
- 「アプリケーション」から「ユーティリティ」へ
- 「アクティビティモニタ」をクリック
- 「表示」メニューから「すべてのプロセス」をクリック
- 「プロセス名」でウイルスを探す
- 覚えのないアプリケーションをインターネットなどで調べる
- ウイルスを発見したらアクティビティモニタを終了する
- アプリケーションフォルダを開き、7で発見したウイルスの名前を探す
- ゴミ箱にドラッグして、空にする
アクティビティモニタでアプリケーションを一つ一つ確認し、覚えのない怪しいアプリケーションがあれば、インターネットで調べ、不要であれば削除しましょう。ゴミ箱へドラッグしたらすぐに削除するのが大切です。
最近ダウンロードしたアプリケーションやソフトで、ダウンロードした後にMacの調子が悪くなったなど、怪しいものから調べていきましょう。
不要であれば、CPUの使用率が高いアプリケーションを終了すると、Macの動きが軽くなります。
ダウンロードしたフォルダーを確認する
Macのダウンロードフォルダを確認して、身に覚えのないフォルダーがないかを確認しましょう。
万が一、怪しいフォルダーを見つけても開かないで、ダウンロードした日時を確認して本当にダウンロードしたものでないかを詳しく確認します。全く身に覚えのないフォルダーであれば、削除しましょう。
怪しいフォルダーをオンラインスキャンしてみるのも、方法の1つ。無料でウイルスに感染しているかを調べられます。
Macのウイルスを除去する方法

Macがウイルスに感染したら、早急にウイルスを除去する必要があります。自分でできるウイルス除去の方法を6つ紹介します。
- アプリをアンインストールする
- ログイン項目から削除する
- ポップアップ広告を削除する
- Macの拡張機能を削除する
- セーフモードで起動する
- Macを初期化する
それぞれ、わかりやすく解説します。
アプリをアンインストールする
万が一、ダウンロードしたアプリがウイルスの原因の場合は、すぐにアンインストールしましょう。不要なアプリをゴミ箱に入れるだけでは万全ではなく、完全にアンインストールするのがおすすめです。Macでアプリをアンインストールする手順は、以下の通りです。
- 「アプリケーション」フォルダから「Launchpad」を開く
- 「Launchpad」で怪しいアプリケーションを探す
- 「option」キーを長押しするか、App のいずれか 1 つをクリックして押さえたまま、すべての App が小刻みに揺れ始めるまで押し続ける
- 削除したいアプリケーションの横にある「✕」をクリックして削除する
Macの場合、Finderを使用してもアプリを完全にアンインストールできます。
- DockのFinderアイコンをクリック
- 「アプリケーション」フォルダから、アンインストールしたいアプリを選択
- アプリケーションをドラッグしてゴミ箱に移動する
- 「Finder」から「ゴミ箱を空にする」を選択して完全に削除する
Macに必要なアプリは、ゴミ箱に移動できないため、間違えてアンインストールする心配がありません。
ログイン項目から削除する
アドウェアやスパイウェアなどのウイルスは、起動プロセスに侵入するものも多いのですが、ログイン項目から対処できます。
- 「Apple」メニューをクリック
- 「システム環境設定」から一般をクリック
- 「ユーザーとグループ」をクリック
- 「ログイン項目」のタブを開く
- カギのアイコンをクリック
- 怪しいログイン項目の横にあるチェックボックスをオンにする
- 見覚えのないアプリが表示されたら消去する
- カギアイコンをクリックして新しい設定を確認する
- Macを再起動する
以上の手順で、ログイン項目から侵入しようとするウイルスを削除できます。
ポップアップ広告を削除する
不要なポップアップ広告が表示される場合は、クリックしないで無視しましょう。頻繁に表示される場合は、広告の削除がおすすめです。ポップアップ広告はブラウザに表示されるため、使用しているブラウザごとの対策が必要です。
【Safariの場合】
- Safariを開き、メニューから「環境設定」をクリック
- 「Webサイト」のタブで「ポップアップウインドウ」をクリック
- Webサイトのポップアップメニューで「ブロックして通知」または「開かない」を選択する
この時、「許可」を選択すると、Webサイトでポップアップ広告が表示されます。本当に不要なポップアップ広告であれば「開かない」を選択するのがおすすめです。
【Chromeの場合】
- Chromeを開き、右上のメニューから「設定」を開く
- 「プライバシーとセキュリティ」タブから「サイトの設定」をクリック
- 「コンテンツ」メニューの「ポップアップとリダイレクト」をクリック
- 「サイトにポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可しない」にチェックする
Macの拡張機能を削除する
Macに感染したウイルスを除去するためには、ブラウザの拡張機能の削除も必要です。ブラウザの拡張機能は、メモの整理やポップアップ広告の削除、パスワード管理など便利な機能が豊富です。
拡張機能の中には、偽装したウイルスが存在しており、便利だからといって、内容を理解せずに、増やしすぎるのは危険。怪しい拡張機能は削除するのが懸命です。
【Safariの場合】
- Safariの設定から「拡張機能」をクリック
- 怪しい拡張機能を選択して「アンインストール」をクリック
【Chromeの場合】
- Chromeを起動してメニューをクリック
- 「その他のツール」を選択
- メニューに表示される「拡張機能」をクリック
- 怪しい拡張機能を選び「削除」を選択
セーフモードで起動する
Macをセーフモードで起動すると、ウイルスやマルウェアが読み込まれずに、macOSに必要最低限のアプリケーションとプロセスのみで起動します。
そのためウイルス感染によってMacが使えない状態でも、セーフモードでは動作する可能性があります。つまり、セーフモードで起動すれば、Mac本体には問題がなくウイルス感染などの原因によって、不具合が起こっていることがわかります。
セーフモードでの起動方法は、搭載しているチップによって変わります。わからない場合は、Appleメニューの「このMacについて」から確認可能です。
【Appleシリコンを搭載したMacの場合】
- Appleメニューから「システム終了」を選択
- Macが完全にシステム終了するまで待つ
- 「起動オプションを読み込み中」と表示されるまでMacの電源ボタンを押したままにする
- ボリュームを選択
- Shiftキーを押したまま「セーフモードで続ける」をクリック
その後、Macが自動で再起動します。ログインウインドウが表示されたら、メニューバーに「セーフブート」と表示され、セーフモードで起動していることがわかります。
【Intelプロセッサを搭載したMacの場合】
- Macを起動または再起動したらすぐに「Shift」キーを押したままにする
- ログインウィンドウが表示されたらはなす
- Macにログインする
- もう一度ログインを求められたらログインしなおす
最初もしくは2番目のログインウインドウのいずれかで、メニューバーに「セーフブート」と表示されます。
Macを初期化する
あらゆる方法を試してもウイルスが除去できない場合は、Macの初期化もおすすめです。Macを工場出荷状態にすることで、ウイルスを除去できますが、データを復元するとウイルスに再び感染する恐れもあります。
Macを初期化する方法は、「すべてのコンテンツと設定を消去」を使います。
【macOS Venturaの場合】
- Apple メニュー から「システム設定」を選択
- 「一般」をクリック
- 「転送またはリセット」をクリック
- 「すべてのコンテンツと設定を消去」をクリック
【macOS Montereyの場合】
- Apple メニュー から「システム環境設定」を選択
- 「システム環境設定」メニューから「すべてのコンテンツと設定を消去」を選択
Macの初期化に関しては、下記記事でも詳しく解説しています。
Macを初期化する方法】事前準備や初期化できない時の対処法も解説>>
Macでセキュリティ対策する方法

Macもウイルス感染するため、セキュリティ対策は必須です。Macを使う際に注意する点や、セキュリティ対策には以下があります。
- メッセージの中身をよく読む
- パスワード管理を徹底する
- よくわからないWebサイトは閲覧しない
- 見覚えのないメールのリンクはクリックしない
- 不審なメールの添付ファイルは開かない
- よくわからないサイトからのソフトウェアやデータのダウンロードをしない
- Webサイトに表示される広告やポップアップをクリックしない
- OSやブラウザのバージョンを常に最新にする
- ファイヤーウォールを有効にする
- 定期的にスキャンを実行する
- セキュリティソフトを導入する
Macに対するウイルスは、さまざまな場所から感染します。不用意にメールのリンクを押したり、添付ファイルを開いたりしないようにしましょう。
また、アプリケーションはAppStoreでおこなう、よくわからないサイトのソフトウエアはダウンロードしないことも徹底しましょう。
OSやブラウザのバージョンを常に最新にすることも有効です。バージョンアップすると、新しいウイルスへの対策もされるため、よりセキュリティ効果が増します。
ファイアウォールとは、インターネットからの不正侵入を防ぐシステムのことです。ファイアウォールには、OSに付いているもの、セキュリティ対策ソフトに付いているもの、ルーターが有しているものなどがあり、無効にすると攻撃を受けやすくなるため、有効にしておきましょう。
セキュリティソフトの導入も1つ方法ですが、オンライン上にはセキュリティソフトを装ったウイルスも存在しているため、信頼できるソフトを使用しましょう。
まとめ:Macもウイルス感染対策は必須!

Macはかつて、そのシェア数の低さから、ハッカーから狙われにくく、ウイルスに感染しないと言われていたこともあります。
しかし、Macユーザーは増加しており、Macを狙ったウイルスも多数、確認されており、ウイルス対策は必須です。Macがウイルス感染すると、急に重くなったり、ポップアップ広告が何度も表示されたり、頻繁にフリーズしたりするようになります。
ウイルス感染すると、Macが使用できなくなるだけでなく、アカウントの乗っ取りや個人情報の抜き取りなどの被害を受ける可能性があります。日頃から、怪しい広告や添付ファイルをクリックしない、OSやブラウザのバージョンを最新にする、ファイアウォールを有効にするなどで、ウイルス感染対策を徹底しましょう。
もしも、Macがウイルスに感染してしまい、使えなくなった場合は、Macの買い替えも1つです。
不要になったMacの処分が必要になった場合は、パソコン廃棄.comでの処分がおすすめです。事前申し込みなしで、故障しているMacでも無料で処分できます。データ消去も安全におこなってくれるため、ぜひご検討ください。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
Macで不具合が生じた際、原因の追求や症状の改善に役立つのがセーフモードです。
しかし、どのように操作すればよいかわからないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、Macでセーフモードを起動する方法や、万が一セーフモードが正常に起動しない場合の対処法について解説しています。
Macをご利用中の方はぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- Macでセーフモードを起動する方法
- セーフモードで期待できる効果
- セーフモードが起動できないときの対処法
Macのセーフモードとは?

Macのセーフモードとは、必要最低限の機能のみでコンピューターを起動した状態を指します。
セーフモード下においては、不要な拡張機能やインストールされていないソフトウェアは使用できません。
また、起動ディスクのチェックやシステムキャッシュの削除などが自動で行われるため、不具合の解消につながる場合があります。
セーフモードで期待できる効果

セーフモードを活用することで、現在Macで起きているトラブルの原因が、ソフトウェアによるものなのかハードウェアによるものなのかを見極めることが可能です。
たとえば、これまで生じていた不具合がセーフモードの起動時には発生しない場合、ソフトウェアに何かしらの原因があることが考えられます。
また、セーフモードの起動時にはシステムの修復が自動的に実施されるため、画面がフリーズする・パソコンからログインできなくなるといった問題が解決することがあります。
セーフモードの起動方法

セーフモードを起動させる際、Macの種類によって操作方法が変わるため注意してください。
使用中のMacについては、アップルメニューから種類を確認できます。
ここでは、それぞれの手順について具体的に解説します。
Intelプロセッサを搭載したMacの場合
Intelプロセッサを搭載したMacでセーフモードを起動する場合、以下の手順で操作を行ってください。
【セーフモードを起動する手順】
- Macを起動したら、すぐにShiftキーを長押しし、ログインウインドウが表示されたら放す。
- Macにログインする。ログイン画面のメニューバーに「セーフブート」が表示されているのを確認する。(再度ログインを求められる場合もある。
参考:Macをセーフモードで起動する – Apple サポート (日本)
ログイン画面で「セーフブート」と表示されていない場合はセーフモードを起動できていないため、1からやり直す必要があります。
Appleシリコンを搭載したMacの場合
Appleを搭載したMacでセーフモードを起動する場合、以下の手順で操作を行ってください。
【セーフモードを起動する手順】
- アップルメニューを開き、「システム終了」を選択する。
- システムが完全に終了したことを確認できたら、電源ボタンを押す。
- 起動音が聞こえたらShiftキーを押し、そのまま「セーフモードで続ける」をクリックする。
- コンピューターが自動的に再起動されるため、ログイン画面のメニューバーに「セーフブート」が表示されているのを確認する。
参考:Macをセーフモードで起動する – Apple サポート (日本)
セーフモードの確認方法

Macがセーフモードで起動しているかどうかは、アップルメニューのシステム情報から確認できます。
具体的な手順は以下の通りです。
【セーフモードで起動しているか確認する手順】
- Optionキーを押しながら、アップルメニューの「システム情報」を選択する。
- サイドバーから「ソフトウェア」を選択する。
- 「システムソフトウェアの概要」内の「起動モード」に表示されている値を確認する。「セーフ」と表示されている場合はセーフモードで起動している。
参考:Macをセーフモードで起動する – Apple サポート (日本)
なお、起動モードの値が「正常」である場合はセーフモードは使用されていません。
セーフモードの終了方法

セーフモードは、Macの電源を切ることで自動的に終了します。
アップルメニューから「システム終了」を選択してパソコンをシャットダウンしてください。
その後、Shiftキーを長押しせずにMacを起動させましょう。
セーフモードが起動しないときの対処法

さまざまな不具合解消に役立つセーフモードですが、Macの状態によっては起動できないこともあります。
ここでは、セーフモードが起動しないときの対処法を6つ紹介します。
macOSを最新バージョンに更新する
macOSのバージョンが古いと、セーフモードを正常に起動できない場合があります。
最新バージョンになっていない場合は、以下の手順に従って更新を行ってください。
【macOSをアップデートする手順】
- アップルメニューから「システム設定」を選択する。
- 「一般」をクリックし、「ソフトウェアアップデート」を選択する。
- 新しいソフトウェアが見つかった場合は、画面の案内に従ってインストールを実行する。
参考:Mac の macOS をアップデートする – Apple サポート (日本)
すでに最新バージョンのmacOSを使用している場合は、別の方法を試してみましょう。
Optionキーから起動させてみる
Optionキーを使用することで、セーフモードを起動できる場合があります。
具体的な手順は以下の通りです。
【Optionキーからセーフモードを起動する方法】
- Macの電源を切る。
- 電源が完全に切れたことを確認したら、電源ボタンを押しながらOptionキーを長押しする。
- 起動するドライブを選択し、Enterキーを押す。
手動で起動させてみる
Macの起動時にShfitキーを押してもセーフモードに遷移できない場合は、手動でセーフモードを起動させてみましょう。
具体的な手順は以下の通りです。
【セーフモードを手動で起動させる手順】
- 「Command」キーと「Space」キーを同時に押して、Spotlight検索を表示させる。
- 「ターミナル」と入力し、「ターミナル.app」をクリックしてターミナルを起動する。
- ターミナル画面に「sudo nvram boot-args=”-x”」と入力し、実行する。
セーフモードを終了する場合は、再度ターミナルから「sudo nvram boot-args=””」と入力して実行してください。
セキュリティ設定を確認する
Macのセキュリティ設定の内容によっては、セーフモードを起動できなくなる場合があります。
以下の手順を参考に、設定の見直しを行ってください。
【セキュリティ設定の確認方法】
- Macをシャットダウンする。
- 電源ボタンを押し、起動中に「Command」キーと「R」キーを同時に長押しする。
- パスワードを入力し、言語を日本語に選択する。
- 「ユーティリティ」-「起動セキュリティユーティリティ」をクリックする。
- 「ファームウェアパスワードをオフにする」を選択し、オフに変更する。
- パスワードを入力して無効化を確定する。
SMCをリセットしてみる
SMC(システム管理コントローラ)とは、パソコンの起動・バッテリーなど、コンピューターの電源に関する機能を管理するシステムです。
SMCをリセットすることで、セーフモードに関する不具合を解消できる場合があります。
【SMCをリセットする手順】
- Macの電源を切る。
- 電源が完全に切れたことを確認したら、「control」キー+「option」キー+「shift」キー+電源キーを同時に7秒間押す。
- 7秒後、Macの電源を入れ直す。
まとめ:Macのセーフモードを活用しよう

この記事では、Macのセーフモードについて解説しました。
パソコンをセーフモードで起動させることで、システムの不具合を解消したり、トラブルの原因を切り分けたりすることが可能です。
しかし、セーフモードを起動しても問題が解決しない場合、ハードウェアの故障が考えられます。
その場合、この記事で紹介した方法では対応できないため、修理に出すか新しい機器への買い替えが必要です。
不要になったMacのパソコンは、パソコン廃棄.comなどを利用して適切に処分してください。
今回の記事もぜひ参考にしてくださいね。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
「PS5から音が出なくて困っている」
「自分でできる対処法はない?」
いつも通りPS5をプレイしようとしたところ、なぜか音が出なくて困っている、という方もいらっしゃるでしょう。
音が出なくなってしまう原因は様々ですが、個人で対応できるケースも珍しくありません。
そこでこの記事では、なぜPS5で音が出なくなってしまうのか、どのように対処すればいいのか、といった点を中心に解説していきます。
【この記事でわかること】
- PS5で急に音が出なくなる原因
- PS5で音が出ない時の対処法
- すべての対処法を試しても改善しない場合
PS5で急に音が出なくなる原因

PS5で音が出なくなってしまう代表的な原因は、以下の通りです。
- 単純な確認ミス
- テレビ側の不具合
- HDMI接続に問題が生じている
- システムトラブル
- ハードウェアの故障
- パソコン側の設定
単純な確認ミス
意外にやりがちなのが、「まさかそんなことが原因だとは思わなかった」というような単純なミスです。
例えば、テレビの音量がミュートになっていたり、テレビ側の設定でスピーカーがオフになっていたり、ヘッドセット用の端子に差し込んだままヘッドセットを放置していたり、といったことです。
もちろん、このような状態であればテレビから音が聞こえてくることはありません。
テレビ側の不具合
PS5の問題ではなく、テレビ側で何かしらの不具合が起きていることも考えられます。
例としては、音声に関するハードウェアの故障や、ソフトウェアのトラブルなどです。
別のテレビやHDMI端子のあるモニターに繋げてみて、正常に音が出るようならば、テレビ側の不具合がほぼ確定します。
HDMI接続に問題が生じている
HDMIとは「High-Definition Multimedia Interface」の略で、映像や音声などについてのデジタル信号を1本のケーブルでまとめて送ることのできる通信規格のことです。
「ゲーム機とテレビ」や「パソコンとモニター」などの接続に使用されます。
このHDMI関連で、以下のような問題が起こっていると、正常に音が出ないことがあります。
- HDMIケーブルの差し込みが甘い
- HDMIケーブルを間違った場所に差している
- HDMIケーブルが劣化していて断線などの不具合が発生している
システムトラブル
音が出ない原因の一つとして、PS5を正常に動作させるためのシステムに何らかのトラブルが発生している可能性もあります。
音声に直接関わるシステムはもちろん、直接的に関係ない部分で問題が生じていても、音が出ないという現象に繋がってしまうことは充分に考えられます。
システムトラブルは、電化製品であればいつ起こっても不思議ではありません。
PS5の場合も、普通にプレイしているだけで問題が起こってしまうこともあります。
ハードウェアの故障
稀に、PS5のハードウェアの一部が故障していることによって音が出ないこともあります。
特にPS5の使用頻度が高い場合には、ハードウェアのトラブルも発生しやすくなります。
- PS5を落下させてしまった
- 湿度の高い場所でプレイすることが多かった
- 毎日長時間プレイをしている
こういった場合には、ハードウェアのトラブルが起こりやすくなってしまうでしょう。
パソコン側の設定
普通にプレイしている時には問題がなくとも、リモートプレイにすると、パソコンに接続したイヤホンやヘッドセットから音が聞こえないという場合は、パソコン側のサウンド設定に問題があるのかもしれません。
この場合は、パソコン側で一度正しく設定を行ってしまえば解決するので、そこまで深刻なトラブルではありません。
PS5で音が出ない時の対処法

PS5で音が出ない場合には、個人で対処できる方法もいくつかあります。
メーカーへ問い合わせたり、どこかへ修理に出したりする前に、一度以下の対処法を試してください。
- テレビの音量を確認する
- テレビの入力切替が正しいか確認する
- モニターにスピーカーが搭載されているか確認する
- HDMI関連に問題がないか確かめる
- 3Dオーディオモードを無効にする
- PS5の音声設定を確認する
- PS5のシステムソフトウェアを最新のものにアップデートする
- リモートプレイ時に音が出るように設定する
テレビの音量を確認する
まずは、基本的な確認から行うようにしてください。
単純なミスとして多いのは、「テレビの音量がミュートになっている」・「テレビの音量が小さすぎて聞こえない」といった現象です。
テレビのリモコンを使って音量を上げることで、あっさり解決することもあります。
また、PS5本体の方がミュート状態になっていないかどうかも確認してください。
テレビの入力切替が正しいか確認する
こちらも単純なことですが、テレビの入力切替が正しいかどうかについても確認してください。
テレビ側で、PS5をプレイするための入力モードを選択できていない場合、映像や音声が正しく出力されません。
モニターにスピーカーが搭載されているか確認する
出力先がテレビではなく、モニターを利用している場合は、モニター自体にスピーカーが搭載されているかどうか確かめましょう。
当然、スピーカーがなければ音声は出ません。
「モニターならば音が出て当然」という思い込みを持っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、古いタイプのモニターや、音声出力を前提としていないモニターも存在するため、一度しっかりチェックする必要があります。
HDMI関連に問題がないか確かめる
映像や音声を1本のケーブルでまとめて送ることができるHDMIケーブルですが、正しく使用できていないことで音が出なくなってしまうことがあります。
- HDMIポートに別のゲームのHDMIコードが差し込まれていないか
- HDMIケーブルの差し込みが甘くないか
- HDMIケーブルが劣化していないか
こういった点についてしっかり確認してみましょう。
なおPS5は、HDMI2.1という規格、および4K 120Hzビデオ出力に対応しているため、古いケーブルを使っていないか確かめることも重要です。
こちらの規格は、まだ市場では浸透していないため、適当に選んだHDMIケーブルを使用している場合には要注意です。
3Dオーディオモードを無効にする
PS5の設定で、「3Dオーディオモード」が有効になっていると、音が出なくなってしまう可能性があります。
理由としては、3Dオーディオは対応するヘッドセットのみでサポートされているため、ゲームによっては対応できずに音が正常に出ない状態となってしまうのです。
こうしたケースを考え、一度3Dオーディオを無効にしてみてください。
無効にする手順は以下の通りです。
- 設定 ⇒ サウンド ⇒ 音声出力 ⇒ 3Dオーディオ(テレビのスピーカー)と進む
- 「テレビのスピーカーで3Dオーディオを出力」のチェックを外す
参照:PS5で3Dオーディオをセットアップする方法 | Playstationサポート
PS5の音声設定を確認する
PS5の音声設定が適切でないことが原因で、音が出ないということもあります。
一度、PS5の音声設定について確認してみましょう。
ホーム画面から「設定 ⇒ サウンド ⇒ 音声出力」と進むことで、出力機器や、自動での出力機器の切り替え、HDMI機器の種類などを設定することができます。
その他、テレビオーディオ設定や対応ヘッドホン設定など、PS5の音声に関する全般的な確認ができますので、適切な形に設定してみてください。
参照:PS5の音声設定を変更する方法 | Playstationサポート
PS5のシステムソフトウェアを最新のものにアップデートする
システム的なトラブルによって、音声に悪影響が出ているというケースもあります。
特に、アップデートの失敗によるトラブルというのは珍しくありません。
したがって、一度最新システムへのアップデートを試してください。
手動でアップデートを実行する場合の手順は以下の通りです。
- 「設定 ⇒ システム ⇒ システムソフトウェア」と進む
- 「システムソフトウェアアップデートと設定」を選択する
- 新しいバージョンがあれば、「アップデートが利用できます」と表示されるので、「システムソフトウェアをアップデート」を選択する
これで、最新ファイルのダウンロードとインストールが完了します。
もし何回か試しても正しくダウンロード・インストールが完了しない場合は、以下の手順を試してください。
- 一度PS5の電源を落とす
- WindowsかMacを搭載したパソコンを使い、FAT32またはexFATにフォーマットされたUSBドライブに「PS5」という名前のフォルダを作成する
- 作成したフォルダ内に「UPDATE」というフォルダを作成する
- PS5のアップデートファイルをダウンロードして、「PS5UPDATE.PUP」というファイル名でUPDATEフォルダに保存する
- ダウンロードしたファイルをUSBに移し、PS5に差し込む
- PS5をセーフモードで起動する
- 電源ボタンを長押しして、二度目のビープ音が鳴ったら電源ボタンから手を離す
- 「システムソフトウェアをアップデートする」を選択する
- 「USBストレージ機器からアップデートする」を選択してから、「OK」を選択する
これで、USBを使ってのアップデートが完了します。
もしPS5がアップデートファイルを認識しない場合は、フォルダ名とファイル名に誤りがあったり、小文字になっていたりしないかを確認してください。
フォルダ名・ファイル名ともに、すべてアルファベットの半角大文字となります。
参照:PS5のシステムソフトウェアをアップデートする方法 | Playstationサポート
リモートプレイ時に音が出るように設定する
パソコンを使ってリモートプレイをしている時に音が出ない場合は、以下のように設定するとPS5本体から音が出るようになります。
- コントロールパネルを開く
- 「ハードウェアとサウンド ⇒ サウンド」と進む
- 「再生」タブにある「スピーカー Wireless Controller」を右クリックで無効にする
すべての対処法を試しても改善しない場合

これまで紹介してきた対処法を試しても症状が改善しない場合は、以下のいずれかの方法を選択することをおすすめします。
- メーカーへ修理に出す
- 専門業者を探す
- 買い替えを検討する
特に、ハードウェアの故障である場合は個人での対応はほぼ不可能ですので、上記のような対応が必要となります。
メーカーへ修理に出す
最も確実な方法は、メーカーへ修理に出すことです。
保証期間が残っている場合は、迷わずメーカーに問い合わせて修理を依頼すべきでしょう。
言うまでもないことですが、メーカー保証期間であれば、故意による故障でなければ無料で対応してもらえます。
初期不良の問題であれば、新品との交換というケースもありますので、まずはメーカーに連絡するようにしてください。
専門業者を探す
保証期間を過ぎている場合は、PS5などの修理を行っている専門業者を探して依頼するのも一つの手段です。
メーカー修理の場合、保証期間を過ぎていると修理料金が高くなってしまいがちな上、手元にPS5が返ってくるのも遅いということが珍しくありません。
しかし専門業者ならば、比較的安価で修理期間も短い、というところも多く存在します。
ただし、業者によってはあまり質のよくないところもあるため、修理が不十分だったり、不誠実な対応を取られたりといったリスクもあるため、業者を利用する場合は依頼先を慎重に吟味するようにしてください。
買い替えを検討する
PS5は、発売されてまだ3年程度しか経っていませんが、利用頻度や利用環境によっては激しく劣化しているという可能性もあります。
例えば、PS5に熱がこもりやすいような環境で毎日のように長時間プレイしている、といったようなケースです。
PS5も電化製品である以上、使うたびに消耗・劣化していきますので、過度に使用していた場合は一度新品に買い替えるということも検討した方がいいかもしれません。
音が出ないという不具合を修理しても、全体的に劣化しているようならば、またすぐにどこかが故障してしまい、違う不具合が発生してしまう可能性もあります。
一般的な利用範囲を超える使い方をしていた場合には、買い替えについても視野に入れてみましょう。
まとめ:PS5で音が出ないトラブルは自己解決できることも多い

以上、PS5で音が出ない時の原因や対処法について解説してきました。
本記事の通り、音が出ないというトラブルについては、自己解決できることも多いです。
単純ミスやちょっとした設定のズレによって音が出ないこともあるため、メーカーなどへ問い合わせる前に、是非一度確認してみてください。
なお、2023年現在では、発売からまだ3年ほどしか経っていないPS5ですが、使用方法によっては劣化が激しいということもあり得るでしょう。
その場合は、PS5の買い替えも視野に入れる必要があります。
もしPS5を買い替える場合は、お手持ちの古いPS5が不要になるかと思われます。
そんな時は「パソコン廃棄.com」の利用が便利です。
「パソコン廃棄.com」ならば、費用は一切かからず、事前のやり取りも不要。
ただ不要になったPS5を梱包して送付するだけで、無料廃棄が完了します。
もしよろしければ、是非お気軽にご利用ください。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
いつもは聞こえない音がパソコンから聞こえてくると、不安になるものです。中でも、HDDは通常でも「シーク音」などの音がするパーツですが、カチカチなど大きな異音がする場合は故障が考えられます。
この記事では、HDDから異音がした場合の音の種類から原因や対処法、注意点を解説します。HDDから聞える音から判断できる内容なので、ぜひ参考にしてください。
【この記事でわかること】
- HDDから聞える音の種類
- HDDから異音がする原因は物理障害が多い
- 異音がした場合の対処法はまず原因の特定すること
- HDDから異音がした場合は使用を中止する
HDDの仕組みとは?

HDDの仕組みを知ることによって、異音が出ている場所や原因を知ることができます。
HDDは、レコードのようなプラッタと呼ばれる円盤型の装置にデータを記録します。HDDの中では複数枚のプラッタが高速回転しており、それぞれの表面でデータを読み書きするための磁気ヘッドが動いています。磁気ヘッドはわずかにプラッタから浮いており、経年劣化などでプラッタに接触するようになると異音がすることがあります。
HDDはモーターを回転させてプラッタにデータを読み書きするため、経年劣化や衝撃、転倒などによって故障しやすいパーツです。磁気ヘッドと磁気ディスクのすき間は数ナノメートルほど。ナノメートルは髪の毛の1/40,000程度の大きさです。そのため、ほんの小さなホコリやチリによって、HDDが障害を起こし異音が発生する事があるのです。
HDDはその仕組みから、通常「ブーン」といった回転音や、「カタカタ」といったシーク音が発生します。大きな異音は故障の可能性が大きいのですが、反対に無音の場合も、HDDが動作しておらず、故障している可能性があります。
HDDから異音がする場合の音の種類と原因

HDDから異音がする場合、HDDから聞こえる音がどのような音なのかを聞く必要があります。聞こえてくる音は、異音の場合と正常な音の場合があるため、良く聞いてみましょう。
HDDからの異音は、「物理的音」と機械的な音である「ビープ音」の2種類です。ここでは、さらに詳しくHDDから聞こえる音の種類や原因を解説します。
「ジージー」「カリカリ」と音がする
「ジージー」「カリカリ」と音がするのは、正常です。「シーク音」と呼ばれ、HDDがデータを読み書きしている場合に発生します。シーク音がしている場合には、電源を切ったり、振動を与えたりしてはいけません。HDDに物理障害が発生し、故障やデータ破損の原因になります。
シーク音が気になる場合は静音のHDDを選んだり、ケースに入れたりすることで音を抑えられます。
「ブーン」「ブォーン」と音がする
「ブーン」と音がする場合は、HDDからの音ではなくパソコンの冷却ファンによる回転音です。音が大きすぎる場合は、ファンにほこりが溜まっている可能性があります。
ファンにほこりが貯まり排熱機能が低下すると、パソコンに熱が蓄積し熱暴走を起こす可能性があります。早めにファンの掃除をしましょう。
また、HDDのモーターの回転音がHDDと共振することによって、音が大きくなっているケースもあります。床や家具など硬い場所に直接パソコンやHDDを置いている場合に起こることが多く、故障ではありません。柔らかいシート等を挟むと音が抑えられる可能性があります。
「ガリガリ」「カタカタ」と音がする
「ガリガリ」、「カタカタ」と音がする場合は、磁気ヘッドや磁気ディスクに異常が起こっている可能性が考えられます。HDDの劣化や衝撃が加わったことにより、磁気ヘッドとディスクが接触している、磁気ヘッドの駆動部分やモーター部分などの異常の可能性があります。HDDが使用できる場合でも、使用をやめて修理などの対処をしましょう。
「カチカチ」「キュルキュル」「カコンカコン」と音がする
金属同士が接触するような異音がする場合は、HDDのデータを読み書きするパーツが故障し、物理障害が発生している可能性があります。磁気ヘッドが破損して、アームやプラッタなどのパーツに接触しているケースが考えられ、使用し続けることで症状が悪化する可能性があります。
「シー」「シャー」と音がする
HDDから「シー」などとこすれるような音がする場合は、何らかの原因によりHDD内部でパーツが接触し、円盤状のパーツ(プラッタ)に異常が生じている可能性があります。使い続けると、プラッタの傷が深くなり、データを消失することがあります。こすれるような音がしたら、使用を中止して通電もしないようにしましょう。
「ピー」「プー」などの電子音がする
HDDから聞こえる異音の中でも、「ピー」などの電子音が聞こえる場合は、磁気ヘッドとプラッタが接触したままなど、正常の位置とは異なる場所で磁気ヘッドが停止していることが考えられます。
これらの電子音は非常に小さい音のため、よく耳をすまさなければ聞き逃してしまいますが、聞こえた場合は、使用をやめて電源を切りましょう。HDDの異常を示す電子音のため、使用を続けるとHDDが完全に故障しデータの取り出しが難しくなる可能性があります。
激しい異音がする
「ガチャガチャ」、「ゴットンゴットン」など激しい異音がする場合は、HDDが完全に故障する寸前の可能性があります。あまりにも激しい異音がする場合は、すぐにHDDの使用を中止しましょう。データのバックアップが取れる場合は取りますが、無理に保存すると完全に故障し、データの取り出しが難しくなる場合もあります。
動作音が全くしない
HDDが動作していれば、通常はシーク音と呼ばれる動作音がします。全くの無音の場合は、正常に動作していないこともあります。HDDの動作音は非常に小さい音のため、よく耳をすまして聞いてみてください。
全く音がしない場合は、HDDのモーター部分が破損し、回転していないことが考えられます。HDDのモーターは高速回転し、一定の速度以上になると動作音が発生します。モーターが損傷すると、回転数が足りなくなったり、不安定になったりして、動作音も聞こえなくなります。
動作音が聞こえない場合は、モーターだけでなく基板や電力供給部分に不具合が出ている可能性もあります。正常に動作しないままHDDに通電を続けると、症状が悪化することもあるため、使用を中止するのがおすすめです。
HDDから異音がする原因
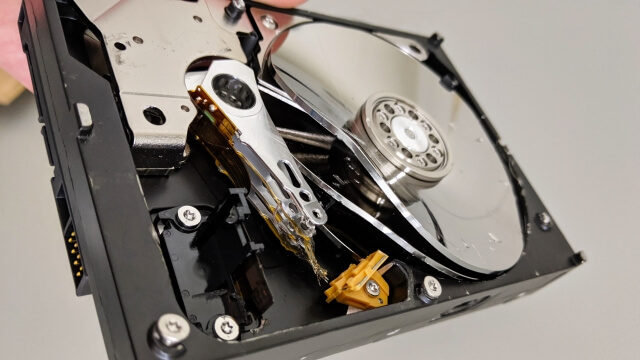
HDDから異音がする原因は、さまざまです。HDDはそもそも、それほど大きな音が発生する装置ではありません。そのため異音の種類にかかわらず、通常とは違う音がする場合はHDDの異常を疑いましょう。
HDDから異音がする原因は、以下があります。
- データの読み書き音
- 磁気ヘッド不良・磁気ヘッドの接触
- 不良セクタの蓄積(プラッタの劣化)
- ファームウェアの異常
HDDの異音の原因は、大きく落下や転倒などの物理ダメージと、経年劣化による部品の消耗が考えられます。それぞれ、異音の原因を解説します。
データの読み書き音
HDDを使用していると、シーク音と呼ばれるデータの読み書き音が発生します。シーク音は、「ジージー」「カリカリ」と音がしますが、正常な動作音のため問題ありません。
磁気ヘッド不良・磁気ヘッドの接触
HDDを落とすなどの衝撃で、磁気ヘッドが故障することがあります。磁気ヘッドが故障すると、同じ場所を往復するなど正常に動作しなくなります。磁気ヘッドのアーム部分がストッパーにあたり、データの読み込みが正常にできず、「カチカチ」と異音が発生します。
さらに、磁気ヘッドがプラッタと接触すると、「カチカチ」などの異音に加え、擦れたような異音もします。プラッタに接触したまま使い続けると、プラッタが傷つきデータを損傷する可能性があります。磁気ヘッドに接触していることが考えられる場合は、HDDの使用を中止しましょう。
不良セクタの蓄積(プラッタの劣化)
不良セクタとはなんらかの原因によって、データの読み書きができなくなっている箇所のことです。不良セクタはHDDの製造段階から存在しており、メンテナンス機能によってその箇所を避けてデータの読み書きが行われます。HDDの経年劣化などによって領域が拡大すると、メンテナンス機能では修復できず、正常に動作しなくなり異音が発生します。
ファームウェアの異常
HDDは、ファームウェアによって動作を制御されています。ファームウェアは、HDD内のチップに搭載されています。
チップに搭載されたファームウェアが破損すると、磁気ヘッドやストッパーへ正しい指示を出せません。そのため磁気ヘッドが正常に動かない、データの読み書きができないなどの不具合が起こり、「カチカチ」などの異音が発生します。
HDDから異音がする場合の対処法
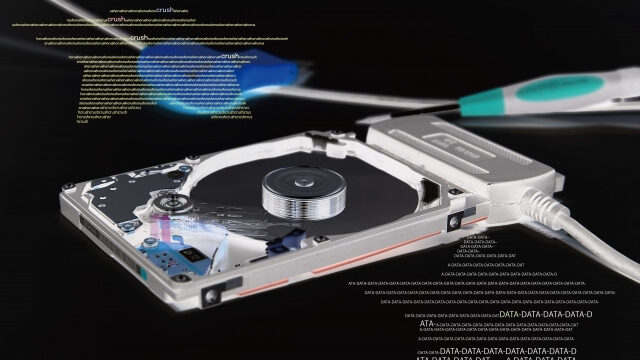
HDDから異音がする場合は、危険な状態の可能性が高いです。データを消失する可能性もあるため、早めの対処が必要です。対処方法は以下の通りです。
- 異音の原因を特定する
- 通電と操作をやめる
- データのバックアップが取れる状態なら取る
- HDDを交換する
HDDから異音がしている場合、素人が対処することは難しいケースが多いです。HDDやパソコンの状況から、対処法を実行しましょう。異音が発生している場合にできる対処法を、詳しく紹介します。
異音の原因を特定する
パソコン内部から異音がする場合、内蔵HDDからの異音か、別の箇所からの異音かを特定する必要があります。例えば「ブーン」と音がする場合は、HDDではなく冷却ファンの音の可能性もあります。
冷却ファンが原因の場合は、以下の方法で改善するケースもあります。
- ファンの周りのホコリを掃除する
- ファンの周りのケーブルを固定する
- パソコンを放熱する
ファンにホコリが付くと回転数が上がり、異音の原因になることがあります。また、ファンとケーブルが接触している場合は、結束バンドで固定することでケーブルがファンにあたらないようなります。
パソコン内部の温度が高温になると、排熱のためにファンの回転数が上がり、音が大きくなります。そのため涼しい部屋で、パソコンの電源を落とし、ケーブル類をすべて外し放熱すれば異音がなくなる可能性があります。
通電と操作をやめる
HDDから異音がする場合は、HDDに通電をやめて操作もやめましょう。外付けHDDはパソコンから取り外し、内蔵HDDならパソコンの電源を切りましょう。
HDDから異音がする場合は、物理障害を起こしている可能性が高く、通電を続けることで症状が悪化する可能性があります。異音が大きくなったり、データの取り出しが不可能になるケースもあります。
データのバックアップが取れる状態なら取る
HDDから異音がする場合、それ以上の作業は症状を悪化させる可能性があります、データのバックアップを取るのはHDDに負荷がかかり、バックアップ中にHDDが動作を停止する可能性もあります。
データのバックアップが取れる状態であることを慎重に判断し、実行しましょう。ある程度パソコンの知識があれば、内蔵HDDを取り出し、他のパソコンとつなぎデータをコピーする方法もあります。しかし、HDDが完全に壊れるリスクもあるため、難しい場合は専門業者へデータ取り出しを依頼するのがおすすめです。
HDDを認識しない場合は使用しない
HDDから異音がして、さらに認識しない場合は、重度の物理障害が発生していることがほとんどです。HDDは経年劣化や、衝撃などで破損しやすい精密機械です。
異音がしているHDDを無理に認識させようとして動作を続けると、データを完全に損傷し、復旧も難しくなります。早めに専門のデータ取り出し業者への依頼がおすすめです。HDD内のデータよりも、パソコンの復旧を希望する場合はメーカーや購入店などに修理を依頼しましょう。
HDDを交換する
HDDを3~5年程度使用している場合は、寿命の可能性があります。寿命の場合は修理するよりも、HDDを交換するのがおすすめです。HDDは、知識があれば自分で交換も可能。難しい場合は、外付けHDDの利用やパソコンごと買い替えることも検討しましょう。
パソコンを買い替えたら、適切に処分する必要があります。パソコン処分.comなら不要なパソコンを箱に詰めて送るだけで、処分可能です。事前連絡不要、データ消去も不要のため、手軽な点もおすすめです。
HDDの交換方法や認識しない場合の対処法に関しては、下記記事でも詳しく紹介しています。
HDDの交換は自分でもできる!デスクトップ・ノートPCでの手順を解説>>
【内蔵・外付け共通】HDDを認識しないときの対処法を解説!>>
HDDから異音がするときの注意点

HDDから異音がする場合は、以下のように注意することもあります。
- HDDに通電しない
- 何度も電源のオンとオフを繰り返さない
- 何度も再起動しない
- 分解しない
- HDDを叩いたり揺らしたりしない
- データ復元ソフトを使わない
- 異音を放置しない
これらの点に注意しなければ、HDDが完全に故障し、パソコンも動作しなくなる可能性もあります。HDDの不具合を最小限に留めるためにも、注意しましょう。それぞれ、順番に解説します。
HDDに通電しない
HDDから異音がする場合は、すぐに電源を切りHDDに通電しないようにしましょう。
HDDに通電を続けると、磁気ヘッドが不規則に動作し、プラッタに接触してより深刻なダメージを与える可能性が高くなります。プラッタの傷が深くなると、データを損傷し、復元も難しくなります。
何度も電源のオンとオフを繰り返さない
電源のオン・オフはHDDに大きな負担がかかる作業です。HDDが正常に動作しない場合、慌ててパソコンの電源のオン・オフを繰り返してしまいがちですが、多くの場合は症状が悪化します。
HDDに不具合がある場合は、異音の有無にかかわらず電源のオン・オフを繰り返さないようにしましょう。
何度も再起動しない
パソコンの再起動も、同じくHDDにとって負担が大きい動作です。パソコンに不具合がある場合は、再起動を繰り返すこともありますが、HDDから異音がする場合は避けた方が無難です。症状をさらに進行させるケースもあるため、パソコンの電源を切ってHDDを修理しましょう。
分解しない
HDDは、少しのちりやホコリでも内部に入ると障害が起こります。そのため専門業者は、ホコリの不着を避けるためにHDDの開封をクリーンルームでおこないます。通常の環境でHDDを分解すると、ホコリが付着し症状が悪化します。
また、磁気ヘッドとプラッタのすき間はわずか数ナノミリメートルです。手で触って少しでも位置が変わると、プラッタを傷つける原因にもなりかねません。
HDDの開封や分解は、クリーンルームと熟練した技術や専門知識が必要です。開封することで、メーカー保証の対象外にもなるため、絶対に分解や開封はしないようにしましょう。
HDDを叩いたり揺らしたりしない
HDDでデータの読み書きができなくなっても、HDDを叩いたり、揺らしたりしてはいけません。
HDDは繊細で精密な機械であり、少しの衝撃でも障害が起こる可能性があります。異音が発生しているHDDは、すでに障害が起こっているため慎重に扱う必要があります。
叩くなど衝撃を与えることで、磁気ヘッドが異常な動きをして、プラッタが傷つき、データの取り出しが不可能になることもあります。
データ復元ソフトを使わない
データ復元ソフトは、物理障害には対応していません。異音が発生している状態では、物理障害を起こしている可能性が高く、データ復元ソフトをダウンロードし、何度もスキャンすることで症状が悪化する可能性があります。
データ復旧の専門業者でも取り出し不可能になる可能性もあるため、異音の原因がわからない場合は使用を避けましょう。
異音を放置しない
HDDから異音がすると、ほうっておいても改善することはありません。HDDから異音がする場合は、すでに物理障害が起こっている可能性が高く、HDDが致命的な状態になっているケースも少なくありません。
HDDから異音がする場合は放置せず、電源を切って適切な対処法を実行しましょう。
それでも直らない場合は修理や買い替えを検討しよう

HDDは、通常の動作でも「ジージー」「カリカリ」などシーク音と呼ばれる音が発生します。しかし、「カチカチ」「カクンカクン」など大きな異音がする場合は、物理障害を起こしている可能性が高いです。
異音がする場合は、すぐに電源を切り、操作をやめるのがおすすめです。データを取り出せる場合は取り出しますが、HDDが物理障害を起こしている場合は途中で止まる可能性もあり、データが完全に取り出せなくなる可能性もあります。
難しい場合は、専門のデータ取り出し業者に依頼しましょう。データよりもパソコンの復旧を優先させる場合は、パソコンメーカーや購入店で修理がおすすめです。
HDDの寿命は3~5年程度のため、経年劣化によって不具合が起こった場合はパソコンごと買い替えるのもおすすめです。


監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
「パソコンのキーボードが外れてしまったけど、どうすればいい?」
デスクトップでもノートパソコンでも、使い方によってはキーボードのキーがいつ外れてしまうかわかりません。
そして、もしキーが外れてしまった場合には、大変不便な思いをするでしょう。
そこでこの記事では、キーボードが外れてしまった時の対処法を中心に、なぜキーが外れてしまうのか、キーボードが壊れた時にやってはいけないことは何か、といった点についても解説していきます。
【この記事でわかること】
- パソコンのキーボードのタイプ
- パソコンのキーボード(キートップ)が外れてしまう原因
- パソコンのキーボード(キートップ)が外れた時の対処法
- 個人では対処不可能なケース
- パソコンのキーボードが外れた時にやってはいけないこと
パソコンのキーボードのタイプ
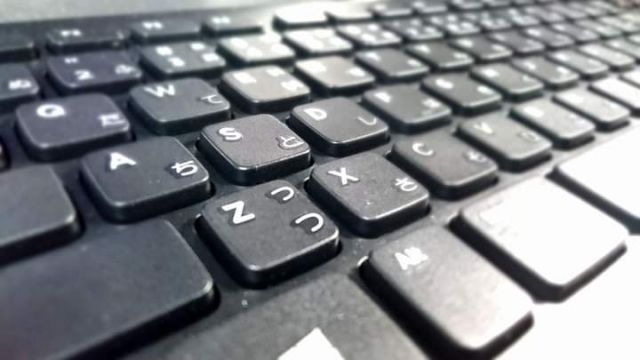
キーボードには、構造の異なるいくつかの種類が存在します。
メジャーなのは、以下の3種類となっています。
- メンブレン式
- メカニカル式
- パンタグラフ式
メンブレン式

画像引用:ELECOM株式会社
メンブレン式とは、キーボードのキーと基板の間にシリコンゴムなどで作られた柔らかいシートがあり、そのシートがキーを押し戻すという方式のものです。
主にデスクトップパソコンで使われているキーボードで、デスクトップパソコンを購入するとデフォルトで付属していることが多いです。
形状や配列の選択肢が多いのに安価で購入できる、という点がメリットです。
メカニカル式
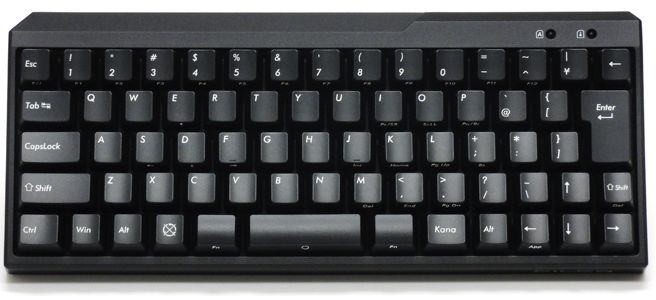
画像引用:ダイヤテック株式会社
メンブレン式が「同じシートですべてのキーをカバーしている」のに対し、メカニカル式は「各キーが独立している」点が特徴です。
したがって、一つのキーが故障したとしても、それぞれが独立しているため、故障したキーだけを修理すれば使い続けることができるというメリットがあります。
その分、メンブレン式と比べるとやや高価になってしまうのが難点です。
パンタグラフ式

画像引用:サンワサプライ株式会社
ほとんどのノートパソコンで採用されているのが、このパンタグラフ式です。
キーの下にX型のプラスチックを搭載することで薄型化を実現しています。
デスクトップに使用されているメンブレン式とは違い、浅いタッチでも反応することが魅力で、ソフトなキータッチが好みの方にとっては使い心地がよいでしょう。
ただし、メンブレン式やメカニカル式と比べてキーボードが外れやすいというデメリットがあります。
パソコンのキーボード(キートップ)が外れてしまう原因

通常の使用範囲ではそう簡単に外れないキーボード(キートップ)ですが、以下のようなケースに該当すると外れてしまうこともあります。
- 初期不良
- キーボードの扱いが雑すぎる
- 経年劣化
初期不良
あまり多くはありませんが、初期不良によってもとから壊れていた、もしくは壊れやすくなっていた、という場合があります。
キーボードに限らず、まったく同じように製造していても、稀に不良品が混じってしまうのはやむを得ないことです。
購入したばかりのデスクトップに付いてきたキーボードやノートパソコンのキーボードが、すぐに外れてしまったような時は、メーカーに連絡してみましょう。
保証期間内ならば、無償で対応してもらえます。
キーボードの扱いが雑すぎる
キーボードを頻繁に落下させたり、タイピングの力が強すぎたり、といった雑な扱いをしていると、当然キーが外れやすくなってしまいます。
特にパンタグラフ式のキーボードは、日常的に乱暴なタイピングをしていると、キートップが外れたりパンタグラフが壊れたりしやすいです。
ノートパソコンはキーボードと一体型なので、キーが故障するとノートパソコン自体を修理に出さないといけなくなるため、必要以上に強いタイピングはNGです。
経年劣化
キーボードは消耗品のため、どれだけ丁寧に使用していても、徐々に劣化してしまいます。
したがって、長年使い続けているキーボードのキーが外れやすくなってしまうことは仕方のないことでしょう。
電化製品でも周辺機器でも、物には寿命があるため、経年劣化による故障は避けようがありません。
パソコンのキーボード(キートップ)が外れた時の対処法

パソコンのキーボード(キートップ)が外れた場合の主な対処法は、以下の通りです。
- キートップを元の位置に置いて指で押す
- パンタグラフを正常に取り付ける
- デスクトップのキーボードが外れた場合は買い替える
- 外れたキーの上に両面テープを貼る
キートップを元の位置に置いて指で押す
キーボード側にパンタグラフが残っており、キートップだけが外れたという場合には、キートップを元の位置に置いた後に、垂直に指で押し込むだけで直ることが多いです。
押し込んだ時に、「パチっ」といった音が鳴って、キーが固定されたようならば、取り付け完了となります。
ただ、見た目だけではわからないので、念のため再起動してから、取り付け直したキーが正常に動作しているかどうか確認してください。
パンタグラフを正常に取り付ける
キートップだけでなく、パンタグラフも一緒に外れてしまった場合は、少々手順が面倒になります。
手順については以下の通りです。
- 分離している二つのパンタグラフを取り付ける。小さい方の部品にある出っ張りを、大きい方の部品のくぼんでいる部分にはめこむ
- 修復したパンタグラフを、ノートパソコン本体に取り付ける。はめこむ箇所が4つあるので、出っ張りやくぼみに合わせてはめる(1つでも外れている箇所があると破損する可能性があるので注意)
- キートップを元のキーの上に置いて、垂直に指で押し込む。「パチっ」といった音がすればはめこみ完了
文字だけの解説ではイメージが湧きづらいという方は、以下のLenovo公式サイトを参考にしてください。
わかりやすく図解されています。
参照:キーボードのキートップが外れた場合の対処方法 – Lenovo Support JP
なお、上記はLenovoのノートパソコンにおける手順となり、同じパンタグラフ式であっても多少手順が異なる場合があるのでご注意ください。
デスクトップのキーボードが外れた場合は買い替える
ノートパソコンの場合、本体とキーボードが一体となっているため、キーが外れた場合は自分で取り付け直すか修理に出すしかありませんが、デスクトップのキーボードは本体と別になっているため、キーが外れたり壊れたりしたら買い替えてしまった方が早いです。
デスクトップ用のキーボードの価格はそれほど高いものではなく、2,000~3,000円で購入できるものが多いです。
特に、長年使っていたキーボードのキーが外れたのならば、その他のキーも劣化している可能性が高いので、買い替えをおすすめします。
外れたキーの上に両面テープを貼る
あくまで応急処置とはなりますが、外れたキーの上に両面テープを貼りつけて凌ぐ、という方法もあります。
これで、とりあえず問題なくタイピングができるでしょう。
できれば、クッションのついた柔らかい両面テープを使うと、タイピングの際の使い心地もよくなります。
個人では対処不可能なケース

キーボードの状態によっては、個人で対処することができないこともあります。
以下のような時は、メーカーや専門業者へ修理を依頼するしかないでしょう。
パンタグラフが破損している
ノートパソコン本体とキーの間にあるパンタグラフが破損していると、キーとしての役割を正常に果たすことはできなくなります。
こうした物理的な故障がある場合には、基本的に個人で対応することができません。
パンタグラフはそこまで強い耐久性がないため、指でキーを引っかけたり、やたらと強い力でタイピングし続けたりすることでダメージを蓄積し、外れやすくなってしまうので要注意です。
ノートパソコン本体の突起やツメが破損している
パンタグラフを装着するノートパソコンの本体側の突起やツメが破損した場合も、個人での対応がほぼ不可能になります。
上記のパンタグラフの破損同様、物理的な故障については、メーカーや専門業者に修理を依頼するしかありません。
パソコンのキーボードが外れた時にやってはいけないこと

パソコンのキーボードが外れた時に、何とかして直そうと思って強引なやり方を選んでしまう人もいるかもしれません。
しかし、無理な直し方をすれば、状況は余計に悪化してしまいます。
特に以下のような行為は避けましょう。
強引にキートップを押し込む
なかなか「パチっ」とはまらないからといって、キートップを必要以上の力で押し込んだり、ぐりぐりとねじ込もうとしたりするのは避けてください。
強引にキートップを押し込んでしまうと、パンタグラフやパソコン本体側の突起やツメが破損してしまうかもしれません。
一回押しただけでは上手くはまらないこともありますので、押し込む角度を変えつつ、適切な力で根気よくはめこむ作業を行うべきです。
接着剤でキートップをくっつける
パンタグラフが壊れていたり、本体側の突起やツメが破損していたりする場合には、メーカーや専門業者へ修理に出すしかありません。
しかしノートパソコンの場合、一体型であるため、壊れたキーがたった一つであってもキーボードごと交換となってしまい、高額な修理費が必要となることもあります。
そのため、高額な修理費を払うのを避けようとして「とりあえずキートップを接着剤でくっつけておこう」と考える方もいるかもしれませんが、絶対にやってはいけません。
接着剤が内部にまで入り込んでしまい、キーボードだけでなく他の不具合まで誘発してしまう可能性があります。
結果的に、キーボード交換だけでは済まなくなり、さらに高額な修理費がかかってしまうこともありますので気を付けてください。
まとめ:キートップが外れただけならばすぐに対応可能!物理的に破損していたらメーカーや業者へ依頼しよう

以上、パソコンのキーボード(キートップ)が外れてしまう原因や対処法について解説してきました。
ノートパソコンでキートップが外れただけならば、正しくはめ直すだけで元通りになります。
しかし物理的な破損があれば、修理に出すしかありません。
ノートパソコンはキーボードと一体型になっているため、場合によっては高額な修理費用が必要となるケースもあります。
今使っているノートパソコンを修理して今後も使い続けるのか、長い年数にわたって使用してきたので買い替えるのか、そのあたりは個人の判断となるでしょう。
なお、買い替えを選択する場合には、お手持ちのノートパソコンが不要になるかと思われます。
そんな時は「パソコン廃棄.com」の利用が便利です。
「パソコン廃棄.com」ならば、費用は一切かからず、事前のやり取りも不要。
ただ不要になったパソコンを梱包して送付するだけで、無料廃棄が完了します。
送られてきたパソコンに入っているデータ消去も、責任を持って行わせていただきますので、セキュリティ的にも安心です。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
マウスがあればSurfaceでの作業が効率よく進められるため、使用している方も多いのではないでしょうか。
しかし、マウスを使用していると突然反応しない、クリックしても動かないなどが起こり、対処に困ることも。マウスが反応しなくなる原因はさまざまあるため、改善するためには一つひとつ対処法を試す必要があります。
この記事では、Surfaceのマウスが反応しない場合の対処法を、複数紹介しています。Surfaceのマウスが反応しなくて困っている場合は、ぜひ参考にしてください。
【この記事でわかること】
- Surfaceのマウスの動きが悪い場合の対処法
- まずは使用環境の見直しや掃除をしよう
- バッテリーや電池切れなら補充するだけで直ることも
- どうしても直らない場合は強制終了する
Surfaceのマウスの接続タイプは3種類

Surfaceのマウスには、Microsoft社製の純正と非純正があります。純正のSurfaceマウスは、接続や設定がスムーズな点がメリット。また、Surfaceと統一されたデザインや使いやすさも魅力です。
Surfaceには、Microsoft社製のマウスではない非純正のマウスも接続可能です。使いたい機能がある場合や、好みのデザインのマウスを使いたい場合は、非純正のマウスを選びましょう。
Surfaceのマウスには、以下3つの接続タイプがあります。
- Bluetooth
- USB
- 有線
接続タイプによって異なる対処法もあるため、まずは使用しているマウスの接続タイプを確認しましょう。Surface純正マウスは、Bluetooth接続です。USB接続や有線マウスを選びたい場合は、非純正マウスを選びましょう。
Bluetooth
Bluetoothマウスは、無線通信技術の1つであるBluetoothを利用したマウスの接続方式です。SurfaceはすべてのモデルにBluetoothを内蔵しているため、Bluetoothマウスの接続が可能です。
USBレシーバーが不要なため、USBポートがないパソコンでも利用できます。ペアリングの設定が必要で、接続が不安定になる場合がある点がデメリットです。
USB(2.4GHz)
USBレシーバー(2.4GHz )マウスは、USBポートにレシーバーを挿して使います。接続設定が不要で、接続が安定している点もメリット。USBポートが1つつぶれることや、レシーバーがないと接続できない点がデメリットです。SurfaceはUSBポート数が少ないため、使いにくい可能性があります。
有線
有線マウスは、USBポートにケーブルを接続して使用します。安定性や反応速度の速さを重視する場合は、有線マウスがおすすめです。有線マウスは、ケーブルの取り回しが面倒な点がデメリットです。
Surfaceのマウスの動きが悪い場合の対処法

Surfaceのマウスが反応しても動きが悪い場合は、以下の方法で改善する可能性があります。
- 開いているアプリを閉じる
- ポインターの速度を調整する
マウスカーソルの動きが悪い場合や、クリックしても動かない、正常に反応しない場合に試してみてください。
開いているアプリを閉じる
多くのアプリを開いている場合に、マウスへの接続が妨害されることがあります。マウスの動きが悪い場合に、アプリを複数開いている場合は、すべてのアプリを閉じてみましょう。アプリを閉じれば、マウスの動きが改善する可能性があります。
ポインターの速度を調整する
マウスポインターの動きが遅い場合は、設定から調節も可能です。以下の手順で、マウスカーソルの設定を変更しましょう。
- 「スタート」ボタンをクリック
- 「設定」をクリック
- 「デバイス」をクリック
- 「マウス」から「その他のマウスオプション」、「ポインターオプション」をクリック
- ポインターの速度を調整する
マウスの設定からは、ポインターの大きさやスクロールの行数なども変更可能です。
参考:Microsoft マウスまたはキーボードに関する問題のトラブルシューティング
Surfaceのマウスが反応しない場合に確認すること

Surfaceを使用していて、急にマウスが反応しなくなった場合、まずはマウス本体が汚れていないことを確認しましょう。マウスが汚れている場合は、乾いた布や綿棒、ブロアーなどを使用して掃除してください。マウスを掃除しても反応がない場合は、使用環境やSurfaceの状態を確認しましょう。
Surfaceのマウスの使用環境を確認する
光学式マウスやレーザーマウスを使用している場合は、光学式マウス専用のマウスパッドを使ってみてください。柄が印刷されているマウスパッドを使用している場合は、無地のマウスパッドに変更してみましょう。ガラスや金属などの透明な素材や光を反射する素材、凸凹の素材の上ではマウスが正しく反応しない場合があります。マウスを別の場所に移動しましょう。
Surfaceの状態を確認する
マウスだけでなくSurfaceがフリーズしていないかを確認することも大切です。マウスが反応しない場合、マウスの問題だけでなく、Surface本体が不具合を起こしている可能性もあるためです。
Surfaceがフリーズしていないかを確認するためには、まずHDDランプを確認してください。点灯や点滅していれば、ハードディスクも動作しており、Surfaceも動作しています。また、キーボードの反応も確認してみましょう。マウスが反応しない場合でもキーボードが反応すれば、Surfaceを操作可能です。
ノートパソコンの場合は、タッチパッドの反応も確認しましょう。マウスが反応しない場合でも、タッチパッドが反応すれば操作可能です。
いずれも反応がなく、Surfaceがフリーズしている場合は、使用しているアプリを終了したり、Surfaceを再起動してみましょう。改善しない場合は、Surfaceが故障している可能性もあるため修理や買い替えが必要です。
Surfaceがフリーズした場合の対処法に関しては、下記記事でも詳しく解説しています。
Surfaceがフリーズした場合の対処法!多発する場合はどうする?>>
マウスが反応しない原因を切り分ける
別のパソコンがある場合は、反応しないマウスを別のパソコンに接続してみてください。問題なく動作する場合は、Surfaceがマウスを認識していない可能性があり、動作しない場合は、マウスが故障している可能性があります。
また、別のマウスがある場合は、Surfaceに別のマウスを接続してみて反応を確かめる方法もあります。別のマウスも動作しない場合は、Surfaceの接続に問題が発生している可能性があり、動作する場合はマウスに原因があると考えられます。
このように別のパソコンやマウスを使用して、原因の切り分けもできます。次からは、Surfaceのマウスが反応しない場合の対処法を紹介します。
Surfaceのマウスが反応しない場合の対処法

Surfaceのマウスが反応しない場合、すべてのマウスに共通する対処法と、接続方式によって異なる対処法があります。
ここでは、すべてのマウスに共通する対処法と、Bluetooth、USB、有線の接続方式の違いによる対処法をそれぞれ紹介します。
バッテリー残量を確認する
Surfaceのマウスが反応しない場合、まず確認することはマウスのバッテリー残量です。Bluetooth、USBマウスの場合、マウスのバッテリーがなくなると反応しなくなります。
光学式マウスの場合は、バッテリー残量があればマウスのセンサーが光っているはずです。センサーが光っていない場合は、新しい電池に入れ替えましょう。
機内モードのオン・オフを切り替える
Surfaceの機内モードとは、飛行機や病院などで使用する場合に飛行機の通信機器や医療機器に電波干渉を起こさないために、無線通信をおこなわない設定のことです。
機内モードを設定していると、Bluetoothマウスが反応しなくなります。出張などで飛行機に乗った際に、機内モードにしたまま解除を忘れたなどのケースも。以下の手順で、機内モードを解除しましょう。
- 「スタート」ボタンをクリック
- 「設定」をクリック
- 「インターネット」から「機内モード」を選択
- 機内モードをOFFにする
なお機内モードがONの場合でも、USBマウスと有線マウスは使用可能です。
ワイヤレス機器の受信を妨げるものを調べる
BluetoothやUSBなどのワイヤレスマウスの場合、周囲に金属物など受信を妨げるものがあると反応が悪くなることがあります。とくに、金属製の机や棚などを使用すると、起こる場合があります。マウスをSurfaceに近づけて、反応するのかを確認しましょう。
Windows Updateを実行する
Surfaceのマウスが反応しない場合、システムに異常が起こっている場合があり、Windows Updateが有効な可能性があります。以下の手順でWindows Updateを実行し、最新の状態になっていることを確かめましょう。
Windows Updateはインターネット接続が必要です。時間がかかる可能性があるため、余裕を持って実行しましょう。
- 作業中のアプリをすべて終了する
- 「スタート」ボタンをクリック
- 「設定」ボタンをクリック
- 「Windows Update」をクリック
- Windowsの状態を確認する
- メッセージに従ってWindows Updateを実行し、Surfaceを再起動する
Windowsが最新の状態の場合は、「更新プログラムのチェック」をクリックすると、新しいプログラムの有無を確認できます。あらたに更新プログラムが見つかった場合は、「利用可能な更新プログラム」が表示されます。インストールが完了するのを待ちましょう。
「最新の状態です。」と表示された場合は、Windows Updateを実行する必要はありません。
ドライバーを更新する
マウスが反応しない場合、ドライバーに問題が起こっている可能性があります。以下の手順で、マウスドライバーを再インストールしましょう。
- 「スタート」ボタンを右クリック
- 「デバイスマネージャー」から「マウスとそのほかのポインティングデバイス」の項目を選択
- 使用しているマウスを右クリックして表示されるメニューから「デバイスのアンインストール」または「削除」をクリック
- 「デバイスのアンインストール」または「デバイスのアンインストールの確認」が表示されたら「OK」をクリック
- マウス操作ができなくなるのでキーボード操作する
- 「Alt」キー+「F4」キーを押して「デバイスマネージャー」を閉じる
- デスクトップが表示されたら「Alt」キー+「F4」キーを押して「Windowsのシャットダウン」から「再起動」を選択
- 「Enter」キーを押す
Surfaceの再起動が終わったら、ドライバーの再インストールは完了です。マウスが反応することを確認しましょう。
Surfaceを再起動する
Surfaceに不具合がある場合は、再起動して、使用しているアプリやソフトを終了することで改善する可能性があります。Surfaceの再起動の方法は以下の通りです。
- 「スタート」ボタンをクリック
- 電源マークから「再起動」をクリック
- Surfaceが再起動するまで待つ
Surfaceが再起動したら、マウスを使ってみましょう。
Bluetoothマウスの場合
Bluetoothマウスが反応しない場合は、以下の方法を試してみましょう。
- Bluetoothのペアリングを確認する
- ペアリングランプを確認する
- Bluetoothの省電力モードを解除する
それぞれの手順は以下の通りです。
Bluetoothのペアリングを確認する
Bluetoothマウスの場合、ペアリングされていなければ反応しません。反応しない場合は、ペアリングが解除されている可能性があるため、次の手順で設定しなおしましょう。
正常にペアリングされている場合は、いったん解除して、再接続することで不具合が改善する可能性もあります。
- 「スタート」ボタンから「設定」をクリック
- 「Bluetoothとデバイス」を選択
- 「Bluetooth」がオフの場合はオンにする
- 「Bluetoothとその他のデバイス」をクリック
- Bluetoothマウスのデバイス名を選択して「デバイスの削除」をクリック
- 確認メッセージが表示されたら「はい」を選択(ペアリングが解除される)
- 「デバイスの追加」をクリック
- ペアリングしたいマウスのボタンを押して画面上の「Bluetooth」を選択
- マウスが検出されればペアリング終了
キーボード操作の場合は、「Tab」キーと上下矢印キーで選択項目の変更、「Enter」キーで決定の操作ができます。
数分待ってもデバイスが検出されない場合は、「戻る」を選択して、ペアリングをやり直しましょう。
何度実行してもデバイスが検出されない場合は、マウスの電源の入れ直し、電池の確認、Surfaceの再起動などを試してください。それでも検知しない場合は、マウスが故障している可能性があります。別のマウスを使って、反応を確かめましょう。
ペアリングランプを確認する
ペアリングランプが3回点滅して消える場合、マウスが一定の範囲内にある別のパソコンに接続されていることを意味しています。
マウスが別のパソコンに接続されている場合は、ペアリングされているパソコンでデバイスを削除しましょう。マウスのペアリングを解除したら、使用しているSurfaceでBluetoothマウスをペアリングし直します。
Bluetoothの省電力モードを解除する
Bluetooth接続のマウスが反応しなくなる原因に、省電力モードが作用しているケースがあります。Bluetoothデバイスは、バッテリーの寿命を延ばすためにマウスを使用していない時間が続くと、休止状態になります。休止状態の後にマウスを使い始めるとマウスの再接続に時間がかかることがあります。
また、Bluetoothの省電力モードがオンになっていると接続が不安定になることもあり、以下の手順で解除することで改善する可能性があります。
- 「スタート」キーを右クリック
- 「デバイスマネージャー」をクリック
- 「Bluetooth」から使用しているマウスをダブルクリック
- タブから「電源の管理」をクリック
- 「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外し「OK」をクリック
以上で、省電力モードが解除されます。
USBマウスの場合
USBマウスが反応しない場合は、以下の方法を試してみましょう。
- レシーバーが接続されているかを確認する
- デバイスマネージャーでデバイスの認識を確認する
- USB セレクティブサスペンドを無効にする
以下から詳しく紹介します。
レシーバーが接続されているかを確認する
USBマウスの場合は、USBレシーバーが外れていないかを確認しましょう。USBマウスの場合、レシーバーが正しく挿し込まれていなければ反応しません。USBメモリー等を使用の際に外している可能性もあるため、接続を確認しましょう。
レシーバーが外れていない場合、マウスに対応しているレシーバーであるかを確認しましょう。USBレシーバーは、メーカーや機種によって異なります。USBマウスに同梱されているレシーバーを使用しましょう。
また、USBレシーバーを抜き差しする、別のUSBポートに差し替えるなどで改善する可能性もあります。いったんSurfaceの電源を落とし、USBポートからレシーバーを取り外し、再接続してみましょう。
デバイスマネージャーでデバイスの認識を確認する
マウスが正しく認識されているのかは、デバイスマネージャーで確認できます。正しく認識されていないデバイスには、「?」や「!」マークなどが表示されたり、不明なデバイスとして表示される場合もあります。
デバイスが正しく認識されていない場合、マウスは正常に反応しません。誤認識されている場合は、デバイスを削除して、再接続することで改善する可能性があります。デバイス名が表示されず、全く認識されていない場合は、USBレシーバーを抜き差ししてください。
USB セレクティブサスペンドを無効にする
Windowsでは初期設定時に、電源の消費を抑えるためにUSBポートの電源が自動で切れる機能が設定されています。USBセレクティブサスペンドによって、マウスが反応していない可能性があります。以下の手順で無効にしましょう。
- 「コントロールパネル」から「ハードウェアとサウンド」をクリック
- 「電源オプション」をクリック
- 「プラン設定の変更」をクリック
- 「 詳細な電源設定の変更 」 をクリック
- 「 USB 設定 」 をダブルクリック
- 「 USB のセレクティブ サスペンドの設定 」 をダブルクリック
- 「電源に接続」を無効にする
- 設定が変更されたら「OK」をクリック
すべての操作が完了したら、Surfaceを再起動しましょう。
有線マウスの場合
有線マウスが反応しない場合は、次の対処法を試しましょう。
- ケーブルを抜き差しする
- 別のマウスを接続してみる
ケーブルを抜き差しする
有線マウスの場合はケーブルを抜き差しすれば、反応する可能性があります。一時的なトラブルの場合は、ケーブルを抜き差しするだけで改善するケースが多いです。まずは、ケーブルを抜いて接続しなおしてみましょう。
別のマウスを接続してみる
Surfaceに接続しているマウスに原因がある可能性も考えられるため、別のマウスを接続してみましょう。別のマウスが問題なく動作する場合は、マウスが故障している可能性があります。
Surfaceを強制終了する
ここまですべての方法を試してみても、マウスが反応しない場合は、Surfaceを強制終了しましょう。ただし、強制終了は何度も実行するとSurfaceに負担がかかり、データが消える、起動しなくなるなどトラブルの原因となることもあります。
Surfaceを強制終了するのは、どのような対処法を実行しても改善しない場合に留め、頻繁におこなわないようにしましょう。
Surfaceを強制終了する方法は、主に以下2種類。
- 音量の「-」ボタンと「電源」ボタンを電源がオフになるまで15~30秒押し続ける
- 電源ボタンを30秒以上押し続ける
モデルによって異なるため、使っているモデルに合わせて実行しましょう。頻繁に強制終了が必要な場合は、Surfaceが故障している可能性もあります。その場合は、Surfaceの買い替えも検討しましょう。
Surfaceの強制終了に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。
Surfaceを強制終了する方法は?できない場合の対処法も解説>>
まとめ:Surfaceのマウスが反応しないなら接続を確認しよう

Surfaceのマウスが反応しない場合は、まずマウスの掃除や使用環境を見直してみましょう。それでも反応しない場合は、マウスを付け替えたり、パソコンを変更したりすることで原因の切り分けも可能です。
使用しているマウスの接続方法によっても対処法が異なります。Bluetooth、USB、有線など接続方法を確認して、それぞれの対処法を試してみましょう。
いかなる方法を実行しても改善しない場合、Surfaceを強制終了すれば改善する可能性もあります。しかし強制終了は、Surface本体に負担が大きいため頻繁に実行するのはおすすめしません。
頻繁に強制終了が必要な場合は、Surfaceが寿命を迎えている可能性もあります。その場合は、Surfaceの買い替えもおすすめです。
Surfaceを買い替えたら、古いものは適切に処分する必要があります。パソコン廃棄.comでは、Surfaceを無料で処分できます。事前の申し込みやデータも消去も不要。データ消去は、専門の知識を持ったスタッフによって的確におこなわれるため安心して処分できます。
利用方法は、Surfaceを箱詰めして指定住所に送るだけ。段ボール箱の中に故障したマウスを同梱すれば、一緒に処分できる点もメリットです。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
「PS5から出る異音が気になる」
「『ブーン』『ジー』『カタカタ』といった異音は、なんで発生する?」
異音は、快適なゲームプレイを妨げてしまいます。
したがって、PS5をお使いの方の中には、上記のような悩みを持っている方も多いでしょう。
そこでこの記事では、PS5からいろいろな異音が発生してしまう原因や、異音への対策法について詳しく解説していきます。
PS5の異音に悩んでいる方は、是非参考にしてください。
【この記事でわかること】
- PS5の異音の種類と原因
- PS5で異音がする場合の対策法
- 自分で対策してもPS5の異音が改善されなかった場合
PS5の異音の種類と原因

PS5の代表的な異音は、以下の5種類です。
- 「ブーン」という異音
- 「ジー」という異音
- 「ピピピ」という異音
- 「パキパキ」という異音
- 「カタカタ」という異音
「ブーン」という異音
「ブーン」という音は、正常な音の場合と異音の場合があります。
まず正常な「ブーン」という音は、ディスクを入れたままPS5を起動した時にする音です。
ディスクトレイに入っているディスクを読みこもうとして鳴っている音なので、何も問題ありません。
PS5に限らず、パソコンでも、ディスクを入れたまま起動するとブーンという音がします。
異音と言えるのは、以下のようなパターンです。
- 冷却ファンの異常回転
- コイル鳴き
最も多いのが、冷却ファンが通常の範囲を超えるほどの勢いで回転することによって発生する「ブーン」という異音です。
長い間通風孔の掃除をしておらず、ホコリが大量に付着しているような時には、なかなか本体を冷やすことができず、必要以上にファンが回転してしまうため、音がうるさくなってしまうのです。
次に考えられるのが、「コイル鳴き」です。
ただコイル鳴きの場合、「ジー」や「ジジジ」といった音が鳴るのが一般的なため、ファンが原因であることが多いでしょう。
「ジー」という異音
PS5本体から聞こえてくる「ジー」という異音は、ほぼ間違いなくコイル鳴きによるものです。
コイル鳴きとは、PS5に負荷がかかっている時に発生する音のことで、本体に内蔵されているコイルが、周波数や電流を安定させるために細かく振動することで音が鳴ります。
特に、「原神」のような重いゲームをプレイする時に発生しやすいです。
しかしコイル鳴きに関しては故障ではなく、正常な動作の範囲という扱いなので、もし修理に出しても「異常なし」ということになってしまいます。
「ジー」「ジジジ」といったコイル鳴きの音は非常に耳障りですが、基本的に直接的な対策法はなく、我慢するしかありません。
しかし、コイル鳴きによる音の不快さを軽減する方法はあります。
こちらについては、対策法紹介の項目で詳しく解説します。
「ピピピ」という異音
「ピピピ」という異音は、PS4の時代に言われていた問題で、静電気の影響で入っているディスクが勝手に出てきてしまうというハードウェアのトラブルでした。
しかし、PS5では改善され、基本的にこのような問題は起こらないようになっています。
PS5における「ピピピ」という音は、ディスクを取り出すためのボタンであるイジェクトボタンを押した時に、ディスクが入っていないと鳴る音です。
こちらは異音というわけではなく、「ディスクが入っていない」ということを告知するための音となっています。
ただ、「レストモード中に停電で電源が落ちる」など、ごく一部の特殊な環境においては、PS5の場合でも「ピピピ」という音が鳴ることがあるようです。
「パキパキ」という異音
電源がオフになっているPS5から「パキパキ」といった異音がする、という悩みを持っている方もいらっしゃるようですが、結論からお伝えしますと、こちらは異音ではありません。
これは、PS5本体の温度変化によって、本体のプラスチック部分が膨張・収縮したことできしむ音です。
パキパキ音は、PS5に限ったことではなく、クーラーやファンヒーターなど、プラスチックを用いた電化製品ならばすべてに起こりうることですので、気にする必要はありません。
「カタカタ」という異音
PS5を起動した時に、ファンの音だけでなく、カタカタという異音が発生することがあります。
様々な原因が考えられるのですが、主な原因としては以下の通りです。
- 初期不良
- 本体カバーのネジ止めが甘い
- PS5の振動で近くにある物が共振している
最も多いのは、PS5起動時の振動に耐えられないほど本体カバーのネジ止めがゆるい、というパターンかと思われます。
稀ではありますが、初期不良という可能性もありますので、以下で紹介する対策法をすべて試しても改善しないようならば、メーカーに問い合わせてみるとよいでしょう。
PS5で異音がする場合の対策法

PS5で異音がする場合には、いきなり修理に出したりせず、まずは自分でできる範囲の対策法を実践すべきです。
個人でできる異音対策としては、以下のような方法があります。
- 風通しの良い場所でプレイする
- 通風孔を掃除する
- PS5本体をアップデートする
- 光学ドライブのネジを調整する
- 吸音材を使用する
- ヘッドホンを装着する
- PS5を離れた棚などに収納してプレイする
風通しの良い場所でプレイする
PS5の本体が熱くなりすぎると、それに応じて冷却ファンの回転も激しくなっていきます。
回転が激しくなれば、それだけ「ブーン」という音も大きくなり、気になるようになってくるでしょう。
PS5の本体が熱を持たないようにするためには、なるべく風通しの良い場所にPS5を置いてプレイするのが一番です。
物に囲まれた場所にPS5を置いていると、風通しが悪く熱がこもりやすくなってしまい、ファンの音も常にうるさい状態が続いてしまいます。
また、PS5を置く場所にも注意すべきです。
熱を溜めやすいような、厚い毛の多い絨毯の上に置きながらプレイしていると、PS5本体の温度も上がりやすくなってしまいますので気を付けてください。
通風孔を掃除する
PS5には、内部の熱を排出するための通風孔があります。
しかし、通風孔はそれほど大きな穴ではないため、一定期間掃除をしていないと、ホコリで穴が詰まってしまい、適切に熱を排出できなくなってしまいます。
そうなると、当然冷却ファンにかかる負担が増え、必要以上に回転することになり、ブーンという音がさらに大きくなってしまうので、通風孔の掃除は定期的に行うようにしましょう。
参照:PS5から音がする | Playstationサポート
PS5本体をアップデートする
あまり大きな効果はないかもしれませんが、念のためPS5を常に最新の状態にしておくことも意識した方がよいでしょう。
システムが古いことで本体に負荷がかかり、余計な処理が増え、熱を溜めやすくなるということも考えられます。
PS5のシステムに何か更新があった際に、いちいち手動で更新するのは面倒ですし、更新を忘れることもあると思われますので、自動で更新されるように設定しておくことをおすすめします。
自動アップデートの設定手順は簡単で、以下の2ステップで完了します。
- 「設定」⇒「システム」⇒「システムソフトウェア」⇒「システムソフトウェアアップデートと設定」と進む
- 「アップデートファイルを自動的にダウンロードする」と「アップデートファイルを自動的にインストールする」を有効にする
この設定を完了させることで、アップデートファイルがある場合には、レストモード中にシステムソフトウェアのアップデートが自動的に行われます。
参照:PlayStationで自動ダウンロードと自動アップデートを設定する方法 | Playstationサポート
光学ドライブのネジを調整する
「カタカタ」という音が気になる場合は、PS5本体を開き、光学ドライブのネジを締め直すという方法もあります。
しかし分解の程度によっては、今後メーカーのサポートを受けられなくなってしまうリスクがあるため、知識のある人以外は安易に分解しない方がよいでしょう。
吸音材を使用する
吸音材とは、音の振動である「空気伝播音」を反射させずに吸収し、熱エネルギーに変換することで、音の大きさを小さくする物のことを指します。
吸音材をPS5本体に貼ることで、本体から発せられる音が吸収されるため、何もしないよりはかなり音が抑えられることでしょう。
ヘッドホンを装着する
苦肉の策ではありますが、PS5側に何らかの対策をするのではなく、ユーザーがヘッドホンを装着して物理的に音を遮断するという方法もあります。
こちらは、主にコイル鳴きへの対策法となります。
コイル鳴きは故障や異常ではないため、避けることができません。
したがって、やや強引な方法ではありますが、ヘッドホンをすることで「ジー」といった不快な音によるダメージを軽減することができるでしょう。
PS5を離れた棚などに収納してプレイする
こちらもコイル鳴きの対策となります。
コイル鳴きの音をうるさく感じてしまうのは、ユーザーがPS5の近くでプレイしているからとも言えます。
そのため、PS5との物理的な距離を取れば、必然的に音は気になりにくくなるでしょう。
さらに、風通しの良い棚などを用意し、そこに収納しながらプレイすれば、「ジー」というコイル鳴きの音はかなりカットできる可能性が高まります。
自分で対策してもPS5の異音が改善されなかった場合

ここまで解説してきた対策法を実践しても異音が改善されなかった場合は、自分で解決することを諦め、メーカーや専門業者への依頼を検討すべきです。
メーカーへ修理に出す
異音に悩んでいる場合、まずはメーカーへ問い合わせてみましょう。
オンライン修理受付サービスを利用することで、オンライン上で解決してしまうこともあります。
オンライン上での解決が無理でも、保証期間内ならば無料での修理や交換が可能となっています。
特に、カタカタという異音がする場合は初期不良も考えられるため、メーカーへ連絡することで新品交換となることもあります。
参照:オンライン修理受付サービス | Playstationサポート
専門業者へ依頼する
保証期間が過ぎた状態でメーカーに修理を依頼すると、確実な修理を受けられるものの、高額な修理費用が必要となってしまうことがあります。
かつ、修理が込み合っているとなかなかPS5が返ってこない可能性もあるでしょう。
そういった場合に便利なのが、街やオンラインで探すことのできる専門業者です。
業者によっては、メーカー修理よりも安い費用で、修理期間も短いというケースもあります。
しかし、専門業者はピンキリであり、質が良いところもあれば悪いところもあります。
そのあたりの見極めができる自信がなければ、多少割高になろうとも、メーカーに修理依頼を出した方がよいでしょう。
また、一度専門業者に修理を依頼すると、メーカーサポートを受けられなくなってしまうことがほとんどですのでご注意ください。
まとめ:避けられない異音もあるため上手く付き合おう
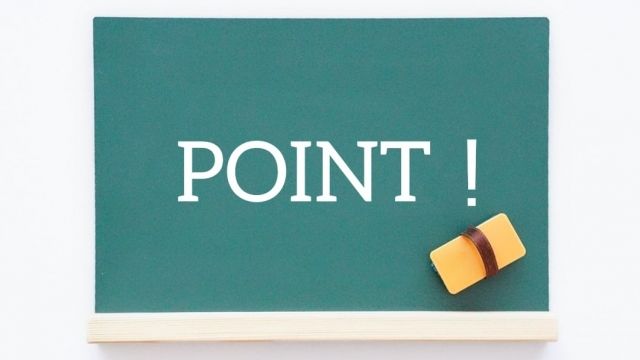
以上、PS5の異音の種類や原因、異音に対する対策法などについて解説してきました。
PS5で遊ぶ以上、避けられない異音もあります。
代表的なのは、「ジー」「ジジジ」といったコイル鳴きです。
重いゲームをする場合には、こういった異音と上手く付き合っていくしかないでしょう。
この記事で紹介した対策法を参考にしつつ、可能な限り異音が気にならない形を作り、快適なプレイを楽しんでください。
なお、2023年現在では、発売からまだ3年ほどしか経っていないPS5ですが、使用方法によっては劣化が激しいということもあり得るでしょう。
その場合は、PS5の買い替えも視野に入れる必要があります。
もしPS5を買い替える場合は、お手持ちの古いPS5が不要になるかと思われます。
そんな時は「パソコン廃棄.com」の利用が便利です。
「パソコン廃棄.com」ならば、費用は一切かからず、事前のやり取りも不要。
ただ不要になったPS5を梱包して送付するだけで、無料廃棄が完了します。
もしよろしければ、是非お気軽にご利用ください。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
「最近、パソコンの動きが重い」
「急にシャットダウンしたりフリーズしたりすることが増えた」
このような症状にお悩みの方はいらっしゃらないでしょうか?
パソコンは消耗品のため、使えば使うほど劣化してしまうことは避けられませんが、まだそれほど使用していないのに上記のような症状が出てしまった場合には、解決する方法があります。
それが、HDD(ハードディスク)の初期化です。
そこでこの記事では、HDDの初期化が有効なケースや、Windowsの各バージョンごとのHDD初期化手順、HDDを初期化する際に注意すべきことについて詳しく解説していきます。
【この記事でわかること】
- HDDの初期化が必要なケース
- WindowsパソコンのHDDを初期化する方法
- HDD初期化に関する注意点
HDDの初期化が必要なケース

HDDの初期化とは、インストールされているすべてのソフトや、これまで作成してきたデータを削除し、工場出荷時の状態に戻すことです。
初期化は、主に以下のような時に行います。
- パソコンの動作が重い
- パソコンの挙動がおかしい
- 重要なシステムファイルを削除してしまった
- ウイルス感染が疑われる
- パソコンを譲渡・廃棄する
パソコンの動作が重い
パソコンの動作が重くなる理由には、主に以下のようなものがあります。
- HDDの経年劣化
- HDDの空き容量が極端に少ない
- ウイルス感染
- システムファイルの損傷や不具合 …など
動作の遅さに困っている場合は、まずHDDの空き容量を増やしてみましょう。
空き容量が少ない場合、作業領域が減ってしまい、パソコンの動作が遅くなってしまいます。
なお、充分な空き容量を作っても改善しないようならば、HDD自体に何らかの原因がある可能性が高まります。
ただし経年劣化の場合は、初期化しても症状が改善する可能性は低いでしょう。
HDDの性能自体が衰えているので、システムファイルやデータといった中身をすべて入れ替えても効果はほとんど期待できません。
この場合は、古いHDDを新しいHDDやSSDに交換するしかありません。
なお、ウイルス感染やシステムファイルの不具合については後述します。
パソコンの挙動がおかしい
いきなりシャットダウンしてしまったり、頻繁にフリーズしたりするようになったパソコンのHDDには、何らかの異常が発生していることが疑われます。
こういった場合に、初期化は大変有効です。
初期化することで、不具合の原因となっているファイルを削除し、新たにOSやソフトウェアのシステムファイルをインストールすることになるため、中身を綺麗にすることができるのです。
経年劣化ではなく、まだ使用し始めてそれほど期間が経っていないような新しいHDDの場合には、是非初期化を試してください。
重要なシステムファイルを削除してしまった
長くパソコンを使っていると、誤って重要なシステムファイルを削除してしまった、というようなこともあるでしょう。
また、パソコンを通常使用していても、重要ファイルが損傷してしまうこともあり得ます。
そして、パソコンの起動や操作に影響するファイルが無くなったり壊れたりすると、あらゆる不具合が起こりやすくなります。
こういったケースでも、初期化を試す価値があります。
ウイルス感染が疑われる
ウイルス感染によってパソコンが動かなくなってしまったり、動きが不安定になったりした時にも、初期化は有効です。
コンピュータウイルスには様々な種類があります。
情報を盗み取るもの、そのパソコンを「ウイルスをバラまく媒体」にしてしまうもの、単にパソコンに悪影響を及ぼすもの、などです。
いずれにせよ、パソコンの動作に何かしらの影響が出る可能性が高いため、怪しいサイトを訪問したり、見知らぬ相手からのメールに添付されたファイルを開いてしまったりした後にパソコンの動きがおかしくなったら、ウイルス感染を疑ってみるべきでしょう。
ウイルスを完全に排除するためには、ウイルスが入り込んでいるHDDを初期化してしまうのが一番です。
なおパソコンが完全に動かない場合は、セーフモードでの立ち上げを試し、そこで立ち上がれば、セーフモードで初期化を実行してください。
参照:Windows で PC をセーフ モードで起動する | Microsoft
パソコンを譲渡・廃棄する
誰かにパソコンを譲渡したり、中古ショップに売ったり、パソコンを廃棄したりする場合も、HDDの初期化は必要です。
HDD内には、個人情報が多く含まれているはずです。
もし、その残っている情報を悪用するような人間の手にパソコンが渡ってしまえば、どのような被害に遭うかわかりません。
したがって、何らかの形でパソコンを手放す時には、必ずHDDの初期化を行ってデータを消しておきましょう。
WindowsパソコンのHDDを初期化する方法

この項目では、WindowsパソコンにおけるHDDの初期化方法について解説していきます。
OSのバージョンごとに多少手順が違いますので、それぞれのOSごとに手順を紹介します。
Windows7
Windows7の場合、メーカーや機種によって初期化の手順が異なります。
一例として、「VAIO」での初期化方法を紹介します。
- 電源が切れた状態で「F3キー」or「F4キー」を押しながら、電源ボタンを押す
- 「VAIO レスキューモード」画面にて、「BIOS 設定を起動」をクリックする
- BIOS画面でMainメニューが表示されていることを確認した後、矢印キーを使ってBootメニューを選択する
- 「Boot Mode」の項目が「Legacy」であることを確認する(Windows7の場合は必ずLegacyと表示される)
- 設定を変更した場合は、矢印キーを使って「Exit」を選択する
- 「Save Configuration and reset ?」もしくは「Save configuration changes and exit now?」というメッセージが表示されるので、「Yes」を選択してからEnterキーを押す
- 「VAIO レスキューモード」画面が表示されるので、「VAIOのリカバリー機能を開始」をクリックする
- 「リカバリー開始」画面にて「リカバリー開始」をクリックすると、「本当によろしいですか?」という確認メッセージが出るので、「OK」をクリックする
- 初期化が開始される。数分から数十分かかるので、途中で電源を切らないように注意する
以上で初期化作業は完了となります。
Windowsが数回再起動した後、Windowsセットアップ画面が表示されるので、指示通りに進めていってください。
参照:[Windows 7] リカバリー(再セットアップ・初期化)を行う方法 | VAIO
なおWindows7においては、以下のような初期化方法もあります。
Windows7の初期化方法は?注意点や初期化できない際の対処法も解説>>
Windows8.1
Windows8.1の場合も、メーカーによって多少手順が異なる場合がありますが、概ね同じような手順となります。
Windows8.1での初期化手順は以下の通りです。
- 画面右下から「設定」画面を開く
- 設定のオプションから「PC設定の変更」をクリックする
- PC設定画面が開くので、「保守と管理」をクリックする
- 保守と管理画面が開くので、「回復」をクリックする
- 「すべて削除して Windows を再インストールする」の項目にある「開始する」をクリックする
- 「PCを初期状態に戻す」という画面が表示されるので、「次へ」をクリックする
- 複数のドライブがある場合は、「Windowsがインストールされているドライブのみ」と「すべてのドライブ」が表示されるので、どちらの方法で初期化するかを選択する
- 「ドライブを完全にクリーンアップしますか?」というメッセージが表示されるので、「ファイルの削除のみ行う」・「ドライブを完全にクリーンアップする」のどちらかを選択する(完全な初期化を行うためには、後者のクリーンアップを選択した方がよい)
- 「PCを初期状態に戻す準備ができました」という画面が表示されるので、「初期状態に戻す」をクリックする
- 初期化が開始されるので、作業が終了するまで電源を切らない
これでWindows8.1における初期化作業は完了です。
初期化完了後は、自動で再起動が行われます。
参照:Windows 8.1で「PCのリセット」を行う方法 | NEC LAVIE公式サイト
Windows8/8.1の初期化方法を解説!初期化できないときの対処法も紹介>>
Windows10/11
Window10と11は、初期化手順がほぼ同じとなっています。
Window10/11で初期化を行う際は、まず「個人用ファイルを保持する」か「すべてを削除する」かのどちらかで初期化を行うことになります。
前者は簡易的な初期化で、システムファイルのみを削除するという方法です。
後者がいわゆる一般的な初期化であり、システムファイルを含むすべてのファイルを削除する方法です。
パソコンの不具合を修正したい場合は「個人用ファイルを保持する」を選択し、他人へパソコンを譲渡する場合は「すべてを削除する」を選択するとよいでしょう。
以下に、それぞれの方法での初期化手順について解説していきます。
参照:Windows の回復オプション | Microsoft
【Windowsパソコンの初期化方法】手順や注意点をわかりやすく解説>>
「個人用ファイルを保持する」のHDD初期化手順
- Windowsボタンをクリックし、設定画面を開く
- 「更新とセキュリティ」をクリックしてから、左メニューの「回復」をクリックする
- 「このPCを初期状態に戻す」の項目にある「開始する」をクリックする
- 「オプションを選択してください」のメッセージの下にある「個人用ファイルを保持する」をクリックする
- 「Windowsを再インストールする方法選択します」のメッセージが表示されるので、「ローカル再インストール」をクリックする
- 「準備しています」のメッセージが表示された後、「お使いのアプリは削除されます」というメッセージの下に、削除されるアプリ一覧が表示されるので、問題が無ければ「次へ」をクリックする
- 「このPCを初期状態に戻す準備ができました」というメッセージが表示されるので、「初期状態に戻す」をクリックする
- 初期化作業が始まる
あとは、初期化が終わるまで電源を切らずに待っていてください。
「個人用ファイルを保持する」の場合は、作業完了までにそれほど時間はかかりません。
「すべて削除する」のHDD初期化手順
- 上記「個人用ファイルを保持する」の1~3までの手順と同じ
- 「オプションを選択してください」のメッセージの下にある「すべて削除する」をクリックする
- 「Windowsを再インストールする方法選択します」のメッセージが表示されるので、「ローカル再インストール」をクリックする
- 「準備しています」のメッセージが表示された後、「お使いのアプリは削除されます」というメッセージの下に、削除されるアプリ一覧が表示されるので、問題が無ければ「次へ」をクリックする
- 「このPCを初期状態に戻す準備ができました」というメッセージが表示されるので、「初期状態に戻す」をクリックする
- 初期化作業が始まる
以降は、初期化が完了するまで電源を切らずに待ってください。
なお、ドライブクリーニングも実施したい場合は、「4.」の画面で表示される「設定を変更」をクリックすれば、ドライブのクリーニングも行なわれます。
パソコンを高速化したい場合に有効です。
HDD初期化に関する注意点

HDDの初期化を行う前には、以下のような点に注意してください。
- バックアップを取っておくことを忘れない
- OSの再インストールやデータの移し替え作業が発生する
- 完全にデータが完全削除されるわけではない
- 初期化すれば症状が改善するとは限らない
バックアップを取っておくことを忘れない
HDDを初期化することによって、すべてのデータが消えてしまうため、大事なデータについては事前にバックアップを取っておく必要があります。
外付けのHDDなどを購入しておき、あらかじめデータを移しておきましょう。
クラウドサービスを利用するのも便利です。
OSの再インストールやデータの移し替え作業が発生する
初期化によってHDD内のデータはすべて消えるため、初期化後にはOSの再インストールが必要となります。
パソコン購入時に付属しているリカバリーディスクを使って、OSを入れ直しましょう。
再インストールが完了したら、外付けHDDやクラウドに保存しておいたデータをHDDにすべて移せば元通りとなります。
完全にデータが完全削除されるわけではない
上の項目で、「初期化するとデータが消える」と記載しましたが、正確には、初期化だけでは完全に削除されるわけではなく、データが表示されなくなるだけです。
我々ユーザーの目には見えない状態ですし、使用することもできませんが、HDD内にはしっかりとデータが残っています。
参照:パソコンを譲渡する。返却する。売却する。廃棄する。そんな時、HDD/SSDのデータはどうやって消去する? | バッファロー
したがって、専用のツールを使ったり、専門家に依頼したりすることで、初期化後のデータを取り出すことが可能な場合もあるのです。
こうした事情から、絶対に見られたくない情報や企業の機密情報などがある場合は、初期化ではなく、物理的にHDDを破壊して復元不可能な状態にする必要があります。
「水没させる」「トンカチなどで砕く」といった方法で物理的に壊してしまえば、絶対にデータを復元することはできません。
初期化すれば症状が改善するとは限らない
パソコンの動作が重い場合や、動作異常がある場合に、初期化によって症状を改善させようと考えることも多いと思います。
しかし、諸々の動作不良が「HDDの経年劣化」によって引き起こされている不具合ならば、初期化をしても期待通りの結果になるかはわかりません。
経年劣化が原因であれば、HDD自体が弱っているため、いくらデータを丸ごと入れ替えても症状が変わらないということも大いにあり得るのです。
HDDの初期化をしても、必ず症状が改善されるわけではない、ということも覚えておきましょう。
まとめ:パソコンが重いと感じたらHDDの初期化を試してみよう

以上、HDDの初期化を行うべき場面や、OSのバージョン別の具体的な初期化方法などについて解説してきました。
購入してからそれほど年数が経っていないパソコンならば、動作スピードの改善や不具合改善のために、HDDの初期化という方法は大変有効です。
それほど難しい手順も必要ないため、パソコンの動きが不安定な場合には是非試してください。
なお、長年使ったパソコンの場合は、HDDを交換しても他のパーツが劣化している場合もあるため、買い替えた方がよいケースもあります。
したがって、使用年数の長いパソコンについては買い替えを検討するのもおすすめです。
もしパソコンを買い替える場合には、お手持ちのパソコンが不要になるかと思われます。
そんな時は「パソコン廃棄.com」の利用が便利です。
「パソコン廃棄.com」ならば、費用は一切かからず、事前のやり取りも不要。
ただ不要になったパソコンを梱包して送付するだけで、無料廃棄が完了します。
送られてきたパソコンに入っているデータ消去も、責任を持って行わせていただきますので、セキュリティ的にも安心です。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
「HDDを自分で交換したいけど、どうすればいい?」
「デスクトップ・ノートパソコン、それぞれの交換手順を知りたい」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
古くなってきたHDDはいろいろとトラブルも増えてくるため、新しいHDDに交換したいと思うのも自然なことでしょう。
そこでこの記事では、以下のようなことについて詳しく解説していきます。
【この記事でわかること】
- HDDの交換が必要な理由
- HDD交換前の準備
- デスクトップでのHDD交換手順
- ノートパソコンでのHDD交換手順
- HDDの交換をする際の注意点
HDDの交換が必要な理由

HDD(ハードディスクドライブ)は、状況に応じて交換した方がよい場合があります。
HDDの交換を行うことで、以下のようなメリットが得られます。
- パソコンの動作が早くなる
- 故障によるデータ損失を防げる
パソコンの動作が早くなる
HDDは消耗品なので、使用すればするほど劣化していきます。
劣化が進んだHDDの場合、処理速度が落ちて非常に使い勝手が悪くなってしまうので、早めに新しいHDDへ交換した方がよいでしょう。
なお、空き容量がほとんどなくなった時にも動作が遅くなってしまいますので、空き容量が少ない時は、一度不要なファイルを削除して充分な空き容量を確保してください。
それでもパソコンの動作が遅いようならば、HDDの経年劣化による動作不良の可能性が高くなります。
動作の遅いパソコンを使うことにストレスを感じる場合は、新たなHDDに交換することで悩みが解消されることでしょう。
故障によるデータ損失を防げる
HDDは、いつ壊れてしまうかわかりません。
特に以下のような症状が現れた場合は、故障が近いと判断した方がよいです。
- HDDから異音がする
- いきなりシャットダウンしたりフリーズしたりする
- その他、パソコンの動作が通常とは違う
突然HDDが故障してしまうと、大事なデータを取り出せなくなってしまうことがあります。
取り出すとしても、個人で行うのは困難で、専門業者に高額な費用を払う必要がありますし、専門業者でも必ずデータを取り出せるとは限りません。
毎日のようにデータのバックアップを取っている人ならば問題ないかもしれませんが、日々欠かさずバックアップを行うというのはなかなか難しいでしょう。
バックアップ作業にはある程度時間がかかるため、いつ訪れるかわからない不意の故障に備えて毎日外付けHDDやクラウド上に手動でデータを保存し続けるのは大変です。
新規作成や更新したファイルのみを選んでバックアップを取れば容量は抑えられますが、毎日どのファイルを作成・更新したかを把握しながらバックアップを取り続けるのも至難の業でしょう。
したがって、HDDに故障の前兆症状が出始めたら、早めに交換することをおすすめします。
HDD交換前の準備

HDDの交換作業をする際には、事前に以下のような準備をしておきましょう。
- 新しいHDDを用意する
- HDDのクローンを作成する
新しいHDDを用意する
HDDの交換を行うため、まずは新しく換装するHDDを用意する必要があります。
新しいHDDを購入する際は、以下の3つの点に注意してください。
- HDDの回転数
- HDDの大きさ
- HDDの接続規格
まずは、HDDの回転数についてです。
HDDの回転数は「rpm」という単位で表され、「5400rpm」と「7200rpm」の2種類が存在します。
この数字は「1分間でHDDが回転する回数」であり、当然回転数の多い7200rpmの方が高性能で処理の早いHDDとなります。
HDDの大きさは「2.5インチ」「3.5インチ」の2種類が主流で、2.5インチは主にノートパソコン、3.5インチは主にデスクトップで使用されます。
稀に「1.8インチ」のものもありますので、交換前にHDDの大きさをしっかりと確認しておきましょう。
最後に、接続規格についてです。
「IDE」「SATA」の2種類がありますが、IDEは2008年くらいまで主流だった古い規格であり、現在ではSATAがメインとなっています。
多くの場合はSATAだと思われますが、念のためパソコン購入時の説明書を読むか、フリーソフトで接続規格を確かめるなどの方法で確認しておいた方がよいです。
HDDのクローンを作成する
新しいHDDに交換すると、これまで作成・保存してきたデータはもちろんのこと、OSから各種ソフトウェアまで、すべてが存在しないまっさらな状態となります。
当然、OSが入っていなければパソコンは動きませんし、これまで使っていたソフトウェアやデータがないのも不便です。
そこで便利なのが、HDDのクローンを作成するという方法です。
こちらの方法を実行することで、いちいちOSをインストールしたり、データを移し変えたりといった面倒な作業を省くことができます。
なお、HDD⇒HDDだけでなく、HDD⇒SSDへの換装にも活用できるため、大変おすすめです。
クローンを作製するには、有料の専用機器を購入するか、フリーのクローン作製ソフトを使うという方法があります。
有料の専用機器を活用する場合は、ロジテック社の以下のような製品を使用するとよいでしょう。
参照:パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能 | ロジテック
費用はかかりますが、その分安全にデータを移行できるというメリットがあります。
フリーソフトで対応する場合は、「hdd クローン フリーソフト」といったようなキーワードで検索すると、該当するソフトを見つけることができます。
デスクトップでのHDD交換手順

デスクトップとノートパソコンでは、HDDの交換手順が異なります。
この項目では、デスクトップパソコンにおけるHDD交換手順について解説していきます。
なお交換の手順は、現在主流となっている接続規格「SATA」を前提としています。
すべての接続機器を取り外す
まずは、電源ケーブルやマウス、キーボード、外付けハードディスクなどの、すべての接続機器を取り外します。
何らかの機器が接続されたままですと、不要な電気残ってしまうこともありますので、一旦すべてを取り外した後に時間をおいてから、HDDの交換作業に入るようにしましょう。
古いHDDをパソコンから取り出す
デスクトップパソコンのネジ止めされている部分をはずし、交換対象である古いHDDを取り出せる状態にします。
なお取り出しの際は、他の部品を傷つけないように慎重に行うようにしてください。
パソコン内部には、メモリやCPUといった重要パーツが搭載されており、そういったパーツを傷つけてしまうと、せっかくHDDを新しくしても動作不良を起こしてしまう可能性が高くなります。
なおHDDのサイズを把握していなかった場合は、一度取り出してからサイズを測り、その後に新しいHDDを購入しても問題ありません。
新しく購入したHDDを取り付ける
交換用に購入した新しいHDDを換装します。
取り付けの際は、HDDが外れないようにきちんとネジ止めをしてください。
HDDを正しく換装できたら、外していたパネルもネジ止めして元の形に戻し、それから電源ケーブルやマウス、キーボードなどを接続します。
その後電源を入れ、BIOS画面を表示させてからHDDが認識されているかどうかを確認しましょう。
BIOS画面を表示させる方法は、多くの場合、パソコンが起動した直後に「F2キー」か「Deleteキー」を連打することで表示させることができます。
ただし、メーカーによって多少違う場合があるので、お使いの機種に合わせて対応してください。
例えばLenovoの特定機種の場合は、メーカーロゴが表示されている間に「F1キー」を連打する必要があります。
参照:推奨する BIOSの起動方法 – Lenovo デスクトップ/オールインワン – Windows – Lenovo Support BO
OSの再インストールやバックアップデータの移行を行う
HDDの交換が正しく完了した後は、OSの再インストールを行います。
HDDには何も入っていない状態なので、まずはパソコンを動作させるためのプログラムであるOSを入れなければなりません。
Windowsの場合は、パソコン購入時に付属しているリカバリディスクを利用することでOSを再インストールすることができます。
OSの再インストールが完了したら、次はバックアップしてあるデータをすべて新しいHDDへ移行してください。
これでHDD交換作業は完了となります。
なお、HDDのクローンを作成してある場合は、交換の前に新しいHDDへクローンデータを丸ごと移行させておくだけで、OSの再インストールやデータ移行の作業を省くことができます。
クローンデータの移行は、専用のソフトを使うことで簡単に実行できます。
参照:HDDのデータを丸ごとコピーするには?2つのコピー方法とメリットを併せて解説 | ロジテック
ノートパソコンでのHDD交換手順

次に、ノートパソコンでのHDD交換手順について解説していきます。
デスクトップに比べ、ノートパソコンでのHDD交換はやや難しくなるため、自信がない場合は無理をしないようにしておきましょう。
また超薄型モデルの場合は、専門家以外では交換自体ができないこともあるのでご注意ください。
なお交換の手順は、現在主流となっている接続規格「SATA」を前提としています。
バッテリーを取り外す
ノートパソコンでHDD交換をする場合は、まずバッテリーを取り外します。
ノートパソコンの場合、電源ケーブルを抜いてもバッテリーの中に電力が残っているため、通電していない状態にするにはバッテリーを外す必要があります。
ACアダプタに接続されておらず、バッテリーも外されている、という状態をしばらく維持し、完全な放電を行ってください。
古いHDDをマウンタから取り外す
放電完了後は、HDDが内蔵されている部分のネジを外していきます。
HDDはマウンタに取り付けられた状態となっているので、一旦マウンタごと取り外します。
なおマウンタとは、ノートパソコンにHDDを取り付けるための金具のことです。
次に、HDDとマウンタを固定しているネジを取り外し、新しいHDDを装着できる状態にします。
新しいHDDをノートパソコンに換装する
新しく用意したHDDをマウンタに取り付け、バッテリーやカバーもすべて元通りに戻します。
その後、HDDが正しく認識されるかどうかを確認しましょう。
以降の手順は、基本的にデスクトップと同じです。
まずはBIOS画面を表示させてHDDが認識されているか確認し、その後にOSの再インストールやデータ移行を行います。
HDDの交換をする際の注意点

HDDの交換を自分で行う場合は、以下のような点に気を付けてください。
- 自分でHDD交換をした場合はメーカー保証の対象外となる
- HDDのクローン作製やバックアップを忘れない
- 動作が不安定なら専門業者へ相談する
自分でHDD交換をした場合はメーカー保証の対象外となる
自分でHDD交換を行ったパソコンについては、基本的にメーカーのサポート対象外となってしまいますのでご注意ください。
特に保証期間が残っている場合は、自分で交換作業をするかどうか熟考すべきです。
何かパソコンにトラブルがあっても無料で対応してもらえる期間を、自ら捨ててしまうことになってしまうからです。
HDDを交換する際は、メーカーサポートを失ってまで実行する価値があるのかどうかをしっかり考慮してから行うようにしてください。
HDDのクローン作製やバックアップを忘れない
HDDを交換する前には、HDDのクローンを作成しておくか、データのバックアップを取っておきましょう。
できればクローン作製が理想ですが、難しいようでしたら、最低でもデータのバックアップだけは必ずしておくべきです。
なお、データのバックアップのみの場合は、OSを再度インストールする必要があるため、その点だけ注意が必要です。
また、今まで使っていたソフトウェアについてもすべて入れ直さなければなりません。
HDDのクローン作製には、専用機器を購入するか、フリーソフトを探すか、といった多少のリテラシーが必要ですが、後々苦労しないためには、クローンを作っておく方がよいでしょう。
動作が不安定なら専門業者へ相談する
HDDの交換は、必ず成功するとは限りません。
したがって、もし交換後にパソコンの動作が不安定なようならば、一度専門業者に相談するようにしてください。
特にノートパソコンの場合はデスクトップより交換作業が難しいため、何らかの不具合が出てしまう可能性もあります。


監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
Surfaceがフリーズした、マウスが動かないなどの状況では、強制終了が有効な場合があります。
しかし、Surfaceを強制終了したいけど方法がわからない、Surfaceの強制終了ができない、と困ることもあります。
Surfaceの強制終了の方法は、モデルによって異なります。また、Surfaceに不具合が起こっている場合はうまく強制終了できない場合も。
この記事では、Surfaceを強制終了する方法やできない場合の対処法を紹介します。突然、強制終了して困った場合の対処法も合わせて紹介していますので、参考にしてください。
【この記事でわかること】
- モデル別のSurfaceを強制終了する方法
- Surfaceのアプリを強制終了する方法
- 強制終了できない場合の対処法
- 強制終了しても再起動する場合の対処法
- 突然強制終了された場合の対処法
Surfaceを強制終了する方法!モデル別に紹介

Surfaceを強制終了するには、ツーボタンシャットダウン、電源を押し続けるだけのワンボタンの2つの方法があります。モデルによって、強制終了の方法が異なるため、まずは、お手持ちのSurfaceのモデルを確認してください。
一般的なパソコンは、電源を長押しすれば強制終了できることがほとんどです。しかし、Surfaceの場合は、強制終了する方法が通常とは異なるモデルがあります。
ここでは、Surfaceのモデル別に、強制終了する方法を紹介します。同じモデルでも、シリーズによって強制終了の方法が異なる場合があるため、よく確認しましょう。
Surface Pro、Surface Pro X
| Surface Pro (第 5 世代)、Surface Pro 6、Surface Pro 7、Surface Pro 7 以降、Surface Pro 8、Surface Pro 9 (すべてのモデル)、Surface Pro X、Surface Pro X (Wi-Fi) |
これらのSurface Proは、電源ボタンを30秒以上押し続けることで強制終了できます。
| Surface Pro、Surface Pro 2、Surface Pro 3、Surface Pro 4 |
強制終了の方法は、ツーボタンシャットダウンです。音量の「-」ボタンと「電源」ボタンを15~30秒押し続け、電源がオフになれば強制終了完了です。
Surface Proは、ノートパソコンとしても、タブレットとしても使用できる2in1のパソコンです。Surfaceの代表的なモデルで、キーボードを取り外して、ノートパソコンとタブレットパソコンを使い分けできます。
Surface Go
| Surface Go (すべてのモデル)、Surface Go 2 (すべてのモデル)、Surface Go 3 |
これらのSurface GOの強制終了の方法は、電源ボタンを30秒以上押し続けることです。電源がオフになれば、強制終了完了です。
Surfaceの中でも最も軽量な小型モデル。画面サイズは、10インチです。気軽に、さまざまな場所に持ち歩きたい方にもおすすめです。
Surface Book
| Surface Book 2、Surface Book 3 |
これらのSurface Bookは、電源ボタンを30秒以上押し続けることで強制終了できます。
| Surface Book |
強制終了の方法は、音量の「+」ボタンと電源ボタンを15秒程度押し続けます。電源がオフになれば、完了です。
Surfaceの中でも、高性能CPUを搭載したハイスペックモデル。動画編集などクリエイティブ作業をする方やオンラインゲームを楽しみたい方にもおすすめです。
Surface RT
電源ボタンのみを30秒押し続け、電源がオフになれば強制終了完了です。
WindowsRTのOSを搭載した、Surfaceの格安モデル。発売時期が古いモデルです。
Surface Laptop
| Surface Laptop (第 1 世代)、Surface Laptop 2、Surface Laptop 3、Surface Laptop 4、Surface Laptop 5、Surface Laptop Go、Surface Laptop Go 2、Surface Laptop Studio、Surface Laptop SE |
電源ボタンのみを30秒押し続け、電源がオフになれば強制終了完了です。
キーボードが一体になった、Surfaceのノートパソコン型モデル。大容量のバッテリーを備え、キーボードがしっかりとしており、電源のない場所での作業も快適です。
Surface Studio
| Surface Studio (第 1 世代)、Surface Studio 2、Surface Studio 2 以降 |
Surface Studioは、電源ボタンを30秒以上押し続ければ、強制終了できます。
Surface Studioは、28インチタッチディスプレイと本体、キーボードからなるオールインワン型のデスクトップパソコン。大画面と高性能なCPUを備え、クリエイティブ作業も快適にこなします。
参考:Microsoftサポート Surface を強制的にシャットダウンし、再起動する
Surfaceのアプリを強制終了する方法

Surfaceを使っていると、アプリがフリーズしてしまい終了できないこともあります。ここからは、Surfaceのアプリを強制終了する3つの方法を紹介します。
強制終了するアプリで未保存のデータは、保存できません。アプリのフリーズは、しばらく待つと復帰する可能性もあります。強制終了は、アプリのフリーズが続く場合に実行しましょう。
ショートカットキーを使う方法
アプリを強制終了するには、「Alt」キーと「F4」キーを同時に押し続けます。アプリが完全に終了するまで押し続けてください。
アプリのウィンドウが閉じれば、強制終了ができたことになります。
タスクマネージャーを使用する方法
【Windows10】
- 「Windows」ボタンをクリックしてアプリの一覧を表示する
- 「W」欄の「Windowsシステムツール」をクリック
- 「タスクマネージャー」をクリック
- 「タスクマネージャー」で終了したいアプリをクリック
- 「タスクの終了」をクリック
- 選択したアプリが終了したらタスクマネージャーを閉じる
【Windows11】
- 「Windows」ボタンを右クリック
- 表示された一覧から「タスクマネージャー」をクリック
- 「タスクマネージャー」で終了したいアプリをクリック
- 「タスクの終了」をクリック
- 選択したアプリが終了したらタスクマネージャーを閉じる
タスクマネージャーを使用すれば、実行中のアプリを強制的に停止できます。フリーズして、終了できない場合に試してみてください。
コマンドを使う方法
アプリを強制終了するには、コマンドを使う方法もあります。ただし、コマンドはシステムに直接命令する方法のため、コマンドを間違えるとデータ消去やシステムの不具合につながる可能性があります。操作内容を良く理解し、慎重に実行してください。
- 検索ウィンドウで「コマンドプロンプト」と入力
- 「開く」を選択
- コマンドプロンプトが起動したら、「taskkill /im 〇〇.exe」のコマンドを入力
- Enterキーを押す
○○には、終了したいアプリ名を入れます。例えばエクセルを終了させたい場合は〇〇にはexcelを入れてください。
Surfaceを強制終了できない場合の対処法

Surfaceを強制終了したくてもできない、シャットダウンができない場合は、システムがフリーズしている可能性があります。電源長押しなどの強制終了を実行しても、再起動すると再びフリーズしてしまう、などの症状が続く場合もあります。
強制終了できない場合は、Surfaceが故障している可能性もありますが、正しい対処法を実行すれば自分で直すことも可能です。
Surfaceを強制終了できない場合は、以下の方法を試してみましょう。
- 周辺機器をすべて外して放電する
- Windows Updateを実行する
- ショートカットキーで強制終了
- 電源を強制的に落とす
順番に詳しく解説します。
周辺機器をすべて外して放電する
Surfaceを長時間使用している場合は、Surface内に帯電して不具合が起こっている可能性があります。外部機器をすべて取り外し、Surfaceを放電しましょう。
また周辺機器の不具合によって、シャットダウンを妨げている可能性もあります。
まずは、Surfaceに接続している外部機器をすべて取り外します。電源コードをコンセントから抜き、電源アダプター、タイプカバー(キーボード)、マウスなどのアクセサリ、メモリカードなどをすべて取り外します。
外部機器をすべて取り外したら、5~10分程度そのまま放置します。再度、すべての機器を取り付けて電源を入れ、Surfaceが正常にシャットダウンできることを確認しましょう。
Windows Updateを実行する
Windowsが強制終了できない場合は、Windows Updateを実行することで改善する可能性があります。
Windows Updateには、インターネット環境が必要です。インストールするプログラムや通信環境によっては、時間がかかる可能性もあります。充分な時間を確保して実行しましょう。
- 作業中のアプリをすべて終了する
- 「スタート」をクリック
- 「設定」をクリック
- 「Windows Update」をクリック
- Windowsの状態を確認する
- メッセージに従ってWindows Updateを実行し、Surfaceを再起動する
スタートメニューに「設定」がない場合は、「Windows」ボタンをクリック後、右上の「すべてのアプリ」から「設定」に進んでください。
表示されたWindowsの状態によって、さまざまなメッセージが表示されます。表示されたメッセージにしたがってWindows Updateを実行してください。
Windowsが最新の状態の場合は、「更新プログラムのチェック」をクリックすると、新しいプログラムの有無を確認できます。
なお、Windows Updateは、Surfaceが突然シャットダウンする場合にも有効です。Surfaceは、突然シャットダウンする不具合が起こる場合があります。多くの場合は、Windows Updateで改善される可能性が高いです。
ショートカットキーでWindowsを強制終了する
Surfaceがフリーズして、強制終了できない場合は、ショートカットを使って強制終了する方法もあります。
「Alt」+「F4」
- 「Alt」キーを押しながら「F4」キーを押す
- 「Windowsのシャットダウン」を選択して「OK」をクリックする
「Ctrl」+「Alt」+「Del」
- 「Ctrl」+「Alt」+「Del」を同時に押す
- 右下の電源マークをクリック
- キーボード操作の場合は「Shift+Tab」を押すか、「Tab」キーでカーソル移動して「Enter」キーで選択
- 「シャットダウン」を選択し「Enter」キーで実行
いずれかの方法でSurfaceの電源が完全に切れたら、そのまま10秒以上待ってからSurfaceの電源を入れましょう。
電源を強制的に落とす
ここまでの方法で、強制終了できない場合は、コンセントから電源ケーブルを抜き、強制的に電源を落としましょう。また、Wi-Fiなどのネットワーク通信が原因で強制終了できない可能性もあるため、ネットワークも切断しましょう。
Surfaceを強制終了しても再起動する場合の対処法

Surfaceを強制終了しても、突然再起動する不具合が起こることがあります。再起動する場合は、以下の対処法を試してください。
- 再起動する場合はShiftキーを押す
- 高速スタートアップ機能を無効にする
- 再起動機能を停止する
それぞれ解説します。
Shiftキーを押す
「Shift」キーを押しながらSurfaceをシャットダウンすると、再起動しません。しかし、Shiftキーを押す方法は、一時的な方法で根本的な解決にはなりません。
強制終了しても再起動する症状が続く場合は、別の方法を実行しましょう。
高速スタートアップ機能を無効にする
高速スタート機能は、パソコンを高速起動するために、シャットダウン時にメモリやCPUに一時的にデータを保存しておく機能です。
パソコンが高速で起動することはメリットですが、シャットダウンする前の状態を保存するため動作が不安定になる場合があります。高速スタートアップ機能を無効にしても、立ち上がりの時間が少しかかるだけで大きな問題は起こりません。
高速スタートアップを無効にする手順は、以下の通りです。
- 「スタート」ボタンを右クリック、「電源オプション」をクリック
- 「電源とスリープ」が表示されるので「電源の追加設定」をクリック
- 「電源オプション」が表示されるので「電源ボタンの動作の選択」をクリック
- 「システム設定」が表示されるので「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリック
- 「シャットダウン設定」にある「高速スタートアップを有効にする(推奨)」をクリックしチェックを外す
- 「変更の保存」ボタンをクリック
以上で高速スタートアップが無効になります。
参考:富士通FMVサポート 高速スタートアップを無効にする方法を教えてください。
緊急の再起動オプションを停止する
Windowsには、システムエラーが発生すると、自動で再起動する機能があります。強制終了しても再起動する場合は、再起動オプションが動作している可能性があります。
Surfaceを購入時のまま使用していると、再起動オプションが有効になっているため、自動で再起動しないように以下の手順で設定してください。
【Windows10】
- 「Windows」ボタンをクリック
- 「設定」から「システム」をクリック
- 画面左下の「詳細情報」から「関連設定」欄の「システムの詳細設定」をクリック
- 「システムのプロパティ」から「詳細設定」タブをクリック
- 「起動と回復」欄の「設定」をクリック
- 「システムエラー」欄の「自動的に再起動する」のチェックを外し、「OK」をクリック
- 「システムのプロパティ」画面で「OK」をクリック
- 「設定」画面を閉じる
参考:NEC LAVIE公式サイト Windows 10でシステムエラー発生時に自動で再起動しないよう設定する方法
Surfaceが突然強制終了された場合はどうする?

Surfaceは、突然シャットダウンする不具合が起こる場合があります。作業中に突然強制終了された場合には、次の2つの方法を試してみましょう。
- Windows Updateの実行
- Intel®MEの設定変更
それぞれ、紹介していきます。
Windows Updateの実行
Surfaceが勝手にシャットダウンされるのは、Windows Updateによるドライバーの更新が、正常に適用されていないことが原因になっている可能性があります。
Windows Updateを最新になるまで更新しましょう。最新の状態まで実行したら、Surfaceの公式サイトにある、それぞれのモデルに合ったドライバーをダウンロードし、インストールしてください。インストールが完了すると、再起動を求めるポップアップが表示され「YES」を選択すると再起動されます。Surfaceの状態が改善されていることを確認しましょう。
Intel®MEの設定変更
Intel®MEとは、Surface内のシステムにさまざまな機能やサービスを提供する機能です。低消費電力や盗難防止などの機能があります。
Intel®MEの「電源の管理」の設定を変更することで、勝手にシャットダウンする症状が改善する可能性があります。
- スタートボタンを右クリック
- 「デバイスマネージャー」をクリック
- 「システムデバイス」の中の「Intel (R) Management Engine Interface」を右クリック
- 「プロパティ」をクリック
- 「電源管理」のタブを選択
- 「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックマークを外す
Surfaceを強制終了する注意点

強制終了は、Surfaceに大きな負担がかかる作業です。そのため、これから紹介する注意点を守って、強制終了を実行しましょう。
Surfaceを強制終了する場合の注意点は、以下の3つです。
- データが消える可能性がある
- 強制終了を繰り返さない
- 何度も電源をON、OFFしない
順番に解説します。
データが消える可能性がある
Surfaceを強制終了する場合、保存されていないデータは消える可能性があります。データを保存できる状態であれば保存してから強制終了を実行しましょう。
パソコンのアクセスランプが点滅中の場合は、パソコンがデータを書き込み中です。ハードディスクが動作中に強制終了を実行すると、データが消えるだけでなく、ハードディスクが故障する可能性もあります。アクセスランプが点滅中の場合は、強制終了を実行しないように注意してください。
強制終了を繰り返さない
Surfaceを強制終了しても、すぐに故障につながることはありません。しかし、強制終了を実行すると、次回起動時の準備ができないため、起動時のトラブルが起こりやすくなります。
強制終了は、パソコンに大きな負担がかかります。短時間に何度も繰り返す、頻繁に強制終了することで、システムにも負担がかかります。強制終了する場合は、一定の時間を空けて実行しましょう。
何度も電源をON、OFFしない
電源のONやOFFは、パソコンに大きな負担がかかります。何度もパソコンに通電を繰り返すのは、Surfaceの症状を悪化させる可能性もあります。通電することでデータが上書きされ、元のデータを復元できなくなる場合もあるため、不用意に電源のONとOFFを繰り返さないようにしましょう。
またSurfaceが起動しない、充電しない場合は、下記の記事でも対処法を紹介しています。参考にしてください。
【Surfaceの充電ができない!】症状別の対処法を詳細解説>>
【Surfaceが起動しない時の対処法】症状別に具体的な手順を解説!>>
Surfaceの強制終了が何度も必要になる場合は寿命の可能性

強制終了は、Surfaceになんらかの不具合がある場合に実行することです。何度も強制終了を実行すると、パソコンに大きな負担がかかり、さらに不具合が増えるケースも。
さまざまな対処法をおこなっても、何度も強制終了が必要になる場合は、システムの不具合や老朽化によってSurfaceが寿命を迎えている可能性も高いです。購入からすでに何年も経っているなら、Surfaceの買い替えも検討しましょう。
Surfaceを買い替えたら、古いものは処分が必要です。パソコン廃棄.comでは、故障していても無料で処分できます。事前の申し込みやデータも消去も不要。Surfaceを指定住所に送るだけで手軽に処分できます。データ消去は、専門の知識を持ったスタッフによって的確におこなわれるため安心して処分できることもメリットです。
まとめ:Surfaceの強制終了する方法はモデルによって違う

Surfaceを強制終了する方法は、ツーボタンシャットダウン、電源を押し続けるだけのワンボタンの2つの方法があり、モデルによって異なります。
強制終了が必要な場合には、まずSurfaceのモデルを確認し、正しい方法で強制終了を実行しましょう。強制終了できない場合は、システムがフリーズしている可能性があります。フリーズした場合は、放電やWindows Update、ショートカットキーを試しましょう。
強制終了が頻繁に必要になる場合は、Surfaceが寿命を迎えている可能性もあります。強制終了を頻繁に実行すると、パソコンに負担がかかるため、購入から何年も経過している場合は買い替えの検討もおすすめです。
Surfaceを処分する場合は、事前申し込み不要、無料で処分できるパソコン廃棄.comがおすすめです。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。